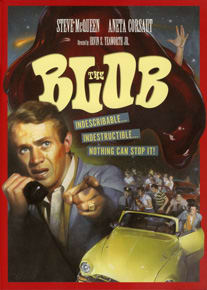M. Butterfly@VHSビデオ、デイヴィッド・クローネンバーグ監督(1993年アメリカ)
男は一度もそこに触れずに愛しつづけた。
1964年、北京。フランス大使館の外交官ルネ・ガリマール(ジェレミー・アイアンズ)は、ある夜会で見たプッチーニのオペラ『蝶々夫人』でマダム・バタフライを演じるソン・リリン(ジョン・ローン)に、激しく心を揺さぶられてしまう。毅然たる美貌と恥じらいと慎みをたたえたミステリアスな東洋の美女。
「君は僕のバタフライか?」──妻がいる身でありながら禁じられた恋路に足を踏み出すルネ。だがソンは中国当局からある任務を受けたスパイであった。そうとは知らず愛と官能の世界に耽溺するルネ。その彼の前に、さらなる衝撃の事実が!
錯綜する裏切りと陰謀、歴史の裏側の舞台でうごめく性の幻想。世界中を騒がせた衝撃のスキャンダルが、オスカー俳優ジェレミー・アイアンズ、艶麗な女装姿のジョン・ローン、異才監督クローネンバーグによって白日の下にさらされた、驚愕の一作。


先日の吉田豪や松本ともこの出演したイベントで、豪さんが言ってたんですけどさ。マイケル・ジャクソンの死去について「音楽評論家」の富澤一誠が、こうコメント。「彼は人種の壁を超えて愛されたスーパースターでした」。みんな知ってる。真顔で言ってたらしい。以前には「最近海外では“ディーヴァ”という音楽が流行しているようです」とも真顔で言ってたんだとか。おっかしい。
ニューミュージックみたいなくだらん音楽を正当化することで、マスコミで発言する利権をつかんだ。そ~ゆ~既得権益汚やじが鈴なりにしがみついて沈没してゆくマスコミ業界を象徴。といって、もっとこう、マイケル・ジャクソンの音楽や芸能生活について、ちゃんとした意見を述べている業界人がいるとしても、それはそれでやっぱり釈然としない。
彼が薬漬けになって早世してしまった結果がわかったうえでの、後出しジャンケンのように思うんです。
マイケルがスーパースターとして絶頂にいた、同時代に言っていただけないと。江口寿史氏は、白人のような風貌へ整形を繰り返し、ディズニーランドのアトラクションにもなってた、その同じ時代にマイケルに対する微妙な違和感をマンガのオチで表現した。↓誰もが眠るが、ロボットみたいなマイケル・ジャクソンは眠らないのかも…。
“まんが書店”の客を客とも思わない常識外れの商法についても、江口氏は当時マンガ化してる。型にはまった“風刺漫画”などとはひと味もふた味も違う、あっぱれな芸だったといえよう。

スパイの京劇俳優死去 時佩璞氏
【パリ=AFP・時事】男性でありながら女性のふりをしてフランス人外交官に色仕掛けで近づき、仏機密文書を入手し、1986年にスパイ罪で有罪判決を受けた中国人の京劇俳優、時佩璞氏が6月30日にパリの自宅で死亡した。70歳だった。側近が1日明らかにした。
時氏は中国の山東省生まれ。64年にフランス人外交官ベルナール・ブルシコ氏と出会い、自らを女性と信じ込ませ愛人関係に。ブルシコ氏はモンゴルの仏大使館に勤務していた77年から79年にかけて約30件の極秘文書を中国政府に渡していた。
83年にブルシコ氏とともに逮捕され、86年に禁固6年の判決を受けたが、87年に当時のミッテラン大統領が恩赦を与え、その後パリに居を構えていた。 ─(東京新聞7月2日夕刊)

1986年5月、パリの法廷で、ベルナール・ブルシコ氏(左)とともに被告席に立った時佩璞氏=AFP・時事
実話MW。MWより奇妙。事実は小説より奇なり。この事実から想を得て、舞台化されたものを、さらにクローネンバーグ監督が映画化。舞台版よりも映画では、男性と女性、あるいは西洋と東洋、といったことに政治的な寓意が込められてるんだとか。京劇で男が女を演じることの意味をジョン・ローンが「どのように振る舞えば“女”になるのか、男だけが知ってる」と言う場面も。
クロネンさん自身「ジョン・ローンそのものが、この映画の特殊効果だ」と語ったとかで、クロネンらしい特殊効果なしのフェアプレーながらも、その色っぽさ、女性らしさは、それだけで一見の価値あり。公開中の『MW』は映画化にあたって、ホモとか女装とかを排除して凡庸なアクション作になってしまったので、そこを正面突破したクロネンさんはさすがだと思います。
見ているとなるほど、身長、骨格、皮膚の質感など、アジア人男性であれば、「東洋の女性は慎み深い」という西洋白人の固定観念にも乗じて、性交時に脱がず触らせず、18年間も女であるとだましおおせることも可能かもしれない。なにしろ実話に基づく。
欧米白人にとっては、日本人と朝鮮人と中国人、あるいはベトナム人やタイ人との違いもわからないし興味もない。彼らは“上から見てる”ので。いっぽうわれわれは、下から隙あらばのし上がろうと狙ってるので、さまざまな民族・文化の違いに興味津々にならざるをえないのかも。
おそらくクローネンバーグ監督も、アジアとヨーロッパの中間地帯で歴史に翻弄されてきたユダヤ系の一員として、そうしたことに敏感で、この難しそうだがやりがいのある題材をぜひ自分の手で成し遂げたかったんではないでしょか。
いわゆるユダヤ人が金儲けがうまい、というような定評や彼らの映画や音楽に発揮する才能などもおそらく、差別されてきたからこそチャンスに敏感であることの表れかもしれないし、逆に、祇園精舎の鐘の音=盛者必衰の理なんてのも、上の立場、権力側に立つとどうしても鈍感になって、江口寿史やクローネンバーグのような《気づく力》を失ってしまいがちなことにもよるのではないか。

男は一度もそこに触れずに愛しつづけた。
1964年、北京。フランス大使館の外交官ルネ・ガリマール(ジェレミー・アイアンズ)は、ある夜会で見たプッチーニのオペラ『蝶々夫人』でマダム・バタフライを演じるソン・リリン(ジョン・ローン)に、激しく心を揺さぶられてしまう。毅然たる美貌と恥じらいと慎みをたたえたミステリアスな東洋の美女。
「君は僕のバタフライか?」──妻がいる身でありながら禁じられた恋路に足を踏み出すルネ。だがソンは中国当局からある任務を受けたスパイであった。そうとは知らず愛と官能の世界に耽溺するルネ。その彼の前に、さらなる衝撃の事実が!
錯綜する裏切りと陰謀、歴史の裏側の舞台でうごめく性の幻想。世界中を騒がせた衝撃のスキャンダルが、オスカー俳優ジェレミー・アイアンズ、艶麗な女装姿のジョン・ローン、異才監督クローネンバーグによって白日の下にさらされた、驚愕の一作。


先日の吉田豪や松本ともこの出演したイベントで、豪さんが言ってたんですけどさ。マイケル・ジャクソンの死去について「音楽評論家」の富澤一誠が、こうコメント。「彼は人種の壁を超えて愛されたスーパースターでした」。みんな知ってる。真顔で言ってたらしい。以前には「最近海外では“ディーヴァ”という音楽が流行しているようです」とも真顔で言ってたんだとか。おっかしい。
ニューミュージックみたいなくだらん音楽を正当化することで、マスコミで発言する利権をつかんだ。そ~ゆ~既得権益汚やじが鈴なりにしがみついて沈没してゆくマスコミ業界を象徴。といって、もっとこう、マイケル・ジャクソンの音楽や芸能生活について、ちゃんとした意見を述べている業界人がいるとしても、それはそれでやっぱり釈然としない。
彼が薬漬けになって早世してしまった結果がわかったうえでの、後出しジャンケンのように思うんです。
マイケルがスーパースターとして絶頂にいた、同時代に言っていただけないと。江口寿史氏は、白人のような風貌へ整形を繰り返し、ディズニーランドのアトラクションにもなってた、その同じ時代にマイケルに対する微妙な違和感をマンガのオチで表現した。↓誰もが眠るが、ロボットみたいなマイケル・ジャクソンは眠らないのかも…。
“まんが書店”の客を客とも思わない常識外れの商法についても、江口氏は当時マンガ化してる。型にはまった“風刺漫画”などとはひと味もふた味も違う、あっぱれな芸だったといえよう。

スパイの京劇俳優死去 時佩璞氏
【パリ=AFP・時事】男性でありながら女性のふりをしてフランス人外交官に色仕掛けで近づき、仏機密文書を入手し、1986年にスパイ罪で有罪判決を受けた中国人の京劇俳優、時佩璞氏が6月30日にパリの自宅で死亡した。70歳だった。側近が1日明らかにした。
時氏は中国の山東省生まれ。64年にフランス人外交官ベルナール・ブルシコ氏と出会い、自らを女性と信じ込ませ愛人関係に。ブルシコ氏はモンゴルの仏大使館に勤務していた77年から79年にかけて約30件の極秘文書を中国政府に渡していた。
83年にブルシコ氏とともに逮捕され、86年に禁固6年の判決を受けたが、87年に当時のミッテラン大統領が恩赦を与え、その後パリに居を構えていた。 ─(東京新聞7月2日夕刊)

1986年5月、パリの法廷で、ベルナール・ブルシコ氏(左)とともに被告席に立った時佩璞氏=AFP・時事
実話MW。MWより奇妙。事実は小説より奇なり。この事実から想を得て、舞台化されたものを、さらにクローネンバーグ監督が映画化。舞台版よりも映画では、男性と女性、あるいは西洋と東洋、といったことに政治的な寓意が込められてるんだとか。京劇で男が女を演じることの意味をジョン・ローンが「どのように振る舞えば“女”になるのか、男だけが知ってる」と言う場面も。
クロネンさん自身「ジョン・ローンそのものが、この映画の特殊効果だ」と語ったとかで、クロネンらしい特殊効果なしのフェアプレーながらも、その色っぽさ、女性らしさは、それだけで一見の価値あり。公開中の『MW』は映画化にあたって、ホモとか女装とかを排除して凡庸なアクション作になってしまったので、そこを正面突破したクロネンさんはさすがだと思います。
見ているとなるほど、身長、骨格、皮膚の質感など、アジア人男性であれば、「東洋の女性は慎み深い」という西洋白人の固定観念にも乗じて、性交時に脱がず触らせず、18年間も女であるとだましおおせることも可能かもしれない。なにしろ実話に基づく。
欧米白人にとっては、日本人と朝鮮人と中国人、あるいはベトナム人やタイ人との違いもわからないし興味もない。彼らは“上から見てる”ので。いっぽうわれわれは、下から隙あらばのし上がろうと狙ってるので、さまざまな民族・文化の違いに興味津々にならざるをえないのかも。
おそらくクローネンバーグ監督も、アジアとヨーロッパの中間地帯で歴史に翻弄されてきたユダヤ系の一員として、そうしたことに敏感で、この難しそうだがやりがいのある題材をぜひ自分の手で成し遂げたかったんではないでしょか。
いわゆるユダヤ人が金儲けがうまい、というような定評や彼らの映画や音楽に発揮する才能などもおそらく、差別されてきたからこそチャンスに敏感であることの表れかもしれないし、逆に、祇園精舎の鐘の音=盛者必衰の理なんてのも、上の立場、権力側に立つとどうしても鈍感になって、江口寿史やクローネンバーグのような《気づく力》を失ってしまいがちなことにもよるのではないか。