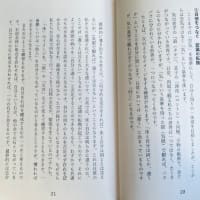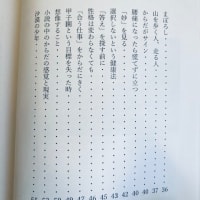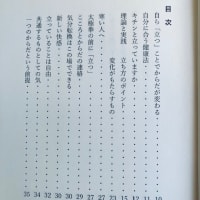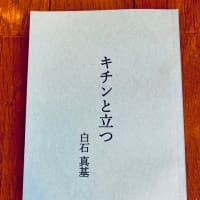相変わらず下手な渓流釣りを続けているが、フェイスブックの方に記事を載せているので、こちらで書くのは久しぶりである。昨年は都留漁協の方へ通っていたが、今年はまた桂川漁協に戻って来た。
解禁日から各地の沢を廻って釣り糸を垂れてきたが、暖かくなってそろそろ本流でも釣れるのではと、昨日は8メートルの竿を持っていったが、アタリすらなかった。餌もミミズ・クロカワムシ・オニチョロと色々試してみるが全く反応がない。2時間魚に無視され続けて、あきらめが付いた。魚には魚の事情があるのだと、技術が無いだけなのに言い訳をする。
沢に行くことにした。下流は入渓者が多いので、暫く山道を歩いてから釣り始める。小さな山女魚をリリースしながら登っていくが、なかなか良いサイズが出ない。この沢には数年前に2、3度来たことがあるが、いつも本流や他の沢の「ついで」だったのと、さほど釣れないので短い時間で止めていた。今回、初めて先(上流)に進んでみる。1時間半ほど経ち、小さなポイントでアタリがあった。鈍い重みを手に感じた後、一転して魚が左右に走った。水面に顔を出さして、引き寄せているその途中にバラシてしまった(こんな処でバラスなんてあまり無いことだ。そんなに暴れたワケでもないのに)。
岩魚がいることを確信すると、俄然意欲が湧いて来た。居るか居ないか分からないで釣りをするのと、居るはずだと思って釣りをするのでは、釣りの丁寧さ(ポイントに静かに近づいたり、仕掛けを変えたり)が違う。疲労感も違う。
上流では水が少ないから、ポイントが限られる。落差があり水の溜まっているポイントに、慎重に餌を落とす。餌が一瞬止まった(岩魚が喰い付いたに違いない)。糸を弛ませてテンションをかけないようにする。その間に岩魚がミミズを、喰う。しっかり針掛かりさせるために、待つ。
およそ26センチの岩魚。

その後、これより大きい岩魚も釣れて、もっと上に行きたかったが帰りの体力を考慮し、納竿した。もちろん次回は更にこの「先」を目指すことは言うまでもない。「魚止めの滝」を自分の足で確認するまでは登り続けるだろう。恐らくそれは釣り人の習性である。

解禁日から各地の沢を廻って釣り糸を垂れてきたが、暖かくなってそろそろ本流でも釣れるのではと、昨日は8メートルの竿を持っていったが、アタリすらなかった。餌もミミズ・クロカワムシ・オニチョロと色々試してみるが全く反応がない。2時間魚に無視され続けて、あきらめが付いた。魚には魚の事情があるのだと、技術が無いだけなのに言い訳をする。
沢に行くことにした。下流は入渓者が多いので、暫く山道を歩いてから釣り始める。小さな山女魚をリリースしながら登っていくが、なかなか良いサイズが出ない。この沢には数年前に2、3度来たことがあるが、いつも本流や他の沢の「ついで」だったのと、さほど釣れないので短い時間で止めていた。今回、初めて先(上流)に進んでみる。1時間半ほど経ち、小さなポイントでアタリがあった。鈍い重みを手に感じた後、一転して魚が左右に走った。水面に顔を出さして、引き寄せているその途中にバラシてしまった(こんな処でバラスなんてあまり無いことだ。そんなに暴れたワケでもないのに)。
岩魚がいることを確信すると、俄然意欲が湧いて来た。居るか居ないか分からないで釣りをするのと、居るはずだと思って釣りをするのでは、釣りの丁寧さ(ポイントに静かに近づいたり、仕掛けを変えたり)が違う。疲労感も違う。
上流では水が少ないから、ポイントが限られる。落差があり水の溜まっているポイントに、慎重に餌を落とす。餌が一瞬止まった(岩魚が喰い付いたに違いない)。糸を弛ませてテンションをかけないようにする。その間に岩魚がミミズを、喰う。しっかり針掛かりさせるために、待つ。
およそ26センチの岩魚。

その後、これより大きい岩魚も釣れて、もっと上に行きたかったが帰りの体力を考慮し、納竿した。もちろん次回は更にこの「先」を目指すことは言うまでもない。「魚止めの滝」を自分の足で確認するまでは登り続けるだろう。恐らくそれは釣り人の習性である。