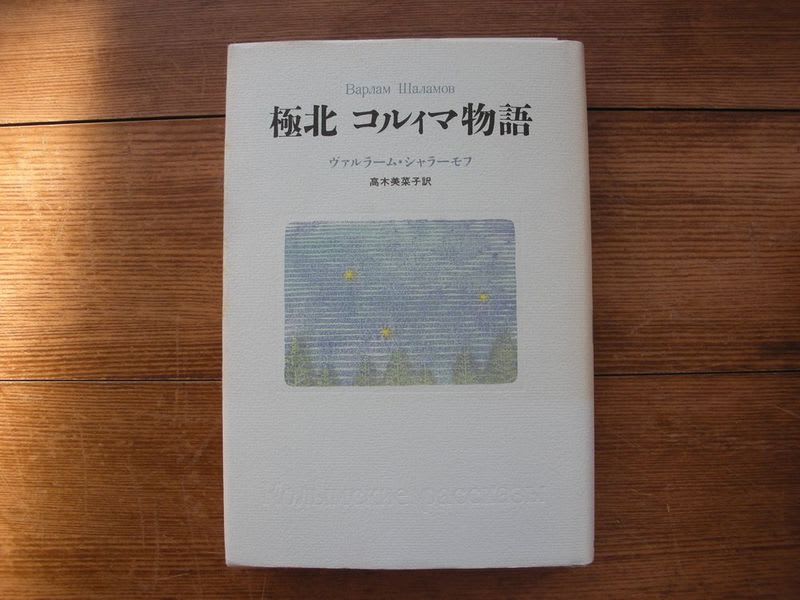国際会議などで使用する同じ内容の文書を、各言語で作成すると、中国語で書かれたものが一番短いと聞いたことがある。このことが何を意味しているかと言うと、一文字あたりに含まれる内容が他の言語よりも多いということだ。
中国には、古代漢語と呼ばれる古文もある。論語も史記も三国志も杜甫も皆、古代漢語である。この古代漢語、現代の中国語よりも、相当短い。短いことは、伝達が上手く行けば、便利だが、情報量が少ないが故に、理解しづらい。
昔の中国人は、文書をできるだけ短く書こうとしていたようだ。韻を合わせたり、対句にしたりもするが、何よりも短さにその意識が向けられているようだ。省略できる文字はとことん削り、最後に残ったものだけで勝負するという感じである。
読んですぐにわからないということは、読み手側の情報不足と、感受性(察する能力)の鈍さが原因である。逆に言えば、それを磨けば少しづつでもわかるようになる。
現在の世の中では、文字(言葉)をできるだけ多く使う方向にあるようだ。テレビ然り、小説然り・・・
文字を削っていくことで生まれるものがある。それは美かも知れないし、自分の能力かも知れない。それを楽しみにしている。