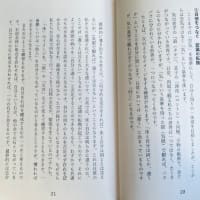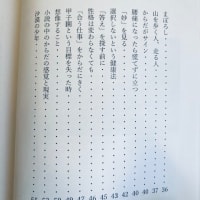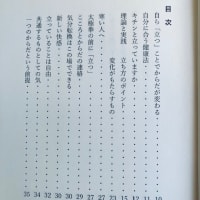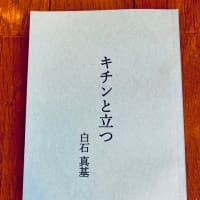最上級生になって、一時監督が若い先輩に代わった。歳が近いこともあって親近感を持ち、新たな気持ちで野球に取り組むようになった。その頃、こんなことがあった。練習試合で私がサヨナラヒットを打って勝った試合後のこと。「あんなあたりなら打たない方が良かったんだよ!」と言われた。確かに「ドン詰まり」のあたりで、きれいなヒットではなかった。また私が毎試合1本程度のヒットしか打てないでいたとき、「1本のヒットで満足してるなよ」と言われた。どうしたらいいのか分からなかった。満足したことなど一度もないし、どの打席でも同じように「打つ気」でいたのだから。
秋の大会ではブロック予選の決勝まで行き、1対2で惨敗した(私たちが負けたその相手が勝ち進み春の選抜甲子園に行った)。試合前に監督から「必ずカーブ(スライダー)が来るから、それを狙え」と指示があり、実際それをヒットした。試合後に「言った通りだろ」と言われた。監督は自分の思い通りに選手が動くことを望んでいたのかも知れない。もっとも当時の多くの高校は、監督がリーダーシップを取り、選手が付いて行く形だっただろうから、おかしいことではない。上から下への命令系統が明確で、意思が統一されるから成果が出やすいかも知れない。しかし選手の自発性は減るだろう。もっと言えば人の生きている勢いのようなものがなくなるのではないだろうか。
監督と選手の関係は、国家と民の関係に似ている。私は老子が言うように国家の存在を意識することなく(感じないで)、生きていけるのが理想だと思っている。高校野球における監督と選手の関係も同様、監督が目立つことなく、選手が自身で考え行動するのが理想である。しかし、そのためには選手一人ひとりが自立していることが前提になる。私にはそれが足りなかった。監督云々ではなく、自分がどう生きたいのか、どういう野球をやりたいのか、そういうことを自問しなければならなかったのだ。
秋の大会ではブロック予選の決勝まで行き、1対2で惨敗した(私たちが負けたその相手が勝ち進み春の選抜甲子園に行った)。試合前に監督から「必ずカーブ(スライダー)が来るから、それを狙え」と指示があり、実際それをヒットした。試合後に「言った通りだろ」と言われた。監督は自分の思い通りに選手が動くことを望んでいたのかも知れない。もっとも当時の多くの高校は、監督がリーダーシップを取り、選手が付いて行く形だっただろうから、おかしいことではない。上から下への命令系統が明確で、意思が統一されるから成果が出やすいかも知れない。しかし選手の自発性は減るだろう。もっと言えば人の生きている勢いのようなものがなくなるのではないだろうか。
監督と選手の関係は、国家と民の関係に似ている。私は老子が言うように国家の存在を意識することなく(感じないで)、生きていけるのが理想だと思っている。高校野球における監督と選手の関係も同様、監督が目立つことなく、選手が自身で考え行動するのが理想である。しかし、そのためには選手一人ひとりが自立していることが前提になる。私にはそれが足りなかった。監督云々ではなく、自分がどう生きたいのか、どういう野球をやりたいのか、そういうことを自問しなければならなかったのだ。