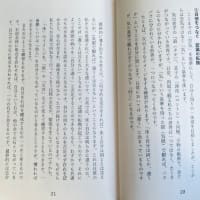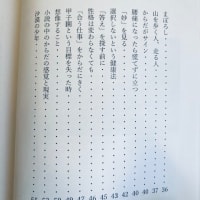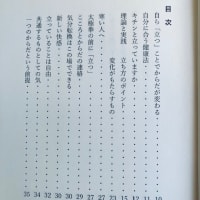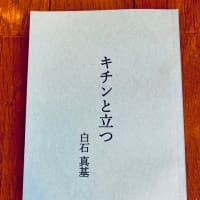「気」は壮大で、いろいろな意味を持つ。万物の根源としての気、エネルギーとして体内を流れる気、ふとそんな気がするというときの気…私が今関心を持っているのは、他者と共通するものとしての気。
キチンと立つ練習をしていると、丹田腹式呼吸から全身呼吸になる。腹式呼吸というのは横隔膜が上下することで腹の起伏がおこる呼吸法で、実際の息は肺までしか入らないが、あたかも腹にまで入っているような感じがする。同様に全身呼吸は呼吸に合わせて足の裏や掌、顔や頭まで変化を感じ、まるで全身に息(空気)が満ちているようになる。実際にはそうでなくても、そういう感じがあるのだから、ここではからだの中に空気があると思ってみる。からだの周りの空気と、自分のからだの中の空気を(科学的でなく感覚で)比べてみると、その空気の質は同じとは言えないが、違うとも言えないという気がする。この「違うとは言えない」ということには、大変な意味がある。なぜなら普段は、自分と空気は全く違うものだと確信しているのだから。日常は常識や相対的に物を見るから、自分と他の物が一緒になることはないが、こうして感覚を基準にすれば、物の捉え方が変わってくるのである。
私はここで相対的な物の見方を否定して、からだの基準が正しいと言おうとしているのでなく、自分と他の物、或いは他の人との間に共通するものを認めると、自分の身心が変わるということを言いたいのである。からだは余分な力は抜けて安定し、ココロは雑念が減り穏やかになる。他者との共通するもの、たとえば血液や骨、内臓、神経…はいくらでもあるが、知識という表層のレベルで共通を認めても、自分の身心は変わらない。たとえば自分のからだの中に空気を感じるような状態を作ることで初めて、相手の中に空気を想像することができる。自身の体感が深い想像をさせるのである。ここでいう空気を、気と呼んでも同じことである。私たちは、からだを整える手段として気(空気)を使うことができる。
キチンと立つ練習をしていると、丹田腹式呼吸から全身呼吸になる。腹式呼吸というのは横隔膜が上下することで腹の起伏がおこる呼吸法で、実際の息は肺までしか入らないが、あたかも腹にまで入っているような感じがする。同様に全身呼吸は呼吸に合わせて足の裏や掌、顔や頭まで変化を感じ、まるで全身に息(空気)が満ちているようになる。実際にはそうでなくても、そういう感じがあるのだから、ここではからだの中に空気があると思ってみる。からだの周りの空気と、自分のからだの中の空気を(科学的でなく感覚で)比べてみると、その空気の質は同じとは言えないが、違うとも言えないという気がする。この「違うとは言えない」ということには、大変な意味がある。なぜなら普段は、自分と空気は全く違うものだと確信しているのだから。日常は常識や相対的に物を見るから、自分と他の物が一緒になることはないが、こうして感覚を基準にすれば、物の捉え方が変わってくるのである。
私はここで相対的な物の見方を否定して、からだの基準が正しいと言おうとしているのでなく、自分と他の物、或いは他の人との間に共通するものを認めると、自分の身心が変わるということを言いたいのである。からだは余分な力は抜けて安定し、ココロは雑念が減り穏やかになる。他者との共通するもの、たとえば血液や骨、内臓、神経…はいくらでもあるが、知識という表層のレベルで共通を認めても、自分の身心は変わらない。たとえば自分のからだの中に空気を感じるような状態を作ることで初めて、相手の中に空気を想像することができる。自身の体感が深い想像をさせるのである。ここでいう空気を、気と呼んでも同じことである。私たちは、からだを整える手段として気(空気)を使うことができる。