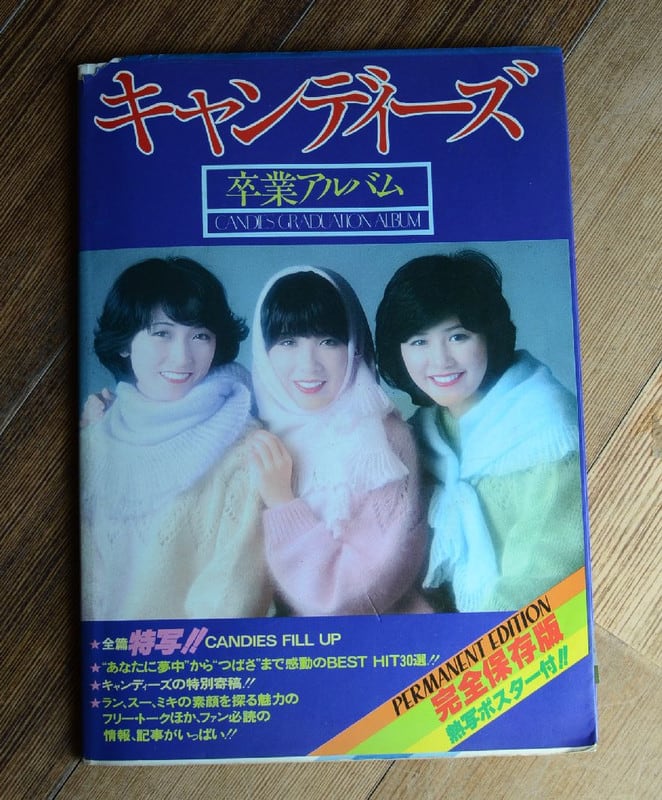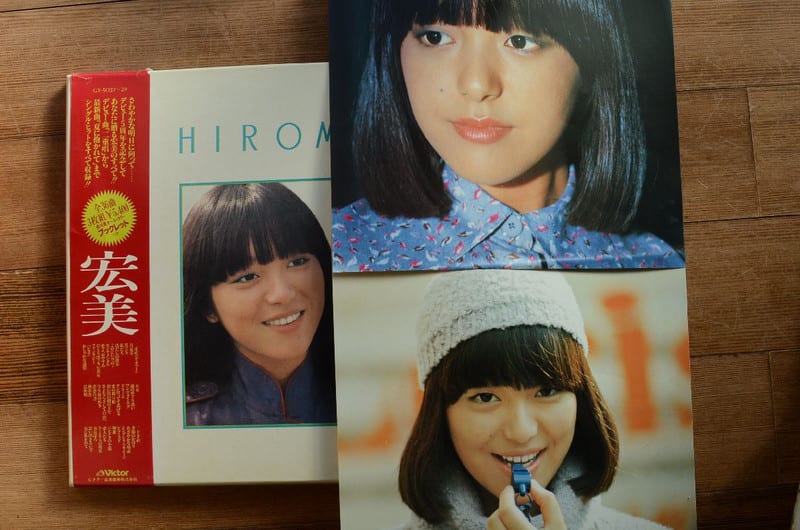谷村新司の「残照」を聴いていたのは、二十歳前後だっただろうか。
「久しぶりに散歩する 父と二人の遠まわり」
最近まで、この親子の間には生き方をめぐる確執があった。
「はるか昔に この人の背中で聞いた 祭りばやし」
父に背負われていたことを思い出した。
「“人生は祭りのよう” 何気なく貴方は言った」
人生は苦しく、働くばかりで、一時の楽しみしかない。それでさえ過ぎてしまえば、まぼろしの如くである。
「その後の 淋しさにたえる 勇気ができました」
「その後」とは父のなくなった後のこと。
「残り少ない 祭りの夜は」
父の人生が長くないことを暗示している。
「哀しくて 哀しくて 体全部が哀しくて 目頭が熱くなり思わず貴方を追いこした」
互いを理解できずに過ごして来た時間が、あまりにも長かったことが、哀しかった。
「見えていますか これが貴方の 見えていますか これが貴方の 夢を削った 夢をこわした背中です 震えているのは きっと きっと きっと・・・」
父は息子に夢を預けたが、それは叶わなかった。父の夢と息子の夢は違っていた。今にして思えば、父の進めた道を進んだ方が良かったのではという思いが少しはある。いまだに自分の人生に対する自信なども持てずにいる。
父の夢をこわした息子が初めて、父親に見せた背中は、遠い昔に祭りばやしを聞いた時の、父の背中と同じ背中だった。
そこには「夢」など何処にもなく、ただ男の背中が二つあった。