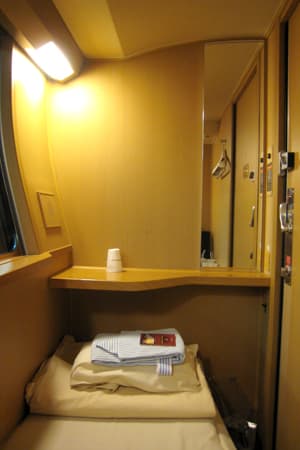駒沢オリンピック公園に行くのは、大学生の時以来だから、随分久しぶりの訪問です。大学生当時は、建物にさほど興味は抱かなかったのですが、今回の訪問で改めていい建物だったんだな~って再認識しました。1960年代らしいシンプルなデザインは何年たっても色あせてないんだなって感じました。
◆体育館
芦原義信の設計による建物です。東京オリンピックの際には、バレーボールの会場として使用されていました。

◆管制塔
この塔の設計も、体育館と同じく芦原義信です。木組みを思わせる構造がとても美しいですね。

◆陸上競技場
こちらの建物は、村田政眞です。大きくせりだしたキャンティレバーがとても印象的な建物です。シンプルですが豪快なイメージを作り出していますね。


◆2016年
オリンピック招致は成功するのでしょうか。。。

これだけ、景気が低迷してる中、招致が成功すれば内需拡大には役立つとは思いますが。。。どうなるでしょう
◆体育館
芦原義信の設計による建物です。東京オリンピックの際には、バレーボールの会場として使用されていました。

◆管制塔
この塔の設計も、体育館と同じく芦原義信です。木組みを思わせる構造がとても美しいですね。

◆陸上競技場
こちらの建物は、村田政眞です。大きくせりだしたキャンティレバーがとても印象的な建物です。シンプルですが豪快なイメージを作り出していますね。


◆2016年
オリンピック招致は成功するのでしょうか。。。

これだけ、景気が低迷してる中、招致が成功すれば内需拡大には役立つとは思いますが。。。どうなるでしょう