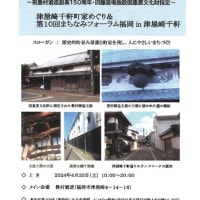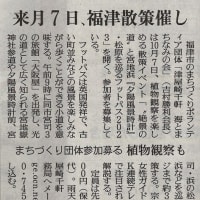写真①:江戸の風情が漂う〝小江戸・川越〟の町並み
=埼玉県川越市中央通で、2016年4月10日午前11時30分撮影
〈東京・町歩きスポット〉 17
:小江戸・川越
4月10日、東京の娘宅から娘婿の運転する車で首都高速道路を走り、埼玉県川越市中央通の〝小江戸・川越〟の町並み=写真①=を散策しました。
明治26年(1893年)の川越大火で、焼け残った建物が伝統的な蔵造りだったことから、蔵造り建築の店舗・「店蔵」が「江戸黒(えどぐろ)」と呼ばれる江戸の町並みを模した黒漆喰仕上げの壁で建てられたという。この「店蔵」造りの重厚な建物=写真②=30数軒が連なる町並みは、平成11年に国の「重要伝統的建造物群保存地区」に選定されています。

写真②:重厚な「店蔵」が中央通に軒を連ねる国選定「重要伝統的建造物群保存地区」
川越大火の際にも焼け残り、川越最古の蔵造りという「大沢家住宅」(重要文化財)=写真③=は寛政4年(1792年)、呉服太物を商う豪商・「近江屋」の西村半右衛門が建てた二階建てです。

写真③:川越最古の蔵造りの「大沢家住宅」
明治26年(1893年)に煙草卸商・小山文造が建てた蔵造りの町家だった「蔵造り資料館」(市指定文化財)=写真④=では、蔵造りの構造や意匠を見学できます。

写真④:煙草卸商が明治26年に建てた蔵造りの「蔵造り資料館」
館内の展示室には、江戸の大火と街づくりの解説パネル=写真⑤=もありました。

写真⑤:江戸の大火と街づくりの解説パネル
「蔵造り資料館」近くの中央通から入った横道にあり、川越の象徴として知られる鐘楼・「時の鐘」(市指定文化財)=写真⑥=を聞こうと訪ねましたが、耐震化工事中で1日4回(6時、正午、15時、18時)を告げる鐘の音は聞けず、残念でした。江戸時代初期の寛永年間に川越藩主・酒井忠勝が建築、明治時代の川越大火の直後に再建されたといい、記念写真を撮る観光客らの人気を集めています。

写真⑥:川越のシンボル・「時の鐘」を撮影する人たち
「時の鐘」から歩いて中央通に戻り、青緑色の塔屋が印象的な「埼玉りそな銀行川越支店」=写真⑦=が、目にとまりました。大正7年(1918年)に保岡勝也の設計で第八十五銀行の本店として、ネオ・ルネサンス様式で建てられ、国登録有形文化財です。

写真⑦:ネオ・ルネサンス様式の洋風建築の「埼玉りそな銀行川越支店」