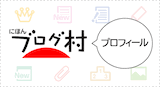20232=令和 5年 7月も、拙ブログを宜しくお願い致します。今月は 中旬頃に拙 PCの交代が予想され、為に例年より掲載頻度が減る可能性があるも、どうかご理解を賜れれば幸に存じます。
近年は 大きな風雨に伴う風水害の被害レベルが増大し、地方都市や郡部における住民高齢化などもあって、被災からの復興にも日時を要する様になった印象だ。その時 力を発揮するのが陸上初め自衛隊諸関係の各位。諸々の不祥事も生じ、それらへの強い対応も是非願う一方で、この所進み始めた同盟同志諸国の安保組織との連携も進められるべきと心得る。ここの所は米軍に続き、オーストラリア軍との連携深化が図られている様だ。以下 先日の産経新聞ネット記事を引用して、みて参ろうと思う。
「日・米・豪、災害対応でも連携 演習で多国間調整を訓練」
大規模災害の発生時、他国といかに連携し 効果的な初動対応につなげるか、6/26から始まった 自衛隊の 2023=令和 5年度統合防災演習(JXR)に今回、オーストラリア軍が初参加した。従来参加してきた在日米軍も含め、日・米・豪が築く強固な関係性は 安全保障環境が厳しさを増し、自然災害も激甚化するインド太平洋地域の「要石」となる。
6/28午後、防衛省内の会議室に自衛隊統合幕僚監部、在日米軍司令部、豪軍統合作戦本部のスタッフが集まった。発災後、米豪両軍が派遣する救援部隊と自衛隊の活動を振り分ける「多国間調整所」の運営訓練だ。調整では 被災空港の優先復旧順や、航空機・船舶での支援が到着する見込みなどを共有し、効果的な部隊展開を目指した。
今年度の JXRは、日向灘を震源とした 南海トラフ巨大地震による甚大な被害への対応が主眼だ。
東日本大震災の際は 内陸部から伸びる東西方向の道路を切り開き、津波で大きな被害を受けた沿岸部に救援隊や物資を輸送した。南海トラフ大地震の場合も 各地で同種の計画が立案されているが、想定される被災地は 関東から九州にかけて広範囲にまたがり、沿岸部や離党などで交通網が途絶し、孤立状態に陥るケースは避けられない。発災後には 警察、消防や国内外の民間団体が被災地に向かうが、自己完結可能な (自衛隊含む)軍隊の果たす役割は 初動対応で極めて大きい。
各国軍から救援部隊の派遣が見込まれるが、効果的な運用には調整が欠かせない。過去の JXRでは 在日米軍との 2国間で手順などの確認を行っていた。ただ 自衛隊では多国間の訓練が必要だとして、各国に参加を打診していた。豪軍の参加は、政府が 2022=令和 4年に閣議決定した国家防衛戦略で「日米防衛協力に次ぐ緊密な協力関係」と位置づけた日豪両国が 災害対応でも協調した形となる。
今回の運用訓練は諸外国の関心も高く、中国(大陸)など計 16カ国の在京武官が訓練を聴講した。JXRは 日本が被災国で他国を受け入れる想定だが、地震が多発し「台風銀座」でもあるインド太平洋地域の特性を踏まえれば 逆の展開もあり得る。多国間調整プロセスの洗練は 発災後の救援に大きなプラスとなる。特に日・米・豪 3カ国は装備・人員面で地域屈指の能力を有するだけに、連携が深まる意義は大きい。(引用ここまで)
日米両国間の 統合防災演習の動きは薄々存じてはいたが、恥ずかしながら JXRの名称は今回初耳。これに豪州も参加とは心強いと心得る。米・豪両国も、それは大災害と無縁とは参らないだろう。近年特に目立つのが、地域住民各位や農業関係に甚大な被害を及ぼす広域森林火災だろう。
各国が見舞われる災害の差異を踏まえた上で、より実態に見合った対応が叶う様 連携を強化し深めて頂きたいものだ。もう一つ。災害対応への動きは、参加各国の双方向性が大事。ある国が大災害に見舞われた折には、他の参加国が直ちに救援や復興へと動く態勢を 一応は平穏な今の内から積み重ねておく必要があるという事だろう。勿論我らが自衛隊も、必要とあらば速やかに対外救援に動ける様、法整備を含めての早めの準備を要しよう。
大災害向けの普段からの国際的連携は、結局は参加各国の安保に資する所も大きかろう。まずは米・豪両国と我国の連携から。そして インド太平洋地域の安定を図るなら、次は 4カ国関与の連携「クァッド」を構成するインド国の参加を図るべき。これでもまだ 前述地域の安全安定の為の基礎固めレベルだろう。
難しい所もあり、又 詳しい国名を挙げるのはここでは控えたいが、他に二心ない連携の志ある国ならば 更なる参加考慮も吝かではないとの姿勢を示しても良いかとも思う所だ。ここは JXRのこれからの進行を見守りたいと思う者だ。今回画像は少し前、当地北郊の JR東海道本線・尾張一宮駅構内で待機する、超長寸の線路、所謂「ロング・レール」輸送専用列車編成の威容をもう一度。