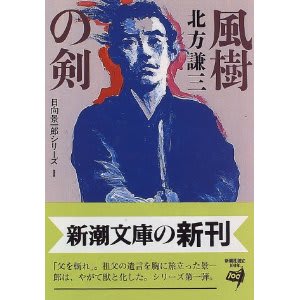
『風樹の剣』 北方謙三 ☆☆☆☆
友達から借りて読んだ、北方謙三の時代小説。そもそも北方謙三という人の小説を初めて読んだ。
時代小説というものをそもそもあまり読まず、山田風太郎、司馬遼太郎の新撰組もの、吉川英治、山本周五郎、あたりの(おそらくは)基本篇しか知らないが、やはり書き手によって世界観が大きく違うということが今回よく分かった。北方謙三のそれも、かなり独特である。
主人公は日向景一郎。もちろん、並ぶもののない剣客だけれども、もともとは臆病な性質であり、冒頭では刀を向けられて小便を漏らしたなんてエピソードすらある。この臆病なところがむしろ剣の天稟があるとされ、どんどん強くなり、しまいには人間離れした剣士になる。臆病さゆえに「負けない剣」であり、「生き延びる剣」である。だから自分より強い、本来なら勝てない相手にも「負ける」ことがない。という、なかなか隠微な匂いのする剣士で、性格もクールというよりむしろ暗めで、内気。ただし状況に応じていきなり獣になる。主人公だけれども決して正義漢などではなく、それどころか親切な人を斬り、優しくしてくれた女性を犯すことさえある。善悪を超越している。だからこの小説は、全然勧善懲悪ではない。ついでにいうとこの日向景一郎、なぜかメチャメチャ絶倫という設定である。
彼はすごい剣豪である祖父に日向流という、きわめて実践的な流派を仕込まれるが、この祖父が死の間際に言い残した「父を斬れ」という言葉を胸に、父を探して放浪する。なぜ父を斬らなければいけないのかよく分からないが、そうしないと何も始まらない、という、なんだか茫洋とした宿命観のようなものが根底にあるらしい。こういう世界観もまた独特で、本書を読むと侍というのは特に理由もなく斬り合いをするものらしい。いや、もちろん侍なりの理由はあるのだが、それはなんとなく「そこに山があるから登る」ではないけれども、目の前に他の侍がいるから斬る、みたいな、人命尊重の現代人感覚からすると限りなく無理由に近い理由だったりする。
たとえば終盤で日向景一郎は同じ日向流の使い手と知り合うが、知らぬ者同士でとりあえずまず斬り合いをし、そこで知己になってなんとなく仲良くなり、最後にまた斬り合いをする。よく分からない。フツーに友達になったら駄目なのだろうか。
それから、こういう壮絶な侍たちの世界なので、その強さ、剣客たちの斬り合いの凄まじさは想像を絶している。それはもう、ほとんど神秘的な営みである。向き合っただけで気が押し寄せてくるのが分かったり、自分より強いということが分かったりは当然で、剣を構えてじっと向き合っているだけで相手が死んだりする。斬りかかると自動的に負けて、斬りかかりたくなるのを我慢してじっとしていると勝つのである。あと、知らないうちに手首が飛んだり、首が離れたり、体が真っ二つになったりする。名人になると、じっと向き合っていて、上段から下段に知らないうちに構えが変わっていたりする。構えの変化が見えないのである。すご過ぎる。こういう常人離れした剣士たちの異常な世界を、本書はかなりのリアリティと説得力を持って描き出している。テンションの高さは相当なものだ。
言葉遣いも作家によって特色があり、本書でひっきりなしに出てくる「斬撃」という言葉は多分、初めて聞いた。描写は簡潔で、力強く、常に一抹の残酷さを湛えている。本書の世界は無情の世界であり、日向景一郎の歩む道は修羅の道である。とにかくどんどん人が死んでいく。
構成は基本的に父を探し歩く景一郎のロード・ノヴェルになっていて、旅の途上で出会う人々とのエピソードが入れ替わり立ち替わり語られる。それは女との出会いだったり、侍との斬り合いだったりする。男色の師弟、海辺の海女のエピソードなどが印象に残った。絶倫の景一郎と海女が夜中に海辺でセックスしまくるのだが、景一郎が海で獲った魚をすぐにさばいて刺身にして喰うところが旨そうだ。
そしてもちろん、最後には父と出会い、斬り合いをする。なぜ父と子が普通に再会を喜ばず、斬り合いをしなければならないかは先に書いた通りよく分からない。が、両者ともそこは納得しているらしい。まあそんな感じの、一種ストイックな妖気が漂う剣客小説だった。
友達から借りて読んだ、北方謙三の時代小説。そもそも北方謙三という人の小説を初めて読んだ。
時代小説というものをそもそもあまり読まず、山田風太郎、司馬遼太郎の新撰組もの、吉川英治、山本周五郎、あたりの(おそらくは)基本篇しか知らないが、やはり書き手によって世界観が大きく違うということが今回よく分かった。北方謙三のそれも、かなり独特である。
主人公は日向景一郎。もちろん、並ぶもののない剣客だけれども、もともとは臆病な性質であり、冒頭では刀を向けられて小便を漏らしたなんてエピソードすらある。この臆病なところがむしろ剣の天稟があるとされ、どんどん強くなり、しまいには人間離れした剣士になる。臆病さゆえに「負けない剣」であり、「生き延びる剣」である。だから自分より強い、本来なら勝てない相手にも「負ける」ことがない。という、なかなか隠微な匂いのする剣士で、性格もクールというよりむしろ暗めで、内気。ただし状況に応じていきなり獣になる。主人公だけれども決して正義漢などではなく、それどころか親切な人を斬り、優しくしてくれた女性を犯すことさえある。善悪を超越している。だからこの小説は、全然勧善懲悪ではない。ついでにいうとこの日向景一郎、なぜかメチャメチャ絶倫という設定である。
彼はすごい剣豪である祖父に日向流という、きわめて実践的な流派を仕込まれるが、この祖父が死の間際に言い残した「父を斬れ」という言葉を胸に、父を探して放浪する。なぜ父を斬らなければいけないのかよく分からないが、そうしないと何も始まらない、という、なんだか茫洋とした宿命観のようなものが根底にあるらしい。こういう世界観もまた独特で、本書を読むと侍というのは特に理由もなく斬り合いをするものらしい。いや、もちろん侍なりの理由はあるのだが、それはなんとなく「そこに山があるから登る」ではないけれども、目の前に他の侍がいるから斬る、みたいな、人命尊重の現代人感覚からすると限りなく無理由に近い理由だったりする。
たとえば終盤で日向景一郎は同じ日向流の使い手と知り合うが、知らぬ者同士でとりあえずまず斬り合いをし、そこで知己になってなんとなく仲良くなり、最後にまた斬り合いをする。よく分からない。フツーに友達になったら駄目なのだろうか。
それから、こういう壮絶な侍たちの世界なので、その強さ、剣客たちの斬り合いの凄まじさは想像を絶している。それはもう、ほとんど神秘的な営みである。向き合っただけで気が押し寄せてくるのが分かったり、自分より強いということが分かったりは当然で、剣を構えてじっと向き合っているだけで相手が死んだりする。斬りかかると自動的に負けて、斬りかかりたくなるのを我慢してじっとしていると勝つのである。あと、知らないうちに手首が飛んだり、首が離れたり、体が真っ二つになったりする。名人になると、じっと向き合っていて、上段から下段に知らないうちに構えが変わっていたりする。構えの変化が見えないのである。すご過ぎる。こういう常人離れした剣士たちの異常な世界を、本書はかなりのリアリティと説得力を持って描き出している。テンションの高さは相当なものだ。
言葉遣いも作家によって特色があり、本書でひっきりなしに出てくる「斬撃」という言葉は多分、初めて聞いた。描写は簡潔で、力強く、常に一抹の残酷さを湛えている。本書の世界は無情の世界であり、日向景一郎の歩む道は修羅の道である。とにかくどんどん人が死んでいく。
構成は基本的に父を探し歩く景一郎のロード・ノヴェルになっていて、旅の途上で出会う人々とのエピソードが入れ替わり立ち替わり語られる。それは女との出会いだったり、侍との斬り合いだったりする。男色の師弟、海辺の海女のエピソードなどが印象に残った。絶倫の景一郎と海女が夜中に海辺でセックスしまくるのだが、景一郎が海で獲った魚をすぐにさばいて刺身にして喰うところが旨そうだ。
そしてもちろん、最後には父と出会い、斬り合いをする。なぜ父と子が普通に再会を喜ばず、斬り合いをしなければならないかは先に書いた通りよく分からない。が、両者ともそこは納得しているらしい。まあそんな感じの、一種ストイックな妖気が漂う剣客小説だった。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます