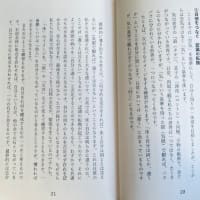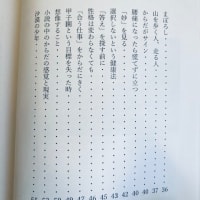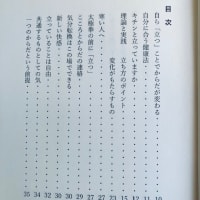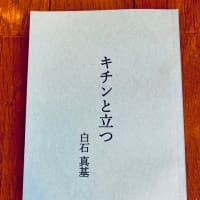荘子の「坐忘」について書かれた一文(大宗師篇)「堕肢體、黜聡明、離形去知、同於大通」は、「立つ」練習のときのイメージとしてそのまま使うことができる。
みぞおちから全身の力を抜いていくと、次第に肉体的感覚が薄くなる(堕肢體)。目や耳の感覚に頼らない(黜聡明・相対的な考えを排する)。肉体がなくなれば(離形)、雑念が湧かなくなる(去知)。これが自然の道に適う生き方であり、「立ち方」である。
スポーツや健康法などで「脱力」という言葉をよく聞くが、私はあまり使わない(初心者に説明するときやウェブ上では使うこともある)。なぜなら「立つ」練習に於いて、力が抜けるときの感じは、「脱力」よりも「解体」「くずれる」の方がはるかに近い(「墜」には「くずれる」と言う意味がある)。みぞおちを弛めた瞬間、全身の力は一気に抜けて行く。だからと言って、見た目には「ふにゃ」っとしたようには見えない(最低限必要な力は維持される)。むしろ崩れるのは、からだよりも意識の方である。意識はみぞおちを弛める時を境に、180度価値の違う別の世界へ行こうとするからだ。この意識の大転換は「解体(崩れる)」という言葉で表現されるにふさわしい。ダイナマイトで「ビルを解体する(崩す)」感じと似ていないこともないからだ。
「齊物論」の「郭象」の注釈に「嗒然解體(我を忘れ、からだを解く)」とある。「解」には「ほどく」、「からだを煩いから解き放つ」という意味があり、「我を忘れる」ことは、日常の緊張(凝り固まった意識)から解放されることだ。その実際は普段とモードが変わる(先の180度別の世界へ行く)ことであり、それはただぼんやりとボーすることではなく、相対的な物の観方から絶対的な物の観方に向かうことなのだ。
「(輪郭を)解体する」という言葉を、私はイメージの練習でよく使っていたから、この言葉を観たときに驚くとともに、我が意を得たりと嬉しくなった。
みぞおちから全身の力を抜いていくと、次第に肉体的感覚が薄くなる(堕肢體)。目や耳の感覚に頼らない(黜聡明・相対的な考えを排する)。肉体がなくなれば(離形)、雑念が湧かなくなる(去知)。これが自然の道に適う生き方であり、「立ち方」である。
スポーツや健康法などで「脱力」という言葉をよく聞くが、私はあまり使わない(初心者に説明するときやウェブ上では使うこともある)。なぜなら「立つ」練習に於いて、力が抜けるときの感じは、「脱力」よりも「解体」「くずれる」の方がはるかに近い(「墜」には「くずれる」と言う意味がある)。みぞおちを弛めた瞬間、全身の力は一気に抜けて行く。だからと言って、見た目には「ふにゃ」っとしたようには見えない(最低限必要な力は維持される)。むしろ崩れるのは、からだよりも意識の方である。意識はみぞおちを弛める時を境に、180度価値の違う別の世界へ行こうとするからだ。この意識の大転換は「解体(崩れる)」という言葉で表現されるにふさわしい。ダイナマイトで「ビルを解体する(崩す)」感じと似ていないこともないからだ。
「齊物論」の「郭象」の注釈に「嗒然解體(我を忘れ、からだを解く)」とある。「解」には「ほどく」、「からだを煩いから解き放つ」という意味があり、「我を忘れる」ことは、日常の緊張(凝り固まった意識)から解放されることだ。その実際は普段とモードが変わる(先の180度別の世界へ行く)ことであり、それはただぼんやりとボーすることではなく、相対的な物の観方から絶対的な物の観方に向かうことなのだ。
「(輪郭を)解体する」という言葉を、私はイメージの練習でよく使っていたから、この言葉を観たときに驚くとともに、我が意を得たりと嬉しくなった。