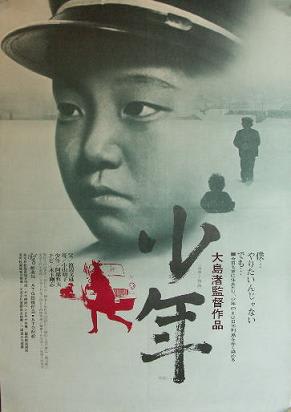*ネタバレにご注意ください!
松本清張といえば、先週、BSでかつてのTVドラマ「砂の器」が3日連続・全6話が再放映された。その最初の日に、青豆さんという方が「本日から再放映されています」というコメントをくださった。僕が映画「砂の器」の大ファンだったことをご存知だったのかなぁ、と思ったりしていますが、そのとおりで、僕はこの映画を、今でも自分が見た邦画の中でベスト1だと思っています。
TVドラマのほうは1977年に放映されたものだそうだ。しかし僕はこのドラマを見なかったと思う。というのも、その3年前に映画の「砂の器」にあまりに感動し、何度も何度も映画館に足を運んだことがあるからだ。その後原作を読んだけれど、正直言って期待はずれだった。映画とはかなりイメージが違っていた。映画のストーリーは、原作から大きく逸脱しながら卓越した映像と心に沁みる音楽で、素晴しいもう一つの「砂の器」の世界を作り出していた。
77年のTVドラマも、もし原作に忠実であれば、僕の中にある映画のイメージを壊されてしまう、という懸念があって、あえて見なかったのかもしれない。だから刑事・今西栄太郎役の仲代達也や、和賀英良役の田村正和は、僕の中では何の記憶もない。それで今回は37年ぶりのこのドラマ全6話を録画して、4日前から1話ずつ見て昨日第4話を見終えたところだ。話はいよいよ佳境に入ってきた。思ったよりも見ごたえがある。いつか、スマップの中居君が主演をしたTVドラマ「砂の器」はつまらなかったが、こちらはなかなか迫力がある。あと2話を今日と明日で見るのが楽しみだ。
映画の「砂の器」は、過去にテレビで放映されたが、この映画の重要な鍵となるのがハンセン氏病(つまり昔で言うライ病)であり、世間にはその病気に対する偏見が強かった。ライ病は気持ちの悪い病気で人に感染すると信じられていた。だからみんなライ病患者を毛嫌った。
映画はそういう時代を背景にしたもので、ライ病を患った本浦千代吉という石川県の田舎に住んでいた男性が、村から追われるような形で小学生の息子・秀夫を連れ、お遍路姿で物乞いの放浪の旅に出る。まだ子供の秀夫にとって辛い辛い放浪の旅だったが、島根県の亀嵩(かめだけ)という地にたどり着いた時、三木という情け深い巡査に会って保護され、父親は療養所へ入り、秀夫は三木巡査夫婦があずかる。…が、秀夫は家を飛び出し行方不明になる。
映画は、その何十年か後、退職した三木巡査が東京の蒲田操車場内で惨殺死体となって発見されるシーンから始まる。ベテランの今西刑事(丹波哲郎)と若手の吉村刑事(森田健作)の地道な努力で過去をさかのぼり、やがて1人の男性が捜査線上に浮かぶ。それはかつて三木巡査に助けられたが家出した息子・秀夫で、今や新進ピアニストとして脚光を浴び、大臣の娘と婚約してマスコミの寵児となった和賀英良であった。三木元巡査は伊勢参りに行った時、たまたま映画館に貼ってあった和賀英良の写真を見つけ、あの秀夫に間違いない…と、今や有名人となった彼を訪ねて東京へ行き「おまえの父が療養所でまだ生きている。ぜひ会いに行ってやってくれ。行かなければ首に縄つけででも連れて行く!」と迫るのである。忌まわしい自分の過去がバレるのを恐れた和賀英良は、かつての恩人を殺害する…という筋立てだ(ネタバレごめん)。
この映画の最大の見どころは、和賀英良が音楽界注目のコンサートで「宿命」という曲を弾くクライマックス場面。曲を背景に、お遍路姿で放浪する父と子の姿が、和賀英良の回想とシーンとして描写される。吹雪の中や桜の花が散る中、蝉が鳴く中、2人は延々と歩く。そのシーンには今でも思い出すと胸がつまる。ちなみに、原作にはそういう描写はない。
今見ているドラマは全6話という長時間ドラマなので、原作に忠実な部分があり、映画には出てこないが、原作では重要な役割を演じる人物が登場したりしている。しかし刑事が和賀英良にたどり着くまでのプロセスには、結末はわかっているのにハラハラする。さて、どんなラストシーンになるのか…? 久しぶりに見る「砂の器」に胸がざわざわ…である。
映画のほうはBSあたりでまた再放映をして欲しいのだが、以前放映されたのを見ていたら、刑事の丹波哲郎が「本浦千代吉は、ライ病だったのです」と捜査会議の場で説明するシーンの「ライ病」という言葉がカットされていた。差別用語なのか? これがキーワードなのに、カットされると、初めて見る人はワケがわからないと思う。それでもカットするくらいだから、今後テレビでは再放映されないのだろうと思う。ところで、今見ているドラマでは、父は「ライ病」ではなく、精神障害ということになっている。そこに限っては、放浪の旅に出る根拠がやや物足りないが、「ライ病」を使えないなら仕方ないのでしょうね。あの中居君の「砂の器」では、父はもはや病気でもなく、殺人犯の設定だった。それで各地を放浪とするというわけである(苦しまぎれだな~)。
ところで、朝日新聞に「be」という土曜日版があって、そのトップ面で「映画の旅人」という連載物があるけれど、偶然にも一昨日は「砂の器」が取り上げられていた。清張のこの複雑な原作を映画化することの難しさを、脚本の橋本忍と山田洋次がふり返る話などに思わず引き込まれた。朝日新聞を購読しておられる方で一昨日の「be」のその記事をまだご覧になっておられない方は、ぜひ読んでいただきたいと思います。
松本清張は当時この映画について「ぼくの小説の映画になったもので、いちばん出来がよかった」と語っていた…と「be」に載っていました。

12月20日の朝日土曜版「be」の第一面。