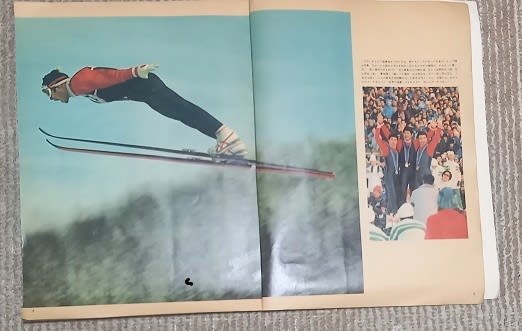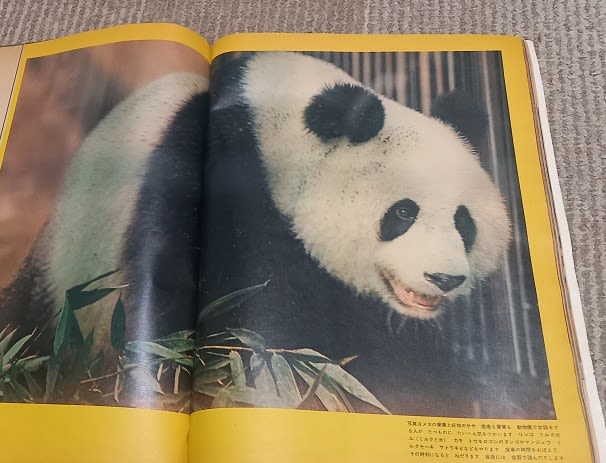カムチャッカ半島沖の巨大地震の影響で日本に大きな津波が…
…というニュース。
日本の広範囲に津波警報が出され、その日、7月30日のテレビはどのチャンネルもすべて津波のニュースが放送されていました。
結果は、恐れられていたほどの大きな被害はなかったのですが、
誰もが2011年の東日本大震災に伴う津波を思い浮かべて、日本中、特に沿岸地域の方たちは大きな不安に陥っていたことだと思います。
さて、
カムチャッカ、と言えば、平成の頃、細川たかしが歌った
「北緯五十度」という歌が思い浮かびます。
僕はこの歌が好きで、カラオケでもよく歌ったものです。
♪北緯五十度~ カムチャッカ沖だぁ~
こんな時にも心の中で
赤く燃えてる~ 命の恋よ~
というような歌でしたね。
だから、「カムチャッカ」が連呼されていたあの日は、
細川たかしの
♪カムチャッカ沖だぁ~
…のメロディがず~っと頭の中で響いていました。
ともあれ、「東日本大震災」の時のような被害につながらなかったことで一安心でした。
僕が小学生ぐらいの時だったか、南米のチリで起きた地震で、日本に大きな津波被害をもたらしたというニュースを覚えています。
あの広い広い太平洋の向こう側、いわゆる地球の裏側で起きた地震で発生した津波が日本にまで来た、ということ自体、小学生だった僕はまったく意味がわからなった。
自然災害というのは、本当に怖いです。
もうひとつ、カムチャッカで思い出すのは、これは自然災害でなく、
「大韓航空機撃墜事件」と呼ばれている大事件で、
1983年(昭和58年)9月1日に起きました。
この事件は、米のニューヨークの空港を出発し、アラスカのアンカレッジ国際空港を経由し、韓国ソウルの金浦(キンポ)空港に向かう大韓航空機が、ソビエト連邦の領空を侵犯したとして、ソ連軍に撃墜された事件です。
これで、大韓航空機の乗員と乗客合わせて269人全員が死亡。日本人も30人近く乗っていました。とても恐ろしい事件でした。
なぜそうなったかというと、
大韓航空機はアラスカからソウルに向かうのに、カムチャッカ半島の上を飛んでいたそうで、ソ連の防空レーダーがそれに気付き、ソ連軍機が攻撃したが失敗。
カムチャッカ上空を通過した大韓航空機はそのあとサハリンの上空を飛んでいたところで、ソ連軍に撃墜されてしまい、上記の通り269人全員が死亡した、という痛ましい事件でした。
これはむろん大ニュースになり、「カムチャッカ」や「サハリン」という地名がず~っと報道されていたのを覚えています。
そして、これは僕自身の話になるのですが、
この撃墜事件があったのが、1983年9月1日でした。その約1カ月後に、僕は自身で初めての海外旅行に出かけました。行く先はニューヨークで、観光ではなく、ニューヨークマラソンに出場するため。
そのマラソンツアーに申し込んで、妻と2人の息子たちに見送られ、大阪を出発。十数人のマラソンツアーの人たちと共に、まずは大阪の空港からソウルの金浦空港へ行き、そこで乗り換えてニューヨークへ行くのです。
そしてその飛行機が!
なんとまぁ、1カ月前に撃墜されたと同じ、あの大韓航空機でした。
コースも、ソウルからアラスカのアンカレッジ国際空港を経由してニューヨークへ行くというもの。つまり、撃墜された飛行機と、進行方向は逆ですが、まったく同じコースをたどるわけです。
つい先日、あれだけの大事件があった後ですから、まさか同じような領空侵犯はしないでしょうけど、マラソンツアーのメンバーの人たちと、
「怖い場所を飛ぶんやなぁ」
と、つぶやき合ったものです。
そしてサハリンの近く、さらにカムチャッカの近くを通る時は、僕たち全員「なんか、気持ち悪いなぁ」と不気味感に包まれました。
そして、アラスカのアンカレッジ空港に着き、そこで給油後、無事にニューヨークに着きました。マラソンも完走でき、そのあとは一人でニューヨークの街歩きを楽しんだりして、結果としてはいい思い出が作れました。
「カムチャッカ」
というと、その当時の記憶も鮮明によみがえってきます。