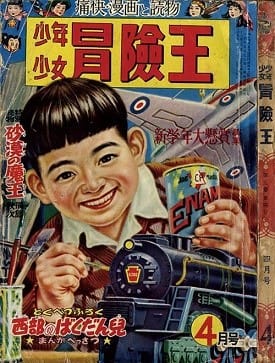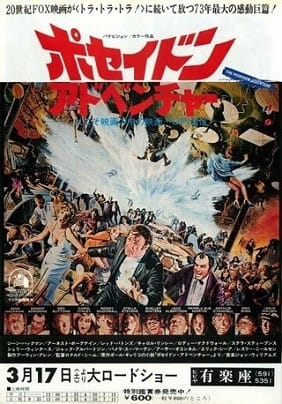「女性蔑視」の発言で物議をかもした東京五輪組織委員会の会長・森喜朗センセイがやっと辞任するようです。あれだけ世間…日本だけではなく海外からも激しく非難されたら、もう辞めるよりほかありませんよね。まったく今回の東京五輪はコロナやらこんな騒動やらと、ケチがつきまといますね。いったいどうなることやら。予定通りの開催は無理でしょうから、どこまで規模を縮小してやるのか?きっぱりと中止か延期にするのか? 僕は「きっぱり」のほうがいいんじゃないか、と思うんですけど。
さて、そんなことで世情が騒然としている中ですが…
昨日の10日、大阪府では私立高校の入試が行われました。モミィも大阪市阿倍野区にある高校を受験しました。早いものですね~。このブログを始めた時はモミィは2歳でした。それが今では高校の受験生ですからね。
で、昨日モミィは元気に「行ってきま~す」と家を出たので僕も妻もホッと胸をなでおろしました。もしも風邪を引いたり体調を崩したりしたらどうしよう、という心配をしていたのです。それには忌まわしい思い出がありましたから。
私立高校の受験といえば…
「あの日のこと」を思い出さずにはいられないのです。もう30年以上も前。長男(モミィのパパ)が私立高校を受験した時のことです。
長男は前夜から高熱を出し、妻が一晩中看病しました。しかし熱は下がらない。その日は大事な受験の日だからお医者さんにも行けない。受験する高校は大阪市天王寺区にある清風高校でした。かなり難しい高校で、体調万全で実力を発揮しても合格するかどうかわからない状況なのに、高熱に浮かされたまま、長男はフラフラの状態のままで家を出て行きました。
そして夕方に帰宅した時も熱は引いておらず、すぐに妻が布団に寝かせました。
「あんな心配だったことは、人生の中でもめったになかった」
と、今も妻は語り草にしています。
そんな状態だったのですが、信じられないことに合格しました。おかげで次に公立高校のほうは、当時の学区の中では難関校だった松原市にある生野高校にチャレンジすることができ、その結果も合格でした。松原市といえば僕は松原市役所に勤めていたので、生野高校はすぐ近くです。合格発表の日、職場の人たちが僕に「近くなんやから、息子さんの結果、見に行っておいで」と言ってくれたので、歩いて高校へ行き、合格発表の貼り紙を見て長男が合格をしたことを知り、思わずパチパチと手を叩きました。
まぁ、そんな悲喜こもごもの思い出がよみがえってきます。
それが、今度は長男の娘であるモミィが高校受験ですからね~。嫌でもあの時の長男の様子が目に浮かんできます。だからモミィも熱なんか出したら大変、と受験の日まで真剣に心配していたのです。
そういうわけで昨日の朝、モミィが元気に出て行ったのを見て、僕たちは心から安堵したわけです。正直なところ、結果はどうでもよろし。まずは元気に受験できたのだからそれで良し…。と、そんな気持ちで満たされていました。
さて、その昨日の夕方ですが。
「だだいま~」と帰宅したモミィに、「試験、どうだった?」と聞いたら、「あぁ~」と大声でため息をつき、「あかんわ。むずかしかったぁ~」と言って、あとはわけのわからないことをワイワイとわめいていました。だいたいモミィはよくしゃべるのですが、起承転結がないので、内容はさっぱり理解できないのです(笑)。
でも、僕も妻も、むろん合格すれば嬉しいに決まっていますが、たとえ結果がダメだったとしても、さほどガッカリしないと思います。繰り返しますが、元気に試験を受けられたことが何よりだったんですからね~。もう、あの長男の時のような思いは二度としたくありませんので。
合否の通知は明後日の13日(土)、速達郵便で送られて来るそうです。
結果は、またご報告しますね。