スクールカウンセラーの岩宮恵子さんって、読みがとても深くて、岡崎玲子さんのマンガ『陰陽師』をときほどいてくれたときには愕然とするほどでした。その岩宮さんが、
今までの本では、クライエントの自分についての深い語りからの発見やイメージ表現を通じて、「深層」で動きだした力が現実への変化につながっていくプロセスについて考えていた。しかし今回は「表層」でのエピソードにとことん注目することで見えてくるものを中心に考えてみたのである。何せ、「深層」に至らない…いや、もしかしたら「深層」などという内面がないのではないかと思わされるような思春期の子たちともこれから会い続けるためには、このようなことを考える必要を感じたのである。
思春期がある種の迷宮に入り込む時期であるのはいつの時代も変わらないが、トラッドな「ふつう」の思春期と今時の「フツー」の思春期の迷宮の違いについて、ここで一度立ち止まって考えておくことが、これからの自分の臨床を考えるうえで切実に必要だったのである。
として著述したのが『フツーの子の思春期 心理療法の現場から』(岩波書店)。
「思春期と超越体験」の章から抜粋します。
特別な能力や、才能があるわけでもなく、日常の適応を崩すほどの大きな困難を抱えることもない自分を受け入れていく……というプロセスは思春期の大切なテーマである。普通の人間に与えられた使命は、当たり前の日常を誠実に暮らすことなのだ。いつまでも「特別な自分」への憧れから自由に慣れないと、子のプロセスがとてつもなく困難になっていく。
思春期の子どもは、自分は異質な人間であり、特別な能力があるのだというイメージをもつことも多い。
中途半端な異能性や異質性の自覚が、日常と接点をもった現実的なレベルで投影されると、このように芸能界への憧れという形で出てくることがある。その一方で、この異能性や異質性の感覚が、問題行動の形をとって出てくることもある。自分の異質性に見合った言動を日常の中で行ってしまうと、それは大きく日常の常識を揺るがすことになるのだ。
思春期の異界体験は言語化が困難であるため、表面から見た言動の非常識さのほうに目も心も奪われがちである。しかし思春期の子どもをめぐるさまざまな問題に向かいあうときには、この世の常識的な観点を押さえた上で、このような視点を加えて理解の方向性を考えていくことが、大人の側には必要となるように思う。
本当にそうだなあ。それと、今は勉強やスポーツなどで「特別な存在でなくてはならない」という親などからの期待で苦しんでいる子も多いんじゃないかしら。
それはさておき、岩宮さんは
さまざまなことで悩み、葛藤したのが思春期の自分だった……という遠い記憶をもつ大人が、目の前の子どもを自分の思う「ふつう」の子の思春期のパターンに当てはめて考えようとしても、それが通用しない子が増えてきている。
とも書いているけど、岩宮さんがあげている“ふつうの思春期のパターンが通用しない子”の例って、私は「そうなんだよねー!」ととっても納得したんだわ。ウーン……。










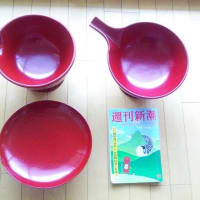



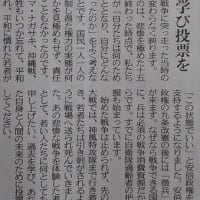
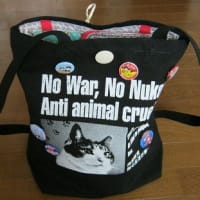
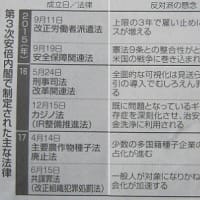




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます