自分のゼニコじゃないからさ、パーにしたって自分のふところが痛むわけじゃないもんねー。ウハウハやりたい放題。
えーとですね、10月30日の東京新聞朝刊の「こちら特報部」で、年金がギャンブルに使われていることが記事になってたんだけどね、もうねー、あたしら国民は安倍政権のおもちゃなのねって……。
国民年金って、これまでは「安全第一」で手堅く運営されてたんだけど、去年の10月に国内外の株式と外国債券を拡大したんだって。最初はアベノミクスでだよイケイケってぇ安倍政権のおかげで急激な株高と円安が進んで年金の運用は好調だったけど、世界的な株価暴落のせいで状況一変。
それなのに、というかそれだから、言うなれば負けを取り戻そうとして危険なギャンブルに走ってる状態らしい。アホやん。
記事から抜粋します。
●年金 やはり大幅損か 安倍政権危ういマネー術 高リスク「ジャンク債も」
安全性の高い国債を減らし、リスクの高い株式の比重を増やしてきた年金積立金管理運用独立行政法人(GPIH)。その7~9月期の運用成績は世界的な株安が響き、民間の試算によると、10兆円近くのマイナスになったもようだ。 株価が下がれば、損をするのは分かりきっていただけに、案の定である。しかも驚くなかれ、海外の低格付け(ジャンンク)債の投資にも手を出そうとしている。アベノミクスはギャンブルか。国民の老後を株価対策の犠牲にしていいのか。
低格付け債とは、投機的水準である「ダブルB」以下の債権を挿す。「ジャンク債」とも呼ばれ、財政危機にひんしているギリシャ国債も含まれる。高利回りが期待できるものの、債務不履行に陥る危険性もある「ハイリスク・ハイリターン型」の投資だ。
この先、株式を含めた運用の損失が拡大した場合はどうするのか。なんと(厚生労働省の)担当者は「保険料を上げて対応することも考えられる」と応えたのだ。
(塩崎厚生労働相は)「運用の責任は当然のことながら厚生労働大臣が負うことになっている」と発言しているが、結局のところ、運用の失敗のツケは保険料の引き上げという形で国民に回るわけだ。
(ちょっとアンタ、塩崎厚生労働相とやら、責任を負うってどうやるのさ。「責任をとって辞任します」ってか?
それだけで済むんだからいいよねー、十兆円はどうなるのさ。「やりたい放題、ラッキ!」ってか?!)
●「国民の老後」株価の犠牲 利益・損失 議論ないまま
経済評論家の山崎元氏は「株式投資の運用を増やせば十兆円儲けることもあるが、十兆円損することもあるのは当たり前。問題は、四半期で何兆円も損するような運用を年金でやっていいと、国民自らが決めたかどうかだ」と指摘する。
(日本総研上席主任研究員の)西沢氏も、国民の判断をあおぐことなく公的年金の運用方針が転換されたことを問題視する。「リスクを知った上で自ら決め、利益を享受し、損失をかぶるのが鉄則。選挙などを通じて議論されるべき極めて重大な政策が、国民をかやの外に置いて決まっている」
経済ジャーナリストの荻原博子氏は「安倍政権は株価さえ上がればいいと思っているからでしょう。年金が行き詰まったころにはもういないとタカをくくっている」と嘆く。
「株が上がれば半年後には経済が良くなるのが経済学の常識だが、だれも株価が実体経済を反映しているとは思っていない。東京五輪までは持ちこたえるかもしれないが、その後にひずみが一気に出る。塩崎厚労相は『責任を取る』と言っているが、どうやって取るつもりか』
だからさ、責任なんてだれも取らないんだよ、やったほうはさ。やめりゃーいいだけって思ってて、アーンド「人の噂も七十五日」で、ましてや日本人は忘れっぽいから逃げ切れると思ってるんだよ。逃がしちゃうほうにも責任があるけどねー。
年金資本にギャンブルして、原発で金儲けて、戦争でワクドキで遊んで金も儲けて、って、たっのしーねー安倍政権。
やばくなったらやめればいいし、海外に高飛びしちゃえばあとは知らないで済むもんねー。
で済ませちゃいけんでしょうが。 異議申し立てして当然じゃわ。
異議申し立てして当然じゃわ。















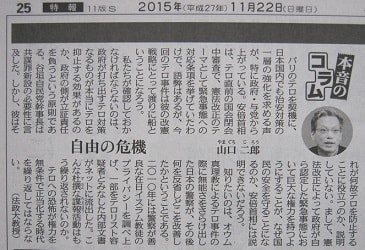





 異議申し立てして当然じゃわ。
異議申し立てして当然じゃわ。


