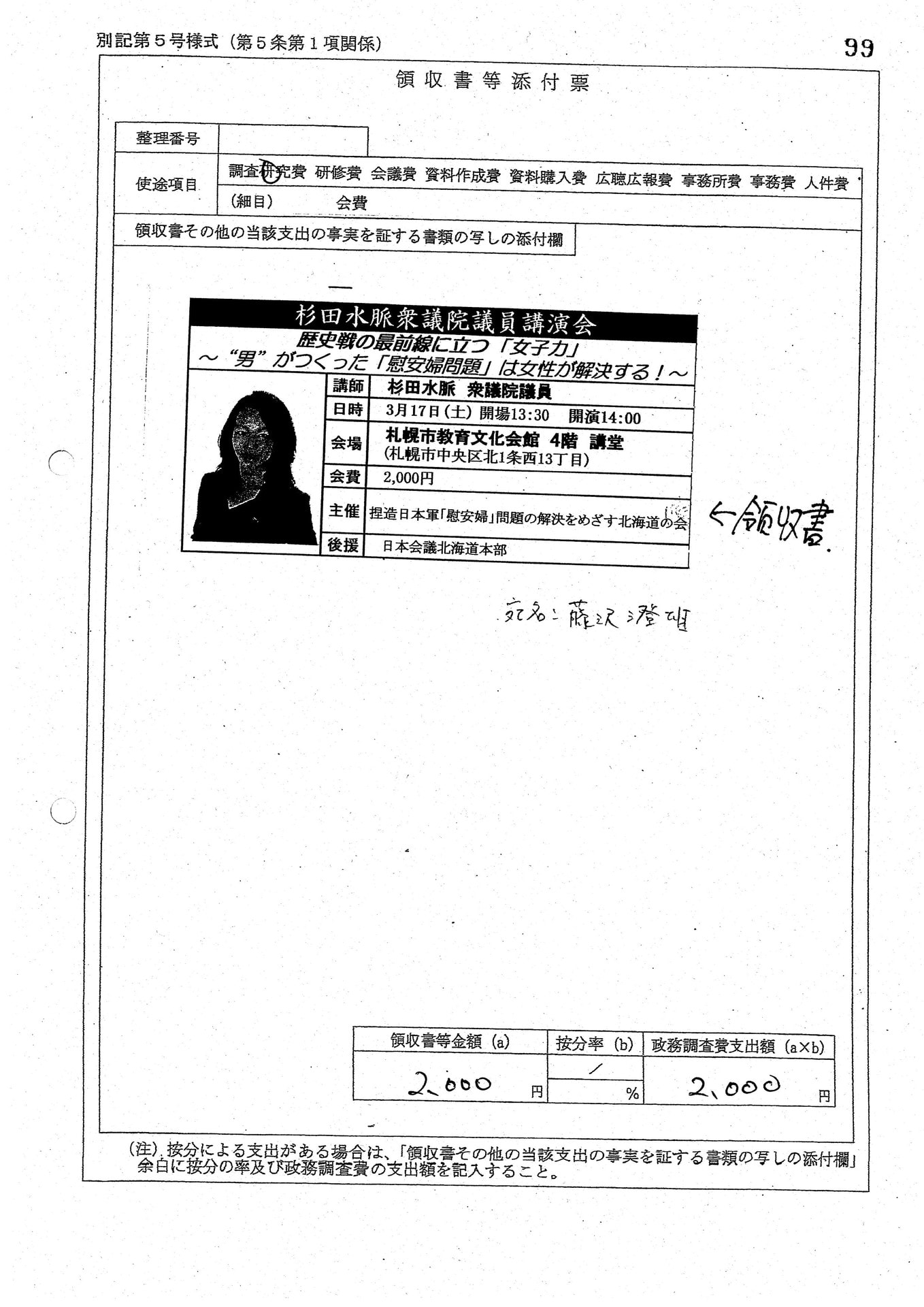JR運賃値上げで意見交換会(NHK北海道)
---------------------------------------------------
JR北海道が予定している運賃の値上げについて意見を交わす会合が開かれ、出席者からは、高校生の通学定期券など家庭に重い負担となる値上げには配慮が必要だという意見が出されました。
この会合は、JR北海道がことし10月に計画している運賃の値上げについて意見を交わすため、20日夜、開かれました。
この中で、出席した有識者は、値上げにあたってJRの経営努力が不十分なことや、新幹線の延伸に多額な投資を行いながら利用者に負担を強いることへの問題点などを指摘しました。
会場の出席者からは、特に高校生の通学定期券の値上げは家庭に重い負担となるため、配慮が必要だという意見が出されました。
運賃の値上げは、国土交通省の運輸審議会が認可すべきかどうか審査していて、来月1日には、札幌市で公聴会を開き、JR側やさまざまな立場の人たちから意見を聞く予定です。
---------------------------------------------------
21日に、札幌市内でJR北海道の運賃引き上げに反対する集会が開かれ、当研究会代表も「市民公述人」として意見を述べた。
今回の値上げは、JR北海道という企業の息の根を止めることになると思う。何年後になるかわからないが、そう遠くない将来にJR北海道の経営破綻のニュースが流れたときに「今思えば、あのときの大幅な値上げが運命の分かれ道だった」と振り返られることになる歴史的ターニングポイント。そんな値上げだと思っている。
というのも、旧国鉄が1976年に行った「運賃5割値上げ」が、最終的に国鉄の息の根を止めた先例があるからだ。
歴史的に見ると、国鉄ではこの前年、1975年にあの「スト権スト」があり、全国で8日間にわたり列車が止まった。このストの影響は大きく、特に貨物で荷主の国鉄離れを決定的にした。この大幅減収局面に慌てふためいた国鉄が、翌年に行ったのがこの5割という大幅値上げだった。
当時の国鉄は今のJR北海道経営陣と同じで「満員列車で都心の企業に通勤しているサラリーマンたちは、どうせ他の交通機関の選択肢を持たないのだから、大幅に値上げしても結局は今まで通り国鉄に乗るだろう」と考え、高を括っていた。しかし値上げの結果は悲劇的で、競合私鉄、地下鉄にどんどん客を取られていった。値上げする→客が離れる→さらに赤字がひどくなる→また値上げする……という死のスパイラルに入っていった国鉄は、その11年後にJRとなり、姿を消した。
当時の国鉄は赤字と言われながらも、高騰する建設費と不当に高い利払いを除けばそれほど財務状態は悪くなかった。単に国鉄という組織が列車を動かして得た利益で自分たちの生活費をまかなうという部分のみに着目すれば、赤字ではあっても国が救済できないと絶望視するような状況にはなかったのである。それなのに、5割の値上げが打撃となり、国鉄は以後、急坂を転がり落ちるように破局へ向かって突き進んでいった。
今回、JR北海道の値上げは最大3割にも及ぶもので、これほどの大幅なものはこのときの国鉄以来だろう。76年5割値上げの大失敗を思えば、JR北海道が同じ道をたどるであろうことは容易に想像できる。JR北海道が出している赤字額の7~10倍も稼いでいる会社が同じJRグループ内にあるのに(参考;
衆院予算委員会(2017年2月17日)における本村伸子議員の提示資料)、なぜその格差を埋める努力もせずに値上げなのか。首都圏の人たちも北海道産農産物を食べているのに、なぜそれを輸送するための除雪費も保線費用もJR北海道と道民の負担なのか。「鉄道を残したいなら残したいと思っている道民が金を出せ」というコメントがネット上には目立つが、それなら「北海道産のジャガイモやタマネギを首都圏に輸送するための費用は首都圏の食べたいと思っている者が払え」というのが当研究会の主張である。
なお、当研究会代表は、7月1日、国の運輸審議会が行うJR値上げに関する公聴会でも公述人として意見を述べることになっている。以下、公述書の内容を全文公開するので、是非皆さんもこの「格差」問題を考えていただきたいと思っている。
---------------------------------------------------------------------
公 述 書
北海道旅客鉄道株式会社(JR北海道)が申請した鉄道旅客運賃・料金の上限変更認可申請に対し、反対の立場で公述します。
今回の変更申請が認可されると、JRグループ発足以来、消費税の導入または税率改定を除いた運賃値上げは二度目となります。消費税の導入または税率改定を除くと、JR東日本・東海・西日本の3社は一度も値上げをしておらず、JR四国・九州も1996年に一度値上げを行ったのみで、以降は値上げをしていません。
旧国鉄では、幹線または地方交通線による格差はあっても地域による格差はない、全国統一の運賃制度を採用していました。旧国鉄の線路を継承させるため、国が政策としてJRグループ各社を発足させた経緯からも、地域間の運賃・料金の格差は最小限度に留めるべきであり、また鉄道をはじめとする公共交通は、ユニバーサルサービスとして全国どこでも同一のサービスなら同一の費用で提供されることが原則でなければなりません。
JR北海道の経営が苦境に追い込まれた根本原因は、そもそも旧国鉄を地域ごとのJRグループ各社に分割した際の切り分け方にあります。JRグループが発足した初年度、1987年度決算において、JR7社の営業収入全体に占めるJR北海道の割合はわずかに2.5%、JR四国は1%、JR九州も3.6%に過ぎませんでした。グループ発足初年度から、JRグループ7社の営業収入の43.1%をJR東日本だけで占めるほど、JR各社間の格差ははっきりしていました。JR北海道全体の営業収入は919億円で、この数字は当時の東京駅の収入より少なかったというデータもあります(注1)。
このような大きな経営上の格差は、グループ発足後30年経過した現在も改善されていません。2016年3月期決算において、JR北海道は483億円の損失を計上しているのに対し、JR東日本は3722億円の利益を上げています。JR北海道の赤字額の7.7倍に当たる数字です。JR北海道、四国、九州、貨物4社の赤字額の合計は741億円であるのに対し、本州の3社で最も利益の少ないJR西日本でも1242億円の利益を上げています(注2)。本州3社で最も経営基盤の弱い会社でも赤字4社をまとめて救済できるほど、同じJRグループ内で大きな格差ができていることを示しています。
国鉄改革に当たって、国は、JR北海道・四国・九州3社に経営安定基金を用意し、金利を赤字補填に充てさせる一方、本州の3社には旧国鉄の債務の一部を返済させる措置を講じました。しかし、その後の低金利・無金利政策により、JR北海道・四国両社は経営安定基金による赤字補填ができなくなる一方、本州の3社は債務負担が軽くなり、さらに利益が増加しました。低金利政策は、ただでさえ大きかったJRグループ会社間の格差をさらに拡大させることにつながったのです。
今回の上限運賃の変更申請は、JRグループ各社間に元々存在した格差に加え、その後の低金利政策によってさらに拡大した格差を是正するための努力を行うことなく、不利な条件の下に置かれてきた北海道の利用者だけに新たな負担を求めるものであり、また憲法が保障する法の下の平等にも反するものです。
農林水産省が公表している都道府県別食料自給率(2012年)によれば、北海道の食料自給率(カロリーベース)は200%である一方、東京は1%に過ぎません。北海道は他の地域の食料供給に大きな役割を果たしており、また食料品の多くはJRの貨物列車で道外に輸送されています。北海道経済連合会が公表した資料(注3)によると、道産タマネギは全体の67.6%、豆類50.0%、米類40.3%、馬鈴薯も39.1%がJRの貨物列車で道外に輸送されています。
2016年夏、北海道に4つの台風が上陸し、函館本線や石勝線などの重要路線が長期にわたって不通となりましたが、この際、首都圏でポテトチップスが姿を消し「ポテチショック」などと騒がれました。北海道に鉄道があることによって首都圏をはじめ日本全国にその恩恵が及んでいます。それにもかかわらず、北海道に貨物列車を走らせるための保線費用も、冬の除雪費も、既に日本一高い運賃を通じて北海道民がそのほとんどを負担させられているのは理不尽というほかありません。全国がその恩恵を受けている以上、北海道の鉄道を維持するための費用は全国であまねく負担すべきものです。
国鉄末期には貨物列車安楽死論も唱えられる中で、JRグループ発足以来30年間、JR貨物はそうした社会的逆風に耐え、懸命な企業努力を続けてきた結果、ここ数年は毎年100億円程度の経常利益を上げられるまでになりました。しかし、国が定めた指針により、JR貨物は貨物列車が走ることによって新たに必要となる費用(アボイダブルコスト)以外の負担をしなくてよいことになっており(注4)、また線路もほとんど旅客会社から借りることで貨物列車を運行しています。このため、年間483億円の赤字にあえぐJR北海道が、年間100億円の利益を出しているJR貨物を支えなければならないという別の面からの理不尽な状況も生まれています。
このような事実を総合すると、今、JR北海道の運賃・料金の値上げを通じて北海道民だけに新たな負担を求めることが国として適切な政策であるとは思えません。JRグループ各社の企業努力を超える格差が厳然と存在し、またその拡大が続いているこの間の社会経済情勢の変化を踏まえると、企業努力の範囲を超える格差に関してはその是正のための制度を導入することこそ国として、今行うべき政策であるというのが当研究会の基本的な立場です。新たな負担の導入や地方路線の廃止など利用者に不利益をもたらす措置は、これら最大限の政策的努力が行われた後に初めて検討されるべきものであり、こうした努力が十分に行われているとは考えられない現状での運賃・料金の改定申請に対しては、当研究会として反対を表明せざるを得ません。
以 上
注1)「JRの光と影」(立山学・著、岩波新書、1989年)P.75~76
注2)衆院予算委員会(2017年2月17日)における本村伸子議員の提示資料
注3)「JR北海道に対する当会のスタンスについて」(北海道経済連合会)P.7「主要農産品等の輸送機関別シェア」より
注4)「新会社がその事業を営むに際し当分の間配慮すべき事項に関する指針」(平成13年国土交通省告示第1622号)II-1-2に規定