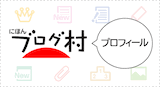2015=平成27年7月も第2週、昨日辺りより、梅雨の晴れ間に入って日中は暑くなって来た当地愛知である。南方にはこの時季の主役 梅雨前線と複数の台風が控え、悪くすると台風第11号が我国本土近くを通り、広い地域にて荒天となる事も懸念されるとか。今週後半は、可能なら日本海側へ遠出のつもりもあるので、空模様とも相談の上になりそうだ。
政治社会の事共は、内外共に難しい状況が続く。今年初来の懸案、安全保障法制案は、目玉とも言える、集団的自衛権の限定容認を巡って揺れ続け、今週後半に見込まれる衆院採決も難航しそうだ。政府与党の説明が依然不十分もさる事ながら、野党側の調査研究不足から来る無理解と無用な反発も目立つ。報道メディアにしても、本当に国民市民が理解できる様配慮した伝え方が不足している印象もある。十分な議論もそれは必要だろうが、「何が一番大事か」と言う、いわば真理の見極めの様な心がけが圧倒的に不足しているのではないか。この様な国民的課題の解決には、(左派野党の嫌う)挙国一致的な取り組み姿勢が是非とも必要だと心得る。それがあってこそ、国民的合意・コンセンサスも得られると愚考するのだが。
安保法制問題一つ取っても、与野党双方の主張合戦はあっても、必要な場面での一致協力が少な過ぎるのではないか。この様な無用な対立が多過ぎる様に見えるのは、やはり戦後教育の弊害と見て良いと思う。過日の新聞記事で恐縮だが、京都大名誉教授 佐伯啓思さんと地元紙 C新聞論説委員 大西 隆さんの対談記事後半を引用して、以下見て参りたい。両氏は対談の前半で、20世紀の先の大戦後、米合衆国主導で全世界的に強行されて来た、理工系など自然科学分野での統計数字や成果を崇拝する実証主義科学史観が、その尺度では測れない人文社会科学分野を脅かし続けて来た事実を指弾した上で、その悪弊が国際テロや凶悪な少年非行、遺伝子操作などの生命倫理の欠落などに繋がっている事を指摘されている。
------------------------------------------------------------------------
「なぜ『学問の危機なのか』~見えぬ『知』に真理宿る」
大西委員「本当の教養とは、幅広い知識を身につけ、英語を操ることではなく、自分なりの考え方や視座、価値観を獲得することと言えそうですね。そうすると、人文社会系の学問を冷遇する大学改革はむしろ害悪でしょう。」
佐伯教授「最も深刻だと思うのは、学問のグローバル競争の中で、人文社会系の知識には国籍があるということが忘れ去られていることです。情報としては確かに国境を越えますが、それが生まれた国の文化的な蓄積と無縁なはずがないのです。西欧の学問のベースには、古代ギリシャ以来の哲学やキリスト教的精神が伝統的価値として流れています。だからこそ、かつて明治の知識人たちは、慌ただしく輸入した西欧の科学や知識を日本の文脈にどう位置づけるのか、学ぶ意味はどこにあるのかと葛藤したと思います。
例えば、西欧化を訴えた福沢諭吉も『独立心』を唱え、古いものを捨て去ることが文明開化ではなく、日本人が自らの頭で考えられるようにならなくては無意味だという立場を取りました。留学組だった森 鴎外は武士道に回帰したし、夏目漱石は『(所謂エゴイズムでない)自己本位』という考えにたどり着いた。西田幾太郎が創始した京都学派はまさにそうですが、東洋思想と西洋哲学の融合に腐心したわけです。そうした背景には漢学や朱子学、儒教、仏教、神道といった精神風土、土着の文化や習俗の中で連綿と培われてきた日本人の感受性というものがあった。学問とは国や地域の歴史観や宗教観、自然観と切り離せないのです。」
大西委員「戦後、戦争イデオロギーとして封印されたり、米国の占領政策で放逐されたりしたものも多かった。でも、今は縮小時代です。生きる意味より生きる糧、教養より仕事が先決だという声も強いですね。」
佐伯教授「もちろん、お金は大事です。けれども、競争主義社会では自分が勝つことは相手の足を引っ張ることだし、年収1億円を稼いでも、家族離散とか子どもの非行とか痛い目に遭う場合もあるでしょう。すると1億円という統計的事実は残りますが、誰かの足を引っ張ったことや家族の悲劇は数値化されないから個人の責任、価値判断の誤りに帰されてしまう。それで幸せで豊かでしょうか。人々が将来共生していけるのでしょうか。戦前戦後を通じ、日本の学問の中心は欧米からの輸入ものばかりでした。日本人は自らの頭で考えるのでなく、欧米の文脈でできた知識や思想をあたかも自ら考えたように扱ってきたのです。グローバル競争が激しくなる中で、日本人の目に見えない感受性、心に響く学問を創り出さなくてはなりません。日本を故郷とする学問こそが最も必要とされる時代だと思うのです。」
----------------------------------------------------------------------
お二方の記事を拝見していると、要するに文教の分野でも、米国流の営利や成果志向とか、費用対効果に代表される効率志向などが、そうした価値観で成り立ってはいない哲学や宗教、人の良心などの分野までも判断基準として押し切ってしまい、為に精神的基盤が崩壊してしまった、正に「戦後の不幸」の姿が窺える。「力で押し切る」のは米合衆国の、他国支配の常套手段である。国際経済の「グローバリズム」も結局は「アメリカニズム」なのだ。正に日本国憲法第23条「学問の自由」が脅威に晒されていると言う事だ。
戦後の荒廃は、この「東京裁判」以来の、社会経済におけるアメリカニズムの暴力的蔓延と誤った自由主義、それに日教組こと日本教職員組合主導の「一見平和教育、実はお人好し仲良し教育」によって、明らさまに罷り通って来た。その結果、内政面では件数こそ減ったものの、深刻さの度合いを増した未成年者による凶悪事件や、こちらは一向に減らない深刻な飲酒交通事故などとか、外交面では朝鮮民主主義人民共和国による日本人拉致事件、それに過激な反捕鯨勢力による我国遠洋漁船攻撃事件などとなって表れているのである。余談かもだが、中高年層を標的にした、続発する特殊詐欺被害も、その様な不良教育と無縁ではないかも知れない。
中国大陸や大韓民国の国民市民は、外交などで相手国に訴え、アピールする「ロビー活動能力」に優れていると言われる。これなどは、小学生など早い段階から、自国民の子弟向けに、こうした活動の重要さを教えているからである可能性が高い。或いは、我国との歴史問題などが、一際異様に加熱する所があるのかも知れないが。「相手国に自国の事共を理解させ、外交を有利に運ぶ事は、大切だし面白い」事を、上手に教えているのだろう。実際に、米大陸に住む中国人や韓国人の団体が、犬を食用としている事実に、現地の動物愛護勢力が攻撃して来る事を抑え込むなど、一定の効果を上げている様だ。勿論、同時に愛国心も大いに教化している事だろう。そうであれば、親や教師がうるさく注意せずとも、子供達は自ずと勉強に打ち込むはずだ。我国の価値基準は、ここの所が首でも切られたかの様に抜け落ちてしまっている。「必ず国籍があり、その事を大切に思う心」が再建されない限り、我国の子供達や若者達は永遠に幸せにはなれないし、閉塞した社会状況も改善しないであろう。そしてそれを妨げているのは、勿論、日本国憲法や、今はないはずの1947=昭和22年教育基本法を後ろ盾にした「米国追随戦後レジーム」である事申すまでもない。残滓は大いに残っている。安倍政権も、その払拭を公約に揚げてはいるが、これは多くの国民市民の自覚がなくては遂げられない事と心得る。
今回画像は先月後半、滋賀県下の琵琶湖東岸で見かけた、美しい田園と、それを横目で応援する様に駆け抜ける、北方を目指す満載の貨物便の様子。この時季の琵琶湖辺りは、どこも田植えを終わった鮮やかな水田が魅力有です。この日本的な風情が永続して欲しいと願うのは、決して俺だけではないと思うのですが。