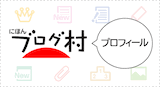コナサン、ミンバンワ!
一昨日、そして昨日と我国の学術研究の分野にての慶事が続いていますね。
世界的なこの分野の功績を上げた方に贈られる最高峰、ノーベル賞に一挙4名の我国の専門家が受賞の栄誉に輝きました。物理学賞3名、化学賞1名で内2名の方が当地名古屋のご出身。本当に大いなる誇りと喜びを感じます。
同時4名受賞は勿論史上初。モノ造り大国日本の再度の面目躍如であると共に、将来に繋がる研究開発の活性化への希望ともなり「まだまだ日本も、捨てたもんじゃない」との想いを新たにしている所です。
来年、そして将来へ向け、この後に続く受賞者をも望みたい所です。
さて、その様な希望の抱ける国のあり様の実現の為には、やはり対外関係が大切な訳ですが、これまでの祖国日本の姿勢にはどうも疑問符がつく所。今月初めのほぼ一週間に亘り取り上げて参った外交評論家 岡本行夫さんの文献「国の生きざま 選択の時」の今回は締めくくりの引用を行い、この問題のひとまずの区切りとしたく思います。
「前線の日本人の加重責任」
現在の世界の最大関心は「本来のテロとの戦争」であるアフガニスタンだ。40の国々がカルザイ同国大統領の要請に基づいて、軍隊や国境警備隊や警察を送り、国家再建に最も必要な「治安」の確保に当たっている。国家治安支援部隊=ISAFには各国から約53000人が参加している。
その中に日本の姿はない。「どうして来てくれないのか?」と訊くアフガニスタン市民に「その代わり、私たちがいるじゃないですか」と日本のNGOメンバーは答えるという。
1992=平成4年、カンボジアのプノンペンにて輝くような日本人青年に会った。同国に平和をもたらす夢を語った彼は「日本が国として何もできない分、我々が一生懸命やらなければならないんです」と力を込めた。名前は「中田厚仁」といった。国際連合ボランティアとしてカンボジアの平和構築のために働いていた同氏はその翌年、ゲリラの銃弾に倒れた。
平成初期の1990年代に世界一と日本が胸を張っていた援助額は、その後4割も減少し欧米主要国の後ろに下がった。ODAの現場では、プロジェクトの打ち切りが続いている。重荷を背負うのは一線の援助関係者だ。カネが足りなくなった分、カネのかからない技術協力を行うJICAの職員や青年海外協力隊員に余分な負担がかかっていないか?予算査定で経済協力費を切り込めば、その分現場に大きなしわ寄せがいく。
政府が平和維持に参加しないこと、経済協力からも後退することが、心ある援助関係者やNGOを悲壮な使命感に駆り立てていないか?
国家の責務を、個人の善意と勇気に頼るのは、国家の怠慢である!
「戦後最大の岐路」
世界が首をひねる理屈で、野党は補給艦をインド洋ソマリア沖から引き揚げようとしている。その時点で日本はテロとの戦いの最前線には一切関与しなくなり、世界の互助会から抜けることになる。自国商船隊の保護任務すら放り出して人任せにすることになる。
1991=平成3年の湾岸戦争への貢献をカネだけで済ませようとした日本は、世界の批判と冷笑を浴びた。今度はカネも出さない。自衛艦体派遣のほかにも政治意思さえあればできることは多くある。しかしやらない。
我々は首をすくめ、息をひそめてテロリストや略奪者たちが日本人や日本船を襲撃しないようにと念じる国家になるのか?日本にだけは何の災厄もかからないようにと祈り続ける国家となるのか?テロリストや略奪者が日本国憲法第9条を読んで反省し「今後日本には手を出さない」と言って来る日を信じるのか?
世界各地で活動する青年協力隊員やNGOの人々を見ていると、日本がそのような国家に落ちなければならない必然性はない。日本には勇気と使命感を秘めた若者が多くいる。彼らにどのような国家を引き継げるのか?
今我々は、国の生きざまを選択する戦後最大の岐路にいるのではないか?
この文献を拝読して、私も色々と考えさせられたものでした。岡本さんの叡智と蛮勇には、この場を借りて心よりの謝意と敬意を表します。
先の大戦後、祖国日本は確かに建前上は議会民主制を標榜する国となった。ただ国家の主権者は国民であり、強固な意思と責任において、国家意思を決定して参らなければなりません。残念ながらこれまでの一般国民にその様な意思や信念があったとは申せず、その事が今の国内の荒廃や混迷に繋がったのではと強く思います。
野党の多くが主張する衆議院の解散総選挙も良いが、その前に我々国民は、これからの対外面をも含めた国家意思の決定にどう関わって行くのか、その為の決意と自覚を大きく問われている様な気が致します。*(日本)*

一昨日、そして昨日と我国の学術研究の分野にての慶事が続いていますね。
世界的なこの分野の功績を上げた方に贈られる最高峰、ノーベル賞に一挙4名の我国の専門家が受賞の栄誉に輝きました。物理学賞3名、化学賞1名で内2名の方が当地名古屋のご出身。本当に大いなる誇りと喜びを感じます。
同時4名受賞は勿論史上初。モノ造り大国日本の再度の面目躍如であると共に、将来に繋がる研究開発の活性化への希望ともなり「まだまだ日本も、捨てたもんじゃない」との想いを新たにしている所です。
来年、そして将来へ向け、この後に続く受賞者をも望みたい所です。
さて、その様な希望の抱ける国のあり様の実現の為には、やはり対外関係が大切な訳ですが、これまでの祖国日本の姿勢にはどうも疑問符がつく所。今月初めのほぼ一週間に亘り取り上げて参った外交評論家 岡本行夫さんの文献「国の生きざま 選択の時」の今回は締めくくりの引用を行い、この問題のひとまずの区切りとしたく思います。
「前線の日本人の加重責任」
現在の世界の最大関心は「本来のテロとの戦争」であるアフガニスタンだ。40の国々がカルザイ同国大統領の要請に基づいて、軍隊や国境警備隊や警察を送り、国家再建に最も必要な「治安」の確保に当たっている。国家治安支援部隊=ISAFには各国から約53000人が参加している。
その中に日本の姿はない。「どうして来てくれないのか?」と訊くアフガニスタン市民に「その代わり、私たちがいるじゃないですか」と日本のNGOメンバーは答えるという。
1992=平成4年、カンボジアのプノンペンにて輝くような日本人青年に会った。同国に平和をもたらす夢を語った彼は「日本が国として何もできない分、我々が一生懸命やらなければならないんです」と力を込めた。名前は「中田厚仁」といった。国際連合ボランティアとしてカンボジアの平和構築のために働いていた同氏はその翌年、ゲリラの銃弾に倒れた。
平成初期の1990年代に世界一と日本が胸を張っていた援助額は、その後4割も減少し欧米主要国の後ろに下がった。ODAの現場では、プロジェクトの打ち切りが続いている。重荷を背負うのは一線の援助関係者だ。カネが足りなくなった分、カネのかからない技術協力を行うJICAの職員や青年海外協力隊員に余分な負担がかかっていないか?予算査定で経済協力費を切り込めば、その分現場に大きなしわ寄せがいく。
政府が平和維持に参加しないこと、経済協力からも後退することが、心ある援助関係者やNGOを悲壮な使命感に駆り立てていないか?
国家の責務を、個人の善意と勇気に頼るのは、国家の怠慢である!
「戦後最大の岐路」
世界が首をひねる理屈で、野党は補給艦をインド洋ソマリア沖から引き揚げようとしている。その時点で日本はテロとの戦いの最前線には一切関与しなくなり、世界の互助会から抜けることになる。自国商船隊の保護任務すら放り出して人任せにすることになる。
1991=平成3年の湾岸戦争への貢献をカネだけで済ませようとした日本は、世界の批判と冷笑を浴びた。今度はカネも出さない。自衛艦体派遣のほかにも政治意思さえあればできることは多くある。しかしやらない。
我々は首をすくめ、息をひそめてテロリストや略奪者たちが日本人や日本船を襲撃しないようにと念じる国家になるのか?日本にだけは何の災厄もかからないようにと祈り続ける国家となるのか?テロリストや略奪者が日本国憲法第9条を読んで反省し「今後日本には手を出さない」と言って来る日を信じるのか?
世界各地で活動する青年協力隊員やNGOの人々を見ていると、日本がそのような国家に落ちなければならない必然性はない。日本には勇気と使命感を秘めた若者が多くいる。彼らにどのような国家を引き継げるのか?
今我々は、国の生きざまを選択する戦後最大の岐路にいるのではないか?
この文献を拝読して、私も色々と考えさせられたものでした。岡本さんの叡智と蛮勇には、この場を借りて心よりの謝意と敬意を表します。
先の大戦後、祖国日本は確かに建前上は議会民主制を標榜する国となった。ただ国家の主権者は国民であり、強固な意思と責任において、国家意思を決定して参らなければなりません。残念ながらこれまでの一般国民にその様な意思や信念があったとは申せず、その事が今の国内の荒廃や混迷に繋がったのではと強く思います。
野党の多くが主張する衆議院の解散総選挙も良いが、その前に我々国民は、これからの対外面をも含めた国家意思の決定にどう関わって行くのか、その為の決意と自覚を大きく問われている様な気が致します。*(日本)*