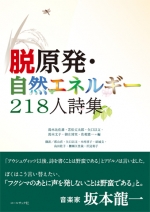verse, prose, and translation
Delfini Workshop
関西での対話(1) 虚子の戦中俳句(二)
2006-08-31 / 俳句
木曜日、 。朝が涼しくなった。夏特有の朝曇もなくいきなり晴れている。もう秋である。旧暦、閏7月8日。
。朝が涼しくなった。夏特有の朝曇もなくいきなり晴れている。もう秋である。旧暦、閏7月8日。
◇
虚子は、周知のように、愛媛県松山市の出身である。関西人である。当然、関西弁のイントネーションで日常会話をしていたものと思っていた。つまり、関東の言葉とは違う言葉で作句していたのだろう。そう思っていた。今度の旅行で、愛媛出身の友だちに会った。彼に、虚子の句をいくつか示して、実際に松山弁で朗読してくれるように頼んでみた。
驚いたことに、関東のイントネーションと同じなのである。友人の解説によれば、松山弁というのは、語尾に特徴があり、かなり、暖かい響きを持った言葉だという。実際、話してくれたのを聞くと実に素朴で、聞いている方は、リラックスしてくるような響きを持っている。関西弁とは、明らかに異なる言葉だった。
ここで、今回、言葉について感じたことをちょっと述べておくと。関東の言葉は、もともとローカルな言葉の集合体で、江戸下町の言葉や山の手言葉、北関東言葉に横浜系の言葉などが入り混じっている。こうした言葉をベースに「標準語」という人工言語ができている。たとえば、大阪で「標準語」で何か店員の女の子に頼む。あるいは、大阪のホテルで案内してくれた従業員の女の子と「標準語」で少し話す。あるいは、芦屋の谷崎潤一郎記念館の受付で、男性の係りの人と「標準語」で言葉を交わす。こうしたとき、相手は、きれいな「標準語」で返事をしてくれるものの、一瞬ではあるが、話しかけられた方は、「ひるむ」。こういう経験はないだろうか。この一瞬の「ひるみ」は、なんだろう。少なくとも、関東圏では、この一瞬の「ひるみ」はない。これは、「標準語」を話したとたん、関西では、何かが起動するのだと思う。それは、たぶん、「権力の響き」なのだ。「標準語」の裏には、近代化、国家、権力といったものが付着している。「標準語」との差異が大きい言語ほど、「権力の響き」が大きい。ここから、導かれる結論は、関西ではできるだけ関西弁でコミュニケーションすべきだということではないか。もちろん、それができれば、の話であるが。こうした言語の基本的な構図は、英語とその他言語の関係やマジョリティとマイノリティの言葉の関係にも言えるはずである。こんなことを、芦屋の谷崎潤一郎記念館の喫茶室で、昨日の六甲の友人と話しこんだ。彼は、関東弁が関西で嫌われるのは、この「権力の響き」と関係があると同意してくれた。
◇
さて、虚子である。昭和12年(1937年)には、12月10日に南京で大虐殺が始まる。その前後の句を見てみよう。
1月23日 マスクして我と汝でありしかな
4月9日 花の如く月の如くにもてなさん
6月5日 老い人や夏木見上げてやすらかに
7月24日 月あれば夜を遊びける世を思ふ
8月8日 夏山やよく雲かゝりよく晴るゝ
10月15日 老人と子供と多し秋祭
11月8日 秋天に赤き筋ある如くなり
11月14日 静かさに耐へずして降る落葉かな
12月8日 砲火そゝぐ南京城は炉の如し
12月8日 かゝる夜も将士の征衣霜深し
12月9日 東京朝日新聞社より南京陥落の句を徴されて 寒紅梅馥郁として招魂社
12月11日 女を見て連れの男を見て師走
12月24日 冬麗ら花は無けれど枝垂梅
12月25日 行年や歴史の中に今我あり
■今では、しきりに、反戦キャンペーンを展開しているが、昭和12年の段階では、朝日新聞は、完全な好戦新聞だったことがわかる。それに応えて、虚子も戦争協力の俳句を詠んでいる。12月25日の句も、勝者あるいは支配者の歴史の中に自分がいるという句であろう。南京大虐殺の実態がわかるのは、戦後なのだから、情報統制化の昭和12年では、やむを得ないという見方もあるかもしれない。だが、12月8日の句に出てくる「征衣」という言葉や9日の寒紅梅の句に見られるように、中国大陸の征服に、祝賀ムードがあったことは確かだろう。「アジアの解放」というスローガンの実態とは「征服の喜び」に近かったのではあるまいか。こうした戦争協力の句に感じるのは、著しい「他者への想像力の欠如」である。
 。朝が涼しくなった。夏特有の朝曇もなくいきなり晴れている。もう秋である。旧暦、閏7月8日。
。朝が涼しくなった。夏特有の朝曇もなくいきなり晴れている。もう秋である。旧暦、閏7月8日。◇
虚子は、周知のように、愛媛県松山市の出身である。関西人である。当然、関西弁のイントネーションで日常会話をしていたものと思っていた。つまり、関東の言葉とは違う言葉で作句していたのだろう。そう思っていた。今度の旅行で、愛媛出身の友だちに会った。彼に、虚子の句をいくつか示して、実際に松山弁で朗読してくれるように頼んでみた。
驚いたことに、関東のイントネーションと同じなのである。友人の解説によれば、松山弁というのは、語尾に特徴があり、かなり、暖かい響きを持った言葉だという。実際、話してくれたのを聞くと実に素朴で、聞いている方は、リラックスしてくるような響きを持っている。関西弁とは、明らかに異なる言葉だった。
ここで、今回、言葉について感じたことをちょっと述べておくと。関東の言葉は、もともとローカルな言葉の集合体で、江戸下町の言葉や山の手言葉、北関東言葉に横浜系の言葉などが入り混じっている。こうした言葉をベースに「標準語」という人工言語ができている。たとえば、大阪で「標準語」で何か店員の女の子に頼む。あるいは、大阪のホテルで案内してくれた従業員の女の子と「標準語」で少し話す。あるいは、芦屋の谷崎潤一郎記念館の受付で、男性の係りの人と「標準語」で言葉を交わす。こうしたとき、相手は、きれいな「標準語」で返事をしてくれるものの、一瞬ではあるが、話しかけられた方は、「ひるむ」。こういう経験はないだろうか。この一瞬の「ひるみ」は、なんだろう。少なくとも、関東圏では、この一瞬の「ひるみ」はない。これは、「標準語」を話したとたん、関西では、何かが起動するのだと思う。それは、たぶん、「権力の響き」なのだ。「標準語」の裏には、近代化、国家、権力といったものが付着している。「標準語」との差異が大きい言語ほど、「権力の響き」が大きい。ここから、導かれる結論は、関西ではできるだけ関西弁でコミュニケーションすべきだということではないか。もちろん、それができれば、の話であるが。こうした言語の基本的な構図は、英語とその他言語の関係やマジョリティとマイノリティの言葉の関係にも言えるはずである。こんなことを、芦屋の谷崎潤一郎記念館の喫茶室で、昨日の六甲の友人と話しこんだ。彼は、関東弁が関西で嫌われるのは、この「権力の響き」と関係があると同意してくれた。
◇
さて、虚子である。昭和12年(1937年)には、12月10日に南京で大虐殺が始まる。その前後の句を見てみよう。
1月23日 マスクして我と汝でありしかな
4月9日 花の如く月の如くにもてなさん
6月5日 老い人や夏木見上げてやすらかに
7月24日 月あれば夜を遊びける世を思ふ
8月8日 夏山やよく雲かゝりよく晴るゝ
10月15日 老人と子供と多し秋祭
11月8日 秋天に赤き筋ある如くなり
11月14日 静かさに耐へずして降る落葉かな
12月8日 砲火そゝぐ南京城は炉の如し
12月8日 かゝる夜も将士の征衣霜深し
12月9日 東京朝日新聞社より南京陥落の句を徴されて 寒紅梅馥郁として招魂社
12月11日 女を見て連れの男を見て師走
12月24日 冬麗ら花は無けれど枝垂梅
12月25日 行年や歴史の中に今我あり
■今では、しきりに、反戦キャンペーンを展開しているが、昭和12年の段階では、朝日新聞は、完全な好戦新聞だったことがわかる。それに応えて、虚子も戦争協力の俳句を詠んでいる。12月25日の句も、勝者あるいは支配者の歴史の中に自分がいるという句であろう。南京大虐殺の実態がわかるのは、戦後なのだから、情報統制化の昭和12年では、やむを得ないという見方もあるかもしれない。だが、12月8日の句に出てくる「征衣」という言葉や9日の寒紅梅の句に見られるように、中国大陸の征服に、祝賀ムードがあったことは確かだろう。「アジアの解放」というスローガンの実態とは「征服の喜び」に近かったのではあるまいか。こうした戦争協力の句に感じるのは、著しい「他者への想像力の欠如」である。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
関西での対話(1) 虚子の戦中俳句(一)
2006-08-30 / 俳句
水曜日、 のち
のち 。旧暦、閏7月7日。
。旧暦、閏7月7日。
昨夜、関西から戻った。梅田、芦屋、三田とめぐって、新大阪より帰還。面白かった。三田で5年ぶりに会った友だちが、白髪になっていて驚いた。もう、そんな歳になったのか。
梅田、芦屋、三田と移動して、場所のインパクトが一番強かったのは、芦屋だった。これまでも何度か行っているが、この歳で再訪すると、いろいろ感じるところがある。芦屋は、すでに瀬戸内だということ。陽光が関東とはまったく違う。背後に六甲山系、前面に海。梅田から向かうと、空気がいいのがよくわかる。
この地域の天気の表現が面白い。関東人のぼくが、「晴れ」と認識する天気を、阪急六甲に住む友人は「曇り」と表現する。なぜだと聞くと、「雲があるやん」。確かに、空には、秋の雲が遠くたなびいている。午後になって、本格的に曇ってきた。「これなら、関東でも立派な曇りだ」と言うと、件の友人は「雨が降りそう」と表現する。この地域では、天気表現が一歩前倒しなのである。それだけ、陽光に恵まれているのだ。
天気に驚いたというのは、たぶん、違う。空気の清澄さと陽光の美しさが、金の力として(あるいは権力の力として)現象してくる事態に圧倒されたと言った方がいい。ここでは、空気も光も個人の財なのだ。芦屋は、有名な高級住宅街である。美術館かと見まごうような民家が、芦屋川に沿って並ぶ。住宅街の道には、車も通らず人もいない。閑静そのものである。近くの著名なフランスレストランの駐車場には、平日の午後から、高級外車が並んでいる。
こういう住宅街の真只中に「虚子記念文学館」はある。虚子は、こんなことを述べている。「能楽の主人公が舞を舞うことによって成仏するように、人には人生の苦しみから救われる舞のような何ものかが必要である」人生の苦しみ。虚子よ、おまえ、恥ずかしくないか、芦屋に鎮座して。この文学館では、おばさまたちが、平日の昼間から「お句会」を開いている。
◇
まったく久しぶりに「のぞみ」に乗った。行き帰りには本を読もうと思ったのである。頻繁に乗っていたころには、気がつかなかったが、新幹線のスピードは異常である。これは、旅でもなんでもない。単なる物理的な移動である。速さには、タイム・イズ・マネーの思想が染み込んでいる。この社会では、マネー以外の価値は、もうほとんど機能していないのではないか。
行きに「虚子五句集」(岩波文庫)を読む。おもな事件の前後の句を調べてみた。
昭和11年(1936年)2月26日 2.26事件
1月2日 鴨の中の一つの鴨を見てゐたり
1月4日 枯れ果てしものの中なる藤袴
1月8日 枯荻に添ひて立てば我幽なり
4月19日 宝石の大塊のごと春の雲
6月11日 濁り鮒腹をかへして沈みけり
7月26日 航海やよるひるとなき雲の峰
9月6日 一夜明けて忽ち秋の扇かな
10月1日 我が息を吹きとゞめたる野分かな
10月19日 掛稲に山又山の飛騨路かな
11月21日 御神籤の凶が出でたる落葉降る
11月21日 人に恥ぢ神には恥ぢず初詣
■全体に時代との関わりは直接見えてこないが、最後の2つの句になると、暗い時代への予感のようなものも感じられる。その意図があるかどうかは別にして。
 のち
のち 。旧暦、閏7月7日。
。旧暦、閏7月7日。昨夜、関西から戻った。梅田、芦屋、三田とめぐって、新大阪より帰還。面白かった。三田で5年ぶりに会った友だちが、白髪になっていて驚いた。もう、そんな歳になったのか。
梅田、芦屋、三田と移動して、場所のインパクトが一番強かったのは、芦屋だった。これまでも何度か行っているが、この歳で再訪すると、いろいろ感じるところがある。芦屋は、すでに瀬戸内だということ。陽光が関東とはまったく違う。背後に六甲山系、前面に海。梅田から向かうと、空気がいいのがよくわかる。
この地域の天気の表現が面白い。関東人のぼくが、「晴れ」と認識する天気を、阪急六甲に住む友人は「曇り」と表現する。なぜだと聞くと、「雲があるやん」。確かに、空には、秋の雲が遠くたなびいている。午後になって、本格的に曇ってきた。「これなら、関東でも立派な曇りだ」と言うと、件の友人は「雨が降りそう」と表現する。この地域では、天気表現が一歩前倒しなのである。それだけ、陽光に恵まれているのだ。
天気に驚いたというのは、たぶん、違う。空気の清澄さと陽光の美しさが、金の力として(あるいは権力の力として)現象してくる事態に圧倒されたと言った方がいい。ここでは、空気も光も個人の財なのだ。芦屋は、有名な高級住宅街である。美術館かと見まごうような民家が、芦屋川に沿って並ぶ。住宅街の道には、車も通らず人もいない。閑静そのものである。近くの著名なフランスレストランの駐車場には、平日の午後から、高級外車が並んでいる。
こういう住宅街の真只中に「虚子記念文学館」はある。虚子は、こんなことを述べている。「能楽の主人公が舞を舞うことによって成仏するように、人には人生の苦しみから救われる舞のような何ものかが必要である」人生の苦しみ。虚子よ、おまえ、恥ずかしくないか、芦屋に鎮座して。この文学館では、おばさまたちが、平日の昼間から「お句会」を開いている。
◇
まったく久しぶりに「のぞみ」に乗った。行き帰りには本を読もうと思ったのである。頻繁に乗っていたころには、気がつかなかったが、新幹線のスピードは異常である。これは、旅でもなんでもない。単なる物理的な移動である。速さには、タイム・イズ・マネーの思想が染み込んでいる。この社会では、マネー以外の価値は、もうほとんど機能していないのではないか。
行きに「虚子五句集」(岩波文庫)を読む。おもな事件の前後の句を調べてみた。
昭和11年(1936年)2月26日 2.26事件
1月2日 鴨の中の一つの鴨を見てゐたり
1月4日 枯れ果てしものの中なる藤袴
1月8日 枯荻に添ひて立てば我幽なり
4月19日 宝石の大塊のごと春の雲
6月11日 濁り鮒腹をかへして沈みけり
7月26日 航海やよるひるとなき雲の峰
9月6日 一夜明けて忽ち秋の扇かな
10月1日 我が息を吹きとゞめたる野分かな
10月19日 掛稲に山又山の飛騨路かな
11月21日 御神籤の凶が出でたる落葉降る
11月21日 人に恥ぢ神には恥ぢず初詣
■全体に時代との関わりは直接見えてこないが、最後の2つの句になると、暗い時代への予感のようなものも感じられる。その意図があるかどうかは別にして。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
いまここに在ることの恥(2)
2006-08-27 / 本
日曜日、 。旧暦、閏7月4日。
。旧暦、閏7月4日。
来週、急に関西に行くことになって、その準備に追われている。医療奉仕に海外に行っていた友だちが帰国するので、みんなで集まることになった。
◇
『いまここに在ることの恥』のもう一つのテーマである「現代のファシズム」について述べる前に、「表現と時代との倫理的な関係」について、考えてみたい。
辺見さんは、1937年の南京大虐殺、1938年の国家総動員法公布という時代に注目して、この暗い時代に、たとえば、辺見さんの好きな太宰は何を書いていたかを問う。太宰は、「満願」という美しい掌編小説を書いていた。辺見さんは、次のように書いている。
「なるほど、うまいなあと私も感じ入る。けれども、うまいぶんだけ、ひっかかる。考えこんでしまう。状況と表現。状況と内面。時代と表現。そのことが、ひっかかってしょうがない。1938年の問題ではあるのですが、2006年のひっかかりとしても、これはある。もちろん、いかなる状況下にあっても『満願』のような物語はありうるし、作品として成立するでしょう。あるいはミニマムな人の常として、表現に値せずとはいえない。たぶん、そういってはいけない。だが、ひっかかる。大いにひっかかる。きょういいたいことの大事な点がここにかかわる。それはやはり恥にかかわるのです。(中略)いまは1938年ではありません、ですが、状況と表現の関係、ないしは時代と個の立ち居ふるまいの関係に苦しむのは無意味とはいえないと私は思うのです。私たちは『満願』を一幅の美しいスケッチとして読むことができます。しかし、『満願』の絵の近景や遠景に、国家総動員法や南京代虐殺といった光の屈折や血の臭いを想像し、必死で助けを求めただあろうはるかな遠音に耳をすますとき、時代を超えて恥はからだの内側から青痣のように浮きでてくるのです」(辺見庸著『いまここに在ることの恥』pp.147-148)
この本を読んで、まっさきに気になったのは、この箇所だった。二つの意味で気になった。一つは、ここに述べられているように、表現と時代の関係について。もう一つは、この本が描く世界と表現の関係について。
最初に述べたように、この本の読後感は暗褐色である。この本が描く世界の現実の中に、詩や俳句は居場所を持っているのか、というのが始めに感じた疑問だった。詩については、いくつも拮抗する作品や詩人をあげることがすぐにできる。たとえば、石原吉郎、鳴海英吉、トラークル。二次大戦を知らない賢治の作品の中にも、拮抗する作品は多くある。
夜の湿気と風がさびしくいりまじり
松ややなぎの林はくろく
そらには暗い業のはなびらがいっぱいで
わたくしは神々の名を録したことから
はげしく寒くふるへてゐる
宮沢賢治『春と修羅』第二集から
では、俳句はどうだろう。俳句は、南京大虐殺の前で、国家総動員法の前で、中国での人体実験の前で、カンボジア難民の前で、現代のファシズムの前で、どんな立ち居ふるまいをするのだろうか。次の句は、この春にぼくが書いた句である。
楽隊の後に楽隊チューリップ
正直言って、辺見さんの世界の中に、この句の居場所はないように思う。この句を辺見さんに見せたら、顔をしかめられそうな気がする。たまたま、自作を取り上げたが、現代に書かれている俳句は、どれもこれと似たような印象を受けるのではないだろうか。
だが、一方で、石原吉郎がシベリア抑留中に句会を行ったという話や金子兜太が戦場で句会を行ったという話は、どう理解したらいいのだろう。単に本土恋しいだけではないように思う。収容所での非人間的な扱いや仲間同士の密告・裏切りといった個々人がバラバラになっていくプロセス。戦場での死と隣り合わせ、といった孤独な極限状況が、逆に、本能的に人間の共同性回復へ向かわせたのではなかったか。句会が非人間的な日常の中で人間的な時間を回復する装置になっていたのではないか。
俳句が一見脳天気に見えるその裏には、世界の地獄があり、人と人の和解や人と自然の和解といった一瞬の現実とも一瞬の理念とも言える何ものかを表現することで、暗褐色の世界に拮抗しているようにも思えるのである。
虚子が戦時中どういう句を作っていたか。今度の関西旅行の車中で、確認してみたいと思っている。
 。旧暦、閏7月4日。
。旧暦、閏7月4日。来週、急に関西に行くことになって、その準備に追われている。医療奉仕に海外に行っていた友だちが帰国するので、みんなで集まることになった。
◇
『いまここに在ることの恥』のもう一つのテーマである「現代のファシズム」について述べる前に、「表現と時代との倫理的な関係」について、考えてみたい。
辺見さんは、1937年の南京大虐殺、1938年の国家総動員法公布という時代に注目して、この暗い時代に、たとえば、辺見さんの好きな太宰は何を書いていたかを問う。太宰は、「満願」という美しい掌編小説を書いていた。辺見さんは、次のように書いている。
「なるほど、うまいなあと私も感じ入る。けれども、うまいぶんだけ、ひっかかる。考えこんでしまう。状況と表現。状況と内面。時代と表現。そのことが、ひっかかってしょうがない。1938年の問題ではあるのですが、2006年のひっかかりとしても、これはある。もちろん、いかなる状況下にあっても『満願』のような物語はありうるし、作品として成立するでしょう。あるいはミニマムな人の常として、表現に値せずとはいえない。たぶん、そういってはいけない。だが、ひっかかる。大いにひっかかる。きょういいたいことの大事な点がここにかかわる。それはやはり恥にかかわるのです。(中略)いまは1938年ではありません、ですが、状況と表現の関係、ないしは時代と個の立ち居ふるまいの関係に苦しむのは無意味とはいえないと私は思うのです。私たちは『満願』を一幅の美しいスケッチとして読むことができます。しかし、『満願』の絵の近景や遠景に、国家総動員法や南京代虐殺といった光の屈折や血の臭いを想像し、必死で助けを求めただあろうはるかな遠音に耳をすますとき、時代を超えて恥はからだの内側から青痣のように浮きでてくるのです」(辺見庸著『いまここに在ることの恥』pp.147-148)
この本を読んで、まっさきに気になったのは、この箇所だった。二つの意味で気になった。一つは、ここに述べられているように、表現と時代の関係について。もう一つは、この本が描く世界と表現の関係について。
最初に述べたように、この本の読後感は暗褐色である。この本が描く世界の現実の中に、詩や俳句は居場所を持っているのか、というのが始めに感じた疑問だった。詩については、いくつも拮抗する作品や詩人をあげることがすぐにできる。たとえば、石原吉郎、鳴海英吉、トラークル。二次大戦を知らない賢治の作品の中にも、拮抗する作品は多くある。
夜の湿気と風がさびしくいりまじり
松ややなぎの林はくろく
そらには暗い業のはなびらがいっぱいで
わたくしは神々の名を録したことから
はげしく寒くふるへてゐる
宮沢賢治『春と修羅』第二集から
では、俳句はどうだろう。俳句は、南京大虐殺の前で、国家総動員法の前で、中国での人体実験の前で、カンボジア難民の前で、現代のファシズムの前で、どんな立ち居ふるまいをするのだろうか。次の句は、この春にぼくが書いた句である。
楽隊の後に楽隊チューリップ
正直言って、辺見さんの世界の中に、この句の居場所はないように思う。この句を辺見さんに見せたら、顔をしかめられそうな気がする。たまたま、自作を取り上げたが、現代に書かれている俳句は、どれもこれと似たような印象を受けるのではないだろうか。
だが、一方で、石原吉郎がシベリア抑留中に句会を行ったという話や金子兜太が戦場で句会を行ったという話は、どう理解したらいいのだろう。単に本土恋しいだけではないように思う。収容所での非人間的な扱いや仲間同士の密告・裏切りといった個々人がバラバラになっていくプロセス。戦場での死と隣り合わせ、といった孤独な極限状況が、逆に、本能的に人間の共同性回復へ向かわせたのではなかったか。句会が非人間的な日常の中で人間的な時間を回復する装置になっていたのではないか。
俳句が一見脳天気に見えるその裏には、世界の地獄があり、人と人の和解や人と自然の和解といった一瞬の現実とも一瞬の理念とも言える何ものかを表現することで、暗褐色の世界に拮抗しているようにも思えるのである。
虚子が戦時中どういう句を作っていたか。今度の関西旅行の車中で、確認してみたいと思っている。
 | いまここに在ることの恥 (角川文庫) |
| クリエーター情報なし | |
| 角川書店(角川グループパブリッシング) |
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
いまここに在ることの恥(1)
2006-08-24 / 本
木曜日、 。旧暦、閏7月1日。
。旧暦、閏7月1日。
辺見庸著『いまここに在ることの恥』(毎日新聞社)を読んだ。この本の感想を何から始めればいいのか。とても、内容をきれいに説明して、それで良しとできる本ではない。この本は色彩で言えば、暗褐色。
時代の危機が一人の個人の危機として現れることはあると思う。この本は、脳溢血・癌という二重の病に見舞われた著者が、自分の極限を見つめることで、時代の極限を見つめた本だと思う。その極限の思索は、ジャーナリストだったときの経験や、同じように極限を見つめた他者の言葉を手がかりにしている。
大きく分けて、この本には、「倫理の麻痺をめぐる問題」と「現代のファシズムをめぐる問題」の二つの中心がある。倫理の問題では、たとえば、カンボジア難民を取材するジャーナリストの資本の論理(ジャーナリストは自分も含めて「糞ハエ」だ!)を批判する中から「恥」という概念が新しく鍛え直されてくる。それは、プリーモ・レーヴィの「人間であることの恥辱」といった考え方・感じ方やジョルジョ・アガンベンの「今きみが語っているその語りかた、それが倫理だ」という言葉と通底している。
この問題を語る辺見さんの逸話の中で、とりわけ強い印象に残ったのは、中国大陸で旧日本軍が人体実験をする話だった。生きた健康な中国人の人体に麻酔をかけて、五臓六腑、手足頭をバラバラに切断していく。この作業をルーティンとして医師や看護婦が淡々と進める。中国人は、自分がどうなるのか、知っているので、手術台に上がろうとしない。そのとき、日本人看護婦が「麻酔をするから痛くありません。寝なさい」と優しくささやき、「患者」はうなずいて手術台にあおむいた。看護婦は医師をふりかえって<どうです、うまいものでしょう>といわんばかりに笑いかけ、ペロリと舌を出してみせた。この「ペロリ」のなんと恐ろしいことだろう。そして、その当時、その場に、日本人として、居合わせたとしたら、自分はどう行動していたか。それを想像することはもっと恐ろしい。
ぼくは、以前、辺見さんの「恥」ではないが、この概念に近いものとして、「原罪」という概念をブログで述べたことがある。宗教的な概念である原罪を社会科学的な概念に作り直せないか考えてみたのだ。
辺見さんの言う「人間の恥」は、人間であるがゆえにアプリオリに存在する恥であり、あるとき、ある場所で、ある行為に、人が恥を感じるというときの恥とは異なる。アプリオリな恥の感覚の鈍磨をするどく告発していて、敬意と共感を覚えた。この鈍磨は、社会全体の近代化と深く関わっているようにぼくは感じた。その意味では、「倫理の麻痺をめぐる問題」は近代批判ともなっている。
辺見さんの本については、他にも述べたいことがあるので、また、稿を改めて論じてみたい。
 。旧暦、閏7月1日。
。旧暦、閏7月1日。辺見庸著『いまここに在ることの恥』(毎日新聞社)を読んだ。この本の感想を何から始めればいいのか。とても、内容をきれいに説明して、それで良しとできる本ではない。この本は色彩で言えば、暗褐色。
時代の危機が一人の個人の危機として現れることはあると思う。この本は、脳溢血・癌という二重の病に見舞われた著者が、自分の極限を見つめることで、時代の極限を見つめた本だと思う。その極限の思索は、ジャーナリストだったときの経験や、同じように極限を見つめた他者の言葉を手がかりにしている。
大きく分けて、この本には、「倫理の麻痺をめぐる問題」と「現代のファシズムをめぐる問題」の二つの中心がある。倫理の問題では、たとえば、カンボジア難民を取材するジャーナリストの資本の論理(ジャーナリストは自分も含めて「糞ハエ」だ!)を批判する中から「恥」という概念が新しく鍛え直されてくる。それは、プリーモ・レーヴィの「人間であることの恥辱」といった考え方・感じ方やジョルジョ・アガンベンの「今きみが語っているその語りかた、それが倫理だ」という言葉と通底している。
この問題を語る辺見さんの逸話の中で、とりわけ強い印象に残ったのは、中国大陸で旧日本軍が人体実験をする話だった。生きた健康な中国人の人体に麻酔をかけて、五臓六腑、手足頭をバラバラに切断していく。この作業をルーティンとして医師や看護婦が淡々と進める。中国人は、自分がどうなるのか、知っているので、手術台に上がろうとしない。そのとき、日本人看護婦が「麻酔をするから痛くありません。寝なさい」と優しくささやき、「患者」はうなずいて手術台にあおむいた。看護婦は医師をふりかえって<どうです、うまいものでしょう>といわんばかりに笑いかけ、ペロリと舌を出してみせた。この「ペロリ」のなんと恐ろしいことだろう。そして、その当時、その場に、日本人として、居合わせたとしたら、自分はどう行動していたか。それを想像することはもっと恐ろしい。
ぼくは、以前、辺見さんの「恥」ではないが、この概念に近いものとして、「原罪」という概念をブログで述べたことがある。宗教的な概念である原罪を社会科学的な概念に作り直せないか考えてみたのだ。
辺見さんの言う「人間の恥」は、人間であるがゆえにアプリオリに存在する恥であり、あるとき、ある場所で、ある行為に、人が恥を感じるというときの恥とは異なる。アプリオリな恥の感覚の鈍磨をするどく告発していて、敬意と共感を覚えた。この鈍磨は、社会全体の近代化と深く関わっているようにぼくは感じた。その意味では、「倫理の麻痺をめぐる問題」は近代批判ともなっている。
辺見さんの本については、他にも述べたいことがあるので、また、稿を改めて論じてみたい。
 | いまここに在ることの恥 (角川文庫) |
| クリエーター情報なし | |
| 角川書店(角川グループパブリッシング) |
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
リルケ最後の詩
2006-08-22 / 詩
火曜日、 。旧暦、7月29日。旧暦だとまだ7月下旬である。確かに8月はもう秋だったのだろう。そう言えば、数日前から、夕方には蟋蟀がしきりに鳴いている。
。旧暦、7月29日。旧暦だとまだ7月下旬である。確かに8月はもう秋だったのだろう。そう言えば、数日前から、夕方には蟋蟀がしきりに鳴いている。
日曜日は句会だった。惨敗。まだ、見直す気になれず。その後、連衆のみなさんと飲む。人生の達人揃いですな。今日は、終日、仕事。図書館に返却しなければならないので、アーレントの思索日記Ⅱを一気に読む。その中に印象的なリルケの詩が引用されていた。
◇
リルケ最後の詩
苦痛について 1926年12月
来るがいい、知る限り最後のものよ
体中の収まりようのない痛みよ。
わが心が燃え上がるように、見よ、おまえの中で
私は燃える。おまえが上げる炎に
木材は長い間屈しようとしなかった。
今や近づいて、おまえの中で私は燃えている。
私の穏やかな顔は燃え上がるおまえの中で
この世ならぬ地獄の憤怒の形相に一変する、
全くプランもなく、未来から完全に自由になって
乱雑に積み上げられた薪の山を登ると
無言の蓄えをいだく心のために
未来のものを買い込むあてもない。
まだ、私は、人知れず燃え上がる者なのだろうか。
私は思い出を引き寄せたりはしない。
生きること、生きることというのは、外部に在ることだ。
私は炎の中にいる。私を知る者は誰もいない。
※1926年12月中旬頃、ヴァン・モンでの最後の手帖の書き込み。本来、タイトルはない。
アーレント『思索日記Ⅱ』p.104から。
 。旧暦、7月29日。旧暦だとまだ7月下旬である。確かに8月はもう秋だったのだろう。そう言えば、数日前から、夕方には蟋蟀がしきりに鳴いている。
。旧暦、7月29日。旧暦だとまだ7月下旬である。確かに8月はもう秋だったのだろう。そう言えば、数日前から、夕方には蟋蟀がしきりに鳴いている。日曜日は句会だった。惨敗。まだ、見直す気になれず。その後、連衆のみなさんと飲む。人生の達人揃いですな。今日は、終日、仕事。図書館に返却しなければならないので、アーレントの思索日記Ⅱを一気に読む。その中に印象的なリルケの詩が引用されていた。
◇
リルケ最後の詩
苦痛について 1926年12月
来るがいい、知る限り最後のものよ
体中の収まりようのない痛みよ。
わが心が燃え上がるように、見よ、おまえの中で
私は燃える。おまえが上げる炎に
木材は長い間屈しようとしなかった。
今や近づいて、おまえの中で私は燃えている。
私の穏やかな顔は燃え上がるおまえの中で
この世ならぬ地獄の憤怒の形相に一変する、
全くプランもなく、未来から完全に自由になって
乱雑に積み上げられた薪の山を登ると
無言の蓄えをいだく心のために
未来のものを買い込むあてもない。
まだ、私は、人知れず燃え上がる者なのだろうか。
私は思い出を引き寄せたりはしない。
生きること、生きることというのは、外部に在ることだ。
私は炎の中にいる。私を知る者は誰もいない。
※1926年12月中旬頃、ヴァン・モンでの最後の手帖の書き込み。本来、タイトルはない。
アーレント『思索日記Ⅱ』p.104から。
コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )
俳句に現れた八月十五日(2)
2006-08-19 / 俳句
土曜日、 。旧暦、7月26日。
。旧暦、7月26日。
なんだか、雑用で終った。仕事、あまり進まず。
◇
敗戦の日のあをぞらを語り継ぐ 野木藤子
近代俳句のもっとも良質な部分が受け継がれた句だと思う。この句には、主体が誓いの形で表現されている。その主体とはとりも直さず、「われわれ」である。このとき、季語は「敗戦の日」が正しく、「終戦の日」では、この句は成り立たない。
では、次の句はどうだろうか。
白雲は天上の花敗戦日 上田五千石
どこか、ちぐはくな感じがしないだろうか。「敗戦日」が浮いている感じがしないだろうか。では、こうだったらどうか。
白雲は天上の花終戦日
しっくりこないだろうか。おそらく五千石氏は、昨日、ぼくが書いた、コンテキストで「敗戦日」を考えていたはずである。氏の思想として、あえて、「終戦日」と言わず「敗戦日」を選んだものと推察する。
もう一つ次の句を見てもらいたい。
終戦日厠の裏に紫蘇ゆたか 飴山實
この句が、逆に
敗戦日厠の裏に紫蘇ゆたか
だったとしたら、落ち着かないばかりか、奇妙な感じさえ受ける。
俳句は、そもそもモノローグなのだろうか。一個の主体が独白するモノローグなのだろうか。おそらく違うだろう。そもそも、共同性が前提の文芸だからだ。連衆や自然との関係性が、作品の基礎にある。連衆への挨拶、自然への挨拶、古人の痕跡を留めたトポスへの挨拶が基礎にある。
さらに言えば、俳句の「己」は限りなく他者あるいは自然と浸透しあっている。別段、この句を詠むのは「己」でなくてもいい。他者や自然、あるいは神であってもいい。万葉集からの「詠み人知らず」の系譜は、俳句にも、ある面、流れ込んでいるとは言えないだろうか。
そんな俳句の体質と責任・主体を強く意識させる「敗戦」は、取り合わせが非常に難しいのではないだろうか。ちぐはぐ、しっくりこない、どうも落ち着かない、といった感じはこの辺から来るように思う。
「敗戦」という言葉を使うとき、自然や社会全体から浮き上がり、自然や社会に対立した国家の姿が現れてくる。戦争は、人間対人間の戦いであるばかりか、自然破壊を伴ない、自然を憎みさえする。人間は、自然あると同時に自然ではなく、いわば、地上に住まうものである。自然に挨拶もすれば自然を壊しもする。
「終戦」という言葉は、人間の側の言葉ではなく、あえて言えば、人間を包み込んだ大いなる地球から発せられた言葉と考えられないだろうか。だから、俳句にはしっくりくるのだ。「終戦」という言葉を俳人が使うとき、戦争責任や戦争主体といった問題を隠蔽してしまうという危険性を自覚しつつも、地球から愚かな人間に発せられたメッセージとして「終戦」という言葉の意味を汲み取ることも大切な気がするのである。
(住むということは痕跡を留めることである。 ベンヤミン)
破壊の痕跡は、今も営々と続いているのであるから。
 。旧暦、7月26日。
。旧暦、7月26日。なんだか、雑用で終った。仕事、あまり進まず。
◇
敗戦の日のあをぞらを語り継ぐ 野木藤子
近代俳句のもっとも良質な部分が受け継がれた句だと思う。この句には、主体が誓いの形で表現されている。その主体とはとりも直さず、「われわれ」である。このとき、季語は「敗戦の日」が正しく、「終戦の日」では、この句は成り立たない。
では、次の句はどうだろうか。
白雲は天上の花敗戦日 上田五千石
どこか、ちぐはくな感じがしないだろうか。「敗戦日」が浮いている感じがしないだろうか。では、こうだったらどうか。
白雲は天上の花終戦日
しっくりこないだろうか。おそらく五千石氏は、昨日、ぼくが書いた、コンテキストで「敗戦日」を考えていたはずである。氏の思想として、あえて、「終戦日」と言わず「敗戦日」を選んだものと推察する。
もう一つ次の句を見てもらいたい。
終戦日厠の裏に紫蘇ゆたか 飴山實
この句が、逆に
敗戦日厠の裏に紫蘇ゆたか
だったとしたら、落ち着かないばかりか、奇妙な感じさえ受ける。
俳句は、そもそもモノローグなのだろうか。一個の主体が独白するモノローグなのだろうか。おそらく違うだろう。そもそも、共同性が前提の文芸だからだ。連衆や自然との関係性が、作品の基礎にある。連衆への挨拶、自然への挨拶、古人の痕跡を留めたトポスへの挨拶が基礎にある。
さらに言えば、俳句の「己」は限りなく他者あるいは自然と浸透しあっている。別段、この句を詠むのは「己」でなくてもいい。他者や自然、あるいは神であってもいい。万葉集からの「詠み人知らず」の系譜は、俳句にも、ある面、流れ込んでいるとは言えないだろうか。
そんな俳句の体質と責任・主体を強く意識させる「敗戦」は、取り合わせが非常に難しいのではないだろうか。ちぐはぐ、しっくりこない、どうも落ち着かない、といった感じはこの辺から来るように思う。
「敗戦」という言葉を使うとき、自然や社会全体から浮き上がり、自然や社会に対立した国家の姿が現れてくる。戦争は、人間対人間の戦いであるばかりか、自然破壊を伴ない、自然を憎みさえする。人間は、自然あると同時に自然ではなく、いわば、地上に住まうものである。自然に挨拶もすれば自然を壊しもする。
「終戦」という言葉は、人間の側の言葉ではなく、あえて言えば、人間を包み込んだ大いなる地球から発せられた言葉と考えられないだろうか。だから、俳句にはしっくりくるのだ。「終戦」という言葉を俳人が使うとき、戦争責任や戦争主体といった問題を隠蔽してしまうという危険性を自覚しつつも、地球から愚かな人間に発せられたメッセージとして「終戦」という言葉の意味を汲み取ることも大切な気がするのである。
(住むということは痕跡を留めることである。 ベンヤミン)
破壊の痕跡は、今も営々と続いているのであるから。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
俳句に現れた八月十五日(1)
2006-08-17 / 俳句
木曜日、 。旧暦、7月24日。猛烈に蒸し暑い一日だった。終日仕事。
。旧暦、7月24日。猛烈に蒸し暑い一日だった。終日仕事。
健康診断の性別(!)が間違っていたので、受診病院に問い合わせると、市役所のインプットミスだと言う。市役所の責任者にクレームをつけると、調べると言う。調べた結果、病院のインプットミスだと言う。はあ? 病院の担当者が、謝罪の電話を掛けてきて言うには、検査委託会社のミスだと言う。はあ? それで、責任はだれが取るわけ? 性別の間違いによって、本来正常のはずだった数値が3つも異常値に分類されてしまった。間違いを認めないメンタリティと無責任体制は、そっくり戦前体制と変わっていない。中国や韓国に批判されると、中国のチベット侵攻や韓国のベトナム参戦を引き合いに出して、悪いのはぼくだけじゃないもん、と幼稚に居直り、間違いを率直に認めることができない子どもじみたメンタリティに通じるところがある。自己批判は「自虐」などという低劣なものとはわけが違う。自己批判こそ、理性の働きであり、自己批判こそ、理性を野蛮に対峙させるものだ。
◇
俳句で敗戦あるいは終戦がどう詠まれてきたのか、気になって調べてみた。たとえば、大型俳句データベースで「敗戦」「終戦」「八月十五日」を俳句に含むものを調べてみた。いくつか重複する俳句はあるが、結果は以下のとおりだった。
・「敗戦」を含む俳句のヒット数 105
・「終戦」を含む俳句のヒット数 120
・「八月十五日」を含む俳句のヒット数 25
全体をざっと読んでみたが、いい句がほとんどない。
木々のこゑ石ころのこゑ終戦日 鷹羽狩行
この句が印象的だった。
上の数字を見てみると、「敗戦」よりも「終戦」を詠んだ句が多い。ここで、「敗戦」と「終戦」という言葉について考えてみたい。初めに、ぼくのこの2つの言葉に対する一般的なイメージを述べて、次に辞書の定義等を検討してみたい。
1) ぼくの一般的なイメージ
「敗戦」という言葉は、「戦いに負けた」という意味だろう。あるいは「負け戦」という風にも読める。この言葉が使用されるコンテキストは、たいてい、戦いの主体が明確で、つまり大日本帝国であり、大日本帝国が侵略戦争を近隣諸国に対して始め、その戦いに敗れた、という場合が多い。つまり、「敗戦」には、第一に、その戦いが「侵略戦争」だったこと(自衛のためでも、アジア解放のためでもなく)、第二に、大日本帝国が、その戦争を始めたということ(戦争責任を問われる者が存在するということ。この意味で、戦争は完全に人為的なものである)。この2点が含まれるように思われる。
他方「終戦」という言葉には、戦いは自然現象という観念があるように思う。戦争はいつのまにか始まり、そうして、いつのまにか終った。そこには、人間が関与した形跡は少ない。あたかも台風か地震のような災害に似ている。ここには、戦争主体の観念は希薄である。しかし、それに巻き込まれた人々は辛酸を舐めた。早く通り過ぎてくれないか、と必死に祈った。ああやっと戦争は「終った」か。そんな庶民の安堵のため息も「終戦」という言葉には感じられる。
2) 日本国語大辞典の定義
2)‐1 「敗戦」
戦争、試合などに負けること。
2)‐2 「終戦」
戦争が終ること。また、戦争を終結すること。特に、太平洋戦争の終結について言うこともある。
この定義を見ると、「敗戦」が敗戦した者あるいは集団の存在が前提であるのに対して、「終戦」は、戦争を終結した者(集団)も開始した者(集団)も、まったく問題化しない。
日本国語大辞典を調べてわかったのは、この2つのことばが、いったいいつからテキスト上に現れたのか、という点である。面白いことに「敗戦」という言葉は、1901年の「一年有半」(中江兆民)にすでに出ている。他方、「終戦」という言葉が初めてテキストに現れるのは、1947年の「嫌がらせの年齢」(丹羽文雄)である。この二つのテキストのコンテキストを調べていないので、詳しいことは言えないが、少なくとも、「終戦」という言葉は、戦前には存在せず、第二次大戦後に日本語になったということである。
ここで、述べておきたいのは、「敗戦」は戦争主体や戦争責任を含むから正しく、「終戦」は主体や責任があいまいだから、俳句に使うのはけしからん、という単純な話ではない。
まず、始めに、俳句を作る者として感じるのは、この季語「敗戦日(忌)」あるいは「終戦日(忌)」という季語の使い方の難しさである。先の、データベースを調べても、手元にある歳時記を何冊か見ても、いいと思う句がなかなかない。これはなぜだろうか。その中でも、ぼくが感じるのは、「終戦日(忌)」を使った句の方が「敗戦日(忌)」を使った句よりも違和感が少ない。これはなぜだろうか。
こういった、問題圏である。これとは別に、ぼくは、個人的には、「敗戦」の方が、歴史的に見て適切な用語だと思っている。が、一方で、「敗」は「勝」と対の言葉である。「敗」は「勝」をめざし、「敗」は「勝」よりも価値が低い。そんなニュアンスを「敗戦」に感じることもある。他方で、「終戦」という言葉には、責任や主体の観念が希薄な代わりに、庶民の安堵感、大掛かりな洗脳システムの犠牲になり、生き残った庶民たちや兵士たちの本音が洩れ聞こえてくる気がするのである。
 。旧暦、7月24日。猛烈に蒸し暑い一日だった。終日仕事。
。旧暦、7月24日。猛烈に蒸し暑い一日だった。終日仕事。健康診断の性別(!)が間違っていたので、受診病院に問い合わせると、市役所のインプットミスだと言う。市役所の責任者にクレームをつけると、調べると言う。調べた結果、病院のインプットミスだと言う。はあ? 病院の担当者が、謝罪の電話を掛けてきて言うには、検査委託会社のミスだと言う。はあ? それで、責任はだれが取るわけ? 性別の間違いによって、本来正常のはずだった数値が3つも異常値に分類されてしまった。間違いを認めないメンタリティと無責任体制は、そっくり戦前体制と変わっていない。中国や韓国に批判されると、中国のチベット侵攻や韓国のベトナム参戦を引き合いに出して、悪いのはぼくだけじゃないもん、と幼稚に居直り、間違いを率直に認めることができない子どもじみたメンタリティに通じるところがある。自己批判は「自虐」などという低劣なものとはわけが違う。自己批判こそ、理性の働きであり、自己批判こそ、理性を野蛮に対峙させるものだ。
◇
俳句で敗戦あるいは終戦がどう詠まれてきたのか、気になって調べてみた。たとえば、大型俳句データベースで「敗戦」「終戦」「八月十五日」を俳句に含むものを調べてみた。いくつか重複する俳句はあるが、結果は以下のとおりだった。
・「敗戦」を含む俳句のヒット数 105
・「終戦」を含む俳句のヒット数 120
・「八月十五日」を含む俳句のヒット数 25
全体をざっと読んでみたが、いい句がほとんどない。
木々のこゑ石ころのこゑ終戦日 鷹羽狩行
この句が印象的だった。
上の数字を見てみると、「敗戦」よりも「終戦」を詠んだ句が多い。ここで、「敗戦」と「終戦」という言葉について考えてみたい。初めに、ぼくのこの2つの言葉に対する一般的なイメージを述べて、次に辞書の定義等を検討してみたい。
1) ぼくの一般的なイメージ
「敗戦」という言葉は、「戦いに負けた」という意味だろう。あるいは「負け戦」という風にも読める。この言葉が使用されるコンテキストは、たいてい、戦いの主体が明確で、つまり大日本帝国であり、大日本帝国が侵略戦争を近隣諸国に対して始め、その戦いに敗れた、という場合が多い。つまり、「敗戦」には、第一に、その戦いが「侵略戦争」だったこと(自衛のためでも、アジア解放のためでもなく)、第二に、大日本帝国が、その戦争を始めたということ(戦争責任を問われる者が存在するということ。この意味で、戦争は完全に人為的なものである)。この2点が含まれるように思われる。
他方「終戦」という言葉には、戦いは自然現象という観念があるように思う。戦争はいつのまにか始まり、そうして、いつのまにか終った。そこには、人間が関与した形跡は少ない。あたかも台風か地震のような災害に似ている。ここには、戦争主体の観念は希薄である。しかし、それに巻き込まれた人々は辛酸を舐めた。早く通り過ぎてくれないか、と必死に祈った。ああやっと戦争は「終った」か。そんな庶民の安堵のため息も「終戦」という言葉には感じられる。
2) 日本国語大辞典の定義
2)‐1 「敗戦」
戦争、試合などに負けること。
2)‐2 「終戦」
戦争が終ること。また、戦争を終結すること。特に、太平洋戦争の終結について言うこともある。
この定義を見ると、「敗戦」が敗戦した者あるいは集団の存在が前提であるのに対して、「終戦」は、戦争を終結した者(集団)も開始した者(集団)も、まったく問題化しない。
日本国語大辞典を調べてわかったのは、この2つのことばが、いったいいつからテキスト上に現れたのか、という点である。面白いことに「敗戦」という言葉は、1901年の「一年有半」(中江兆民)にすでに出ている。他方、「終戦」という言葉が初めてテキストに現れるのは、1947年の「嫌がらせの年齢」(丹羽文雄)である。この二つのテキストのコンテキストを調べていないので、詳しいことは言えないが、少なくとも、「終戦」という言葉は、戦前には存在せず、第二次大戦後に日本語になったということである。
ここで、述べておきたいのは、「敗戦」は戦争主体や戦争責任を含むから正しく、「終戦」は主体や責任があいまいだから、俳句に使うのはけしからん、という単純な話ではない。
まず、始めに、俳句を作る者として感じるのは、この季語「敗戦日(忌)」あるいは「終戦日(忌)」という季語の使い方の難しさである。先の、データベースを調べても、手元にある歳時記を何冊か見ても、いいと思う句がなかなかない。これはなぜだろうか。その中でも、ぼくが感じるのは、「終戦日(忌)」を使った句の方が「敗戦日(忌)」を使った句よりも違和感が少ない。これはなぜだろうか。
こういった、問題圏である。これとは別に、ぼくは、個人的には、「敗戦」の方が、歴史的に見て適切な用語だと思っている。が、一方で、「敗」は「勝」と対の言葉である。「敗」は「勝」をめざし、「敗」は「勝」よりも価値が低い。そんなニュアンスを「敗戦」に感じることもある。他方で、「終戦」という言葉には、責任や主体の観念が希薄な代わりに、庶民の安堵感、大掛かりな洗脳システムの犠牲になり、生き残った庶民たちや兵士たちの本音が洩れ聞こえてくる気がするのである。
コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )
芭蕉の俳句(110)
2006-08-16 / 俳句
水曜日、 のち
のち 。旧暦、7月23日。
。旧暦、7月23日。
マッド小泉が靖国に参拝。「英霊」はお盆でみんな故郷に帰ってるぜ、間抜け野郎!
加藤議員の実家が右翼に放火さる。20代、30代の右傾化顕著。日韓・日中の靖国問題を、すべて外交戦略上の問題に還元する前に、日本人としてどう生きるか、という倫理的な問題への対応をきちんと確立すべきじゃないのかね。産経系は、人間が高くも深くもなく、ただただ、薄っぺらい。You are plastic!
◇
午前中、病院。午後、用事。徹夜で出かけたので、さすがに疲れた。帰りにブックオフで新書を2冊200円で調達。「アメリカの環境保護運動」(岩波新書)、「アメリカのユダヤ人」(同)。今日は、もう読書して寝るだけ。
◇
伊賀の国花垣の庄は、そのかみ奈良の八重桜の料に附けられけると云ひ伝へはんべれば、
一里はみな花守の子孫かや (猿蓑)
■一里はひとさと=一村。花垣とは「花を保護するための垣」(広辞苑)のこと。平安代以来、奈良は八重桜の名所。花垣の庄は、その昔、八重桜の咲く頃は、花垣を結い、里人が桜を守って花守をしたという話を踏まえている。
「この村は全員がその花守の子孫なのだろうか」村人たちがみな花守だったという美しい言い伝えにも惹かれるが、そういう過去を踏まえて、その俤を今の村人一人一人に探している芭蕉の行為自体が美しく感じられた。この句は、その意味では、「過去を含んだ今」であり、美しい時間が二重に流れている。
 のち
のち 。旧暦、7月23日。
。旧暦、7月23日。マッド小泉が靖国に参拝。「英霊」はお盆でみんな故郷に帰ってるぜ、間抜け野郎!
加藤議員の実家が右翼に放火さる。20代、30代の右傾化顕著。日韓・日中の靖国問題を、すべて外交戦略上の問題に還元する前に、日本人としてどう生きるか、という倫理的な問題への対応をきちんと確立すべきじゃないのかね。産経系は、人間が高くも深くもなく、ただただ、薄っぺらい。You are plastic!
◇
午前中、病院。午後、用事。徹夜で出かけたので、さすがに疲れた。帰りにブックオフで新書を2冊200円で調達。「アメリカの環境保護運動」(岩波新書)、「アメリカのユダヤ人」(同)。今日は、もう読書して寝るだけ。
◇
伊賀の国花垣の庄は、そのかみ奈良の八重桜の料に附けられけると云ひ伝へはんべれば、
一里はみな花守の子孫かや (猿蓑)
■一里はひとさと=一村。花垣とは「花を保護するための垣」(広辞苑)のこと。平安代以来、奈良は八重桜の名所。花垣の庄は、その昔、八重桜の咲く頃は、花垣を結い、里人が桜を守って花守をしたという話を踏まえている。
「この村は全員がその花守の子孫なのだろうか」村人たちがみな花守だったという美しい言い伝えにも惹かれるが、そういう過去を踏まえて、その俤を今の村人一人一人に探している芭蕉の行為自体が美しく感じられた。この句は、その意味では、「過去を含んだ今」であり、美しい時間が二重に流れている。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
芭蕉の俳句(109)
2006-08-13 / 俳句
日曜日、 。旧暦、7月20日。
。旧暦、7月20日。
午前中、伯父の新盆、午後、掃除と買出し。新盆の後、従弟にイタリアンをご馳走になった。びっくりした。今まで、料理などしたこともない男がキッチンでせっせと洒落た料理を作っているから。意外に旨かった。
◇
種芋や花の盛りを売り歩く (泊船集)
■花の盛りという風雅、種芋という生活そのもの。この二つの対比に惹かれた。句は一物仕立てであるが、発想は取り合わせというより対比的である。「奥の細道」以降、はっきり作風が変わってきた。文学史上は、「かるみ」と言われている。この変化の一つは、「時間の感覚」にあるように思う。以前は、句は「過去を含んだ今」という時間の二重性が基本だった。謡曲や和歌や事跡を踏まえた句作りに、それは現れている。この句の時間は、現在だけである。「奥の細道」以降、時間の二重性は解消されたのか。この点を一つの問題意識にしてみたい。
 。旧暦、7月20日。
。旧暦、7月20日。午前中、伯父の新盆、午後、掃除と買出し。新盆の後、従弟にイタリアンをご馳走になった。びっくりした。今まで、料理などしたこともない男がキッチンでせっせと洒落た料理を作っているから。意外に旨かった。
◇
種芋や花の盛りを売り歩く (泊船集)
■花の盛りという風雅、種芋という生活そのもの。この二つの対比に惹かれた。句は一物仕立てであるが、発想は取り合わせというより対比的である。「奥の細道」以降、はっきり作風が変わってきた。文学史上は、「かるみ」と言われている。この変化の一つは、「時間の感覚」にあるように思う。以前は、句は「過去を含んだ今」という時間の二重性が基本だった。謡曲や和歌や事跡を踏まえた句作りに、それは現れている。この句の時間は、現在だけである。「奥の細道」以降、時間の二重性は解消されたのか。この点を一つの問題意識にしてみたい。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
芭蕉の俳句(108)
2006-08-11 / 俳句
金曜日、 。旧暦、7月18日。
。旧暦、7月18日。
朝まで、眠れず、11時に起きて、子どもに呆れられる。アーレントの『思索日記Ⅱ』を朝まで読んで、ああ、ぼくは労働に向いていない、そもそも仕事に向いていないのだな、などと勝手に腑に落ちて寝たところ、金がなくて、銀行強盗する夢を見た。マネーロンダリングをどうするか、考えているところで目が覚めた。笑えん夢やな。
◇
路通が陸奥におもむくに
草枕まことの花見しても来よ (茶の草子)
■楸邨曰く「路通への対詠であるから、路通の人柄を一応心におく必要がある。路通は乞食の境涯から芭蕉に拾われて、風雅の道に入るようになったが、性放恣、容易に真の風雅を体得できなかったもののようである・・・路通は蕉門俳人。斎部氏(忌部とも八十村とも)露通、呂通とも書く。漂白の僧として乞食生活をしていたが貞亨2年ごろ芭蕉に入門、『奥の細道』の旅で芭蕉を敦賀に迎え、以降数ヶ月その身辺にあって親炙していたものである。奇行多く驕慢心があり、次第に人々の非難を浴び、ついには芭蕉の勘気をも蒙った」
路通というのは、実に興味深い。こういう一種の奇人変人も蕉門に加えて、めんどうを見ていたのだから、芭蕉という人も幅広い。芭蕉データベースによると、路通は90歳まで生きたらしい。
この句、芭蕉の呆れている様子が伝わってきて面白い。「しても来よ」の「も」にそんな感じが窺われる。しかし、どこか憎めない人柄だったのだろう。
 。旧暦、7月18日。
。旧暦、7月18日。朝まで、眠れず、11時に起きて、子どもに呆れられる。アーレントの『思索日記Ⅱ』を朝まで読んで、ああ、ぼくは労働に向いていない、そもそも仕事に向いていないのだな、などと勝手に腑に落ちて寝たところ、金がなくて、銀行強盗する夢を見た。マネーロンダリングをどうするか、考えているところで目が覚めた。笑えん夢やな。
◇
路通が陸奥におもむくに
草枕まことの花見しても来よ (茶の草子)
■楸邨曰く「路通への対詠であるから、路通の人柄を一応心におく必要がある。路通は乞食の境涯から芭蕉に拾われて、風雅の道に入るようになったが、性放恣、容易に真の風雅を体得できなかったもののようである・・・路通は蕉門俳人。斎部氏(忌部とも八十村とも)露通、呂通とも書く。漂白の僧として乞食生活をしていたが貞亨2年ごろ芭蕉に入門、『奥の細道』の旅で芭蕉を敦賀に迎え、以降数ヶ月その身辺にあって親炙していたものである。奇行多く驕慢心があり、次第に人々の非難を浴び、ついには芭蕉の勘気をも蒙った」
路通というのは、実に興味深い。こういう一種の奇人変人も蕉門に加えて、めんどうを見ていたのだから、芭蕉という人も幅広い。芭蕉データベースによると、路通は90歳まで生きたらしい。
この句、芭蕉の呆れている様子が伝わってきて面白い。「しても来よ」の「も」にそんな感じが窺われる。しかし、どこか憎めない人柄だったのだろう。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
| « 前ページ |