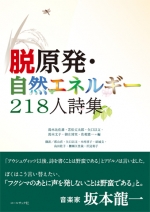verse, prose, and translation
Delfini Workshop
Pascal 『Pensées』を読む(26)

■旧暦1月8日、月曜日、

(写真)降りる
昨日は、所用で大宮まででかける。寒かったが、雪は残っていなかった。久しぶりに大宮の街を歩く。懐かしかった。
先日の東大地震研究所の4年以内にM7級の地震が起きる確率70%という計算を踏まえて、自宅の防災対策の見直しを始めた。記事はここから>>> これが南関東や首都圏直下で起きれば、さらなる放射能災害、富士山の噴火などの複合大災害になる可能性が高いと思っている。防災対策よりも生き残り対策と言った方がいいかもしれない。4年以内というのは、今日・明日も含まれる。
☆
この頃、古い物語に関心を持っている。土曜日、図書館で、日本霊異記、今昔物語、宇治拾遺物語を借りてくる。テリー・イーグルトンが、面白いことを言っている。神学と精神分析は、人間の欲望を物語ったものだと言う。近代になって、精神分析が神学の代わりを務めているとも述べている。この議論は、なかなか説得力があるように思う。神学や精神分析が一つの物語なのだとすれば、古くからの物語も、人間の欲望の表現とも言えるのではなかろうか。そこで、語られている欲望はなにか。そこで語られていない欲望はなにか。語られた欲望は、現在、実現されたのかどうか。こういった点に注目して読んでみたいと思っている。
☆
Qu'est-ce que nos principes naturels sinon nos principes accountumés? Et dans les enfants œux qu'ils ont reçus de la coutume de leurs pères, comme la chasse dans les animaux.
Une différente coutume en donnera d'autres principes naturels. Cela se voit par expérience. Et s'il y en a d'ineffaçables à la coutume, il y en a aussi de la coutume contre la nature ineffaçables à la nature et à une seconde coutume. Cela dépend de la disposition. Pensées 116
われわれの言う自然の原理とは、原理の習慣化でなくてなんであろう。自然の原理とは、ちょうど動物が狩りをするように、父たちの習慣を子どもたちが受け継いだものに他ならない。
習慣が異なれば、違った自然の原理が生じる。それは経験から明らかである。習慣では消せない自然の原理があるかと思えば、自然や第二の習慣では打ち消せない自然に反した習慣もある。これは、集団の特性に左右される。
■最後のla dispositionは、前田陽一、由木康訳では「人々の素質」となっている。ここは、全体の文脈から、ぼくなりの解釈を加えて訳出した。「集団の傾向、性向、性格」といったほどの意味である。非常に重要だと思う断章の一つ。この部分だけに注目しても、マンハイムを400年先取りしている。前回同様、指摘している人はだれもいないが、これは、近代の世界観を突き抜けている。自然の原理のベースには、習慣、すなわち、社会的なものが存在する、という重要な指摘を含んでいるからだ。これは、自然の原理がある世界像に規定されて存在することを意味し、それは、自覚できない、という意味で、イデオロギーと言っていい。この考え方は、ヴィトゲンシュタインに極めて近い。探求の起源や方向性が、ある世界観に規定されているということになるからだ。
近代の世界観を突き抜けている、という意味は、主観・客観の二元論の図式を超えているということで、この二元論は、主体の<外部>に絶対的な真理が存在し、主体はそれを認識できる、という考え方を基本にしている。これは、自然の認識は価値中立的で、だれにとっても役に立ち、時代を超越しているという前提を含む。カント認識論が自然科学を基礎づけている側面である。パスカルの断章116は、自然の認識も社会に規定されると述べている点で、画期的である。自然の認識は、超越的ではなく(つまり、二元論ではなく)、社会的・歴史的なものであることがはっきり述べられている。この点について、すぐれた自然科学者は、科学の言うことは時代とともに変わるとして、うすうす気がついてはいるが、この二元論にとどめを刺したのは「量子論」だろう。量子論については、近代世界像との関わりでいつか整理・分析してみたいと思っている。量子論といえども、「絶対」ではなく、社会的規定性から自由ではないはずなのだ。
ヴィトゲンシュタインのイデオロギー論的読み替えについては、以前、ペーパーにまとめた。ここから>>>
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
Pascal 『Pensées』を読む(25)

■1月4日、木曜日、

(写真)無題
とうとう、PCが壊れた。昨日、修理に出して、今は、代替のノートを使用。ノートは使いにくいので、勢い、ウェブにつなぐ回数が減る。ちょうど、タイミング良く、というべきが、悪くと言うべきか、腰痛が再発。仕方ないので、大人しくしている。腰痛は、完全に運動不足が原因だろう。そろそろ再開しないと。
福島原発事故以来、ここは、ホットスポットになってしまったので、戸外でウォーキングができなくなった。自然の中へ気分転換に行くこともできない。相当ストレスがたまる。こういう精神的な苦痛を与えていることに、世界最大級のデタラメ公害企業、東京電力は、罪の意識を感じているのだろうか。たぶん、何も感じていないだろう。言葉ではなく行動を見ていればわかる。人間を「市場」(あるいは「労働力」)としてしか見なくなり、ナチスのように、人間的な感覚や感情が鈍磨してしまったのだろう。これは大げさな例えではなく、資本主義に内在する構造的な欠陥なのだと思う。危機になるほど、本質がはっきり出る。人間的な感情をもった人々が、これだけ広範囲に苦しみや不安を与えておきながら、原発再稼働と10%の電気料金値上げを前提にして、2014年の3月期に損益を黒字化します、などといった試算を平然と出すだろうか。記事はここから>>>
今日は、もうひとつ、驚くニュースがあった。「命懸けの放送 教材に 埼玉県が『天使の声』独自作成」ここから>>> これは学校教材ではなく、原子力村の成人教育に使ったらどうだろうか。「天使の声」は美談にしてはならないんじゃないか。なぜ、遠藤さんを含めて、町の職員39人が犠牲になったのか、どうしたら、避けられたのか。そうした行政機構としての避難体制や仕組みを、避難誘導との関わりの中で、考え直す教材にすべきで、遠藤さんと同じ犠牲者を再生産する精神主義一辺倒の教材にしてはならないだろう。これでは、あの戦争の教訓が何も生かされていないではないか。美しい心の人間は、帰って来なければならない、と思うがいかがだろうか。
☆
Spongia solis.
Quand nous voyons un effet arriver toujours de même, nous en concluons une nécessité nqturelle, comme qu'il sera demain jour, etc. Mais souvent la nature nous dément et ne s'assujettit pas à ses propres règles. Penséés 559
ソポンジア・ソリ(太陽の海綿)。
いつも結果が同じになるなら、それは自然の必然性だと、われわれは判断する。たとえば、明日も太陽は存在するなど。だが、自然はたびたび我々の予想を裏切り、自然の諸法則を踏み外す。
■これ以降のいくつかの断章は、非常に重要だと思う。ここもそうだが、自然の法則性を、ある意味で、否定している。これは、現代の量子論からすれば、人間を含めた物質には、法則のような必然的なものはなく、存在の有無は、確率論的に決まるとの立場になるから、パスカルに現代科学が追いついた形になる。明日、太陽が存在するのは、確率論的な現象で、必然的ではないことになる。必然性あるいは決定論とは何のか、パスカルの断章は鋭く問いかけている。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
Pascal 『Pensées』を読む(24)

■旧暦1月1日、月曜日、
 、旧正月、新月
、旧正月、新月(写真)無題
今日は旧暦の正月だと思うと、江戸の俳諧師たちの春を待つ心に触れた気分になる。
いわゆるニューハーフ、ladyboysのAVがウェブ上に結構あるので、好奇心から、いくつか観てみた。胸の整形はほぼ完璧で、女性となんら変わらない。二の腕に筋肉がついていると、すぐに、ばれてしまうが、たいてのladyboysは女性よりも華奢な手足をしている。ペニスはあるが、睾丸はあまり目立たない。ペニスは、通常の成人男性の二分の一くらいではなかろうか。ladyboysは、アメリカ、日本、タイなど世界各地にいるが、容貌の美しさでは、ちょっと驚くような人もいる。ただ、その歴史は、ニューハーフと言われるほど、ニューではないだろう。古典古代にまでさかのぼると思う。ローマの子ども奴隷は、今で言う、性的搾取だったし、日本の寺院の稚児は、僧侶の性欲と無関係ではないだろう。ladyboysは、その起源から、男性の性欲と関わっているが、タイのように、ニューハーフが社会的に認知されている国では、教職など、社会進出も盛んである。AVや芸能界、お水系の人が目立つが、必ずしも、仕事をしているのは、そういう業界だけではないだろう。ladyboysのジェンダーは、女であるから、男性の伴侶と結婚生活を送っているケースも、ゲイの結婚とは違った意味で、相当あるに違いない。ただ、表に出ないだけだろう。こういう「境界」にいる人々は、芸術のモチーフとして、もっと、取り上げられていい気がする。たとえば、ルドンやモローがladyboysのヌードを描いたとしても、なんら違和感はない。仏像を始め、両性具有のモチーフは、古くからある。ladyboysは、不思議に、異形という感じがしない。むしろ、どこかハレの気配を漂わせている。
☆
Donc, toutes choses étant causées et causantes, aidées et aidantes, médiates et immédiates, et toutes s'entretenant par un lien naturel et insensible qui lie les plus éloignées et les plus différentes, je tiens impossible de connaître les parties sans connaître le tout, non plus que de connaître le tout sans connaître particulièrement les parties. Pascal Pensées 185
それゆえ、あらゆる事物は、原因になったり結果になったり、促進したりされたり、間接的、直接的に関連したりしている。すべては、遠く離れていても、まったく違ったものであっても、知覚できない自然の絆で結びつけられ、相互に支え合っているから、全体を知らずして、部分を知ることはできないし、逆に、部分を詳しく知ることなく全体を知ることはできないと思う。
■断章185は、示唆に富んだ文章が多い。ここも、単線的な因果連関は否定し、諸部分が全体を構成するという発想が観られ、現代のシステム論や複雑系の考え方と近い。イギリスに亡命したヴォルテールは、「パンセ」は推敲されていない草稿であることに注意を喚起したが、185のような断章を読むと、その先見性に驚く。ニュートン(1642-1727)が因果律原理を前提に、古典力学を完成させるのは、パスカル(1623-1662)の死後である。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
Cioranを読む(91)

■12月28日、土曜日、
 、大寒
、大寒(写真)無題
今日は、朝、あまりにも寒くて、朝一杯と決めている珈琲を2杯飲む。
一仕事して、午後から、Odilon Redon展へ行く。ルドンなどの象徴派は、19世紀に進んだ科学的合理主義に対する反発として現れてくるが、夢や無意識、境界などをテーマにするため、現代のポストモダン状況ととてもよく響きあうように感じた。その意味で、現代的だと思う。面白いのは、科学や技術に対して、単純に反発するのではなく、たとえば、ダーウィンの進化論にヒントを得て、版画集「起源」を制作したり、エジソンの発明した電球の形を、絵のデザインにいち早く取り込んだりと、とても両義的な対処の仕方をするのである。また、1870年にフランスに誕生した、新しい学問、人類学にも敏感に反応している。社会の動きから距離を置いて、隠者のように、神話的なモチーフを描いていた画家、というイメージが、ルドンには強かったので、いい意味で裏切られて楽しかった。まさに、象徴主義は、反近代という社会の一つの大きな動向だったことがわかる。そうなると、当然、こうした画家に影響を与えたポーやボードレール、マラルメ、ユイスマンなどの詩人、作家、ドビュッシーやショーソンなどの音楽家も、近代批判の文脈で捉える必要があるだろう。ルドンと同時代人で、マラルメの「火曜会」の常連だったゴーギャンなどは、非常に分かりやすい反近代の軌跡を描いている。
今日の展覧会の目玉は、パステルの壁画「grand bouquet」(大いなる花束)(162.6cm×248.3cm)だった。しばらく絵の前の椅子でぼーっとしていた。至福の一時だった。ルドンは、初期、「ルドンの黒」と呼ばれ、版画を中心にモノクロの世界を追求するのだが、このとき愛読書だったパスカルの「パンセ」をテーマにした版画集の計画があったという。残念ながら、実現はしなかった。出品された版画「永遠を前にした男」と同じ素描には、パンセから次の言葉が書き込まれている。「この無限の空間の永遠の沈黙がわたしを脅かす」パスカルにはとても関心があるので、ルドンのこの計画が実現しなかったことが、かえすがえすも残念である。

「grand bouquet」(クリックで拡大)
☆
Que surgisse le paradoxe, le système meurt et la vie triomphe. C'est à travers lui que la rasion sauve son honneur face à l'irrationnel. Seul le blasphème ou l'hymme peuvent exprimer ce que la vie a de trouble. Qui ne saurait en user garde encore cette échappatoire: paradoxe, forme souriante de l'irrationnel. Cioran Le Crépuscule des pensées p. 13
パラドックスが現れると、体系は死に生が勝利する。理性が非理性的なものに直面して、己の名誉を守るのは、パラドックスによってである。生のいかがわしさを表現できるのは、冒涜の言葉か賛歌だけである。それができない者にも、抜け道は用意されている。非理性的なものに対する微笑を含んだ形式、パラドックスである。
■とても興味を惹かれる。生のいかがわしさを表現する暴言や賛歌は、詩の起源とも言えるが、パラドックスは、エッセイの起源に位置しているように思えるからだ。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
| « 前ページ |