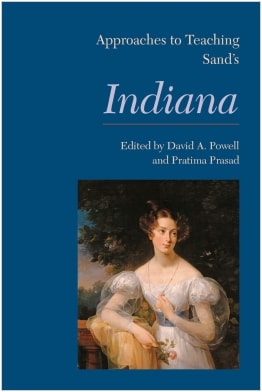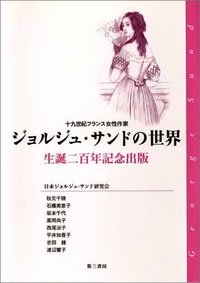『ジョルジュ・サンドの世界』
十九世紀フランス女性作家 ジョルジュ・サンドの世界 ―生誕二百年記念出版
著者:秋元千穂/石橋美恵子/坂本千代/高岡尚子/西尾治子/
平井知香子/吉田 綾/渡辺響子 共著
序章 ジョルジュ・サンドの生涯と作品 平井知香子
第一部 女性作家のエクリチュールの戦略
第一章 『アンディヤナ』の戦略――流行作家への道 石橋美恵子
第二章 『レリヤ』改訂の意図を考える 吉田 綾
第二部 芸術、そして社会へのまなざし
第一章 ジョルジュ・サンドの小説における芸術家像 渡辺響子
第二章 田園小説四部作に見る、パリと地方と理想郷 高岡尚子
第三章 ジョルジュ・サンドの作品に見る演劇性 秋元千穂
第三部 未来への夢――晩年のサンド
第一章 『マドモワゼル・メルケム』に見る理想の女性像 坂本千代
――三十五年後のサンド流ユートピア
第二章 ジョルジュ・サンドと犬 平井知香子
――『アンディヤナ』から『犬と聖なる花』まで
第四部 ジョルジュ・サンドの物語世界における「語り手」の意匠
第一章 女性作者の内在的創造戦略と「語り」の手法 西尾治子
『アンディヤナ』―謎の「語り手」と「私」(je)
第二章 多声的物語世界と「語り」のパラダイム 西尾治子
―『レリヤ』から『モープラ』へ
第三章 『オラース』―「語り手」と歴史の記憶 西尾治子
参考文献
ジョルジュ・サンド年譜
索引
【著者まえがきより(抜粋)】
本書はフランス十九世紀文学を代表するジョルジュ・サンドの生誕二百年を記念して企画
されたものである。東京、関西、九州に在住する私たち八人のサンド研究者が集まり「日本
ジョルジュ・サンドの会」として年二回ほど会合を持つようになったのは二〇〇〇年のことで
あった。サンド生誕二百年にあたる二〇〇四年に向けて、わが国ではほとんど紹介されてい
ない著作の翻訳出版や、絶版になっている翻訳本の再版を働きかけるとともに、私たちの手
で最近の研究成果を多くの方に読んでいただける本として出したいと考えたからである。
サンドに関するこういった試みは日本では初めてであり、試行錯誤の末やっとこのような形で
陽の目を見ることとなった次第である。
サンドはバルザックに匹敵するほど多作な作家であるが、書簡集や紀行文などの翻訳を除き、
わが国で現在も書店で入手できる唯一の小説は『愛の妖精』(岩波文庫)のみであり、その他の
作品はあまり知られていない。作品より人生のほうが面白い作家、男装をし、葉巻をくゆらせ、
パリの街を闊歩し、多くの有名人と交際する飛んでる女サンド。彼女の紹介のされかたはいつも
こんな風であり、詩人ミュッセや、ショパンを恋人とした恋多き女としての名ばかりが先行した。
一九五四年アンドレ・モロワの画期的な伝記『ジョルジュ・サンド』(原題『レリヤあるいはジョ
ルジュ・サンドの生涯』)が日本語に翻訳されたとき、作家の宇野千代(『おはん』、『生きて
いく私』の著者)は阿部艶子との対談で波乱に満ちた自己の人生との類似を認め、「生活者として
の伝記」に興味を持ったと述べている。モロワは伝記の最後で「コンスエロがレリヤに勝った」と
しているが、一八三三年版の『レリヤ』のヒロインをドン・ジュアンにたとえ、「レリヤはどの男も
快楽を与えなかったので男から男へと渡り歩いた」と言っている。このため後の代表作とされる
『コンスエロ』のヒロイン、コンスエロがオペラ歌手として成功し、たくましく生きてゆくのに
対し、伝記の原題名に含まれるレリヤのペシミスティックな女性のイメージの方が強烈な印象を
与え、以後のサンド観に大きな影響を与えた。またサンドと同時代の詩人ボードレールが『赤裸
の心』の中で「悪魔とジョルジュ・サンド」と言ったり、さらに嫌悪に満ちた言葉で激しく揶揄した
ことも大きなマイナス要因になった。
サンドの作品の正当な評価に最も貢献した研究者の一人は、『ジョルジュ・サンド書簡集』(全
二六巻、最終巻は一九九一年)を完結させたジョルジュ・リュバンであろう。リュバンはサンドの
故郷ノアンから二十五キロ離れた地に生まれた。同郷の彼にとって、サンドの田園小説を彩る古い
美しい言葉は祖父や祖母が実際使っていたものであり、登場する農民たちもごく身近な人々であっ
た。小学生の頃からサンドの作品を読んでいたリュバンは最初サンドの伝記を書きたいと思ってい
た。しかし彼自身「すばらしい伝記作者」と認めるざるを得なかったモロワに先を越されてしまう。
彼の関心はこうして書簡編集へと向かう。一九六四年の第一巻から数えて実に二十七年、実質的に
は編者のいう「半世紀に近い」歳月をかけた労作である。十九世紀のフランスが丸ごと映し出されて
いるこの膨大な『ジョルジュ・サンド書簡集』のお蔭で、今後の研究がどれほど実り豊かなものと
なるか計り知れない。こうした先人たちの努力に少しでも報い、本書が再考のきっかけとなって新
たなサンド像の発見となれば幸いである。
本書の第一部は初期の代表作『アンディヤナ』と『レリヤ』を中心に扱う。これらは若き日の
サンドがペン一本で流行作家となるための苦闘の跡がにじみ出た作品である。
第一章ではフェミニスト・サンドの第一声となった『アンディヤナ』をメロドラマ、イギリス趣味、
異国趣味の観点から分析する。
第二章は、初版と改訂版の二つの『レリヤ』をとりあげ、その改訂の意図を探る。従来、モロワが
伝記で強調した初版の『レリヤ』に対し、改訂版の『レリヤ』は舞台が修道院に移ったため面白みの
ない宗教小説と捉えられがちだった。しかしこの改訂こそ「愛と理想と真実を求めてやまないヒロイ
ンの魂」ゆえに作家サンドにとって必要な作業であったとしている。
第二部では円熟期の作品を主に扱い、サンド文学の真髄に触れる。
第一章は『アルディーニ家の最後の令嬢』、『オラース』、『テヴェリノ』を中心に芸術家像を追う。
第二章は社会主義小説から田園小説へ。田園小説が書かれた時期は二月革命を挟んで思想的にも大きな
転換点にあたる。作者の目が社会の不平等や悲惨な下層階級の人々に向けられ、やがて田園の中に理想
社会を求めるようになる。代表作として最もよく知られている田園四部作、『魔の沼』、『棄て子フラン
ソワ』、『愛の妖精』、『笛師のむれ』を「乖離と融合」という共通テーマに沿って分析する。
第三章ではサンドが若い頃から興味を抱いていたファンタスティックと郷土色豊かなメルヴェイユウ
という二大文学ジャンルに焦点を当て、劇作を中心に読み解いている。
第三部は長い作家生活の最後の時期にサンドがいかなる夢を描いたかを見る。
第一章は一八六八年に発表された『マドモワゼル・メルケム』を『アンディヤナ』と比較し、その恋愛観
と結婚観がどのようなものであったかを検討する。
第二章ではサンドの作品における「犬」をトニー・ジョアノの挿絵とともに追う。犬はサンドの作品の初期
から後期に到るまで必ずといっていいほど重要な場面に登場する。オフェリヤ、ブレロー、ラブリッシュ、
パルプリッシュ、バッコ、そしてファデ。サンドが『祖母の物語』の一番後に書いた『犬と聖なる花』では、
なんと犬のファデはルシヤン氏(犬氏)に進化するのである。
最後にサンドの作品群という広大な世界を探索するにあたってこれまでと切り口を変え、「語り手」の問題
を考察する。十九世紀フランスの文壇という男性中心社会で女性作者が生きていくためには、外的創造戦略
としては、「筆名」と「男装」を、内的創造戦略としては「語りの手法」と「仮面」が必要であった。サンドはこれ
らの戦略を縦横無尽に駆使し、独自の小説世界の構築に挑んだのである。『アンディヤナ』、『レリヤ』、
『モープラ』、『オラース』などの主要作品を中心に「語り手」を六種類のパターンに類型化し検討した。
『レリヤ』で論証された「不可視のポエジー」はもうひとつの『レリヤ』を読み解く鍵となるであろう。
http://www.daisan-shobo.co.jp/book/b37459.html