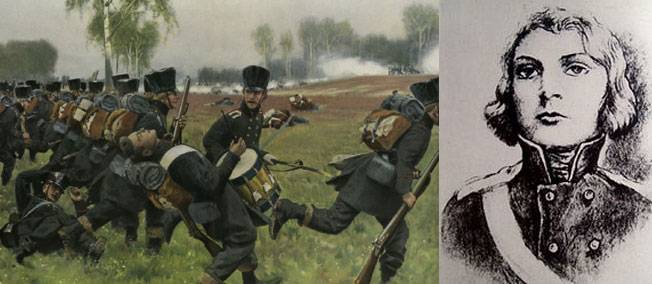Les mémoires, une question de genre ?
Béatrice Didier, « Masculin/Féminin chez George Sand », Itinéraires, 2011-1 | 2011, 85-91.
Au xixe siècle, la différence entre masculin et féminin est fortement soulignée dans le vêtement, dans la répartition des tâches, et G. Sand le rappelle avec humour dans Histoire de ma vie. Cependant son œuvre romanesque semble marquer une nette évolution, dans une transformation du personnage féminin central : de la femme-victime (Indiana, victime du mari, de l’amant, de la société) à la femme forte (Lélia, abbesse des Camaldules dans la version de 1839 ; Tonine, chef d’industrie dans La Ville noire). Mais c’est dans le dialogue avec Flaubert que cette relation du masculin et du féminin prend la forme la plus originale avec l’affirmation que la création est fondamentalement hermaphrodite.
Itinéraires
Masculin/Féminin chez George Sand
Béatrice Didier
p. 85-91
Béatrice Didier, « Masculin/Féminin chez George Sand », Itinéraires [En ligne], 2011-1 | 2011, mis en ligne le 01 avril 2011, consulté le 22 novembre 2017.
http://itineraires.revues.org/1629 ; DOI : 10.4000/itineraires.1629