2019.4.13秋川渓谷の春・広徳寺さんの巨木を見に坂を上る。
説明板発見:広徳寺境域 東京都指定史跡 昭和53年3月6日指定
臨済宗龍角山広徳寺は、応安6年(1373)正応長者の開基で、またその妻、龍智智雲尼が鎌倉の建長寺70世である心源希徹禅師を請うて開山したと伝えられています。その後、天文年間(1532-55)に北条氏康によって堂舎が再建され、江戸時代には幕府から40石の朱印地が与えられ、約12000坪(39600㎡)の境内地を有しました。寺は五日市盆地西縁の秋川右岸の山麓に立地しています。
境内は地形状の制約から、東向きに総門・山門・本堂が東西の中心軸上に配置され、山門と本堂の間の参道を挟んで北側の鐘楼と南側の経蔵とが対置する禅宗伽藍で構成されています。
現在は、18〜19世紀代再興の伽藍と、総門の前面と北側の土塁や貯水池などの遺構が残っています。 平成22年3月設置 東京都教育委員会」
トップ画像は、寺社標のすぐ奥にあった総門から奥に山門を配置して撮影してみた。
説明板発見:広徳寺総門 市指定文化財
切妻造の一間一戸四脚門・桁行は3、64メートル。梁行は3、01メートルある。
中央の2本の柱は円柱、前後の柱は四角柱で、いずれもケヤキ材を使用し、腰貫がしつかり通っており、全体の作りは簡素にして堅固である。
カエル股等も素朴で、室町期の面影を残し、当町内の建築物としては最も古式をとどめている。
正面に掲げられた「龝留禅窟(あきるぜんくつ)」の大額は「前雲国主松平不昧治郷書(さきの国主松平ふまいはるさと)」とあり江戸後期の文化人として高名な出雲の殿様松平不昧公の筆になる。
昭和59年秋より解体修復がされ、さきの扁額が裏面の墨書により文政2年(1819)に作られたことが明らかになった。不昧没後1年を経ている。 昭和44年7月10日指定 あきる野市教育委員会」
散策直後、まだ桜が残ってるうちにと4月15日に散策をダイジェストして記事を投稿してます。
説明板には広徳寺の配置図がありました。
総門から山門の間は参道で結ばれており、広徳寺さんは桜の名所でもあるので、しだれ桜越しに山門を撮影したいところですが、残念ながら参道の桜の見頃が過ぎてました。
なんとなく雰囲気を感じられるように撮影してみた。

説明板発見:
広徳寺山門 市指定文化財茅葺、寄せ棟造の三間一戸二重門である。桁行は6、36メートル、梁行は3・64メートルあり、礎石は自然石。下層より上層の方が大きく、ときょうは綺麗に組まれ、垂木の線も美しい。前面は通路をふくめ3つに区切られているが太い柱と腰貫が安定感を保っている。足の礎盤は木製である。
階上は回廊がめぐり、中央が四扉にあけられ、左右に花灯窓が一つづつある典型的な禅宗(唐様)の山門である。
楼上に「正眼閣」の横額が掲げられており、その額、ならびに建物全体の状況から江戸中期をさかのぼらない建造物と推測される。簡素で調和のとれた建物で、境内に落ち着いた雰囲気をあたえている。
平成3年秋より永く保存し、公開することができるように全解体修復工事がされた。
昭和44年7月10日指定 あきる野市教育委員会」
山門に感激し、満足して振り向いてびっくり!
迫力のイチョウが2本並んでいた。大きさを感じれるように左のイチョウの真下にダンナに立ってもらう。樹齢100年越えは間違いなさそうですが、調べてもこのイチョウの樹齢・樹高・目通り幹囲の資料が見つかりませんでした〜。
大きな茅葺屋根の本堂に参拝。広徳寺さんに立ち寄ったのは巨木のため。本堂の裏手へ向かいます。
画像左にあるのが目的の都内最大のタラヨウです。本堂が大きいので、タラヨウの大きさを感じにくいのが残念。
4月15日の記事に紹介しましたが、タラヨウは葉に字を書くと黒く浮き出る特徴があります。もう一度同じ画像を貼り付けてみる。
説明板発見:広徳寺のタラヨウ 東京都指定天然記念物 昭和27年11月8日 指定
龍角山広徳寺は、五日市の古刹として著名な寺院であり、その本堂の裏手にこの都内最大のタラヨウがそびえています。
タラヨウはモチノキ科の樹木で、主に東海地方から近畿地方以西の日本と、中国大陸の暖帯に分布する高木の常緑樹です。
本樹はほぼ自然形を保っており、主幹は直立し、幹周り2・5メートル、樹高は19・1メートルに達します。その枝張りは東西約14・2メートル、南北15・5メートルの威容を保っています。 平成22年3月設置 東京都教育委員会」
広徳寺には巨木がもう1本ある。
説明板発見:広徳寺のカヤ 東京都指定天然記念物 指定:昭和27年11月8日
広徳寺の北側にそびえるこのカヤは、目通り幹囲5・35メートル、樹高24・45メートルを測る多摩地域で最大のカヤです。このカヤの枝張りは東西13メートル、南北約19・4メートルですが、樹冠下方の大枝は南方向に伸び、北側には大枝がありません。
カヤはイチイ科に属し、暖地の森林中に散在する常緑の高木です。東北地方中部から屋久島までと、韓国の済州島にその分布が見られます。
材は、建築、器具、土木用に利用されるほか、種子から採られる油は、食用油、整髪油、薬用駆虫剤として利用されます。 平成22年3月設置 東京都教育委員会」
巨木の周囲には囲いがあり、木に触れない。残念だ。
見上げて満足する。さて時刻は14時46分、出発だ。
その時強めの風が吹いた。
一斉に桜の花びらが舞う。画像に移る白い点は全て桜の花びらです。
来た時とは別の坂を下りる。
坂道の途中にベンチを見つけあられでおやつ休憩。
再び坂を下りる。画像左手の緑の壁。そこにも桜が植わってて、上に道がある。そこを通ってきたのだ。
ガードレールの向こうに枝をバッサリ切り詰めた木があった。

よく見れば、細い枝に若葉が出てた。なんとか生きてるようで安心した。
長い坂を下りたら庚申塚があった。
これが武蔵五日市駅から歩いてくると広徳寺さんへの道の目印になる。
秋川に向かう途中で振り返る。
降りてきた坂道に沿って桜が並んでいた。
15時5分、小和田橋に到着。武蔵五日市駅側の観光案内所でいただいた観光マップには、小和田橋に秋のビューポイントマークがついている。
たぶん川岸の落葉樹の紅葉が綺麗なんだろうなあ〜。











































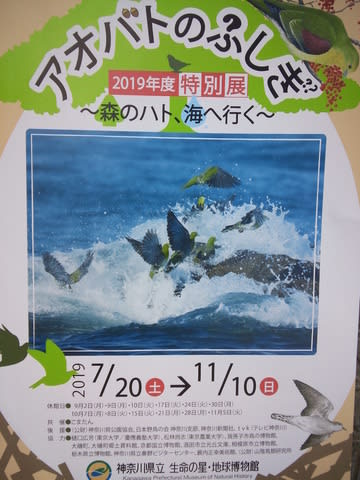






 狛犬も苔が背中についてますね。
狛犬も苔が背中についてますね。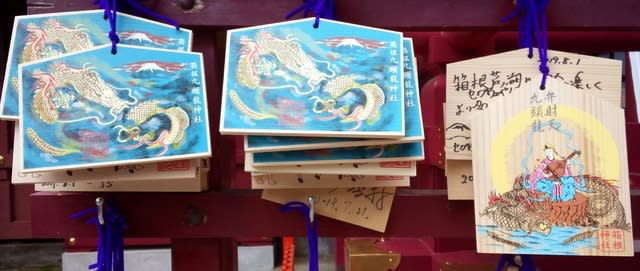

















 (奥が京都方面)
(奥が京都方面)


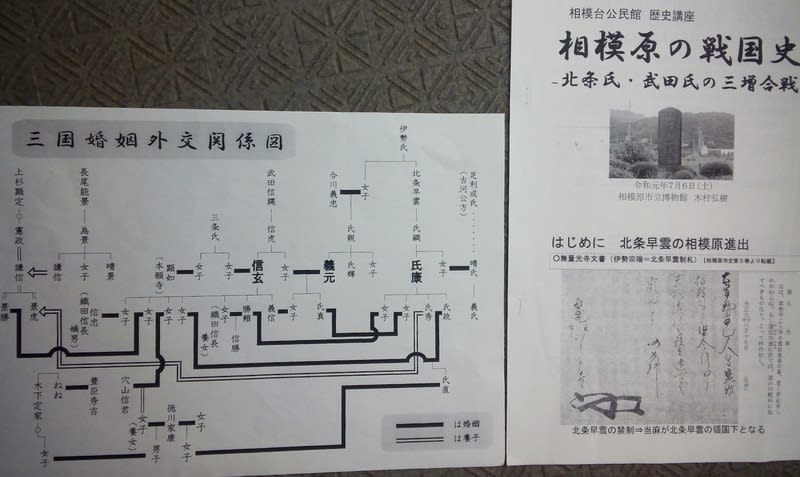
 ご覧の通り、きわまで道路で、歩道がない!ちなみに、目的の木はもう見えてます。道路の向こう側です。
ご覧の通り、きわまで道路で、歩道がない!ちなみに、目的の木はもう見えてます。道路の向こう側です。























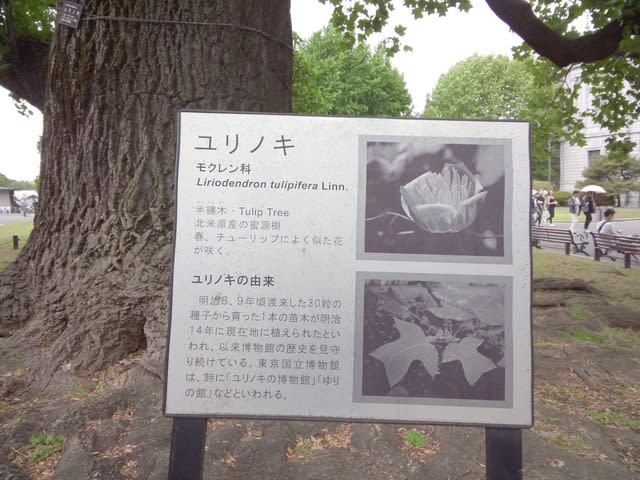










 説明板発見:
説明板発見:









 よく見れば、細い枝に若葉が出てた。なんとか生きてるようで安心した。
よく見れば、細い枝に若葉が出てた。なんとか生きてるようで安心した。












 小さめのマンホールにも秋川を泳ぐ鮎の絵があった。次はどこへ行こうか?迷ったものの、
小さめのマンホールにも秋川を泳ぐ鮎の絵があった。次はどこへ行こうか?迷ったものの、



















