あらためて言うまでもないが、芥川龍之介『蜘蛛の糸』は、蜘蛛の糸によって救われるはずだったカンダタが、自分だけが救われたいという欲を出したために、地獄に再び堕ちてしまうという話である。
地獄に堕ちたカンダタを見て御釈迦様は、「悲しそうな御顔をなさりながら、またぶらぶら御歩きになり始めました」。「御釈迦様の御目から見ると、浅間しく思召されたのでございましょう。しかし極楽の蓮池の蓮は、少しもそんな事には頓着致しません」
まあ、のんきというか薄情というか。
これじゃいくらなんでも、というので、このあと阿弥陀さんがカンダタに説法し、カンダタは無事、極楽往生する、というアニメを見たことがある。
芥川龍之介もあれじゃまずいと思ったのか、『杜子春』を書いている。
仙人になろうと、老人の言葉に従って、何があっても黙っていた杜子春は、畜生道に堕ち、馬になった父母が地獄の鬼から打たれるのを見、そして母が「心配をおしでない。私たちはどうなつても、お前さへ仕合せになれるのなら、それより結構なことはないのだからね。大王が何と仰つても、言ひたくないことは黙つて御出で」と言うのを聞いて、思わず「両手に半死の馬の頸を抱いて、はらはらと涙を落しながら、「お母さん。」と一声を叫びました」。
『蜘蛛の糸』のタネ本は、ドストエフスキイ『カラマゾフの兄弟』の中に出てくる「一本のねぎ」という話だという説があった。(本当のタネ本は鈴木大拙訳『因果の小車』)
グルーシェンカという女が「一本のねぎ」の話をする。
グルーシェンカはカラマゾフ父子を手玉にとる悪女だと思われているのだが、実は心のきれいな女性で、『罪と罰』のソーニャのような聖なる娼婦である。
グルーシェンカは「あたしいけない女だけれど、それでもねぎをあげたことがあるの」と言って、「一本のねぎの話」をする。
そしてグルーシェンカは、「あたしそらで覚えているのよ。だってこのあたしはその意地悪婆さんなんですもの」と言う。
『蜘蛛の糸』と違って、ぐっとくる話である。
守護天使のような、自分のために泣いてくれる人がいるということが救いなのでないか。
そして、杜子春のように、人のために泣けるということが。










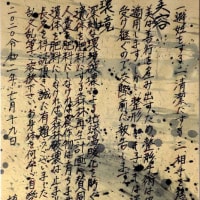
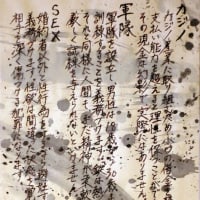
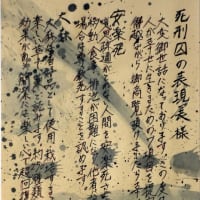

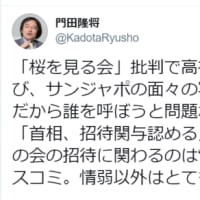
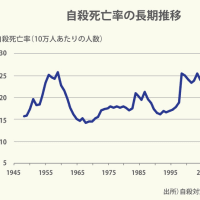
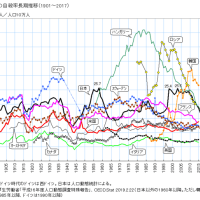
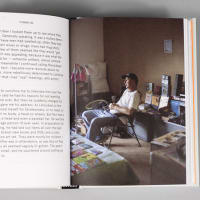
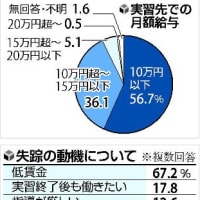

でも、原典にもどればそれは、どういう場所なのでしょうか。。。というところで。
http://www.pure.ne.jp/~ngo/terakoya/2002bara2/01isetcolumn04.html
寄り添ってくれる人(苦楽をともにしてくれる人。自分のことを思ってくれる人。
自分の有り様を嘆き、悲しみ、泣いてくれる人と言っていいでしょうか)そんな人がいないところが、地獄だと源信さんは、言うわけですが。
https://my-mai.mainichi.co.jp/mymai/modules/eye3/index.php?p=221#more-221
17行目にある
>仏教にすがりながら「人の役に立ちたい」と路上のゴミを拾い歩いていた。
という人のことが気になって、記者に問い合わせてみました。すると、連載された記事には
お釈迦さまの弟子に、抜群にデキル兄を持つ周利槃特(チューラパンタカ)っていう人がいて、物覚えが悪いので自身を喪失していたところ、 お釈迦さまに箒を渡されて「塵を払い、垢を除かん」と教えられ、来る日も来る日も塵払いをし続けて、悟りを開いた…っていう話がありまして。
で、この人は仏教学校を出ていて、幼いころに学んだその教えを思い出し、「酒やギャンブルにおぼれ、人に暴力をふるったダメな自分でも、無心でゴミ拾いを続ければ…」という気持ちで、今も毎日、箒を持ち続けているのだそうです。
万Gさんに勧められて、こちら、のぞかせていただいています。
芥川は「カラマーゾフ」を読んで「蜘蛛の糸」を書いたという説が有力です。
守護天使を釈迦と置き換えて「蜘蛛の糸」を書いたとしても、芥川の仏教に対するイメージがかいま見られるところで、円さんの指摘されている違いは興味深いと、自分も思います。
そこには仲間がいますから。
http://ww4.tiki.ne.jp/~enkoji/kodoku.html
ただ一人で掃除を続けるというのは普通はできないことですね。
ひょっとして、その方の孤独はまわりの人にはうかがい知れないものがあるのかもしれません。
教信沙弥ですか、なるほど。
林哲也という人のサイトに「蜘蛛の糸」のタネ本はポール・ケーラス「カルマ」を鈴木大拙が翻訳した「因果の小車」だとあります。
http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/memb/hayashi/akutagawa.html
「一本のねぎ」のタネ本はアファナーシェフ「ロシア伝説集」の中にある「キリスト兄弟」だそうです。
じゃ、「カルマ」の元ネタは何なのか、どうして「キリスト兄弟」と似ているのか、ということが気になります。
芥川龍之介は仏教に関心がなかったそうですが、知識としては私なんかよりはるかにあったでしょう。
「杜子春」は仏教的ですしね。
アディクション(関係性)・モデルで考えると、もはや地獄行きと極楽行きという観念自体が意味を成さなくなるんではないかと思い始めた今日この頃、、、
「宗教を健全な魂の宗教と病める魂の宗教に大別し、前者は楽観的な背改像から自己超克をなす宗教観をなし、後者は反対に、世界を悲観的に捉え、慰めそして救いの信仰を基盤としている」
http://www.eonet.ne.jp/~radical/1902.htm#%83W%83F%83C%83%80%83X%81u%8F@%8B%B3%93I%8Co%8C%B1%82%CC%8F%94%91%8A%81v
自分は罪が深く煩悩が激しいからというので地獄は定まった住みかだと言う親鸞と、犯罪加害者に共感して、親はどういう気持ちでいるだろうかとか、ひょっとして自分も同じことをしていたかもしれないなどと考えるのは病める魂、つまり釈尊的だと思います。
杜子春のオチって、原作と芥川の創作との違いがあるんですね。目の前で苦しんでいる母親に向かって「おっかさーん」と思わず叫んでしまう。
声を出さなきゃ仙人になれたのに。あーあざんねーんという結末。
声を出さなきゃ、お前を殺していたぞーという結末。
声を出したがゆえに殺される。。。って人もいますよね。
仙人になるってなんでしょう。
仙人であるためには人間としての当たり前の感情を持ったらだめだということでしょう。