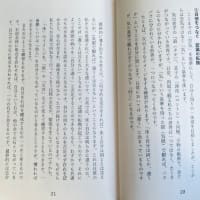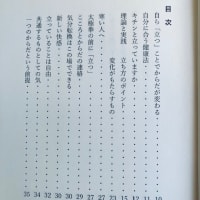井上陽水の歌に「いつのまにか少女は」という歌がある。1番から3番までのサビはそれぞれ「君は静かに音もたてずに大人になった」「君は季節が変るみたいに大人になった」「君の笑顔は悲しいくらい大人になった」と書かれている。
少女に恋心を懐いているであろう「片想いの観察者」は、「いつまでも少女でいてほしかった」のだが、無情にも「大人になってしまった」少女。それは何より激しい音を立てるはずの出来事であるにも拘らず、「観察者」の知らないところで「君は静かに音もたてずに大人になった」のである。
季節はいつでも、人の思惑に関係なく循環するものだが、片想いの観察者にとって季節は止まる。春は春、夏は夏、君は君、「この想い」は「この想い」であり、変わらないものなのだ。しかし無常にも「君は季節が変わるみたいに大人になった」のだ。
少女が大人になるということは、単に身体が変わることではない。今まで守ってきたもの全てを失っても、手に入れたいものができるということ。平等に与えていた「笑顔」を特定のものに限定してしまうことかも知れない。片想いの観察者だけが、少女の一番美しいところを知っている。少女がそれを無くしてしまったことを、少女自身は自覚し得ないが、観察者には「悲しいくらい」良くわかる。3番のサビの直前に「だけど春の短さを誰も知らない」とある。結局手に入れた「春(幸福)」もまた無常の真理(季節が変るみたい)により、変わっていくのだが、それを知らずに求めてしまう「君の笑顔は悲しいくらい大人になった」のである。
変わる少女の後ろには、いつも変わらない「片想いの観察者」がいた。
付
少女が大人になるのに時間はいらない。刹那に変わる。
小椋佳作詞で、陽水も歌った「白い一日」。「ある日踏切りの向こうに君がいて 通り過ぎる汽車を待つ 遮断機が上り ふり向いた君は もう大人の顔をしてるだろう」