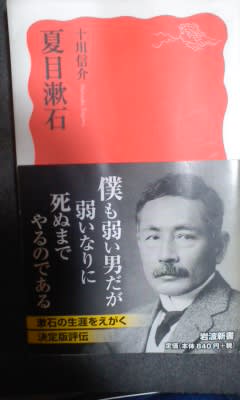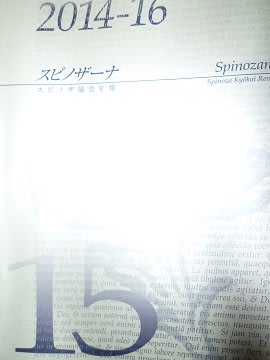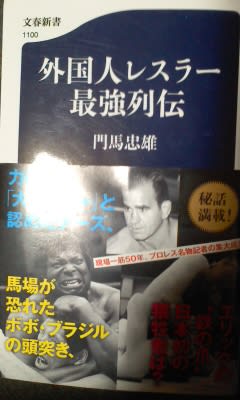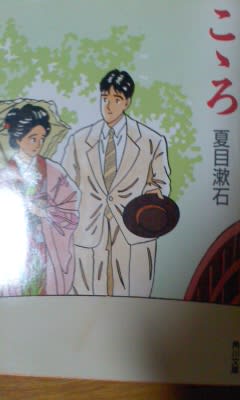スピノザの『エチカ』について僕が考えていることと,趣味である将棋・競馬・競輪などについて綴るブログです。
宇都宮で指された昨日の第43期棋王戦五番勝負第一局。対戦成績は渡辺明棋王が5勝,永瀬拓矢七段が1勝。
振駒で渡辺棋王が先手になり矢倉。永瀬七段は雁木に。この戦型は増えていて,それは後手の矢倉対策として優秀だという認識が主流になっているからですが,この将棋は序盤で先手がうまく立ち回りました。

先手が1筋の位を取った局面。後手は馬を作っていますが持ち歩の数が大差ですでに先手がよいと思われます。
ここで後手は☖4五歩と取って☗同桂☖4四銀右☗3三歩の攻めを呼び込みました。
苦しいながらもここは☖4二金左と逃げておかなければいけなかったのだろうと思います。しかし☖同桂☗同桂成☖同銀の交換に応じたために☗2五桂☖4六歩に☗1四歩☖同歩☗1二歩☖同香☗1八飛と持ち歩を生かした端攻めを喰らうことになりました。
☖2四銀と端を受けたところで☗1三歩☖同香☗同桂成☖同銀と清算されてから☗4四歩。銀を見捨てられないので☖同銀と取って☗7一角の両取りに☖6二飛と受けたものの☗同角成☖同金☗8二飛☖7二桂☗6三歩☖6一金☗8一飛成☖4三角☗6二歩成☖同金☗6四香と流れるように攻められました。

土俵際に追い詰められた感のある第2図以降,後手は腰の重い粘りを発揮して容易には土俵を割らなかったのですが,かといって土俵の中央まで押し戻すということもできず,先手が押し切りました。
渡辺棋王が先勝。第二局は24日です。
希望spesは喜びlaetitiaの一種で不安metusは悲しみtristitiaの一種です。よって希望は恐怖metusより人間の現実的本性essentia formalisに適合します。つまり自己の有を維持するのに役立ちます。しかし希望も不安もその定義Definitioから必然的にnecessario混乱した観念idea inadaequataとともにある感情affectusです。よってあるものに希望を感じようが恐怖を感じようが,そのあるものに対しては必然的に虚偽falsitasです。しかしその虚偽である希望を真verumと錯覚すれば,すなわち誤謬errorを犯した場合は,その希望を否定する者,あるいは不安を抱かせる者と闘争することが勇気animositasと錯覚されることになります。なぜなら勇気は,自己の有を維持することを希求する欲望cupiditasであり,それは能動的な感情でなければならないのですが,誤謬を犯している無知の人は虚偽を真理veritasと妄信しているのですから,それが能動的な欲望であると錯覚するからです。つまり,自身の希望に関して誤謬を犯す人は,その誤謬の対象が戦い得る相手である限り,必然的に勇気についても誤謬を犯すようになっているのです。そしてこのメカニズムが,こうした無知の人に新たな感情を呼び起こすことになります。
第三部諸感情の定義二八は,自己への愛philautiaのために自己を正当以上に感じることを高慢superbiaといっています。勇気について錯覚し,希望を砕き恐怖を呼び起こす相手を否定する,要するに排他的思想を有する人は,この高慢の条件を満たしているとはいえません。ですがこのような無知の人は,実際には高慢という感情にも隷属しているのです。なぜなら,自己を正当以上に感じていなくても,相手のことを正当以下に評価するなら相対的に自己を過大評価しているのと何ら変わるところがないからです。スピノザも第四部定理五七備考で次のようにいっています。
「他人について正当以下に感ずる者もまた高慢と呼ばれるということである。したがってこの意味において高慢は,人間が自己を他の人々よりすぐれていると思う謬見から生ずる喜びであると定義される」。
これが排他的思想を有する人に著しく妥当することは明白でしょう。なぜならその人は,排他的思想の対象者より自分が優れていると思い込んでいるのであって,しかもその思い込みの要因は虚偽による謬見であるからです。
四日市競輪場で争われた第33回全日本選抜競輪の決勝。並びは吉沢‐平原の関東と古性‐村上義弘‐村上博幸‐椎木尾の近畿で新田と原田と山田が単騎。
原田がスタートを取って前受け。2番手に新田,3番手に吉沢,5番手に山田,6番手に古性の周回。残り3周のバックから古性が上昇。吉沢が引いたので古性は新田の後ろに入り,7番手に吉沢,最後尾に山田で,2番手と3番手,6番手と7番手には間隔がある一列棒状に。残り2周のホームから古性が徐々に上昇していき,バックで原田を叩くと打鐘から全開で先行。椎木尾の後ろが内の原田と外の吉沢で併走になり,新田は平原の後ろで山田が最後尾という隊列に。ホームの出口から吉沢が発進していくとバックに入って村上義弘が番手から発進。平原も自力で出ていこうとしましたが村上博幸が牽制。しかし平原を追う形になった新田が大外を豪快に捲り切って優勝。村上義弘が1車身差で2着。村上博幸が1車輪差の3着で新田を追った山田が8分の1車輪差まで迫って4着。
優勝した福島の新田祐大選手は競輪祭以来の優勝でビッグ9勝目,GⅠは7勝目。全日本選抜競輪は初優勝。当地では2013年に記念競輪の優勝があります。このレースは4人で並んだ古性の先行が有力。ただ,吉沢も早めに仕掛けるでしょうし,村上義弘はあまり早くから番手発進するタイプではないので,一列棒状の最後尾にでもならない限り新田の捲りが届く公算が高いと考えていました。その見立て通りのレースになったのですが,無駄に動かないで平原の後ろでじっとしていたのがうまかったように思います。吉沢が仕掛けてそのスピードも使えた分,はっきりとした差をつけての優勝という結果になったのではないでしょうか。競技との関係でこの開催が競輪は今年の初出走だったのですが,今年も中心選手として君臨していきそうです。
無知の人が排他的思想を有するようになると,排他的感情を抱いている相手に対して攻撃性が強化される要因として,以下の事情も作用していると考えられます。
無知の人は自分が正しいと認識しています。これは善bonumという意味で正しく,真verumという意味でも正しいという二重の意味です。このために,自身に不安metusを抱かせる者,自身の希望spesを消滅させる者は誤っているみなします。これもまた,悪malumという意味で誤りであり,虚偽falsitasという意味での誤りであるという二重の意味をもちます。このとき,無知の人にとっては,排他的感情を抱く対象が,自身と同じように無知の人であるか,そうではなく自由の人homo liberであるのかということは関係ありません。自身が正しいと妄信している以上,相手が誤謬errorを犯しているかいないかということは,もはやその人にとっては無関係になってしまっているからです。
このような状態に陥ったときに,無知の人は自分の希望を守るために,それを妨害すると表象するimaginari者のことを排斥しようとします。このことは単に,人間は喜びlaetitiaを希求し悲しみtristitiaを忌避しようとするという現実的本性actualis essentiaを有しているということから説明できます。したがってその希望を妨害する者と戦うこと,つまり攻撃することを是とするようになるのです。一般に排他的思想を抱く人は好戦的であり,平和を追求しないという傾向が顕著であるのは,このような仕組みになっているからです。そこでこうした無知の人は,希望を打ち砕く者と戦うことが勇気animositasであり,逃げ出すこと,より積極的にいえば平和的に融和を図ろうとすることを臆病であると錯覚するようになるのです。この勇気という感情affectusの錯覚が,無知の人を攻撃的にする要因のひとつであると僕は考えています。

スピノザによれば勇気とは,第三部定理五九備考に示されているように,「精神の強さfortitudo」という欲望cupiditasの一種で,能動的に自己の有esseを維持しようとする欲望です。すなわち第三部定理五九であるといわれている能動的な欲望のひとつです。したがって無知の人の勇気は正しい意味での勇気ではありません。それは確かに自己の有を維持しようとする欲望ではありますが,能動的ではなく受動的だからです。
『ドストエフスキイの生活』はドストエフスキーの伝記です。あるいは評伝です。小林秀雄はドストエフスキーの生い立ちがドストエフスキーの作品の理解には欠かせないと考えたので,自身で評伝を欠いたのでした。作家論と作品論の分類でいけばこれは作家論に属し,僕自身の志向からは外れます。ただ,夏目漱石の作品に関しても,漱石の生い立ちがその理解には欠かせないと考える評論家は多くいます。『決定版夏目漱石』を書いた江藤淳や『夏目漱石を読む』の吉本隆明などはその代表といえるでしょう。
僕の志向とは異なるのですが,こうした評論を読む場合には,漱石の伝記があれば便利でしょう。漱石は幼少期から青年期にかけてはドストエフスキーよりもっと複雑な生い立ちをしていて,個々のエピソードとしては有名なものもあり,それは知っているという場合でも,それが時系列としてどの順序で漱石の身に生じたのかということについてはよく分からないという場合もあるであろうからです。
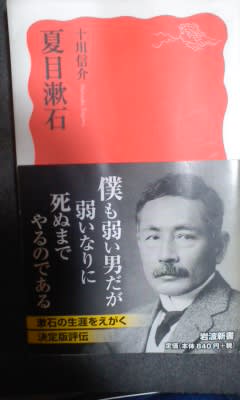
一昨年の11月に岩波新書から発売された十川信介による『夏目漱石』は,そういう場合に便利な一冊です。伝記としてコンパクトにまとまっていて,価格も手頃なものなので,僕は漱石の伝記としてはこれを推薦しておきます。
ただ,伝記とはいってもこれもまた『ドストエフスキイの生活』と同様に,評伝でもあります。漱石は作家なので,作品についても触れられていて,そうした部分に関してはそこに十川による判断が挟み込まれているのは当然で,それは読者も簡単に理解できるでしょう。ただそれとは別に,純粋な伝記として読めそうな部分の中にも明らかに十川の価値判断が入り混じっている部分もあります。
こうしたことは伝記を読むという場合に一般的に気を付けなければならないことですので,そのような判断がどう差し込まれているのかの具体的な一例は,後の機会に説明することにします。
同一の不安metusを多くの人びとが共有し,その恐怖metusが同一のあるいは似通った希望spesによってそれらの人びとのうちで第四部定理七の様式によって除去され,かつそれが偽であるということを認識しない,いい換えれば誤謬errorを犯している場合に,その不安と希望が個人であれ集団であれ人間に向かっているときには,そうした個人あるいは人間集団に対する排他的思想は強力化します。そしてその攻撃性を増加させます。
単に同一の不安を共有している人数が多いだけで,その不安を抱かせる個人あるいは人間集団に対する排他的感情は強化されるということはすでに示しました。これは善悪という規準によって強化されているのです。すなわち排他的感情を有している人が善bonumで,それを共有しない人が悪malumであるという観点から強化されるのです。さらにこの場合には真偽の観点が加わっています。それが強力化の大きな要因になります。すなわち誤謬を犯すことにとって排他的思想を有する無知の人は,自身が真verumで自身の希望を打ち砕く者が偽であるとみなします。したがって,自らが誤謬を犯した上で,誤謬を犯しているのは相手の方であると思い込んでいるのです。よって相手の行いのすべては誤りであって,自分たちの行いが正しいと妄信してしまうのです。この場合,互いが互いにそのように思い込むというケースがあり得るのは確かなことで,そこにはもう両者が一致することができる妥協点すら見出すことが不可能なほどに対立が激化することになるでしょう、
その対象が個人であれ国家Imperiumであれ民族であれ宗教religioであれ,排他的思想を有する人が相手に対する攻撃的な態度を取るケースが生じるのは,概ねこのようなメカニズムに従っているのではないかと僕は考えています。このゆえに,僕は無知の人として希望によって恐怖を打ち消すことを,全面的には肯定しません。不安に苛まれているより希望に満ち溢れている方がまだましではありますが,それはその当人にとってまだましであるというだけにすぎません。誤謬を犯した上で誤謬を犯しているのが相手方であると思い込み,相手方に対する攻撃性を激化させるという側面を見落としてはならないと思います。
⑭-6のような罠が仕掛けられていることを見破った後手は,⑭-5の第2図から☖6五飛と王手を掛けました。

先手はこの手は見落としていたそうです。ですから⑭-4の第1図では☗4四香としておくのが優りましたし,⑭-5の第2図で☗8八金と打った局面でも☗4四龍~☗3二金と進めた方が本当はよかったという結論になるでしょう。実際には第1図も先手が勝っているのですが,安全な橋があったのに最も危険な橋を渡り切るような形になりました。
☖6五飛は王手ですが,真の狙いは飛車を5段目に利かせて後手玉の詰めろを消すことです。ただ王手ですからこれは☗6六歩と受ける一手。さらに詰めろを消した後手がそこで☖8八馬と金を取った手に対しても,後手玉が詰まない以上は先手は☗6五歩と飛車を取る一手です。見落としがあったのですが,必然の手順に進めなければならなくなっていたことは,逆に先手には幸いしたかもしれません。

後手は一時的に詰めろを解消して金を取って馬を先手玉に近付けましたが,その代償に飛車を先手に渡しました。こうなれば後手は受けることはできません。よって第2図は先手玉が詰めば後手の勝ち,詰まなければ先手の勝ちという分かりやすい局面になっています。AbemaTVの解説では一目は詰みと言われていたのですが,実際には詰まないので先手の勝ちです。ただ,最後のところで,別の観点から印象的な出来事がありましたので,終局付近まで進めることにします。
自分が希望spesという感情affectusを抱いている事柄に対して,それは必然的にnecessario偽であるのに真verumだと妄信するとき,その事柄が対人間,個人であろうと集団であろうと対人間の場合に生じると,その個人や人間集団に対する強力な排他的思想になりやすいことは,それ自体で明らかでしょう。なぜならその人は,単にその個人あるいは人間集団が,自分の希望を破壊する,あるいはその希望によって消し去った不安metusを蘇らせるという意味での悪malumと判断しているだけでなく,その個人あるいは集団が,偽であると認識していることになるからです。一般的にいっても,ある人を偽であると判断すれば,その人を信用することは困難です。嘘つきと思っている人の言っていることを信じよといっても,それが容易でないことは,経験的にも理解できると思いますし,またそうした経験がないとしても,それが困難なことであるということは理解できるでしょう。したがってそこでは人間の融和は発生せず,分断だけが発生することになります。
とはいっても,その人がひとりでそのように妄信しているだけなら,確かにその人はある個人や集団に強力な排他的思想を有し,そうした個人や集団を敵視するでしょうが,一定の数の市民Civesのうちでその人だけがそういう思想を有するだけですから,そこまで大きな問題とはなりません。市民の間ではその排他的思想が誤りであるという認識cognitioが共有されているからです。ところが不安と希望は表裏一体の感情であるがゆえに,他人の不安をそれと相反する希望によって打ち消すような操作をすることは不可能なことではありません。第四部定理六三備考でスピノザがいっているのは,まさにそういう操作をする人間が迷信家であるということです。また,すでに示したような,他人の不安につけこむ詐欺行為が成立するのは,実際にそのような操作をすることが可能であるからです。
さらに,恐怖metusというのはあくまでも個別的なものではありますが,異なった人間が同一の対象に対して同じような不安を抱くということはあり得ます。そこでそれらの人びとが同じように自身の希望を真と妄信すれば,排他的思想はそれだけ大きな力を有することになります。
『スピノザ―ナ15号』の上野修の論文で触れられている事柄のうち,当ブログとの関連での注意点は以下のことです。
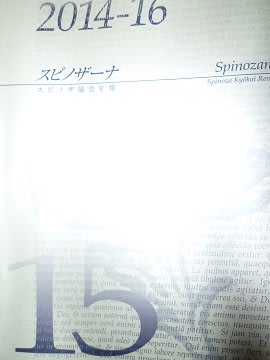
スピノザは自然権を,jus naturae,jus naturale,naturae jus,naturale jusと様ざまに表記します。これはラテン語の活用と関係していて,上野によれば前のふたつは自然の権利と訳し,後のふたつは自然的権利と訳すのが適切なようです。意味の相違は僕には不明ですが,このような例がほかにもあることは僕も気付いていました。たとえば人間の本性はhumana naturaともnatura humanaとも記述されています。上野に従えば前者は人間的本性で後者が人間の本性ということになるのでしょう。
人間の本性の場合はいいのですが,上野によれば自然の権利と自然的権利は,用いられ方に違いがあるのだそうです。端的にいえば自然の権利といわれる場合にはスピノザの哲学に特有の哲学的意味が濃厚で,それに対して自然的権利といわれている場合には政治論的な意味合いがより強くなるということです。僕にはラテン語の素養がない上に,スピノザのテクストのすべてを知っているわけではないので,上野のいっていることの正否については何もいうことができません。ただ,上野がこのようにいっている以上,自然の権利と自然的権利は,意味合いの上で異なる可能性があるということには注意しておかなければならないでしょう。
ただ,僕は政治論ではなく哲学を中心に考えていますし,スピノザの政治論は哲学を基点としていると理解しています。いい換えれば,もし自然の権利と自然的権利に意味合いの違いがあるのだとしても,自然の権利という概念notioなしに自然的権利という概念について説明することは不可能であると考えます。なので今後もこのブログでは,上野がここでいっている相違に関しては頓着せず,どういわれようとそれをただ自然権と表記します。ただ,使い分けでいうなら僕は自然の権利の方を重視しているというように理解してください。
ここにある人間がひとりいて,自分が希望spesを抱いている不確実な事柄に関してそれを真verumと思い込み,その希望を打ち砕くような不安metusを抱かせる何らかの真理veritasに対してそれを偽と思い込んでいると仮定してみましょう。ここまでの説明から明らかなように,こうしたことは論理的に生じ得ますし,また現実的にこのような人間が存在していることも確実です。
この人が無知の人であることは確実です。というより,語の用法として,このような人が無知の人といわれるのでなければなりません。このとき,この人がただひとりでそう思い込み,ひとりでその確実性を疑っていないのなら,この人は一種の妄想家とみなされるでしょう。なのでこの人は非常に厄介な人物であると評価されるでしょうが,この人が偽であるところのものを真と思い込み,逆に真であるものを偽と思い込んでいるということをだれもが理解し得るので,さほど大きな問題を生じさせるというわけでもありません。
ところが,不安と希望は表裏一体の感情affectusで,どちらも不確実なことであるがゆえに,恐怖metusを齎す事象のことは偽と思い,希望を齎す事象のことは真であると思うということは,自由の人homo liberとして対処しない限りではだれにも生じ得ることになります。この場合,不安の方を偽と思うことは,確かにそれが不確実なことであるがゆえに間違いではありませんが,希望の方を真と思い込むことはそれも恐怖と同様に不確実なのですから決定的な誤謬errorであるといえます。そしてひとたびこのような誤謬を犯してしまうと,希望を打ち消すような事柄がたとえ真であるという場合でも,それを真理とは認めずに虚偽falsitasであると妄信してしまうことに陥りやすくなるのです。自分にとって都合の悪い情報に関してはさして吟味することすらせずにそれを偽の情報であると断定してしまうようなことは,概ねこのようなメカニズムで発生することになるのだと僕は考えます。
これは一般的な事柄ですが,この希望と恐怖が,対人間という関係で生じる場合には,強力な排他的思想になります。単に悪malumであるから排他的になっているだけでなく,真であるという誤謬を犯した上で排他的となっているからです。
3日と4日に大田原市で指された第67期王将戦七番勝負第三局。
久保利明王将の先手。かなり駆け引きのある序盤戦から先手の四間飛車,後手の豊島将之八段が中飛車から向飛車に振り直す相振飛車になりました。後手が角損の代償に飛車を成り込むという進展。乱暴な攻め方にも思えましたが,いい勝負になっていました。

後手が2日目の昼食休憩も挟んで3時間11分の大長考で桂馬を打った局面。ここでの大長考はどうやら芳しい展開がなかったからだったようです。第1図は7二にいた玉を後手が引き,先手が4五に歩を打ったところで生じたのですが,玉を引いたのがよくなく,銀を9三に上がって壁型を解消しておけば,まだいい勝負が続いていたようです。
角取りですから逃げるのが第一候補で,それでも先手はやれていたようです。しかし58分の考慮時間で☗4二同角成と踏み込みました。これだと☖同金☗4四歩までは必然です。
先手が長考したのはここで☖1九角と打つ手があるからです。これには☗4七王の一手で,☖4六歩が打ち歩詰めのために逃れている形。この変化が大丈夫と読み切るのに要したのが58分だったということでしょう。
☖9九龍が詰めろ飛車取りですが☗3七歩と角道を遮断。☖8八龍と飛車を取れるのですがそれは☖4三歩成で先手の上部も手厚くなる形。なので☖5一香と角に働きかけたのですが☗4三歩成☖5四香☗4二とと進めて先手の勝勢になっています。

第2図から後手は☖9三銀と上がったのですが,これは☖7一王が不発に終わった形。先に☖9三銀なら難しかったであろうことはここからも理解できます。
久保王将が勝って2勝1敗。第四局は19日と20日です。
第三部定理九備考でいわれている事柄は万人に妥当します。善悪は真偽と異なり,永遠aeterunusで普遍的な概念notioではないからです。同時に,これによってなぜ僕たちが善bonumとみなしていたものを悪malumとみなすようになったり,逆に悪とみなしていたことを善とみなすようになったりすることが生じるかも分かるでしょう。人間の欲望cupiditasはその場その場によって変じるものであるからです。つまり,あるときにはAを欲望し,また別のときにはBを欲望するということがあります。このとき,AとBが相反するものであるなら,善とみなされていたAが悪とみなされ,悪とみなされていたBが善とみなされるようになるのです。原子力発電所は事故を起こせば危険である悪とみなしていた人が,運転されれば長期間にわたって事故を起こさず恩恵を受けるがゆえに善とみなすようになり,しかし一度でも事故を起こすとやはり危険であったという思いからまた悪とみなすようになるのは,その人間の欲望の変化に応じて対象である原発に対する善悪の評価が変じているのです。
自由の人homo liberはこうした変化が起こり得るということ,すなわち善悪は真偽とは無関係であるということをしっかりと理解しています。とりわけ,自分自身の欲望すなわち善悪の規準について理解しています。ですから自身が善とみなすものが真verumであり,悪とみなすものが偽であるというような思い込みをすることはありません。ところが真理veritasの規範を見失う無知の人は,このことに自覚的ではありません。とりわけ自分自身の欲望が善悪の判断規準になっているということを見失ってしまうので,自身が善と判断するところのものを真であるとみなし,悪であると判断するところのものを偽とみなしてしまうことが起こり得るのです。したがって,スピノザは万人に妥当するように,人間は希求するところのものを善とみなし,忌避するところのものを悪とみなすといったのですが,同時に,人間には自分が希求するものを真とみなし,忌避するものを偽とみなすような傾向,危険な傾向があるということもまた事実であると僕は思います。とりわけ善悪が真偽より重要だと判断する人には,この危険性が強いのではないでしょうか。
ダイオライト記念トライアルの第54回報知グランプリカップ。
発走してしばらくはキャプテンキングが先頭でしたが,正面の半ばで外からバルダッサーレがハナを奪い,向正面にかけて後続を引き離しての逃げに。2番手にケイアイレオーネでこれをマークする位置にリッカルド。その後ろに控えたキャプテンキングとロワジャルダンでこの4頭は集団。少し離れてタイムズアローが続き,さらにイッシンドウタイ。その後ろはトーセンハルカゼ,ポイントプラス,グレナディアーズ,フィールザスマートの4頭の集団。エンパイアペガサス,オメガスカイツリーと続いてタマモネイヴィーは取り残されました。最初の800mは48秒8のハイペース。
3コーナーを回るとバルダッサーレのリードがみるみるうちに縮まっていき,4コーナーではケイアイレオーネが先頭。しかしずっとマークしていたリッカルドが直線に入るとすぐにケイアイレオーネを捕まえ,あとは後ろを引き離していく一方となって圧勝。また盛り返してきたバルダッサーレ,ケイアイレオーネ,この2頭の間を割ったキャプテンキング,そしてケイアイレオーネの外から脚を伸ばしたロワジャルダンの4頭が一時的に競り合いとなり,大外のロワジャルダンがここからやや抜け出す形で7馬身差の2着。4分の3馬身差の3着にキャプテンキング。
優勝したリッカルドはこのレースが南関東への転入初戦。したがって南関東重賞は初勝利。JRA時代は一昨年のエルムステークスを勝っていて,それ以来の勝利。エルムステークス以降は落ち込んでしまい,一昨年の11月から昨年暮れまでの10戦は掲示板も外していました。ただ昨年の夏からは勝ち馬から1秒圏内のレースができるようになり,今年1月のオープンは5着と,復調気配にありました。元の力からいえば南関東重賞は勝てる馬で,この着差からするとさらに状態も上がっていたのではないでしょうか。どういう理由で落ち込んでいたのかいまひとつ分からないのですが,今日のレースだけでいえば重賞でもそれなりの期待がもてそうに思えます。父は2005年のJRA賞の最優秀2歳牡馬に選出されたフサイチリシャール。その父がクロフネ。4代母がアリアーン。母の7つ上の半兄が1999年に東京大賞典を勝ったワールドクリークで3つ下の半弟がNARグランプリで2010年と2011年にダートグレード競走特別賞に選出されたスマートファルコン。Riccardoはイタリア語の男性名。
騎乗した大井の矢野貴之騎手は昨年の羽田盃以来となる南関東重賞11勝目。報知グランプリカップは初勝利。管理することになった船橋の佐藤裕太調教師は南関東重賞2勝目で報知グランプリカップは初勝利。
自由の人homo liberは真理の規範を有しているわけですから,希望spesによって不安metusを打ち消した場合でも,その希望が真理veritasではないということ,他面からいえば単に自分にとっての善bonumでしかないということを理解します。というか,正確にいうなら,そのような人のことを自由の人というのです。ところが,人間には真理の規範を見失うということがあって,その場合には恐怖metusを打ち消した希望が単に虚偽falsitasとしての善であるだけでなく,真verumであるとも思い込まれるようになります。つまりただ虚偽に陥るというだけでなく,誤謬errorを犯すようになるのです。これは,善であるものが真であってほしいという欲望cupiditasから生じる誤謬であるといえます。要するにそうであってほしい事柄を実際にそうであると思い込むようになるのです。これは目覚めながら夢を見ているようなものですが,実際にこのようなことが起こるということは僕たちは経験的に知っているといえるでしょう。ある人間が自身の希望を打ち消してしまうような真の情報について,それは偽であると臆面もなくいい張ること,つまり本気で真なるものを偽と思い込み,自身が希望あるいは欲望している偽なるものを真であると真剣に思い込んでいるというような例は実際に存在するとしかいいようがないからです。

スピノザは第三部定理九備考で,僕たちは善であるものを欲望するのではなくて,欲望してるところのものを善とみなすといっています。欲望は第三部諸感情の定義一から分かるように,受動状態における人間の本性essentiaを示します。僕たちは受動passioという状態にあるときは必然的にnecessario混乱した観念idea inadaequataすなわち偽を有しています。ただし,だから必然的に善は偽なるものであるというわけではありません。第三部定理五九から分かるように,僕たちの能動actioから生じる欲望というものもあるにはあるからです。ただ,備考Scholiumのいい方は,欲望しているものについては必然的に善とみなすのですから,僕たちはそれが真であるか偽であるかには関係なく,そのものを善とみなすということは間違いありません。実際,不安を希望で解消することは,それ自体では善です。それは希望が偽であることを認識しているかいないかとは関係ありません。
第45回佐賀記念。
好発を決めたのはコウザンゴールドでしたが先手を奪いにはいかず,ハナに立ったのはコパノチャーリー。ただクリノスターオー,マイネルバサラの3頭で雁行して先行するレースになりました。4番手にキョウワカイザー。5番手にトップディーヴォとルールソヴァールと控えたコウザンゴールド、8番手以下はデリッツァリモーネ,フリビオン,キクノソル,アクロマティック,ミッキーヘネシーという順。スローペース。
2周目の2コーナーを回ると雁行の最も外にいたマイネルバサラが単独の先頭に。この動きにコパノチャーリーとクリノスターオーはついていくことができず,2番手にはルールソヴァールが上がりました。3コーナーを回るとマイネルバサラの外にルールソヴァールが並び掛け,内から追ってきたトップディーヴォが3番手,外から追い上げてきたキクノソルが4番手に。直線に入るとマイネルバサラを楽々と抜き去ったルールソヴァールがそのまま抜け出して快勝。直線で外に出したトップディーヴォがマイネルバサラを捕まえて4馬身差で2着。マイネルバサラが1馬身4分の1差で3着。
優勝したルールソヴァールは重賞初制覇。条件戦からじわじわと力をつけてきた馬で,昨年の11月にみやこステークスを2着になると,暮れにオープンで勝利。このレースでマイネルバサラが4着だったことから,ここは優勝候補の筆頭格でした。地方競馬に出走するのが初めてで,最内枠を引いたことは懸念材料でしたがそれも克服。というよりも適性の高さをみせたという感がありますので,今後の重賞戦線でも要注目の存在になったといえそうです。母の父はフジキセキ。2つ上の全兄に2016年のJRA賞で最優秀ダートホースに選出されている現役のサウンドトゥルー。Leur Sauveurはフランス語でかれらの救い主。
騎乗した幸英明騎手は第25回,40回に続き5年ぶりの佐賀記念3勝目。管理している高木登調教師は佐賀記念初勝利
現状の考察と離れるのですが,真理veritasが万人に共通であることは,スピノザの哲学における主体の排除と関係する面がありますので,これについて若干の私見を示しておきます。
僕は真理は永遠aeterunusに属するものであるから,だれが認識しても共通するといいました。これは認識するcognoscere主体subjectumを想定した説明の仕方で,そういえば分かりやすいだろうからそのようにいうまでです。しかし実際には,だれが認識しようと同一で共通であるなら,その思惟の主体というものは存在しません。ただその観念ideaが神Deusの無限知性の一部を構成しているまでです。ゆえに真理が認識される限りでは,認識する主体が何であるのかは考慮しなくてもいいのです。他面からいえば,それをだれが認識しているのかと問うことは無意味です。それはだれが認識していようと,あるいはだれも認識していなかろうと,永遠の真理であるからです。

ところが善悪の場合はこれとは異なります。なぜなら第四部定理六八にあるように,もしすべての人間が理性ratioに従う自由の人homo liberである限りでは,善悪というのは認識され得ないものであるからです。いい換えれば僕たちは理性に従わない,他面からいえば受動的である限りにおいて善悪を認識するのです。そして第三部定理五一が示す通り,受動passioの様式は各人によってもまた同一の人物にあってもその場その場において異なり得ます。このゆえにだれがいつどのように働きを受けているかということは,現実的に意味を有し得ることになります。つまりだれが働きを受けているのかという観点においては,確かにその働きを受けている主体が何であるのかということは意味を有し得るのです。ただし,主体というのは一般的には働くagereものを意味するのであって,働きを受けるpatiものを意味するとは思われていませんから,これを主体というのはあまり相応しくはないかもしれません。
ただ,このような意味において,受動に対する対処の仕方が,自由の人の対処であるのか,それとは反対の意味において無知の人であるのかということは問われ得るでしょう。よってこの観点から主体が自由の人であるのか無知の人であるのかを分節することは,意味があると思います。
関根名人記念館で指された昨日の第44期女流名人戦五番勝負第三局。
伊藤沙恵女流二段の先手で後手の里見香奈女流名人の三間飛車,先手の向飛車という相振飛車に。互いに飛車先の歩を切った後,後手から飛車交換を挑み,応じた先手がすぐに自陣に飛車を打ち,この飛車を軸に攻めていく将棋に進みました。

後手が4五に進出していた銀を逃げた局面。ここでは☗9四歩が最も自然と感じられる手で,それが最善であったようですが☗7三歩成と強く踏み込みました。☖同金と形を乱してから☗9四歩と取り込む意図です。ただ後手も金が前に出たため☖8四銀が成立することに。
ここで☗2五飛☖3四銀なら実戦とは違った将棋。先手にとってはそちらが有力だったようですが☗6五桂と打っていきました。後手は☖同銀。
これは☗同飛もあった筈ですが☗同歩。こうなれば☖7七角成☗同桂までは必然。後手は☖6二王と受けました。先手は飛車を逃げずに☗6四歩。

一連の手順から分かるように先手はかなり強気です。ただこの強気がこの将棋ではマイナスに働き,第2図から☖8五銀と飛車を取られた局面ではすでに悪くなっていました。したがって第2図では飛車を逃げておかなければならなかったことになります。
とはいえ☗同桂は金取りで☖6四金に☗7三銀が王手金取り。☖5二王☗6四銀成☖同歩☗7三桂成と進んだ局面は,☗6一角の狙いもあって攻めが続きそうではあります。ですがここからの後手の指し回しが巧みでした。
まず☖6五角と打って☖4六桂をみせます。☗5六歩と受けたところで☖8七角成が金取り。☗7八歩の受けに☖7六馬と引いて☖5七銀をみせます。これも☗6七歩の中合いで受かりますがそこで☖8九飛。ここで☗5八金上は☖7九飛打で先手は駒を使わなければなりません。なのでここで☗7九金打でしたが,ここに金を使ってもらえば後手は怖いところがなく悠々と☖9九飛成。

第3図となっては先手は駒が足りなくなりました。ここは後手が勝勢に近いくらいの局面でしょう。
3連勝で里見名人の防衛。第36期,37期,38期,39期,40期,41期,42期,43期に続く九連覇で9期目の女流名人位です。
善bonumや正義justitiaより真verumに重きを置く理由は別の角度からも説明できます。
真理veritasが万人に共通であるのは,それを人間が認識するかしないかと関係なく,永遠aeterunusで不変なものであるからです。平面上に描かれた三角形の内角の和が二直角であることは,たとえ人間が認識しなくとも真理であり,そのゆえにだれが真に認識しようと共通に認識されるのです。これに対して善や正義は永遠不変ではなく,時間的なものです。同一の人間でさえ善と認識していたものを悪malumと認識し直すことがあり得るのですから,善や正義が永遠なものではなく時間的なあるいは持続的なものであることは明白です。そしてこうしたことは単一の人間にとって妥当するだけでなく,集団的にも妥当します。かつては多くの人びとに正義とみなされていたことが,時代の変化とともに不正injustitiaとみなされるようになるということはあり得るのです。
たとえば地動説として主張されている事柄は,人間がそれを発見しようとしまいと,あるいは正しいと認めようと認めまいと,真理ではあるのであって,それが真理であるということは人間の認識cognitioにあたっての態度とは無関係です。しかし人類史において地動説が不正とされていた時代は確かにあったのであって,そのゆえにブルーノは火炙りに処されたのですし,ガリレイは宗教裁判においては,表面的にではあっても自説を撤回したのです。
つまり真理が永遠に属するものであるのに対して善や正義は持続duratioに属するものであり,そのゆえに僕は真理を善や正義より重くみるのです。そしてこう価値規準を決定することは,理性ratioに従う自由の人homo liberであろうと欲する限り,自然なことと僕には思えます。なぜなら第二部定理四四系二にあるように,ものを永遠の相aeternitatis specieの下に認識することが理性の本性natura Rationisに属するからです。よって永遠の相の下にある真理を認識することは,持続的である正義や善を認識することより理性の本性に適合しているからです。かつ第四部定理二四により,それが徳virtusだからです。つまり善や正義を認識することは必ずしも徳ではありませんが,真理を認識することは必然的にnecessario徳だからです。そして第五部定理四二により,それが至福beatitudoでもあるからです。
高松記念の決勝。並びは佐藤‐大槻の北日本,三谷‐山田‐南の近畿,松浦‐香川‐池田の瀬戸内で諸橋は単騎。
三谷と南がスタートを取りにいき前受けは三谷。道中で上昇した佐藤が山田の外で併走。南の後ろに諸橋でその後ろから松浦という周回に。残り2周のホームに入るところで松浦が上昇。ホームで三谷を叩くと諸橋は池田の後ろにスイッチ。さらに諸橋の後ろに佐藤が続き,三谷が7番手の一列棒状に。打鐘で三谷が追い出しを掛けるような形になり,松浦の先行に。池田の後ろを内に斬り込んだ佐藤と諸橋で取り合い。これはコーナーで佐藤が制し,佐藤はバックでインをさらに上昇し,香川の内まで追い上げました。ところが後方から三谷も発進してきていたため,香川は佐藤とは競らずに番手から発進。松浦と香川の間に進路を取った佐藤,香川,捲った三谷の3人がもつれ合うように直線に。直線の入口では香川が先頭で頑張っていましたが,三谷がこれを捻じ伏せて優勝。三谷ラインの3番手から香川と三谷の間に進路を取った南が4分の3車輪差で2着。香川が4分の1車輪差で3着。
優勝した奈良の三谷竜生選手は昨年5月の日本選手権競輪以来の優勝で記念競輪初優勝。その後,5月,6月,7月と3回の落車もあって,確たる実績を残せていませんでした。ここはメンバーから大きなチャンスと思われたところ。レース運びはあまり褒められたものではないのかもしれませんが,こういう大チャンスを逃さずに記念競輪の初優勝を決めることができたのは,まだ長期にわたる選手生活が予想される本人にとっては,今後のためにもよかったのではないかと思います。調子も取り戻してきているようですから,今後も期待していいのではないでしょうか。選手人生にとって今年は勝負の年だと思います。
第四部定理八が示しているのは,現実的に存在している人間にとっての善悪の認識cognitioは,それを認識する当人の喜びlaetitiaないしは悲しみtristitiaという感情affectusの観念ideaであるということです。第三部定理五一が示しているのは,異なった人間が同一の対象から異なった刺激を受けることができる,いい換えれば異なった感情を惹起され得るということであり,また同一の人間が同一の対象から異なった感情を惹起される場合もあり得るということです。したがって,善悪はその人によってまちまちに認識され得ますし,同一の人間の場合でも,善bonumと認識していたものを悪malumと認識するようになったり,悪と認識していたものを善と認識するようになることが生じ得ます。端的にいえば,善悪とは現実的に存在する人間にとっては統一的なものではなく,万人にとって共通する善悪というものはありません。
一方,第二部定理一一系では,現実的に存在する人間の精神mens humanaは神Deusの無限知性infinitus intellectusの一部であるといわれています。そして第二部定理三二により,ある観念が神の無限知性のうちにあるとみられる限りでは,それがどんな観念であろうとも真の観念idea veraです。よってある人間の精神のうちに,すなわちある人間の精神の本性naturaを構成する限りで神のうちに真の観念があるのであれば,その真の観念の形相formaは神の無限知性のうちにある真の観念の形相と同一です。よってAという人間の精神のうちにあろうとBという人間の精神のうちにあろうと,Xの真の観念の形相は同一です。そして真理veritasとは真の観念の総体のことをいうのですから,真理は統一的なものであって万人に共通するものです。
僕はこうした共通性の観点から,善悪より真偽の方に重きを置きます。いい換えれば相対的な価値としていえば善悪より真偽の方が高い,善よりも真verumの方が高く,同様に相対的にいえば人間一般にとって有益であると考えるのです。
真実を暴くことは正義justitiaではないといわれることがあり,これは事実なので僕は反論しません。ですが真実の方が正義より価値が高いと僕は考えます。真実を暴くのは正義ではないというのは確かでも,正義を貫くことは真実ではなく不実であり得るということにも留意してほしいです。
門馬忠雄の『全日本プロレス超人伝説』は,三部作の一作です。その前に書かれたのが『新日本プロレス12人の怪人』で,『全日本プロレス超人伝説』を挟んで『外国人レスラー最強列伝』で完成しました。『新日本プロレス12人の怪人』は僕は現時点では読んでいませんし,あまり読もうという気も起りませんが,『外国人レスラー最強列伝』の方はすでに読了していますので,簡単に紹介しておきます。
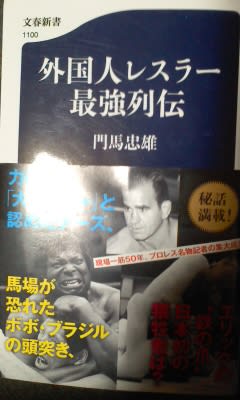
『全日本プロレス超人伝説』のプロローグの中で,門馬は自身のことを馬場べったりの記者と書いています。これは全日本プロレスを中心に取材したという意味かとも思っていたのですが,そうではありません。『外国人レスラー最強列伝』の第1章の冒頭で,門馬は馬場党でアンチ猪木派であること,そしてテーズ派であってゴッチ嫌いであるとはっきりと書いているからです。なのでこれら三部作を読むときには,そういうフィルターも入り混じっているであろうことを念頭に置いておいた方がよいでしょう。
体裁は『全日本プロレス超人伝説』とあまり変わらず,各章でひとりのレスラーについて言及されるという形で,13章まであるので全部で13人です。すでにこのブログでとりあげたレスラーがふたり含まれています。ひとりは第8章の人間発電所で,もうひとりが第11章の人間風車です。
第1章のルー・テーズ,第2章のカール・ゴッチ,第5章のフリッツ・フォン・エリック,第7章のジン・キニスキー,第9章のディック・マードック,第12章のジプシー・ジョー,第13章の大木金太郎についてはいずれ個別に取り上げます。
残りは第3章が噛みつき魔のフレッド・ブラッシー,第4章が黒い魔人のボボ・ブラジル,第6章が生傷男のディック・ザ・ブルーザー,第10章が柔道王のウィレム・ルスカです。馬場にとって最大の好敵手はブラジルだったのではないかと思える部分はあるのですが,これらの選手については僕には多くを語ることができませんので,個別には割愛します。
不安metusすなわち恐怖metusも希望spesも,混乱した観念idea inadaequataとともにでなければあることができない感情affectusなので,Xに対して不安を感じようと希望を抱こうと,それはXに対しては必然的にnecessario虚偽falsitasです。よって恐怖にしろ希望にしろ,そこから生じる欲望cupiditasは虚偽に基づいた欲望であることになります。自由の人homo liberは真理の規範に自覚的ですから,それが虚偽であるということを理解します。つまり虚偽には陥るけれども誤謬errorには陥らないのです。なおかつ不安に関していえば,それは自由の人にとってはそれ自体で無用でありまた悪malumなのですから,不安から生じる欲望に流されるようなことはありません。そしてこれは同時に,希望から生じる欲望に流されることもないという意味です。なぜなら,第三部定理五〇備考にあるように,不安と希望は表裏一体の感情であるからです。
このゆえに,自由の人が自身の恐怖をそれと相反する希望によって打ち消すことを,僕は全面的に肯定します。打ち消された不安も打ち消した希望も,どちらも虚偽であるということを理解した上で,このような対処法を意図的に採用しているとみられるからです。一方,不安に苛まれているより希望に満ち溢れている方がまだましなので,無知の人がこのような手法を採用しても,僕は絶対的な意味においてこれを否定はしません。ですが全面的には肯定しません。というより部分的には否定します。というのは無知の人は打ち消した希望が虚偽であるということには気付いてなく,よって真理の規範を見失い,誤謬を犯すおそれが大であるからです。
同じ受動状態にあるなら悲しみtristitiaに沈んでいるよりは喜びlaetitiaに浸っている方がましであるというのは,善悪の観点からまだましだと僕はいうのです。これは第四部定理八がその論拠になります。したがって自由の人であろうが無知の人であろうが関係なしに,恐怖を希望で解消することは,少なくともその当人にとっては善bonumです。ところが,虚偽に基づく善について,それが虚偽であるということに気付かない場合には,その人間はただそれを善とみなすというだけではなく,真verumであるともみなすようになるのです。僕はこの点について,こうした不安の解消法を否定します。
Kが発した「私は金がない」ということばの奥さんの解釈は,それが嫌味ではないというものであったことは確実だと僕は解します。つまりKが,静は財産を目的として先生と結婚するのであるとか,同様に奥さんは先生の財産を目当てに静を先生と結婚させるのだ,というようには奥さんは受け止めなかったのだと僕は解します。
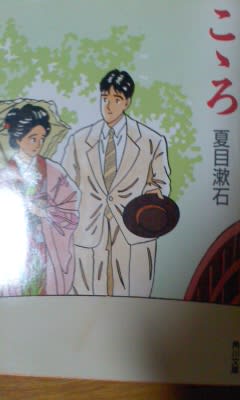
このとき,テクストの上では嫌味として解することが可能なKの発言を,奥さんが嫌味と解さなかった理由については二通りの解釈ができると僕は考えています。
ひとつは,静が先生と結婚するにあたって,Kが先生のライバルとなり得ることが奥さんのうちにはなかったという場合です。この場合,たとえ静が先生と財産を目当てに結婚するのであると仮定しても,財産がないがゆえにKは静とは結婚することができないという意味は奥さんのうちには発生のしようがありません。そして実際に,静に対するKの恋心を知っていたのはKのほかには先生だけであったのですから,奥さんはKが静と結婚したがっているということは知らなかったと解するのは妥当です。
ただ,この解釈には弱みがあります。というのは,先生がKと同居することを提案したときの奥さんの拒絶のあり方から察すると,奥さんはKを同居させれば静の結婚相手としてKが先生のライバルとなってしまうということを十分に想定していたと思われるからです。奥さんは先生との同居を決定したその時点で,先生を静の結婚相手として肯定していたと思われるので,ライバルの存在はむしろ不都合でした。なので,奥さんはKが先生のライバルとなり得ることに関しては十分に想定していたのだけれども,実際に暮らしてみたら,Kは静に対して何の興味も有していないように思われたので,Kの発言があった時点では,Kを先生のライバルとはみなさなくなっていたということが,この解釈の場合には必要になると僕は考えます。
それを明確に否定するようなテクストはありません。しかし肯定するテクストもないのです。よって僕はこの解釈は採用していません。
第二部定理三五は,虚偽falsitasも誤謬errorも同じものとして記述されています。ですが僕は虚偽と誤謬を明確に異なったものとして規定します、すなわち虚偽は混乱した観念idea inadaequataそのもののことであり,誤謬は混乱した観念を十全な観念idea adaequataと思い込むことと規定するのです。
僕の規定に当て嵌めると,この定理Propositioは二重の意味を有するようになります。すなわち,虚偽も誤謬もある認識cognitioの不足によるのですが,虚偽の場合に何が不足しているかといえば,第一部公理四により原因の認識が不足しているのです。重要なのはこれはあくまでも不足であって,欠乏ではないということです。つまり第三部定義一により,部分的原因causa partialisは認識されていて,十全な原因causa adaequataは認識されていないのです。たとえばAとBによってXが発生するというとき,Aだけは認識されていてBは認識されていないというのがこの場合に該当します。したがってこの場合のXの混乱した認識にはBの認識だけが不足していて,Aの認識はあるのです。これがそれは不足であって欠乏ではないという意味です。
一方,誤謬の場合に何が不足しているかといえば,単に虚偽の場合に不足しているのと同じことだけが不足しているわけではなく,それが虚偽であるという認識も不足しているのです。この場合には,ただこれだけでみるなら不足ではなく欠乏であるといっても構いません。ただ,上述の例でいえばXの認識があるということは確かなので,Xが虚偽であるという認識だけが不足していると僕は解します。というのは,これが虚偽であるという認識は必然的にnecessario欠乏するというわけではなく,不足する場合もあれば不足しない場合もあるからです。よってそれが不足していない場合は,その人間の精神mens humanaは虚偽には陥っているけれど誤謬は犯しておらず,不足している場合は単に虚偽に陥っているというだけでなく,誤謬も犯していると僕は解します。ただ,不足というのか欠乏というのかは,単にことばの上での争いにすぎないという面があり,僕がそれで何をいおうとしているのかということを正しく理解してもらえるのであれば,それを不足というのか欠乏というのかということについて争う気は僕にはまったくありません。
2017年の競輪の表彰選手は1月29日に発表されました。
MVPは福島の新田祐大選手。高松宮記念杯,サマーナイトフェスティバル,競輪祭とビッグを3勝。函館記念も優勝しました。昨年は新田の年であったといっても過言ではありません。当然のMVPでしょう。2015年に続き2年ぶり2度目のMVPです。
優秀選手賞は3人。まず三重の浅井康太選手。KEIRINグランプリを優勝。優勝がこれだけであったために勝率や連対率は低いのですが,グランプリの優勝選手はほぼ賞金王になる仕組みで,その選手が受賞できないというのも変ですから順当でしょう。2011年と2015年に続き2年ぶり3度目の優秀選手賞。特別敢闘選手賞も1度受賞したことがあります。
ふたり目は福島の渡辺一成選手。オールスター競輪と寛仁親王牌に優勝。いわき平記念も優勝しました。昨年は新田とセットでの活躍が目立ちました。MVPは新田に譲っても,受賞自体は当然です。国際賞の受賞歴はありますが,それ以外は初受賞。
3人目が埼玉の平原康多選手。全日本選抜競輪を優勝。大宮記念も制しました。平均競走得点が新田に続く2位で,勝率は新田を上回っていますから,3人目の選手としては平原が妥当です。2009年,2015年,2016年に続き3年連続4度目の優秀選手賞。MVPは獲得できていませんが,3年連続で優秀選手賞を受賞するというのは偉業だと思います。
優秀新人選手賞は徳島の太田竜馬選手。選出カテゴリーの中では太田になるのではないかと思います。記念競輪制覇も近いのではないでしょうか。
特別敢闘選手賞は奈良の三谷竜生選手。日本選手権競輪を優勝。三谷も浅井と同じで昨年は優勝はこれだけ。ただGⅠとしては最高峰のレースの優勝者ですから,選出に異論はないです。一方でもう少し活躍してほしいという気持ちも拭えないです。2014年に優秀新人選手賞を獲得して以来の2度目の受賞です。
僕は喜びlaetitiaは小なる完全性perfectioから大なる完全性への移行transitioであり,悲しみtristitiaは大なる完全性から小なる完全性への移行であるということだけから,人間は同じ受動状態にあるのであれば,悲しみに沈んでいるより喜びに浸っている方がまだましであると考えるといいました。このゆえに,不安metusに苛まれているより希望spesに満ち溢れている方がまだましだと考えるのです。恐怖metusも希望も,混乱した観念idea inadaequataとともにでなければ存在し得ない感情affectusですから,どちらも受動passioによって人間が感じる感情です。だから不安に苛まれているより希望に満ち溢れている方がよいとは僕はいいません。まだましだというだけです。
ですがまだましである以上,ある恐怖を打ち消す,すなわちその恐怖と相反する感情である希望があるなら,希望によって不安を打ち消すことを僕は否定はしません。むしろまだましであるという意味において肯定します。そしてこのとき,不安を打ち消している希望もまた,元の不安と同じように虚偽falsitasであるということ,いい換えれば,恐怖に怯えていようと希望に満ちていようと,虚偽に陥っているという点では何ら変わるところはないということを認識しているのであれば,こうした方法によって恐怖に打ち勝つことは,人生における対処法のひとつとして僕は全面的に肯定します。一例でいえば,原子力発電所が事故を起こせば取り返しのつかない事態になるかもしれないという不安を,厳しい基準の下で運転されるのだから事故を起こすことはないだろうという希望によって打ち消すとき,しかしその希望は虚偽であるということ,つまりどんな基準の下に運転されようと事故を起こす可能性が0ではないということを同時に認識しているなら,僕はこうした対処法を全面的に肯定するのです。要するに自由の人homo liberの対処法については全面的に肯定するということです。

このようにいえば,僕が第四部定理七〇で自由の人と対比的に記述されている無知の人というのを,どのような人と解しているのかも分かってもらえると思います。すなわち自由の人が虚偽には陥るけれども誤謬errorを犯さない人であるとするなら,無知の人とは虚偽に陥るばかりでなく誤謬も犯す人のことです。