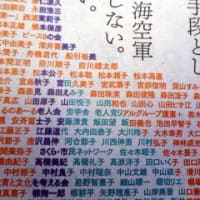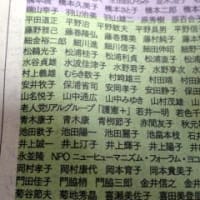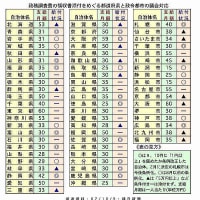今月末からUAEドバイでCOP28が開催される。
我々が現在抱えている気候変動課題に対してCOP28が、そして国際社会がどのような討論を行い、どのような解決策を提示していくのか、を見定める際の参考になれば、との思いから直前に報道されている幾つかのニュースを紹介してみたい。
取り上げたニュースは以下である。
1. DeutscheWelle,2023年11月17日 “Who pays for climate damage and where does the money go?” Jeannette Cwienk記す
2. PakistanDawn,2023年11月18日 ”Climate action" Aisha Khan記す
3. AlJazeera,2023年11月18日 “COP28 must not repeat the mistakes of the African Climate Summit” Sydney Chisi記す
まず、DeutscheWelleの記事(誰が被害の請求書の支払者で、その資金は何処にむかうのか)から始めます。
一つは気候変動を止めるという目的(mitigation)で、もう一つは気候変動の結果として生じる被害に適応する目的(adaption)で、一連の気候変動基金(climate fund)が貧困国向けに約束され用意されている。しかしこれらの用意されている基金が実際には何をカバーしているのか、そして何ゆえにどの基金の運用もが物議を醸すことになっているのか、という疑問がある。
歴史的に見て、化石燃料を産業革命の動力源として利用し、温室効果ガスを大量に発生させ、結果として地球温暖化を引き起こしてきた米国や欧州の様な国が気候変動向けの請求書の支払者になるべきだとの議論がある。しかしながらその意味する所は正確にはどのようなものであろうか?以下順を追って見ていく。
(気候変動融資climate financeとは何か?)
気候変動融資の背後にある考え方の一つに、発展途上国が化石燃料に頼らない経済発展のかじ取りが出来る様に支援することがある。
もう一つの考え方に、気候変動の影響を最も受けている貧困国が気候の変化に適応できるよう、裕福な国々は支援すべきということがある。
これらの考え方は1992年のリオデジャネイロ世界気候サミット以降、世界の気候交渉の中心議題となって来ていた。
気候変動への資金提供というと一般的に連想されるのは、2009年のコペンハーゲン国連気候サミットで先進国が2020年までに年間1000億ドルを調達するという公約をしたことである。2015年のパリにおいて、参加者らはこの金額を2025年まで毎年支払い続けることで合意し、そしてその後新たな金額を設定するとした。
(気候変動融資はどのように実践されるのか?)
公約の1000億ドルの実施の点で、先進国側は当初公的資金(public fund)を想定していた。
しかし先進国側は徐々に民間投資(private investment)を通じての金額を上昇させようとしている。
資金の流れとしては、約50%は供与国から受領国に向けて2国間で流れており、主として開発援助の形式がとられている。
残りの流れは、多国間資金(multilateral money)の形式を取っており、複数の国家が資金を供出し、そして複数の受領国家が受領することを意味している。この資金は世界銀行やアフリカとアジアのそれぞれの開発銀行のような多国籍銀行を経由して運営されている気候変動プログラムから提供されるか、あるいは多国間気候変動基金(multilateral climate funds)を通じて割り当てられる。
(緑の気候基金、Green Climate Fund)
多国間の基金プールの中で最も著名なのは緑の気候基金GCFだろう。この基金は、再生可能エネルギーの拡大などの気候変動を遅らせるための対策向けと、異常気象やその他の温暖化の影響への適応向けの両方を目的とする。
これまでに富裕国側は約200億ドルの提供を約束している。その内128億ドル分のプロジェクトが承認され、これまでに36億ドルが特定のプログラムに既に供給されている。大半がアフリカとアジア向けだが、ラテンアメリカ・カリブ海諸国・東ヨーロッパ向けのプロジェクトもいくらかある。
4年ごとに供出国は基金を補充することが求められている。資金の半分弱は有利な融資の形(favorable loans)で供給され、残りは返済の必要のない直接補助金(direct grants)として提供されている。
(適応基金、Adaptation Fund)
富裕国側が公約する1000億ドルの資金を受け取るもう一つの別の基金(Fund)が適応基金。これは比較的規模の小さい基金であり、基金を補充するシステムはなく、富裕国側は可能な時に、あるいは希望する時に供出するやり方が取られている。
この基金の目的は、異常気象による影響に適応できるように各国の手助けになるプロジェクトを支援することである。これらの異常気象による影響としては、例えば洪水への対策や暑さに強い作物の栽培などの対策が挙げられる。
途上国は、融資の形でなく、補助金の形で受け取る。該当プロジェクトは通常、利益を生むことが無いような適応行動へ資金を提供するということが特徴である。故に売電可能な風力発電やソーラー発電のプロジェクトへの拠出は対象外となる。
(開発程度が最低の国家向け基金、Least Developed Countries Fund、LDCF)
この開発程度が最低の国家向け基金(LDCF)は、最貧国46カ国をカバーしている。
返済の必要のない助成金のみで運営されており、緊急の気候適応資金を提供することを目的としている。これまでにLDCFは360以上のプロジェクトに資金を提供しており、約17億ドルが支払われている。
(1000億ドルの気候変動資金の公約は果たされているか?)
結論としては、果たされてはいない。
OECDのデータによれば、2020年に国際気候変動融資に支払われた総額は約830億ドル。
Oxfamドイツの気候変動・政策責任者のJanKowalzig氏は、「830億ドルという額は大きく聞こえるかも知れないが、グローバルサウスの貧困国が必要としている額はもっと大きい」と指摘している。そして、「我々の調査によれば、適応対策向け費用だけでも、2030年までの期間、毎年3000億ドルを超えるものとなっている。そしてこの数字には気候緩和対策向け費用は含まれていない」とも指摘している。
また、国際開発機関(international development organization)によると、OECDが言う830億ドルは粉飾されている、という。Oxfamの計算では2020年の実際の気候変動支援金額としては最大約245億ドルだったとしている。OECDが公式にリスト化しているプロジェクトの多くは、気候への影響が殆どないものだ、とOxfamは見ている。
「その上、先進国は公約の1000億ドルの支払い方として、多くは融資の形で貸し出している」。従って途上国側はこれらの融資を返済する必要があり、ドイツの支援団体「Bread for the World」のMinninger氏は「このやり方は、ごまかしだ」と主張している。
(損失,Loss,と被害,Damage:気候変動対策資金調達のネックポイント)
世界は何十年もの間、熱波や干ばつによる作物の被害や地域の居住不能化など気候危機により引き起こされている損失(Loss)や被害(Damage)を誰が支払うべきか、について議論を重ねてきている。更に発展途上国はこの目的の為の追加資金を望んでいる。
先進国側は気候変動融資の範囲を超える損害賠償で訴えられることを懸念しており、また彼らは世界最大のCO2排出国の中国など経済的に強い新興国にも同様にドナー国としての支払いを望んでいる。
損失と被害については多くの疑問が未解決のまま残っている状況である。
(気候リスクに対するグローバルなシールド、Global Shield against Climate Risks)
気候リスクに対するグローバルなシールドは、2022年のCOP27においてG7とV20(気候変動リスクを特に大きく受けている約70カ国のグループ)により立ち上げられた。
壊滅的な異常気象に迅速に応えられるように、このシールド(絆創膏といった意味合いか)基金にはあらかじめ決められた金額が割り当てられている。
これまでに2.28億ドル以上が提供されており、その約80%はドイツ拠出となっている。
次いで、PakistanDawnの記事(気候変動への行動)を紹介する。
NASAの代表的科学者のJames Hansen氏は「産業革命以前に比べて世界の平均気温を1.5℃以内に抑えることは、ほぼ絶望的であり、2℃以内に抑えることも、もし我々が迅速かつ適切な行動を取らない限り、非常に困難な状況だ」と指摘している。
この終末論的シナリオ及び気候変動問題の議論に何ら進展が見られないという背景から、国際司法裁判所(International Court of Justice ,ICJ)は諮問手続きを開始している。
手続きには書面及び口頭諮問が含まれ、これにより気候変動に関する各国の義務についての指導基準が与えられることになる。
勧告的意見が下されるのは、2024年後半から2025年初めと見られる。
この動きは国連の下記の動向が引き金になっている。
国連総会(UNGA)はバヌアツ政府からのリクエストを支持する決議を採択した後、ICJに対して気候変動に対する国家の責務に関する勧告的意見を求めることを正式に決定し、ICJ に要請している。
これにより、気候正義の解釈に極めて大きな変化がもたらされ、気候変動対策の将来を形作る上で、またとない機会が提供されることになるだろうとみられる。
地球上から消滅の危険にさらされている国々や、生命を脅かす課題に直面している国々にとって、ICJが今後発表する勧告的意見は、国際法に基づく法的責任を大規模排出国に問う上で役立つ可能性がある。
この勧告的意見は、また現在および将来の世代で最も弱い立場にある人々に損害を与える気候変動に関する行為や不作為に対し政府の責任を追及しようとしている世界中の法域での気候変動に関する訴訟や裁判を強化する可能性がある。
これは気候変動対策の方針を変える画期的な機会を提供することになる。
ICJへの第一回目の書面提出の期限は2024年1月22日まで延長されている。気候危機の前面に立つ国々にとっては、この期間延長は気候正義について、より幅広く議論に取り組むことが出来る機会を提供するものと言える。
気候変動危機に最も責任を負う国々が、脆弱な国々に対する被害を抑制するために、今何を為すべきか、ということをICJ判事らに理解させるには、各国が人権・環境権や気候に関する国際法規的に確固たる証拠と先進的見解を持って、それぞれの訴訟ケースを如何に数多く提供するか、に掛かっている。
このことは、損失と被害を今後の気候変動交渉の最前線に据え、気候危機を管理するには道義的責任を超えて、拘束力を伴う法的義務をも国際社会に認識させることが必要ということである。
ICJの勧告的意見には、諸国が単に慈善的に脆弱国に対し援助を提供するという意識から脱却して、気候変動による被害と損傷に対する公正であり、法的に健全な賠償(reparations)という考えへの移行を促す面もある。被害のみを大きく受けている国々がこの機会を使いタイムリーにそして強力に主張すべきことを展開することが求められる所である。
地球が沸騰する時代、そして暴力が支配する世界にあって、この展開により多国間主義ならびに世界正義に新たな希望が注入される可能性がある。
自主性に任せて排出を削減するという考え方・システムは機能することはなかった。
この自主的削減の考え方は「解決策の計画」を策定する装置にはなったが、公正な将来への希望に関しては、反対に減退させていく方向に働いたと言える。
ICJの勧告的意見により、国家及び非国家主体(多国籍企業体をさすか)は、各国の法的責務を明確にして、履行に対する責任を負うプロセスに参加する機会を得ることになる。
ある国の開発と発展によって、世界の他の地域に暮らす人々の生活や生存が脅かされるのであれば、その開発と発展を推し進める権利は如何なる国であっても持っていない、という当然のことを世界に広める機会に、今回のCOP28がなるべきと考える。
壊滅的な猛暑と洪水が世界の半分に襲いかかるまでに、残されている猶予期間はもう7年だけだ、と言われている。
時を同じくしてネパールでICIMOD主催の初の極間会議(inter-polar conference)とフランスでの極地サミット(Polar Summit)が開催されており、地球の平衡感覚が危機に瀕していることを示す状況が生まれていると思われる。
「地球全体を想定するアプローチ」という視点を欠いては、今後は管理できないことが示されている。
現在人類に課せられた課題は、気候正義というレンズのみを通して判断すべきでなく、地球全体の生命システムの生き残りという全体的見方から判断すべきと、今回の国連総会のICJへの要請決定を捉えるべきである。
そして地球全体の生命システムのなかで、絶滅に向かうスピードを加速させているのが人類だけなのだ。
最後はAlJazeeraの記事(アフリカ気候サミットの間違いを、COP28は繰り返してはならない)になります。
グローバルノースのロビイストらがCOP28で誤った解決策を押し付けてくること、それを許してはならない。
11月末にドバイで開催されるCOP28。しかし会議に先立ち、気候変動政策へのアプローチに大きな変更が無い限り、有意義な進展はないだろうとの指摘が活動家や市民社会から既に打ち出されている。
グローバルサウス諸国側には、富裕国や多国籍企業が通常通りの事業を継続する施策が推進されており、貧困国は単に気候変動の矢面に立たされているのみではないか、という懸念が強くある。
この9月初めにナイロビで開催されたアフリカ気候サミットでも、この懸念は出されており、政府・企業・国際機関・市民団体から数千人の代表が集まったCOP28に先立つアフリカサミットで、アフリカの人々が損失(loss)と被害(damage)の補償、気候緩和、気候変動資金などの問題について共通の立場で合意を得る機会になると見られていた。
しかし発表された最終文書(ナイロビ宣言)ではアフリカ諸国間の一致事項やアフリカ諸国内にある最善の利益を反映するものには適っていなかったと言える。
グローバルノース諸国や多国籍企業のロビイストらには、彼らの誤った解決策を表明する為のスペースが与えられており、そして高いレベルでの会議アクセス権も彼らには与えられていた。
一方アフリカ大陸を支援する目的で透明性ある解決策を要求する活動家や市民社会代表らは、議事進行中のアクセスが困難な状況に置かれ、脇に据え置かれているのではないか、という状況であった。かかる会議の進行を考えるとサミット最終文書の結果は驚くべきことでもないだろう。
結果として、9月のアフリカ気候サミットでは主たる排出国のグローバルノースがアフリカ諸国を補償する政策を推進する一方で、サミットとしてはグローバルノースがアフリカ諸国に被害を与えることを継続するという政策を受け入れさせるものであった。
このサミット宣言では、炭素クレジット・炭素オフセットや炭素取り引きといった問題を含んでいる実践案に重点が置かれ、そしてそれを合法化したものであった。
これらは誤った解決策であり、アフリカ諸国が必要としているものとは言えない。
これらはグローバルノースがアフリカの土地と人々の支配を継続し、そしてアフリカ大陸の排出削減分に見合うクレジットを購入する一方で、グローバルノース側は温室効果ガスの排出を継続することが出来るシステムをアフリカの人々に認めさせたという、新植民地主義の戦術に他ならない。
炭素取り引き(carbon trading)という方策は排出国側が排出を継続することを目指して、その排出分に見合う炭素捕捉活動(アフリカにおける新規植林活動や森林保全活動等)をグローバルサウス側の国で行うというものであるが、ここで問題になるのは、これらの炭素捕捉活動を考えている地域には、そこに存在する森林や土地を生活手段として必要としている地元の人々が現に生活しているということである。
即ち、炭素取り引きの構図には、炭素捕捉という名目および自然保全という名目のもとで、地域に住む人々の生活権・生存権を脅かすという部分が含まれている。
このような計画では炭素排出量の増大に対処はできず、排出量の削減を拒否する富裕企業や先進国のグリーンウォッシングが可能となる構図を助長するということが良く知られている。
炭素取り引きのやり方が解決策でないならば、アフリカ諸国の損失と被害、適応と緩和への資金提供についてグローバルノース側はどういう形で支援を進めていくことが出来るのであろうか?
ここで「キャップとシェア(cap and share)」という考え方が対案となりえる、と気候活動家や市民社会が見なし始めている。
このシステムは世界規模の炭素税(international carbon tax)を中心に据えて、その税金の支払者はグローバルノースの化石燃料採掘組織であり、その主要な消費者だというものである。
この税は、世界規模のグリーンニューディール基金(global Green New Deal fund)向けに年間数兆ドルが見込まれ、その資金で再生可能エネルギー社会への移行や世界の全ての人へのエネルギー供給が可能となると考えられている。またこの資金により、損失と被害向けの助成金、グローバルサウスの適応と緩和活動、そして一般の人々を支援するための現金給付にも提供可能とみられる。
キャップとシェアは国民国家を超えて機能する税制を確立することになる。このことは気候正義の鍵となる考え方であり、永い間待ち望まれていたものである。
モデル化によると、世界規模の炭素税の経済効果は革命的であり、アフリカの全ての極貧状況からの脱却など、大きな利益が得られることが示唆されている。
「護憲+BBS」「新聞記事などの紹介」より
yo-chan
我々が現在抱えている気候変動課題に対してCOP28が、そして国際社会がどのような討論を行い、どのような解決策を提示していくのか、を見定める際の参考になれば、との思いから直前に報道されている幾つかのニュースを紹介してみたい。
取り上げたニュースは以下である。
1. DeutscheWelle,2023年11月17日 “Who pays for climate damage and where does the money go?” Jeannette Cwienk記す
2. PakistanDawn,2023年11月18日 ”Climate action" Aisha Khan記す
3. AlJazeera,2023年11月18日 “COP28 must not repeat the mistakes of the African Climate Summit” Sydney Chisi記す
まず、DeutscheWelleの記事(誰が被害の請求書の支払者で、その資金は何処にむかうのか)から始めます。
一つは気候変動を止めるという目的(mitigation)で、もう一つは気候変動の結果として生じる被害に適応する目的(adaption)で、一連の気候変動基金(climate fund)が貧困国向けに約束され用意されている。しかしこれらの用意されている基金が実際には何をカバーしているのか、そして何ゆえにどの基金の運用もが物議を醸すことになっているのか、という疑問がある。
歴史的に見て、化石燃料を産業革命の動力源として利用し、温室効果ガスを大量に発生させ、結果として地球温暖化を引き起こしてきた米国や欧州の様な国が気候変動向けの請求書の支払者になるべきだとの議論がある。しかしながらその意味する所は正確にはどのようなものであろうか?以下順を追って見ていく。
(気候変動融資climate financeとは何か?)
気候変動融資の背後にある考え方の一つに、発展途上国が化石燃料に頼らない経済発展のかじ取りが出来る様に支援することがある。
もう一つの考え方に、気候変動の影響を最も受けている貧困国が気候の変化に適応できるよう、裕福な国々は支援すべきということがある。
これらの考え方は1992年のリオデジャネイロ世界気候サミット以降、世界の気候交渉の中心議題となって来ていた。
気候変動への資金提供というと一般的に連想されるのは、2009年のコペンハーゲン国連気候サミットで先進国が2020年までに年間1000億ドルを調達するという公約をしたことである。2015年のパリにおいて、参加者らはこの金額を2025年まで毎年支払い続けることで合意し、そしてその後新たな金額を設定するとした。
(気候変動融資はどのように実践されるのか?)
公約の1000億ドルの実施の点で、先進国側は当初公的資金(public fund)を想定していた。
しかし先進国側は徐々に民間投資(private investment)を通じての金額を上昇させようとしている。
資金の流れとしては、約50%は供与国から受領国に向けて2国間で流れており、主として開発援助の形式がとられている。
残りの流れは、多国間資金(multilateral money)の形式を取っており、複数の国家が資金を供出し、そして複数の受領国家が受領することを意味している。この資金は世界銀行やアフリカとアジアのそれぞれの開発銀行のような多国籍銀行を経由して運営されている気候変動プログラムから提供されるか、あるいは多国間気候変動基金(multilateral climate funds)を通じて割り当てられる。
(緑の気候基金、Green Climate Fund)
多国間の基金プールの中で最も著名なのは緑の気候基金GCFだろう。この基金は、再生可能エネルギーの拡大などの気候変動を遅らせるための対策向けと、異常気象やその他の温暖化の影響への適応向けの両方を目的とする。
これまでに富裕国側は約200億ドルの提供を約束している。その内128億ドル分のプロジェクトが承認され、これまでに36億ドルが特定のプログラムに既に供給されている。大半がアフリカとアジア向けだが、ラテンアメリカ・カリブ海諸国・東ヨーロッパ向けのプロジェクトもいくらかある。
4年ごとに供出国は基金を補充することが求められている。資金の半分弱は有利な融資の形(favorable loans)で供給され、残りは返済の必要のない直接補助金(direct grants)として提供されている。
(適応基金、Adaptation Fund)
富裕国側が公約する1000億ドルの資金を受け取るもう一つの別の基金(Fund)が適応基金。これは比較的規模の小さい基金であり、基金を補充するシステムはなく、富裕国側は可能な時に、あるいは希望する時に供出するやり方が取られている。
この基金の目的は、異常気象による影響に適応できるように各国の手助けになるプロジェクトを支援することである。これらの異常気象による影響としては、例えば洪水への対策や暑さに強い作物の栽培などの対策が挙げられる。
途上国は、融資の形でなく、補助金の形で受け取る。該当プロジェクトは通常、利益を生むことが無いような適応行動へ資金を提供するということが特徴である。故に売電可能な風力発電やソーラー発電のプロジェクトへの拠出は対象外となる。
(開発程度が最低の国家向け基金、Least Developed Countries Fund、LDCF)
この開発程度が最低の国家向け基金(LDCF)は、最貧国46カ国をカバーしている。
返済の必要のない助成金のみで運営されており、緊急の気候適応資金を提供することを目的としている。これまでにLDCFは360以上のプロジェクトに資金を提供しており、約17億ドルが支払われている。
(1000億ドルの気候変動資金の公約は果たされているか?)
結論としては、果たされてはいない。
OECDのデータによれば、2020年に国際気候変動融資に支払われた総額は約830億ドル。
Oxfamドイツの気候変動・政策責任者のJanKowalzig氏は、「830億ドルという額は大きく聞こえるかも知れないが、グローバルサウスの貧困国が必要としている額はもっと大きい」と指摘している。そして、「我々の調査によれば、適応対策向け費用だけでも、2030年までの期間、毎年3000億ドルを超えるものとなっている。そしてこの数字には気候緩和対策向け費用は含まれていない」とも指摘している。
また、国際開発機関(international development organization)によると、OECDが言う830億ドルは粉飾されている、という。Oxfamの計算では2020年の実際の気候変動支援金額としては最大約245億ドルだったとしている。OECDが公式にリスト化しているプロジェクトの多くは、気候への影響が殆どないものだ、とOxfamは見ている。
「その上、先進国は公約の1000億ドルの支払い方として、多くは融資の形で貸し出している」。従って途上国側はこれらの融資を返済する必要があり、ドイツの支援団体「Bread for the World」のMinninger氏は「このやり方は、ごまかしだ」と主張している。
(損失,Loss,と被害,Damage:気候変動対策資金調達のネックポイント)
世界は何十年もの間、熱波や干ばつによる作物の被害や地域の居住不能化など気候危機により引き起こされている損失(Loss)や被害(Damage)を誰が支払うべきか、について議論を重ねてきている。更に発展途上国はこの目的の為の追加資金を望んでいる。
先進国側は気候変動融資の範囲を超える損害賠償で訴えられることを懸念しており、また彼らは世界最大のCO2排出国の中国など経済的に強い新興国にも同様にドナー国としての支払いを望んでいる。
損失と被害については多くの疑問が未解決のまま残っている状況である。
(気候リスクに対するグローバルなシールド、Global Shield against Climate Risks)
気候リスクに対するグローバルなシールドは、2022年のCOP27においてG7とV20(気候変動リスクを特に大きく受けている約70カ国のグループ)により立ち上げられた。
壊滅的な異常気象に迅速に応えられるように、このシールド(絆創膏といった意味合いか)基金にはあらかじめ決められた金額が割り当てられている。
これまでに2.28億ドル以上が提供されており、その約80%はドイツ拠出となっている。
次いで、PakistanDawnの記事(気候変動への行動)を紹介する。
NASAの代表的科学者のJames Hansen氏は「産業革命以前に比べて世界の平均気温を1.5℃以内に抑えることは、ほぼ絶望的であり、2℃以内に抑えることも、もし我々が迅速かつ適切な行動を取らない限り、非常に困難な状況だ」と指摘している。
この終末論的シナリオ及び気候変動問題の議論に何ら進展が見られないという背景から、国際司法裁判所(International Court of Justice ,ICJ)は諮問手続きを開始している。
手続きには書面及び口頭諮問が含まれ、これにより気候変動に関する各国の義務についての指導基準が与えられることになる。
勧告的意見が下されるのは、2024年後半から2025年初めと見られる。
この動きは国連の下記の動向が引き金になっている。
国連総会(UNGA)はバヌアツ政府からのリクエストを支持する決議を採択した後、ICJに対して気候変動に対する国家の責務に関する勧告的意見を求めることを正式に決定し、ICJ に要請している。
これにより、気候正義の解釈に極めて大きな変化がもたらされ、気候変動対策の将来を形作る上で、またとない機会が提供されることになるだろうとみられる。
地球上から消滅の危険にさらされている国々や、生命を脅かす課題に直面している国々にとって、ICJが今後発表する勧告的意見は、国際法に基づく法的責任を大規模排出国に問う上で役立つ可能性がある。
この勧告的意見は、また現在および将来の世代で最も弱い立場にある人々に損害を与える気候変動に関する行為や不作為に対し政府の責任を追及しようとしている世界中の法域での気候変動に関する訴訟や裁判を強化する可能性がある。
これは気候変動対策の方針を変える画期的な機会を提供することになる。
ICJへの第一回目の書面提出の期限は2024年1月22日まで延長されている。気候危機の前面に立つ国々にとっては、この期間延長は気候正義について、より幅広く議論に取り組むことが出来る機会を提供するものと言える。
気候変動危機に最も責任を負う国々が、脆弱な国々に対する被害を抑制するために、今何を為すべきか、ということをICJ判事らに理解させるには、各国が人権・環境権や気候に関する国際法規的に確固たる証拠と先進的見解を持って、それぞれの訴訟ケースを如何に数多く提供するか、に掛かっている。
このことは、損失と被害を今後の気候変動交渉の最前線に据え、気候危機を管理するには道義的責任を超えて、拘束力を伴う法的義務をも国際社会に認識させることが必要ということである。
ICJの勧告的意見には、諸国が単に慈善的に脆弱国に対し援助を提供するという意識から脱却して、気候変動による被害と損傷に対する公正であり、法的に健全な賠償(reparations)という考えへの移行を促す面もある。被害のみを大きく受けている国々がこの機会を使いタイムリーにそして強力に主張すべきことを展開することが求められる所である。
地球が沸騰する時代、そして暴力が支配する世界にあって、この展開により多国間主義ならびに世界正義に新たな希望が注入される可能性がある。
自主性に任せて排出を削減するという考え方・システムは機能することはなかった。
この自主的削減の考え方は「解決策の計画」を策定する装置にはなったが、公正な将来への希望に関しては、反対に減退させていく方向に働いたと言える。
ICJの勧告的意見により、国家及び非国家主体(多国籍企業体をさすか)は、各国の法的責務を明確にして、履行に対する責任を負うプロセスに参加する機会を得ることになる。
ある国の開発と発展によって、世界の他の地域に暮らす人々の生活や生存が脅かされるのであれば、その開発と発展を推し進める権利は如何なる国であっても持っていない、という当然のことを世界に広める機会に、今回のCOP28がなるべきと考える。
壊滅的な猛暑と洪水が世界の半分に襲いかかるまでに、残されている猶予期間はもう7年だけだ、と言われている。
時を同じくしてネパールでICIMOD主催の初の極間会議(inter-polar conference)とフランスでの極地サミット(Polar Summit)が開催されており、地球の平衡感覚が危機に瀕していることを示す状況が生まれていると思われる。
「地球全体を想定するアプローチ」という視点を欠いては、今後は管理できないことが示されている。
現在人類に課せられた課題は、気候正義というレンズのみを通して判断すべきでなく、地球全体の生命システムの生き残りという全体的見方から判断すべきと、今回の国連総会のICJへの要請決定を捉えるべきである。
そして地球全体の生命システムのなかで、絶滅に向かうスピードを加速させているのが人類だけなのだ。
最後はAlJazeeraの記事(アフリカ気候サミットの間違いを、COP28は繰り返してはならない)になります。
グローバルノースのロビイストらがCOP28で誤った解決策を押し付けてくること、それを許してはならない。
11月末にドバイで開催されるCOP28。しかし会議に先立ち、気候変動政策へのアプローチに大きな変更が無い限り、有意義な進展はないだろうとの指摘が活動家や市民社会から既に打ち出されている。
グローバルサウス諸国側には、富裕国や多国籍企業が通常通りの事業を継続する施策が推進されており、貧困国は単に気候変動の矢面に立たされているのみではないか、という懸念が強くある。
この9月初めにナイロビで開催されたアフリカ気候サミットでも、この懸念は出されており、政府・企業・国際機関・市民団体から数千人の代表が集まったCOP28に先立つアフリカサミットで、アフリカの人々が損失(loss)と被害(damage)の補償、気候緩和、気候変動資金などの問題について共通の立場で合意を得る機会になると見られていた。
しかし発表された最終文書(ナイロビ宣言)ではアフリカ諸国間の一致事項やアフリカ諸国内にある最善の利益を反映するものには適っていなかったと言える。
グローバルノース諸国や多国籍企業のロビイストらには、彼らの誤った解決策を表明する為のスペースが与えられており、そして高いレベルでの会議アクセス権も彼らには与えられていた。
一方アフリカ大陸を支援する目的で透明性ある解決策を要求する活動家や市民社会代表らは、議事進行中のアクセスが困難な状況に置かれ、脇に据え置かれているのではないか、という状況であった。かかる会議の進行を考えるとサミット最終文書の結果は驚くべきことでもないだろう。
結果として、9月のアフリカ気候サミットでは主たる排出国のグローバルノースがアフリカ諸国を補償する政策を推進する一方で、サミットとしてはグローバルノースがアフリカ諸国に被害を与えることを継続するという政策を受け入れさせるものであった。
このサミット宣言では、炭素クレジット・炭素オフセットや炭素取り引きといった問題を含んでいる実践案に重点が置かれ、そしてそれを合法化したものであった。
これらは誤った解決策であり、アフリカ諸国が必要としているものとは言えない。
これらはグローバルノースがアフリカの土地と人々の支配を継続し、そしてアフリカ大陸の排出削減分に見合うクレジットを購入する一方で、グローバルノース側は温室効果ガスの排出を継続することが出来るシステムをアフリカの人々に認めさせたという、新植民地主義の戦術に他ならない。
炭素取り引き(carbon trading)という方策は排出国側が排出を継続することを目指して、その排出分に見合う炭素捕捉活動(アフリカにおける新規植林活動や森林保全活動等)をグローバルサウス側の国で行うというものであるが、ここで問題になるのは、これらの炭素捕捉活動を考えている地域には、そこに存在する森林や土地を生活手段として必要としている地元の人々が現に生活しているということである。
即ち、炭素取り引きの構図には、炭素捕捉という名目および自然保全という名目のもとで、地域に住む人々の生活権・生存権を脅かすという部分が含まれている。
このような計画では炭素排出量の増大に対処はできず、排出量の削減を拒否する富裕企業や先進国のグリーンウォッシングが可能となる構図を助長するということが良く知られている。
炭素取り引きのやり方が解決策でないならば、アフリカ諸国の損失と被害、適応と緩和への資金提供についてグローバルノース側はどういう形で支援を進めていくことが出来るのであろうか?
ここで「キャップとシェア(cap and share)」という考え方が対案となりえる、と気候活動家や市民社会が見なし始めている。
このシステムは世界規模の炭素税(international carbon tax)を中心に据えて、その税金の支払者はグローバルノースの化石燃料採掘組織であり、その主要な消費者だというものである。
この税は、世界規模のグリーンニューディール基金(global Green New Deal fund)向けに年間数兆ドルが見込まれ、その資金で再生可能エネルギー社会への移行や世界の全ての人へのエネルギー供給が可能となると考えられている。またこの資金により、損失と被害向けの助成金、グローバルサウスの適応と緩和活動、そして一般の人々を支援するための現金給付にも提供可能とみられる。
キャップとシェアは国民国家を超えて機能する税制を確立することになる。このことは気候正義の鍵となる考え方であり、永い間待ち望まれていたものである。
モデル化によると、世界規模の炭素税の経済効果は革命的であり、アフリカの全ての極貧状況からの脱却など、大きな利益が得られることが示唆されている。
「護憲+BBS」「新聞記事などの紹介」より
yo-chan