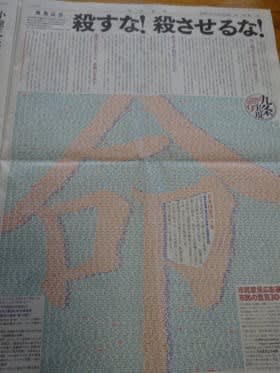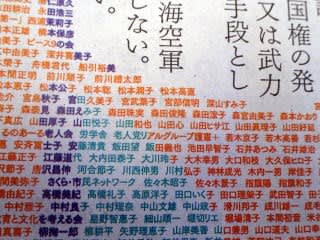1.はじめに
最近、憲法の本を書き出しており、なぜ締め切りのあるコラムなのか、コラム投稿の任が少し負担になっている。
それはともかく、表題が上記のようなタイトルになった。
日本国憲法のミステリーは学生時代から不可思議なものだった。連合軍の占領下で成立した憲法である。学者は間違いを糾すこともないまま、アメリカの占領と発言している。(最近の岩波新書でも、そうなのである。)
確かに、GHQの最高司令官は米軍のトップ、マッカーサー元帥であり、憲法の起草も元帥の名前で呼ばれている。だが、憲法の最大の謎は、制定時はともかく、日本の為政者はGHQの批判を受けて占領軍の草案を少し訂正して、国会の審議を経て、現在の憲法典となっている。
だが、50年代に朝鮮戦争が勃発すると、占領軍はアメリカ主導で日本の再軍備を決行した。そして、あろうことか、戦時中の東条内閣の閣僚であった岸信介を首相に就けて、第二次安保条約を締結したのである。
この急転直下の「憲法」の事実上の「改正」は謎と言わなくして、なんと呼べばよいのか。
2.そういう憲法制定後の世界情勢の激震を受けての、アメリカ主導による、憲法9条の事実上の改正である「自衛隊法の制定」があった。そして、今回の重要な争点となる、米軍の日本在留である「米軍基地の創設」があった。
これが「謎」ではないという憲法学者の日本アカデミーであるが、彼らの憲法テキストには「米軍基地」のきの字もない。(これはジョークだと思うが。)
そうこうして私が悪戦苦闘しているときに、1冊の本が飛び込んできた。矢部宏治(以下矢部氏と言う)著『日本はなぜ、「戦争が出来る国」になったのか』(集英社インターナショナル)という著書である。
3.この矢部氏の本で、私の前述したミステリー;「謎」(疑問)は一気に氷塊した。
矢部氏の言わんとする要点は次のことである。(以下この本の見出しと著者の執筆動機と主張を、冒頭だけ引用します。まだ読み始めたばかりで、コラム投稿には間に合いませんでした。)
『「日本の超エリートも知らない「日米密約」の謎』
「たしかに日米間の軍事上の取り決めには、オモテに出ない闇の部分もあるのだろう、でも、外務省など国家の中枢にはそういう問題も全部わかっている本当のエリートたちがいて、国家の方針を間違わないようアメリカとギリギリの交渉をしてくれているのだろうと。
ところが、全くそうではなかったのです。
現在の日本のエスタブリッシュメントたちは、戦後アメリカとの間に結んできた様々な軍事上の密約を、歴史的に正しく検証することが全くできなくなっている。というのも、過去半世紀にわたって外務省は、そうした密約に関しては体系的に保管・分析・継承することもせず、特定のポストにいるごく少数の人間の個人的なチェックに、その対応を任せてきてしまったからです。
そのため、特に2001年以降の外務省は、「日米密約」というこの国家的な大問題について、ただ資料を破棄して、隠蔽するしかないという、まさに末期的な症状になっているのです。」
(次の見出しがこの本の真髄の、)
『「戦争になったら、日本軍は米軍の指揮下に入る」という密約がある』
「この「日米密約」の世界に一歩でも足を踏み入れてしまうと、世の中の出来事を見る目が、すっかり変わってしまうことになるのです。
例えば、2015年に大きな社会問題となった、安保関連法についてです。(投稿者注記;中略 あの安倍政権で「閣議決定」された集団的自衛権の行使容認問題の案件です。)
けれども、すでにアメリカの公文書で確認されている一つの密約の存在を知れば、あの時起きていた出来事の本質は、あっけないほど簡単に理解できるのです。
その密約は、簡単に言うと、「戦争になったら日本軍は米軍の指揮下に入る」という密約のことです。
1952年7月と、1954年2月に当時の吉田首相が口頭で結んだこの密約が、その後の自衛隊の創設から今回の安保関連法の成立にまでつながる日米の軍事的一体化の法的根拠となっているのです。
けれども、これまでそれは、あくまで日本とその周辺だけの話だった。
ところが、今後はそこから地理的なしばりを外して、戦争が必要と米軍司令官が判断したら自衛隊は世界中どこでも米軍の指揮下に入って戦えるようにする。
そのために必要な「国内法の整備」が、昨年;1916年:ついに行われて」しまった。それがあの安保関連法の本質だったということです。
『日本の戦後史に隠された「最後の秘密」とは?』
「私は今回、この戦争になったら、自衛隊は米軍の指揮下に入る」という密約の行方を追いかけるうちに、これが日本戦後史の「最後の秘密」だろうと思われる、軍事面での「大きな構造」にたどり着くことができました。」
「なぜならそこでは日本の現状が「占領体制の継続」ではなく、それよりもさらに悪いものだということが公文書によって完全に明らかに証明されてしまうからです。」
引用を終わります。
矢部氏は上記の結論を冒頭で述べています。確かに、「本文」を読めば、安保条約が、日米政府のトップではなく、日米合同委員会という、いわば、日本の官僚と在留している米軍のトップ同士の「取り決め」で決定されている素気ないものにすぎません。しかし、これが「日米密約」として、日本の法令と政府も拘束する法制度になっているのです。
次回も、矢部氏の超撃の著書を、ポイントを絞り解読していきます。矢部氏は、真相を知って、悲観的にならないように読者に訴えています。米軍とアメリカ政府の言いなりになっている自民党政権というマスコミ論調ですが、そうではないと矢部氏は主張しています。米軍の日本再占領を強く働き掛けてきたのは政府であると。
トランプ政権時にトランプさんは、米軍基地はそれほど要らないだろうと発言していたこともありました。状況は変わるのだと矢部氏は力説しています。
(次回も続きから、次回は占領下の真実に迫ります。)
「護憲+コラム」より
名無しの探偵