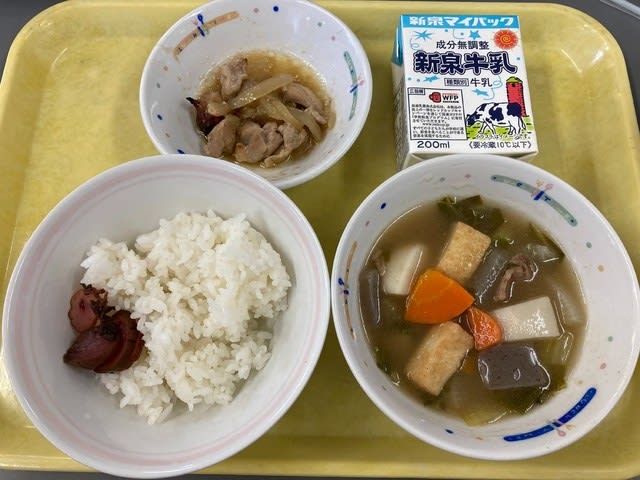「焼きそば」は、中華麺(ちゅうかめん)を肉や魚かい類、野菜といっしょにいためたものです。
中国の「炒麺(チャオメン)」という、めんといろいろな具を塩やしょうゆ味でいためた料理が起源だそうです。
日本に焼きそばが広まったのは終戦後のことで、食べ物が少ない時代に、キャベツなどの野菜をたっぷり入れて量を増やし、塩味やしょうゆ味では味がうすくなるので、こいめのソース味に仕上げたのが最初だとか。
今ではソース味や塩味、しょうゆ味、みそ味など、味付けも様々で、焼いた中華麺(ちゅうかめん)に肉や野菜のあんをかけた「あんかけ焼きそば」などもあります。
日本全国に様々なご当地焼きそばがあり、お祭りの屋台などでも手軽に買うことができる、とても一ぱん的な料理です。
給食でも焼きそばは人気メニューです。
ご家庭では焼きそばだけで一食分の食事になりますが、給食ではおかずとして提供するため、めんの量が少ないのが特ちょう。
焼きそばだけではなく、給食のめん料理は、どれもめん類を具のひとつとして使っていますので、主食であるごはんといっしょに食べても問題ない量です。
「米飯と焼きそば」や「米飯とうどん」といったこん立を見て、「炭水化物ばっかりの組み合わせって栄養がかたよるのではないの?」と心配されるかたもいらっしゃいますが、だいじょうぶです、問題ありませんよ!
今回しょうかいする「いか入り焼きそば」は、給食の分量ではあまりにめんが少ないので、家庭向けに少し量を増やしています。
それでも一食分にするには量が少ないので、これだけでお昼ご飯にしよう、という場合は、材料を倍くらいに増やしてください。
【いか入り焼きそば】

〈材料〉2人分
切りいか(皮なし)・・・30g(冷凍のカットされたものを使うと便利です)
酒・・・・・・・・・・・小さじ1/2
ぶた肉・・・・・・・・・30g
米粉スパゲティ・・・・・40g
にんじん・・・・・・・・1/6本
たまねぎ・・・・・・・・1/6個
キャベツ・・・・・・・・大きめの葉を2~3枚
ニラ・・・・・・・・・・5本
ウスターソース・・・・・小さじ1と1/2
トマトケチャップ・・・・小さじ1/3
塩・・・・・・・・・・・少々
こしょう・・・・・・・・少々
油・・・・・・・・・・・小さじ1

〈作り方〉
1 いかに、酒をふりかけておく。
(そのままいかを使うと生ぐさいにおいが残ります。
酒を全体にふりかけておくことで、においが消えておいしくなりますよ。)
2 ぶた肉は、一口大の食べやすい大きさに切る。
3 なべに水を入れて火にかけ、ふっとうしたら米粉スパゲティを入れて、30秒~1分く
らいゆでる。
火を止めて、ザルに入れ、水をかけて冷ましておく。
(小麦粉でできたふつうのめん類と同じようにゆでるとやわらかくなりすぎて、いた
めた時にぷつぷつ切れてしまいます。
さっとゆでて、まだ固いくらいの状態でザルに移してください。)

4 にんじんは、皮をむいて、短冊切りにする。

5 たまねぎは、皮をむいて、うす切りにする。

6 キャベツは、少し大きめの短冊切りにする。

7 ニラは、2~3cmくらいの長さに切る。

8 フライパンに油とぶた肉を入れ、火にかける。

9 ぶた肉の色が変わったら、にんじん、たまねぎを加えていためる。
10 キャベツを加えて、しんなりするまでいためる。

11 いかを加え、とうめい感がなくなって白く色が変わるまでいためる。
12 ニラを加えて、さっといためる。

13 3の米粉めんを加えていためる。
14 ウスターソース、トマトケチャップを加えて、全体がしっかり混ざるようにいため
る。
15 塩、こしょうを加えて、味を調える。
16 お皿に盛り付けて、できあがり!

今回しょうかいした「いか入り焼きそば」以外にも、米粉めんを使った「きつねうどん(2021年5月1日)」や、「焼きビーフン(2022年6月4日)」、「イタリアンスパゲティ(2022年8月6日)」の作り方をしょうかいしています。
めん類ではありませんが、切り干し大根をめんに見立てた「焼きそば風切り干し大根(2020年4月28日)」や、「切り干しナポリタン(2020年11月7日)」も、カルシウムたっぷりでおすすめです。
ぜひ、作ってみてくださいね。