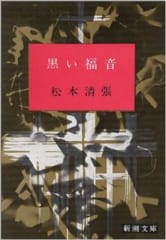
『黒い福音』 松本清張 ☆☆☆☆☆
『憎悪の依頼』と一緒に買った文庫本で、こちらは長編。二冊続けて読むと、『憎悪の依頼』収録の「金環食」と感触が似ていて、まるで「金環食」が本書のプロローグであったかのように感じる。両方とも戦後間もない頃の話で、欧米に見下され、いいように小突き回される日本の姿を描いた社会問題告発型の小説である。しかも本書は1959年に実際に起きたいわゆる「スチュワーデス殺人事件」を題材にしていて、硬派も硬派、「黒い福音」という直球のタイトルもあわせて、松本清張の「これでいいのか」という憤りが伝わってくるようだ。
作品によっては冒頭から一気に掴みに来る松本清張だが、本書はかなりスロースタートである。本題である殺人事件の数年前に起きた、物資の横流し事件から物語の幕が上がる。これは結果的にうやむやに終わってしまうが、特権的な立場を悪用するグリエルモ教会のうさんくささが強く印象づけられる。そして数年後、本題となる殺人事件の経緯が、そもそもの発端から詳述される。
ここでも、いきなり死体が見つかったりはしない。まずは若い神父が登場し、彼が日本の教会で若い女と接するうちだんだんと異性への欲望を高ぶらせていく過程が描かれる。もちろん神父は性欲厳禁だが、若い男の場合はそうも言っていられない。おまけに回りには日本の若い女がたくさんいて、「神父サマ 」みたいに憧れのまなざしを注いでくるのである。こうして彼は気安い女遊びを覚え、やがて本格的に恋をすることになる。この相手がやがて殺人事件の被害者となる、生田世津子である。
」みたいに憧れのまなざしを注いでくるのである。こうして彼は気安い女遊びを覚え、やがて本格的に恋をすることになる。この相手がやがて殺人事件の被害者となる、生田世津子である。
このようにトルベック神父の恋愛話が丁寧に語られていくが、なかなか犯罪物語の様相を呈して来ないので苛立つ読者もいるかも知れない。しかしこのスロースタートぶりが、むしろ松本清張の本気度というか、この題材に対する真摯な姿勢を表わしているように思える。エンタメ的にさっさと盛り上げようと思えばいくらでもできるはずなのだ。そして実際、この愚直なまでの丁寧さが後でじわじわと効いてくる。
トルベックの恋人となった生田世津子は、素性の怪しい男ランキャスターによって「運び屋」として白羽の矢を立てられ、裏の工作によってスチュワーデスとなる。しかしトルベックからランキャスターの命令を伝えられた世津子は、これを拒絶する。ここからトルベックはのっぴきならない状況へと追いこまれていく。恐ろしいランキャスターに、トルベックはとても逆らうことはできない。そして世津子が言うことをきかないこと知ったランキャスターは、彼女を処分するようトルベックに迫るのである。
若いトルベックがランキャスターと恋人・世津子の板挟みになって苦しむくだりは、読んでいて非常に辛い。恐るべき葛藤である。ランキャスターに逆らうことは不可能だが、自分の恋人を殺すことなどとても出来るものではない。世津子が言うことを聞いてさえくれれば解決するのだが、世津子は「そんな悪いことはできないわ。あなたもそんな人とは縁を切るべきよ」と正論で反対し、揺らぐことがない。絶対絶命。こうして恐るべき殺人は起きる。
ここまでが第一部である。スロースタートだった物語はじわじわと緊張感を増して、恐るべき濃度の惨劇へと至る。どっと疲れるほどの読み応えである。そして第二部は死体が発見され、日本の警察が動き出すという、よりミステリ的な展開となる。ここからはもうイッキ読みだ。警察の捜査と教会側の動きが並行して描かれる。刑事たちの捜査によってグリエルモ教会、そしてトルベックが重要な事件関係者として浮かび上がる。捜査陣は緊張する。当時、欧米のキリスト教団が日本において占めていた特権的地位は相当なものだったらしい。普通ならとっくに逮捕状が出ている段階でも、警察はまだ慎重な姿勢を崩さない。やがてマスコミも嗅ぎつけ、グリエルモ教会を取材する。
ここで唖然とするのは、グリエルモ教会の対応である。トルベックの上司にあたるビリエ師が出てくる。新聞記者がトルベック神父に会いたいというと、聖職者の優しい笑顔のまま「そういう名前の神父はここにはおりません」そんなバカな、いるのは分かってるんです、と言っても微塵も揺るがない。平然と見え透いた嘘をつく。記者が呆れて言葉を失うと、今度は豹変して、出て行けと怒鳴り始める。宗教裁判にかけるぞといって威嚇するのだ。ほとんど異常人格者である。
こうした教会側の態度の底にあるのは、日本は野蛮国という見下しであると作者は書く。野蛮国の法律など守る必要はない、というわけだ。大事なのは本国の意向であり、教会の勢力を拡大することにある。そのためには日本の法律など破って構わない。日本の法律を破っても、野蛮人たる日本人を殺しても、神の教えに反することにはならないのだ。
ついに日本の警察はトルベックを訊問する。本書は実際の事件にかなり忠実に書かれているが、容疑者だった外国人神父もここに書かれている通り、長い訊問にもかかわらずまったく水を飲まず、一度もトイレに行かなかったという。それによって血液型を判定されることを恐れたのである。本当に無実だとしたらもちろん、不自然きわまりない行為である。それからまた、教会は信者に命令してトルベック神父のアリバイを偽証させる。鉄壁のアリバイが成立するが、信者以外の証人は一人もいないのである。それにしても、神父の言うことだからと唯々諾々と偽証してしまう信者とは一体何なのか。実際の事件の際も、人格高潔な聖職者がそんなことをするはずがないという警察への批判があったという。
そして結末も実際の事件の通りで、トルベック神父は警察の追及をかわすため外国へ逃げ出してしまう。逃亡ではなく、教会の指示によって堂々と出国していくのである。もちろん、それを許可したのは日本政府である。このニュースを聞いた刑事が驚いて署長に会う場面は忘れられない。「これがもし同僚か後輩だったら、掴みかかっていただろう」という一文に、現場の警察官たちの悔しさが集約されている。そして「日本の警察が、いや日本人全体が灰をかぶった」という一文に、著者の行き場のない怒りが込められている。
やりきれない結末である。そしてこのすべては、当時日本の国際的な立場が極めて弱かったからだという。国際的な立場が弱いと、自国民を殺され、法律を蹂躙されても泣き寝入りするしかないのである。日本人はこの事件を風化させてはならないと思う。
決して後味は良くないが、読み応えは充分の傑作であり、松本清張の本気汁迸る力作である。
『憎悪の依頼』と一緒に買った文庫本で、こちらは長編。二冊続けて読むと、『憎悪の依頼』収録の「金環食」と感触が似ていて、まるで「金環食」が本書のプロローグであったかのように感じる。両方とも戦後間もない頃の話で、欧米に見下され、いいように小突き回される日本の姿を描いた社会問題告発型の小説である。しかも本書は1959年に実際に起きたいわゆる「スチュワーデス殺人事件」を題材にしていて、硬派も硬派、「黒い福音」という直球のタイトルもあわせて、松本清張の「これでいいのか」という憤りが伝わってくるようだ。
作品によっては冒頭から一気に掴みに来る松本清張だが、本書はかなりスロースタートである。本題である殺人事件の数年前に起きた、物資の横流し事件から物語の幕が上がる。これは結果的にうやむやに終わってしまうが、特権的な立場を悪用するグリエルモ教会のうさんくささが強く印象づけられる。そして数年後、本題となる殺人事件の経緯が、そもそもの発端から詳述される。
ここでも、いきなり死体が見つかったりはしない。まずは若い神父が登場し、彼が日本の教会で若い女と接するうちだんだんと異性への欲望を高ぶらせていく過程が描かれる。もちろん神父は性欲厳禁だが、若い男の場合はそうも言っていられない。おまけに回りには日本の若い女がたくさんいて、「神父サマ
 」みたいに憧れのまなざしを注いでくるのである。こうして彼は気安い女遊びを覚え、やがて本格的に恋をすることになる。この相手がやがて殺人事件の被害者となる、生田世津子である。
」みたいに憧れのまなざしを注いでくるのである。こうして彼は気安い女遊びを覚え、やがて本格的に恋をすることになる。この相手がやがて殺人事件の被害者となる、生田世津子である。このようにトルベック神父の恋愛話が丁寧に語られていくが、なかなか犯罪物語の様相を呈して来ないので苛立つ読者もいるかも知れない。しかしこのスロースタートぶりが、むしろ松本清張の本気度というか、この題材に対する真摯な姿勢を表わしているように思える。エンタメ的にさっさと盛り上げようと思えばいくらでもできるはずなのだ。そして実際、この愚直なまでの丁寧さが後でじわじわと効いてくる。
トルベックの恋人となった生田世津子は、素性の怪しい男ランキャスターによって「運び屋」として白羽の矢を立てられ、裏の工作によってスチュワーデスとなる。しかしトルベックからランキャスターの命令を伝えられた世津子は、これを拒絶する。ここからトルベックはのっぴきならない状況へと追いこまれていく。恐ろしいランキャスターに、トルベックはとても逆らうことはできない。そして世津子が言うことをきかないこと知ったランキャスターは、彼女を処分するようトルベックに迫るのである。
若いトルベックがランキャスターと恋人・世津子の板挟みになって苦しむくだりは、読んでいて非常に辛い。恐るべき葛藤である。ランキャスターに逆らうことは不可能だが、自分の恋人を殺すことなどとても出来るものではない。世津子が言うことを聞いてさえくれれば解決するのだが、世津子は「そんな悪いことはできないわ。あなたもそんな人とは縁を切るべきよ」と正論で反対し、揺らぐことがない。絶対絶命。こうして恐るべき殺人は起きる。
ここまでが第一部である。スロースタートだった物語はじわじわと緊張感を増して、恐るべき濃度の惨劇へと至る。どっと疲れるほどの読み応えである。そして第二部は死体が発見され、日本の警察が動き出すという、よりミステリ的な展開となる。ここからはもうイッキ読みだ。警察の捜査と教会側の動きが並行して描かれる。刑事たちの捜査によってグリエルモ教会、そしてトルベックが重要な事件関係者として浮かび上がる。捜査陣は緊張する。当時、欧米のキリスト教団が日本において占めていた特権的地位は相当なものだったらしい。普通ならとっくに逮捕状が出ている段階でも、警察はまだ慎重な姿勢を崩さない。やがてマスコミも嗅ぎつけ、グリエルモ教会を取材する。
ここで唖然とするのは、グリエルモ教会の対応である。トルベックの上司にあたるビリエ師が出てくる。新聞記者がトルベック神父に会いたいというと、聖職者の優しい笑顔のまま「そういう名前の神父はここにはおりません」そんなバカな、いるのは分かってるんです、と言っても微塵も揺るがない。平然と見え透いた嘘をつく。記者が呆れて言葉を失うと、今度は豹変して、出て行けと怒鳴り始める。宗教裁判にかけるぞといって威嚇するのだ。ほとんど異常人格者である。
こうした教会側の態度の底にあるのは、日本は野蛮国という見下しであると作者は書く。野蛮国の法律など守る必要はない、というわけだ。大事なのは本国の意向であり、教会の勢力を拡大することにある。そのためには日本の法律など破って構わない。日本の法律を破っても、野蛮人たる日本人を殺しても、神の教えに反することにはならないのだ。
ついに日本の警察はトルベックを訊問する。本書は実際の事件にかなり忠実に書かれているが、容疑者だった外国人神父もここに書かれている通り、長い訊問にもかかわらずまったく水を飲まず、一度もトイレに行かなかったという。それによって血液型を判定されることを恐れたのである。本当に無実だとしたらもちろん、不自然きわまりない行為である。それからまた、教会は信者に命令してトルベック神父のアリバイを偽証させる。鉄壁のアリバイが成立するが、信者以外の証人は一人もいないのである。それにしても、神父の言うことだからと唯々諾々と偽証してしまう信者とは一体何なのか。実際の事件の際も、人格高潔な聖職者がそんなことをするはずがないという警察への批判があったという。
そして結末も実際の事件の通りで、トルベック神父は警察の追及をかわすため外国へ逃げ出してしまう。逃亡ではなく、教会の指示によって堂々と出国していくのである。もちろん、それを許可したのは日本政府である。このニュースを聞いた刑事が驚いて署長に会う場面は忘れられない。「これがもし同僚か後輩だったら、掴みかかっていただろう」という一文に、現場の警察官たちの悔しさが集約されている。そして「日本の警察が、いや日本人全体が灰をかぶった」という一文に、著者の行き場のない怒りが込められている。
やりきれない結末である。そしてこのすべては、当時日本の国際的な立場が極めて弱かったからだという。国際的な立場が弱いと、自国民を殺され、法律を蹂躙されても泣き寝入りするしかないのである。日本人はこの事件を風化させてはならないと思う。
決して後味は良くないが、読み応えは充分の傑作であり、松本清張の本気汁迸る力作である。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます