前にも書いたことだが、映画の登場人物が無宗教だと発言したり、もしくはキリスト教に疑いを持っていることがあり、そういうのは気になる。
ケイ・ポラック『歓びを歌にのせて』というスウェーデン映画では、牧師の妻が夫である牧師に「罪なんてない。教会が信者を脅すために作り上げたものだ。だから、許しもない」といったことを言うシーンがあった。
牧師の妻がそんなことを言うなんて、と驚いてしまった。
これは神を否定した発言ではなく、教会のあり方を問題にしていると思う。
妻が言う「罪」とは、その後の展開からして、セックスに関するものだろう。
『歓びを歌にのせて』は心臓病になって引退した世界的指揮者が、スウェーデンの故郷の村に住むところから始まる。
教会の聖歌隊を指導することになり、次第にみんなの信頼を集める。
堅物の牧師はそれが面白くなくて、非難めいたことを言う。
そこで先ほどの妻の発言になるわけだ。
牧師は主人公を聖歌隊の指導者から解任し、反発した妻は家を出る。
牧師の妻がああいったことを言ったのは、20年間性欲を抑えてきたということがあるかららしい。
また、聖歌隊のメンバーである中年の独身女性は、他の若い女性メンバーが主人公と仲良くなるのが面白くなく、男の出入りが多いその女性をみんなの前で非難する。
私が中学生のころ(35年前)、スウェーデンといえばポルノ解禁、フリーセックスの国であり、憧れてました。
フリーセックスの国であって、実際はキリスト教的道徳観が大きな影響力を持っているということなのだろうか。
ロジャー・ミッチェル『Jの悲劇』では、Jとは主人公ジョーと、主人公につきまとう男ジェッドのイニシャルだが、Jesusすなわちイエス・キリストのことでもあるそうだ。
冒頭、草原でののどかな食事が一転して、気球に乗っていた人の墜落事故と、あれよあれよという描写には圧倒される。
ジョーとジェッドがかけつけるが、落ちた男性はすでに死んでいる。
ジェッドが「神に祈ろう」と言うが、無神論者のジョーは断る。
これにもいささか驚いた。
宗教を押しつけるのではなくて、死体を前にして、ごく自然に「祈ろう」と声をかけたような感じだったのに、どうして拒んだのかと思った。
日本人だったら、無宗教の人だって、とりあえずは手を合わせて念仏でも称えるところだ。
ジョーがどう断ったか、原作のイアン・マキューアン『愛の続き』を見ると、次のような会話をかわしている。
死体を前にして、ジェッドが「ぼくらにできることがあると思うんだ。ふたりでできることは祈ることなんだけど」と言い、ジョーは「申し訳ない。そういうのは好きじゃないから」と断る。
無神論というのは宗教に無関心ということではなく、ちゃんとした主義なんだということを、あらためて知らされた。
以前、ヨーロッパでは火葬=無神論だったそうだ。
鯖田豊之『火葬の文化』にこう説明されている。
ヨーロッパ近代初期には火葬を希望したひとはすべて骨つぼの地下埋葬を拒否した。(略)
火葬と土葬は二律背反で、焼骨をおさめた骨つぼは地下でなくて、火葬場内外のしかるべきところに安置されなければならなかった。
ずいぶん徹底していると感心してしまう。
ところが、キャメロン・クロウ『エリザベスタウン』でも、父親は火葬にしてほしいと遺言し、ケンタッキーの田舎町の人たちも「カリフォルニアの人間なんだから」と反対はしない。
1999年のイギリスの火葬率は70.4%、アメリカは25.3%である。
現在では、火葬するからといって、無神論という主義を持っているわけでもないのだろう。
それにしても、無神論者は、どういう状況であろうとも、つき合いだろうがなんだろうが、あくまでも神に祈ることはしない、死後の生を認めない、という態度を貫くのは、神が気になるからだと思う。
これは、私は巨人が大嫌いなのだが、しかし巨人の成績に無関心ではいられないというアンチ巨人ファンで、同じ心理ではなかろうかと思う。














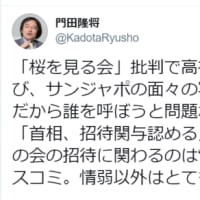
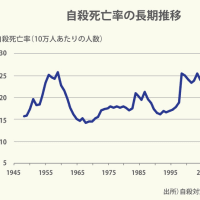
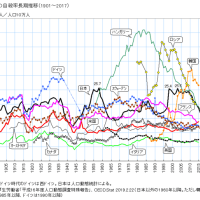

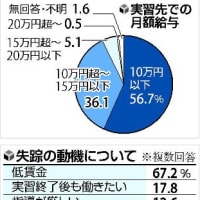






私は市川準の映画が好きですから、悪くは言いたくないんですけど、たしかに減点ですね。
死は決してきれいごとではないと思う。
同感です。
ラストも、「お涙頂戴」ではお粗末過ぎますよね。
所属している映画サークルでも、あのラストでかなり減点した人が多かったです。