加賀乙彦『雲の都』の語り手である悠太、そして母や妻、妹、叔母一家たちはカトリックの信者なので、『雲の都』は神について何度も触れている。
悠太は大学紛争の時に、クギが打ちこんである角材で頭を殴られて入院する。
痛みに耐えながら、このように悠太は考える。
自分が苦しい目に遭った時に十字架上のイエスを思うのはキリスト教徒の常らしく、エリザベス・ギャスケル「ベン・モーファの泉」(『ギャスケル短編集』1850年)にもこんなエピソードが書かれてある。
エレナの一人娘が転倒して半身不随になり、婚約者が去ってしまい、メソジスト派の説教師であるデイヴィッドにエレナは訴える。
デイヴィッドはこのように答える。
イエスに比べると、これくらい大したことがないから我慢しろ、というわけである。
松家仁之『火山のふもとで』に、世界が美しいのは神が創造したからというやりとりがある。
へそ曲がりの私は、だったら醜いものは誰が作ったのかと思う。
『雲の都』でも、悠太の叔母と娘が浅間山を見ながらこんな会話をする。
母「ほんとだね。(略)もし神様がおられなければ、美はこの世に現れなかった。わたしは絶対にそう思う」
娘「(略)どんな山でも美しいのはなぜかという話になった。(悠太)先生の言うには、自然の山で醜いのに出会ったことがないんだって。(略)驚いたことに、あらゆる方向から浅間は美しく見えたんですって。子供が砂山で浅間山を作ろうとしない理由もわかる。それは子供には神の作った浅間山は再現できないからなんですって」
どうして神は浅間山を噴火させ、多くの人を殺したのか、と私は思う。
阪神大震災でボランティアとしてしばらく滞在した悠太は、ある少女が焼け死んでいく姿を想像する。
こういう想像力があるのに、その痛みをもたらした神への疑問は出てこないのが不思議である。
というか、都合よすぎるんじゃなかろうか。
デイヴィッド・ロッジ『どこまで行けるか』は、神への異議をはっきりと述べている。
洪水による土砂崩れが小学校を呑み込み、教師と百十余名の児童が死ぬという事件(実際の事件)が起きる。
ブライアリー神父はこの事件について次のような説教をする。
そして、神に不平をぶちまけ、苦しみを率直に語った『ヨブ記』を引用する。
グレアム・グリーン『事件の核心』では、子供の死について神に問う。
遭難した船から逃れた人たちが乗ったボートが40日間漂流し、女の子は助けられたものの、すぐに死ぬ。
主人公である警察副署長はこう感じる。
グレアム・グリーンやデイヴィッド・ロッジはカトリック作家である。
彼らの小説に登場する人物は、神に異議を唱えても、信仰を捨てず、神に無関心でもない。
疑問を持ちながらもカトリックにこだわり続ける。
そこらがキリスト教徒ではない私にも共感できるわけです。














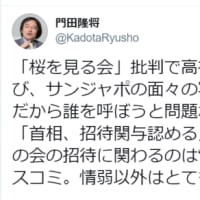
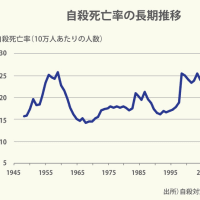
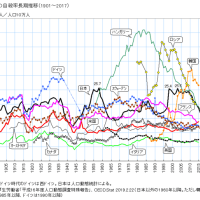

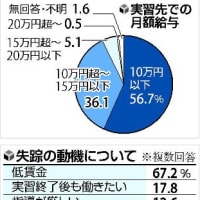






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます