
せびろいや・ごじゅうおとこの臭せびろいや・めざましどけいいや・ねくたいいや・つうきんいや・ちょうれいいや・えいぎょういや・かいぎいや・せったいいや・ぱちんこいや・たばこいや・いざかやのうーろんはいいや・じょうしのわるぐちいや—
トム・ウェイツにI Don't Wanna Grou Up = 大人になりたくないという曲がある。髪が抜け落ちてほしくない・良いボーイスカウトになりたくない・数えることを学びたくない・最大量を持ちたくない—といったことを、その時点で42歳の彼がうめくように歌う。
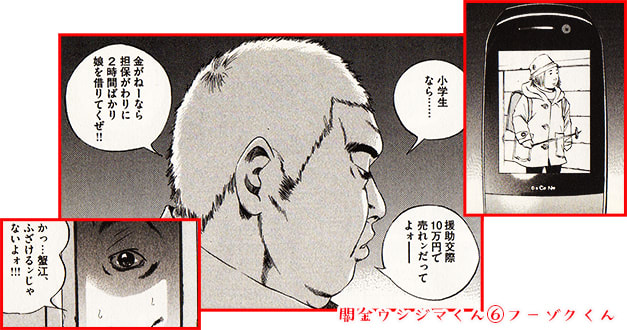
タカ @e9JvbfROlsaMzuv 11月27日
『子供がSNSで知り合った大人に会いに行って誘拐された事件』 じゃなくて 『大人がSNSを利用して子供を探し、少しでも自分の罪と罪悪感を軽くするため・自身の願望を合理化するために「困窮する相手を助けただけ、相手の望みを叶えただけ」と言い訳している誘拐事件』 だと考えよう
後半に引用したグリール・マーカス氏の論評によれば、女優エリザベス・テイラーは「わたしはわたしが所有する産業なのです」と言い切ったそうだ。子どものマイケル・ジャクソンにとって同じように考えることは不可能。産業ではなく産業が扱う商品として大人の欲望にまみれる。
有名人であることはどんな気分だろうか。私が会社を辞めて何もすることがなく、会社員時代末期に先輩から教わった風俗遊びを繰り返していたころ、キャバ嬢や風俗嬢にはマイケル・ジャクソン好きが多かったように記憶する。ベスト選曲のMDをコピーしてほしい、それも自分と親の分2枚—と頼まれたことも。
主婦もジャニーズのタレントやディズニーランドが好きだ。あるいは歌舞伎とか宝塚とか。でも、誰とも分らない、名前も身分もウソかも分らない男をもてなしてサービスしなければならない風俗嬢たちが、さまざまな醜聞が飛び交って既に落ち目になっていたマイケル・ジャクソンに思い入れるのは、もっと切実であると思う。
マイケルは2009年に50歳で亡くなった。後年にやはり早世したプリンスやトム・ペティとも同じ死因=鎮痛・麻酔・睡眠薬の過剰投与であったようだ。人間が資源として囲い込まれ、生きているだけで商品として消耗し、消耗分がそのまま資本側の利益となるようなアメリカ文明が世界を覆うに先駆けて咲いた蓮の花のようなスターであった—💫

iTunes Playlist "28) Michael Jackson" 113 minutes
1) The Jackson 5 / I Want You Back (1969 - The Definitive Collection)
2) The Jackson 5 / Who's Lovin' You (1969 - The Definitive Collection)
3) The Jackson 5 / ABC (1970 - The Definitive Collection)
4) The Jackson 5 / I'll Be There (1970 - The Definitive Collection)
5) The Jackson 5 / Never Can Say Goodbye (1971 - The Definitive Collection)
6) Michael Jackson / Got to Be There (1971 - The Definitive Collection)
7) Michael Jackson / I Wanna Be Where You Are (1972 - The Definitive Collection)
8) Michael Jackson / Ben (1972 - The Definitive Collection)
9) The Jackson 5 / Dancing Machine (1974 - The Definitive Collection)

10) The Jacksons / Show You the Way to Go (1976 - The Jacksons)

11) The Jacksons / Shake Your Body (Down to the Ground) (1978 - The Essential Michael Jackson)
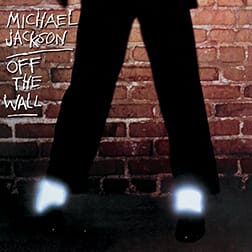
12) Michael Jackson / Don't Stop 'Til You Get Enough (1979 - Off the Wall)
13) Michael Jackson / Rock with You (1979 - Off the Wall)
14) Michael Jackson / She's Out of My Life (1979 - Off the Wall)

15) Michael Jackson / Billie Jean (1982 - Thriller)
16) Michael Jackson / Beat It (1982 - Thriller)
17) Michael Jackson / Human Nature (1982 - Thriller)
18) Michael Jackson / P.Y.T. (Pretty Young Thing) (1982 - Thriller)
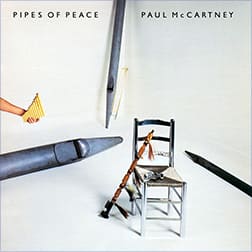
19) Paul McCartney & Michael Jackson / Say Say Say (1983 - Pipes of Peace)
20) Michael Jackson / Thriller (1982 - Thriller)

21) The Jacksons / State of Shock (feat. Mick Jagger) (1984 - Victory)

22) Michael Jackson / Bad (1987 - Bad)
23) Michael Jackson / Man in the Mirror (1987 - Bad)
24) Michael Jackson / Smooth Criminal (1987 - Bad)

25) Michael Jackson / Black or White (1991 - Dangerous)
26) Michael Jackson / Gone Too Soon (1991 - Dangerous)

27) Michael Jackson & Janet Jackson / Scream (1995 - HIStory)

28) Michael Jackson / Love Never Felt so Good (2014 - XSCAPE)
グリール・マーカス/矛盾の商品ジャクソンズの大巡業/ミュージック・マガジン1984年10月号(訳:三井徹)
1984年、ジャクソン主義の台頭
1982年にエリザベス・テイラーが、自分の生活を描いたTV映画の上映を止めさせるべく訴訟を起こすという事件があった。正式に認可はしていない映画だったのだ。「この私は、私自身が所有する産業なのです」と彼女は言った。115年前にカール・マルクスはその奇妙な訴えを『資本論』の中でもとりわけ奇妙な題がついた「商品の物神崇拝とその秘密」の中で予測していた。「商品は一見したところきわめて明白な、取るに足りないものに見える」とマルクスは書いている。「しかし、分析をしてみると、それは非常に不思議なもので、形而上的、また神学的詳細が充満していることがわかる」。
「言うまでもないことだが、人間は自然界の物質の形を、自分の行動によって自分の役立つものに変えてしまう。たとえば木は、それからテーブルを作ろうとすれば、形は変えられてしまう。しかしそれでもテーブルは木であり続ける。平凡な、感覚的なものであることに変わりはない。けれども、それは商品として登場するやいなや感覚性を超越するものに転じる。自分の足で自立するというだけでなく、他のあらゆる商品と関連して、逆立ちをし、その木製の脳から奇怪な観念を展開させる。みずからの意志で踊り始めるという場合よりもはるかにすばらしい観念をだ。」
これはまったくの詩である。神秘的響きがあるのは偶然なのではない。マルクスの言う踊るテーブルというのは心霊論者に言及したもので、当時、ボストン、パリ、プラハ、ペテルブルグで心霊論者たちがテーブルを囲んで手を握りあい、この世を去った家族の霊がその手に木を叩かせ、テーブルを躍らせるのを待ったのだった。心霊論者たちは商品とはまったく関係がなかったが、商品は魔術と大いにかかわりがあった。近代的、科学的概念での変形が、古代の神学的観念の化体に屈するという意味での魔術とかかわりがあったのだ。しかし、たとえ、1867年にマルクスは脱産業社会のテイラー主義を予測しえたとは言えるにしても、ジャクソン主義に対しても用意ができていたとは思い難い。
1984年7月6日に、マイケル・ジャクソンと4人の兄弟がジャクソンズとして『ヴィクトリー・ツアー』の第1回コンサートをミズーリ州カンザス・シティで行った時点で(エルヴィス・プレスリーがテネシー州メンフィスで最初のレコードを作って以来、ちょうどその日で30年経っていた)、マイケルの『スリラー』のTOP10滞在期間は1年半となり、3500万枚が売れていた。「それは誰だったのか」という図像学的神秘を核にしてポップ音楽を再編成するということによって、完璧な商品化体系が生じていたのである。いったんはめこまれれば、それが何であろうとたちまち新商品に転じさせられるというほどに完璧な商品化体系である。
このマイケルの場合、有力な音楽と、それよりさらに有力な流通機構が、壊れそうにない頑丈な螺旋状の商品化体系を作りあげていた。まずは多国籍企業であるCBSがある。それからペプシ・コーラだ。この会社は『スリラー』からの大ヒット、「ビリー・ジーン」の権利を買い、それを避けようのないペプシ兼マイケル・ジャクソン・コマーシャルにしてしまった。それに、マイケルが私生活を完全に守ることを主張して、はでやかな制服、トレードマーク、意匠権を揃えてでないと人前に現れないということを動力源にした、途方もない規模のマス・メディア宣伝がある。そういったものによって、メビウスの帯的な純然たる資本主義が生じたのである。その過程における要素のどれもが他の要素を強化し、また、各要素が識別できないほどに併合しあっている。7月6日の時点では、人はラジオで「ビリー・ジーン」の出だしの和音を聞きながら、もう「ビリー・ジーン」を聞いているのかペプシのコマーシャルを聞いているのかわからなくなっていた。どちらであっても間違ってはいなかったのだ。
今回のツアーは当の過程を実行してみせるものであり、その過程にひとつの偉大な芸術品として刻印を押すか、あるいは、ばらばらに切り刻んで売り払うことになるだろうが、そのツアーが始まった時点で、人びとは、従来理解されてきた意味での商品を消費しているというよりも(レコード、ポスター、本、雑誌、イアリング、キーホルダー、首飾り、ピン、ボタン、かつら、Tシャツ、下着、帽子、スカーフ、白手袋、上着…どうしてビリー・ジーンズという名前のジーンズはなかったんだろう)、自分自身の消費のそぶりを消費していた。つまり、人びとはテイラー主義的マイケル・ジャクソンを消費していたのではなく、認可された付属品かその模造品を消費していたのでもなく、自分自身を消費していたのである。
『スリラー』の大成功は、ポップ爆発のイメージを生み出した。ポップ音楽が政治上、経済上、地理上、人種上の境界線を超える。そういった境界線を非現実的なもの、欺瞞か腐敗の産物、と思わせる。ということは、新しい芸術作品が、無理やりに区分けされた社会生活に取って代わる新しい世界を暗示する。そして、そういう出来事に伴なって、誇大宣伝が果てしなく続き、レコードの売り上げ数が前代未聞となり、人びとの間で急激にデマが飛び交い、また、過去は無意味で未来は可能性に満ちていると思えるほどに日々が新しく感じられる。
そういった意味すべてにおいて『スリラー』は価値があった。マイケル・ジャクソンはアメリカの文化生活の中心を占めていて、他にはその足もとにおよぶ黒人アーティストはいなかった。1970年に『全アメリカ人(ジ・オムニ=アメリカンズ)』の中でアルバート・マリーが、他の誰にも増して黒人は真のアメリカ人である、他の誰にも増して黒人は自分を再生するようにさせられているからだと論じていたが、マイケル・ジャクソンはその命題を究極的に証明するものであると思えた。
しかし、ポップ爆発というものは、階級、場所、肌の色、経済的地位といった境界線でへだてられている者を結びつけるだけなのではない。それは区分もする。エルヴィス、あるいはビートルズというような魅力的で、かつ不穏でもある人なり物なりに直面すると、その場合、反応する人もいればしない人もいる。そして、それが、たとえわずかな間のことであれ、主要な社会的事実となる。可とする声に満ちながらも、ポップ爆発は否を生み出しもする。称賛という文脈においては、それは否定の一変形である。
『スリラー』がほとんど首尾一貫したポップ事実になるにつれ、マイケル・ジャクソンについて何かが毎日報道されるようになり始めるにつれ、『ヴィクトリー・ツアー』の異様な契約上のことがらもまた日々伝えられるにつれ(ジャクソン5兄弟の出演料が4000万ドル、総収入の見積り額が1億ドル、チケットは30ドルで4枚1組分120ドル郵送が必要条件、それに、切符購入のために送金したけれども運悪くチケットが手に入らないファンの金は、返送されるまで8週間銀行に預金されていて、その利子が総額1800万ドルになる見込みだという…しかも、120ドル送金分から手数料として8ドルが差し引かれる)、マイケル・ジャクソンのポップ爆発は新種のものであることが明らかになった。
ロック・スターが最も支配的なスター・システムにこれほど完全に組み込まれるということはかつてなかった。映画スターのブルック・シールズ、TVスターのエマニュエル・ルイス、それにキャサリン・ヘップバーンやジェーン・フォンダと並んで舞台に立ったりしたほかに、マイケルはロナルド・レーガンに招かれてホワイト・ハウスへ行きもした。
ロック・アーティストが、時間の経過によって安全になったとき(エルヴィス・プレスリーやチャック・ベリーの場合のように)ではなく、ポップ瞬間のきわみにいるときに大統領に礼遇されたというのはこれが初めてだ。そして、何故ああも簡単にロナルド・レーガンと並ぶことができたかと言えば、また、ロナルド・レーガンがマイケルと並ぶことができたかと言えば、それはそのポップ瞬間がそれ自体、安全であったからである。マイケルは他の誰かれの名声の機能を果たすものとして存在し、また他の誰かれも彼の名声の機能を果たすものとして存在したか、あるいは存在しなかった。
エド・サリヴァン・ショーに出演し、国中に、そして世界に姿を見せた1956年のエルヴィスのように、『サージェント・ペパー』アルバムによってポップの一時性から芸術の永遠性に持ち上げられた1967年のビートルズのように、スリラーとしてのマイケルには独自の、止めようのないはずみがついていた。しかし、そういったかつてのポップ爆発とは違って、スリラーとしてのマイケルは、人びとがその音楽を模倣してそこに自己表現のはけ口を見出すという騒ぎを生み出しはしなかった。生み出したものは、マイケル扮装騒ぎ、制服、トレードマーク、意匠権を盗用する騒ぎに過ぎなかった。
それが頂点に達したのは『ヴィクトリー・ツアー』の数日前のことで、マイケル・ジャクソンに似ることに浮き身をやつしていた17歳の少年が、マイケルにもっとそっくりになるための整形手術の費用を両親が出してくれないということで自殺したのだった。マイケル自身が『スリラー』に備えて整形手術をし、黒人的容貌をもっとワシ鼻調の、つまり白人ふうのものにしたということは、最高の皮肉でしかない。直面した受け手を区分するのではなく、見出した受け手を具象化するポップ爆発というのはこれが初めてであったからだ。
あのかつての出来事は主観性をもった爆発であった。人はどう反応してよいかわからなかったし、あの疑念の爆発は主観的新風潮を生み出した。男の子たち、女の子たちを惹きつけるために、あるいは自分はじゅうぶんに生きていると感じるために新しい歩き方、しゃべり方をしなければならないとしたら、私はどういう歩き方をし、しゃべり方をするだろう、といったことであった。メビウスの帯の範囲内では、『スリラー』は客観性をもった爆発であった。受け手はそのアルバムを一枚買うことによって、あるいは単に、そのアルバムが存在していることを認めることによって、じゅうぶんに反応することができた。言い換えれば、このポップ爆発は、それが誘発する主観的反応の質によって計られるのでなく、それが引き出す客観的、商業的交換品の数によって計られるというポップ爆発の最初のものであった。
したがって『ヴィクトリー・ツアー』が開始されるすぐ前にマイケル・ジャクソンが、自分の最大の業績は、『スリラー』が他のどのアルバムよりも多くのTOP10シングル(7枚)を生み出したことを証明する『世界の記録ギネスブック』賞を獲得したことだったと語ったのは正しかった。
予想がついたかもしれないが、彼の最大の業績は「人びとに新しい歩き方、新しいしゃべり方を与えたこと」ではなかったし、「音楽は無限であることを証明したこと」でもなかった。「神の手を借りれば夢がかなうことを実際に示してみせたこと」でさえなかった。そういうことが言えるには、ポップ爆発においては、貸借対照表では計りえない価値こそが重要なのであるという含みがなければならない。そういう出来事は、その最も強力な美的、かつ社会的産物として、自分の魂の運命は、あるいは全世界の運命は、ある一定の曲なり演奏なりの成り行きいかんにかかっているという気持ちを参加する者に必然的に与えるものなのである。今回の出来事は、そういうものではなかった。
カンザス・シティのアローヘッド・フットボール競技場で45000人の聴衆を前にしたジャクソン主義は、区分しなかったし、統合もしなかった。エルヴィス、ビートルズのポップ爆発は、社会の境界線を激しく攻撃するか、あるいは覆したのだったが、『スリラー』はその境界線をクロスオーバーしていた。つる草みたいにだ。『スリラー』は、その境界線を壊しはせずに、一時的に見えなくしていただけであったために、さらにもう一度その境界線を否定し難いものにしたのだった。
商品の化体が効を奏した。かつてはジャクソン兄弟は圧倒的に黒人から成る聴衆を相手にしていたのに、今ではほとんど全員が白人である聴衆を相手にしていたのだ。商品が逆立ちしていた。マイケルのポップ爆発は、聴衆をその聴衆に加わろうとはしない者から区分はしなかったのだ。聴衆を聴衆自身から区分していた。

高すぎるチケットの意味
ABCテレビでテッド・コッペルが担当するニュース番組『ナイトライン』に頼まれて、私はカンザス・シティへ行った。『ヴィクトリー・ツアー』の開始について報道するその特別番組は、そのツアーが新聞の第一面を占めていることとぴったり歩調が合っていた。30ドルというチケットの値段に人びとが怒っているという話、興行主が競技場やホテルを無料で使わせろと要求しているという話、そのほか似たり寄ったりの話が『ヴィクトリー・ツアー』を全国規模のスキャンダルにしていたのだ。その番組には数々のインタビューが折り込まれていて、ファンの人たち、評論家のネルソン・ジョージ、ジャクソンズのプロモーターであるチャック・サリヴァン、コンサート興行関係者の中からのサリヴァン批判者、それに衛星中継によってLAからの兄のジャッキー・ジャクソン(足の怪我でツアーに同行せず)が語っており、番組の焦点は“論争”だった。そして、基調は「カンザス・シティはツアーの開始地点であるだけではない、騒ぎが終わる場所でもあるかもしれない」ということだった。
私は幸い最後のひとことを言うということになっていた。その役目でもってジャクソンズのコンサートを見たのだが、実際に見ることができたのは生放送が始まる前の30分間だけではあった(結局は、ショーは90分少々で終わったが、これは当日ジャクソンズの宣伝担当者が保証していた2時間半とは大きく食い違っていた)。
私は、いいショーだった、じゅうぶん練習もしてあるし、上演も真剣だし、標準的なものだと言った。なじみの曲がなじみの方法で処理されていたのだ(チャック・サリヴァンが語っていたレーザー光線、特殊照明、発炎筒、それにキリストの復活、『スター・ウォーズ』、アーサー王伝説をほのめかした寸劇はというと、それは音楽の演奏が標準的であったということの一部を成すものだった。そういった効果は音楽演奏がどこまで行けるかをおおい隠す手段であり、そして、うまくおおってはいなかった)。私はきわめて首尾よくというのではなかったが、カンザス・シティの聴衆を見て受けたショックを伝えようとした。
人口の3割が黒人であるのに聴衆の黒人の割合は5%だった。それに聴衆は95%が白人であるというだけでなく、その圧倒的大多数が裕福であった。黒人の聴衆もその点では同じであった。さらには、聴衆はどう見たって「ロック」聴衆ではなかった。大部分は家族で、40代か50代の両親が小さい子供を連れてきているというものだった。群衆の一部ではあっても聴衆の一部ではなく、誰とも知り合わなければ、共に興奮を分かちあってざわめくということもなく、自分たち家族だけで静かにしゃべっていた。若すぎるか老けすぎであるその群衆のかなりの割合が、それまでロック・ショーといったものには一度も行ったことがない人だったと言い切れるように思う。
始まるまでは何日間か、ジャクソンズのショーで暴動が起きるかもしれないということがしきりに話題になっていた。チケットを持った客が舞台に殺到するとか、入れなかった者が怒って入口に押しかけるとかいった心配である。しかし実際には、チケットがなければ駐車場に入ることもできなかったし、それに誰も舞台に殺到はしなかった。新生児を両親が放ったらかしにしたってあの群衆の中では安全だったと言っていい。梁の湾曲した部分にすずめの巣があるのが見つかったとしても、そっと舞台に手渡され、町の飼鳥園に急いで運ばれるか、あるいはマイケル・ジャクソンの私設動物園のために保管されたことだろう。
私は典型的なロック評論家として、平和、調和、それにカタルシスを覚えさせる暴力といった文脈で、人生の意味がごきげんなビートに合わせてあらわにされるというのでなければ満足はせず、誰かが物を投げるのではないか、少なくともごみを投げるのではないかと身を乗りだした。
黒人の抗議の声が次第に高まり、組織化もされていたが、ツアーの主催者がチケットの値段を下げることなくそれを静めようとした手段のひとつは、全米有色人地位向上協会(NAACP)がコンサート会場に有権者登録所を設けるのを認めたことだった。NAACPはツアーがちょうど始まるときにカンザス・シティで全国大会を開いていて、レーガン政権の人種差別政策を激しく攻撃したのだが、カンザス・シティで登録する有権者の大多数はほぼ確実に、NAACP側ではなくレーガン側についているようだった。
『ナイトライン』でのコッペルの最後の質問は単刀直入だった。「一回見るのに30ドル、それだけの値打ちありますか」。私はないと言った。よく出来た、標準的なショーであったが、それ以上のものではなかったからだ。もっと安い値段でもっと多くを与えてくれるショーがあったからだ。それに、どれだけあのショーが良かったにしてもあの値段に値しなかったのは、本来の聴衆のかなりが、つまり、マイケル・ジャクソンを現在のようなアーティスト、かつ社会現象にしたところの人びとのかなりが、30ドルのチケットを買えないということで自動的に排除されていたからである。
メディアは、マイケル・ジャクソンが歴史的な被害対策行為として前日に120ドル郵送チケットくじを終わらせ、ツアーで稼ぐ金は全額(見積もりでは500万ドル)、名前は伏せた慈善団体に寄付するというニュースで満ちていた。しかし、その行為によってチケットの値段が1セントでも下がったわけではないというニュースで満ちてはいなかったし、『ヴィクトリー・ツアー』があとに残すことがらの中でも特にあとあとまで尾を引きそうなことは、あらゆる種類のコンサートのチケットの値段が一律に引き上げられるということかもしれないというニュースで満ちていたわけでもなかった。
マイケル・ジャクソンのいちばん熱心な、極度のファンは黒人の子供、15歳未満の少年少女であった。その子たちにとってマイケルは解放を、アルバート・マリーが言う自己創造、自由を表すものだった。しかし、その子供たちがマイケルに退却することを余儀なくさせた。子供たちは否と言ったからである。興行主は、カンザス・シティでの公演の場合、1枚のチケットに対して10人が注文してくるだろうと予想していたのだが、そのあとに続く都市でのチケットの売れ行き見込みはかろうじて1対1という程度になったのだった。
コンサートが進行中であるいま、ジャクソン兄弟とプロモーターは、そういったことはすべて忘れさせようとしていたが、私としては、利用できるだけの時間と働かせられるだけの才覚を用いて、それは忘れられるべきではないと言うべく努力した。
翌日になると、私はそのカンザス・シティのコンサートについて、当のコンサート会場に居たときよりもさらに多くのことを知った。それに、紙面に苦心してロック評論を書くことと全国放送でわずかな文句を口にすることの違いについてもけっこう発見があった。
私はカンザス・シティー空港へ行くのにタクシーを拾ったのだが、運転手があのショーを見てきたかと訊いた。見てきたと答えたら、運転手はわたしも行きたかったんです、子供たちが連れて行ってやらなかったもんだから怒ってしまいましてねと言う。その運転手は白人で、年は35ぐらいだった。いやな気持ちでしたよ、連れて行けなくてね。だけど女房と二人して家を買う頭金を貯めてるところでして、ああいうことには金は使えないんです。だけどきのうの晩テレビに出てた人が、それだけの値打ちはなかった、不公平だったと言ってましてね、それ聞いてかなり気が楽になったんです。あれは本当にありがたかったですよ。
もっといい世の中であれば、そのテレビに出てたっていうのは私ですとは言わなかっただろう。しかし、こういう浮世ではそのままに受けとめ、あれは自分だったと言った。
その1時間後、カリフォルニアに帰る便に乗るために列に並んでいたら、ひとりの男が近寄ってきた。これまた白人で、年はたぶん40だった。テレビに出てた音楽評論家はあなたですかと彼が言い、私はそうだと答えた。そうですか、どうもありがとう。あれ聞いて別に恥ずかしくはないんだって気持ちになったんです。どういう意味ですか、と私は訊いた。
その人が説明するには、カンザス・シティでは1984年7月6日という週末に、ジャクソンズのコンサートのチケットを持っていないということは、自分の子供の目には、また同じ社会層の人の目には、経済的にも社会的にも落伍していることを示すものであったという。金を持たないつまらない人間、他人とのつながりのないだめな人間、値打ちのないやつということを意味していたのだ。
私にはチケットを買う余裕はありましたよ、と彼は言った。ただ、子供は3人いましてね、だから女房も加えて5枚必要だったわけですが、ということはつまり8枚注文しなきゃならないってことですよ。チケットを手に入れてくれるそれなりの人もちゃんと知っているつもりでしたが、どうも思い違いだったみたいです。テレビであなたを見てて、ただのショーだったんだなってことがわかりました。チケットを手に入れるのにもっと手を尽くせたとは思いますが、私はそうしませんでした。でもいまは悔やんだりはしてません。
そのふたつの小さな出来事があって、私は、ジャクソンズのツアーがいかにレーガノミックス(レーガン政権の経済政策)を見事に表したものであるかということを痛切に感じた。社会生活は経済戦争であり、戦利品は勝者のものとなるという考えに終始するあの社会理論を完璧に表したものなのだ。ただし、それは私にはわかっていたことだった。知らなかったのは、ジャクソンズのツアーが、少なくともカンザス・シティでは、何よりも社会的地位にかかわる出来事であったということだ。そしてそれによって、これまでロックのショーに行ったことのない人たち、再びまた行くことがないと思われる人たちがあんなに来ていたことの説明がついた。「おかあさん、マイケル・ジャクソンってだれ」と私の後ろの席にいる5歳の子供が訊いた。「歌手よ」と母親は答えた…「ほら、そんなに前の人の席を蹴らないで」。

歴然としたポップス関係の崩壊
『ヴィクトリー・ツアー』はマイケル・ジャクソンに両親と兄弟が強要したものだった。マイケル・ジャクソンが親兄弟との法律上、財政上、芸術上の結びつきを最終的に切ってしまう前の、大金を儲ける最後の機会であったのだ。そこで、レーガノミックスの中枢であるふたつの妙策を思いついた。つまり、金を手にして逃げろ、買い手に用心させろである。父親のジョー・ジャクソンと兄弟たちとは、ツアーを運営するのに黒人のボクシング興行主、ドン・キングを引き入れた。それに対してマイケル・ジャクソンとマネージャーが反対すると、白人のフットボール興行主であるチャック・サリヴァンがキングと入れ替わった。ただし、キングの取り分はそのままだった。
そのどちらの人物にしても賢明な選択ではなかった。ロックは事業としては、アーティストとファンのあいだの独特な相互関係に基づいているものなのだが、そのロックを二人ともわかってはいなかった。それは、売り手が商品を差し出し、買い手が金で応じるというだけのことがらではない。アーティストがファンを創りだし、ファンがアーティストを創りだすのだ。両者の関係は相互の同一化によって、信頼によって、決まるものである。
『ヴィクトリー・ツアー』の条件が新聞で報道されるにつれ、見たところ非道と思われることがらがあとからあとへと続くにつれ、その関係はほどけてきたが、しかしそれでも持続した。マイケル・ジャクソンをじかに、生身で、舞台で、動いているところを見られるという期待がやはり圧倒的だったからだ。けれども、7月1日にテキサスの11歳の女の子がマイケル・ジャクソン宛ての公開状をダラスの新聞に贈ったところで、糸がほどけた。あるいはむしろ、あの裸の王様の昔話のように、制服は着ていながらもマイケルは裸にされたのだった。ラドナ・ジョーンズはこう書いていた。
「あなたにお手紙を書きたかったのは、私がどういう気持ちでいるかを言いたかったからです。今まで私はずっと、あなたが思いやりのある人だと信じていました。よりによってそのあなたがどうしてこんなに利己的なのでしょうか。この町のテキサス・スタジアムに出演するのは金持ちの人たちのためだけなのですか。私はしょっちゅうアルバイトをしてはあなたのポスター、レコード、その他、あなたは私の生活の一部だと感じさせてくれるものをなんでも買ってきました。だけど…(ショーには)行けません。行くには100ドル以上持ってなければだめだからです」
ツアーの興行主はあとでこのお嬢さんに無料のチケットを手配した。これは、腎臓病にかかっている何人かのかわいい子供たちに「個人的に」透析治療を施してやる一方で、そういった治療を必要としている人たちすべてに同様に治療を施そうとする社会計画には反対するというレーガン政権のやり方とまったく同じ調子の行為である。けれどもその動きははるかに遅すぎた。マイケル・ジャクソン版のポップ音楽をすでに破壊してしまった矛盾を強調しただけであったのだ。
ポップ演奏の背後にあるに違いない信頼の矛盾が、遅かれ早かれマイケル・ジャクソンの音楽における矛盾を理解させることになるということはまず確実だと思えた。
ポップ音楽は空想ないしは可視性、それと現実、そのふたつの間の相互関係に支えられている。アーティストとファン場合と同様に、一方がもう一方を創っているのだ。自分の聴衆におびえている無口の、両性具有的な、見たところ性別のない若者と、欲望、興奮、安堵、愉快の話をする歌手とのあいだには矛盾があった。有名人が登場する舞台に現れ、ほとんどしゃべらず、ただもうおとなしく控え目にしている制服姿と、怒り、意志、欲望を伝達し、そのすべてを暴力に近いところまでもっていきながら舞台を交差する華々しい演技者とのあいだの矛盾があった。
『スリラー』が上昇していくあいだじゅう、その矛盾はマイケル・ジャクソンの音楽に緊張を添えるのみであった。なおいっそう生気あるものに思わせるだけだった。けれどもカンザス・シティでは、その矛盾は見えすいていて、あまりに苦しく、あまりに不快であった。
記者が部屋いっぱいにいる中でNAACPから賞を受け取るマイケルは、黒眼鏡、軍服、白手袋、額に計算どおりに垂れた髪の毛というかっこうで、現実ばなれしていた。生身で、手を伸ばせばさわれるところにいたのにそうであった。機械人形のようであったのだ。その晩、アローヘッド競技場にマイケルは黒眼鏡と手袋で登場した。そして、その眼鏡を肩越しに投げ、手袋を捨ててうたいはじめ、動きはじめた。そのとき突然、数百フィート離れたところからでさえ、彼はあざやかに現実的となった。言わんとするところがあり、それをひとことももらさず伝えようとしている人物がそこにいたのである。
しかしそれでも、ラジオでは「ステート・オブ・ショック」が聞こえた。ジャクソンズの新しいアルバム『ヴィクトリー』からのシングルだ(このアルバムはジャクソンズの面々の力作を集めた良くも悪くもないもので、その中の曲はどれもジャクソンズのショーでは取りあげられなかった。…舞台のジャクソンズはただ、なじみの曲をなじみのやり方でうたっていただけだからだ)。
その「ステート・オブ・ショック」で、マイケル・ジャクソンはミック・ジャガーとデュエットしているが、自分をショック状態にして去っていった女のことをきわめておざなりにうたっていて、その文句はひとことも信じられない。おそらく歌唱がきわめて良くない、ただ型通りにやっているだけだということで矛盾が生じたのかもしれないが、しかし、その曲がぐいぐい進んでいくにつれて、「ビリー・ジーン」「ヒューマン・ネイチャー」「ビート・イット」といった、マイケル・ジャクソンの一見強固な歌唱でさえも信じられなくなった。
この無口な、おびえた、軟弱な男がビリー・ジーンと寝たって? 初めはどうしようもない欲望だったのに、それを素朴な人間性として称えたんだって? ちんぴらの喧嘩をやめさせたんだって? どうやってだい。ビリー・ジーンと路地裏の娘と二組の敵対するちんぴらたちとを南カリフォリニアにある自分の城に連れ込んでかい?
そういった曲が、ラジオでは、また舞台では、あれほど圧倒的な説得力をもっていただけになおさら、おおやけの場では制服を着て、小さい、おとなしい、少女っぽい声で「ありがとう」としか言わないマイケル・ジャクソンにまさかあんな出会いについて本当のことが語れるものだろうかという思いにさせられてしまったのだ。
しかし同時に、歌手は本当のことを語るのだという、空想と現実とが一致するポップ前提の矛盾が、信頼というポップ前提の矛盾が火花を散らしていて、マイケル・ジャクソンが次にまた自分自身のすばらしい音楽をやれば…願わくば「ビリー・ジーン」「ヒューマン・ネイチャー」「ビート・イット」のようなすばらしい音楽をやれば…きっとそれも非凡なものだろうということを暗示していた。
『ヴィクトリー・ツアー』はいぜんとして1億ドルの純益をあげるかもしれない。アルバム『ヴィクトリー』は200万枚出荷されたが、それだけの数は売れるかもしれない。あるいはもっと売れるかもしれない。けれども、話はいまや裏切り話、信頼の矛盾の話、混乱の話、確信の矛盾の話である。
歌い踊る魅惑的で、神秘的なマイケル・ジャクソンとは対照したものとしてのジャクソン主義は、自らを自分の商品にしていた。そして、その商品はもう一度、自分は抑制できないものであることを、魔術であることを証明していた。金銭だけではなく、憤りと疑念とにも駆り立てられて、最後にもう一度逆立ちをしたのだ。踊り手としてきわめて活発で滑脱なマイケル・ジャクソンが一片の木になっていた。彼のポップ爆発は実際、否定を生み出した。自らの否定をだ。ゲームはこれで納得された。ポップ音楽は客観的市場における主観のゲームであり、主観が否定されると、つまりファンをパフォーマーに転じる化体作用が停止されると、何も起きないのである。ポップ文化では、商品は支配はするが統治はしない。
☞2008年6月の記事「グリール・マーカスによればマイケル・ジャクソンは」を改題改訂

























