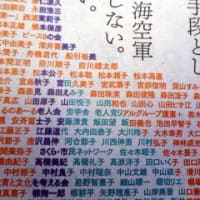『肖像画は歴史を語る』は、西洋史の歴史家樺山氏が西欧にある美術館を訪問して書いたエッセーである。
最初に書かれた肖像画は宮廷画家ベラスケス(スペイン17世紀の画家)の作品「マルガリータ王女」の肖像であり、4点を描いている。樺山氏が一番印象強かった作品は多分1660年に描いた9歳のマルガリータ像(プラド美術館蔵)であろう。この本の冒頭にある挿絵だからである。
ところでこの投稿の主眼は樺山氏の本の紹介ではなく、ベラスケスの肖像画作品それ自体にある。
フランスの作曲家のモーリス・ラヴェルという人はベラスケスの描いたマルガリータ王女の肖像をルーブル美術館(多分スペインから借りたのかもしれない)で観て、ある楽曲を着想した。「亡き王女のためのパヴーヌ」という曲である。この「亡き王女」というのは実はラヴェルのフィクションであり、彼の真意は17世紀の音楽をイメージして王女のための宮廷音楽を創作したのだという。
なぜならベラスケスは9歳になったマルガリータを描いた後に急逝しているからである。そしてこの画家は王女よりも50歳ほど年上であった。(この音楽が私にとって一番印象深いものだった。)
さて、この王女マルガリータの肖像画の一つである「宮廷の侍女たち」(1956年)を観て、20世紀の哲学を変革する作品を書いた哲学者がいる。ミッシェル・フーコー「言葉と物」である。
フーコーが言うようにこのベラスケスの作品は異様である。画面中央に5歳のマルガリータ王女が立ち、侍女たちの左横には画家であるベラスケス本人が絵筆を持って王女を背後から見つめているという構図である。パトロンであり、画家にとって主人である父王フェリペ4世と母マリアーナたちは鏡に映っているにすぎない。
この不思議な構図から、フーコーは国王夫妻こそ本来「観られる対象」のはずであるのに「観る者」に転換されている、つまり肖像画を観る鑑賞者の位置に空間移動されているというのだ。
ここにそれまでの古典的表象の消滅があり、この主体そのものが省略されてしまったという。そして、「主体というこの束縛の関係から自由になった表象は、とうとうみずからを純粋な表象として提示できるようになるのである。」(「言葉と物」)
何を言いたいのかよく分からないが、この作品の構図を直視するなら本来絵画の依頼者であるはずの国王が鏡の中に映るだけになり、絵の鑑賞者の位置という背景に退き、画家とモデルが絵画の中心に位置づけられている。主客の転倒があると言いたいのであろう。
絵画の解釈が最近変わってきたと言われるが、ベラスケスという画家はフーコーにわざわざ指摘されるまでもなく、自分を作品の中に表象させているわけであるから、自覚的に見る主体と観られる客体を転倒させているのであり、フーコーは単にそれを感じ取ったにすぎない。偉大な哲学者でもなんでもなくベラスケスこそ「画家の中の画家」(マネ)と言われる巨匠なのである。
こうして、わたしたちは一枚の絵画から思いがけないインスピレーションを引き出すことが出来ると思われ、芸術がまた芸術を産み出す、あるいは鑑賞者の人生に決定的な影響を及ぼすことがあると言えるのではないだろうか。
「護憲+BBS]「 明日へのビタミン!ちょっといい映画・本・音楽」より
名無しの探偵
最初に書かれた肖像画は宮廷画家ベラスケス(スペイン17世紀の画家)の作品「マルガリータ王女」の肖像であり、4点を描いている。樺山氏が一番印象強かった作品は多分1660年に描いた9歳のマルガリータ像(プラド美術館蔵)であろう。この本の冒頭にある挿絵だからである。
ところでこの投稿の主眼は樺山氏の本の紹介ではなく、ベラスケスの肖像画作品それ自体にある。
フランスの作曲家のモーリス・ラヴェルという人はベラスケスの描いたマルガリータ王女の肖像をルーブル美術館(多分スペインから借りたのかもしれない)で観て、ある楽曲を着想した。「亡き王女のためのパヴーヌ」という曲である。この「亡き王女」というのは実はラヴェルのフィクションであり、彼の真意は17世紀の音楽をイメージして王女のための宮廷音楽を創作したのだという。
なぜならベラスケスは9歳になったマルガリータを描いた後に急逝しているからである。そしてこの画家は王女よりも50歳ほど年上であった。(この音楽が私にとって一番印象深いものだった。)
さて、この王女マルガリータの肖像画の一つである「宮廷の侍女たち」(1956年)を観て、20世紀の哲学を変革する作品を書いた哲学者がいる。ミッシェル・フーコー「言葉と物」である。
フーコーが言うようにこのベラスケスの作品は異様である。画面中央に5歳のマルガリータ王女が立ち、侍女たちの左横には画家であるベラスケス本人が絵筆を持って王女を背後から見つめているという構図である。パトロンであり、画家にとって主人である父王フェリペ4世と母マリアーナたちは鏡に映っているにすぎない。
この不思議な構図から、フーコーは国王夫妻こそ本来「観られる対象」のはずであるのに「観る者」に転換されている、つまり肖像画を観る鑑賞者の位置に空間移動されているというのだ。
ここにそれまでの古典的表象の消滅があり、この主体そのものが省略されてしまったという。そして、「主体というこの束縛の関係から自由になった表象は、とうとうみずからを純粋な表象として提示できるようになるのである。」(「言葉と物」)
何を言いたいのかよく分からないが、この作品の構図を直視するなら本来絵画の依頼者であるはずの国王が鏡の中に映るだけになり、絵の鑑賞者の位置という背景に退き、画家とモデルが絵画の中心に位置づけられている。主客の転倒があると言いたいのであろう。
絵画の解釈が最近変わってきたと言われるが、ベラスケスという画家はフーコーにわざわざ指摘されるまでもなく、自分を作品の中に表象させているわけであるから、自覚的に見る主体と観られる客体を転倒させているのであり、フーコーは単にそれを感じ取ったにすぎない。偉大な哲学者でもなんでもなくベラスケスこそ「画家の中の画家」(マネ)と言われる巨匠なのである。
こうして、わたしたちは一枚の絵画から思いがけないインスピレーションを引き出すことが出来ると思われ、芸術がまた芸術を産み出す、あるいは鑑賞者の人生に決定的な影響を及ぼすことがあると言えるのではないだろうか。
「護憲+BBS]「 明日へのビタミン!ちょっといい映画・本・音楽」より
名無しの探偵