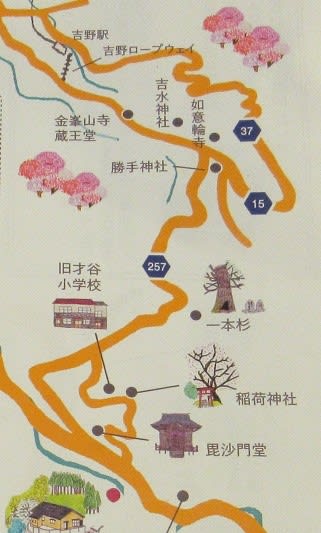さて、ウダウダ会一行は、清水寺をあとに、ワイワイ・ウダウダ言いながら、次の愛染坂に向かいました。
坂の下り口にある愛染堂勝鬘院(あいぜんどう しょうまんいん)から愛染坂と名付けられたのですが、ここは「愛染さん」で有名です。

これは10月末に七坂を歩いた時に撮った写真です。
この時は中に入らず、そのまま正面の大江神社に入り、
そのあと、左側の「愛染坂」を下りました。

で、ここに入るのはこれが初めてなんですが、愛染さんは聖徳太子によって建立され、本尊として良縁成就・夫婦和合で有名な愛染明王が奉安されているとのこと。だから「縁むすび」なんですよね。
門をくぐった右の奥に「愛染かつらの木」があります。樹齢数百年と言われる大きなかつらの木に、ノウゼンカズラのツルが巻き付き、かつらとカズラが一体となったように見えます。つまり仲の良い男女が寄り添っている、あるいは抱き合っているように見えることから、このかつらの木が「恋愛成就、夫婦和合の霊木」として、もう何百年も前からこのあたりでは親しまれているとのことです。この写真、そんなふうに見えます? 言われてみたら、見えますかね~

「縁結びの霊木 愛染かつら」の札もあります。
さて、「愛染かつら」といえば、昔(昭和10年代)に映画が大ヒットし、その映画の主題歌の「旅の夜風」がこれまた映画以上に大ヒットした、ということを前回のブログでも書きました。「花も嵐も踏み越えて~」という出だしで、霧島昇という当時の人気歌手と女性歌手とのデュエット曲でした。また繰り返しますが、うちの母が霧島昇の大ファンで、自分の子供に「昇」という名を付けました。今の僕の名は、霧島昇が存在していなければついていなかったはずの名前です(笑)。
と書きながら、今、思い出しました。
僕は今から11年前の2007年12月1日からこのブログを始めたのですが、その第1回目に「自己紹介と近況報告」というタイトルで、まず最初に自分の名前の由来のことを書いていましたわ(笑)。今、急にそれを思い出しました。
そんな、自分にとっても縁のあるところへ、今回、初めてやって来たというわけです。
ここには「霊木」と共に「霊水」というのもありました。

これがそうですが、立札をアップしてみますと…

「この井戸水を飲めば(中略)愛念を叶え…」とありますね~
もうひとつ、愛染さんの名物は多宝塔です。

解説によりますと、この多宝塔は、推古天皇元年(593年)聖徳太子によって創建されました。その後、織田信長の大阪石山寺攻めの際に焼失しましたが、慶長2年(1597)豊臣秀吉により再建されたということです。現在の大阪市では最古の木造建築物として、国の重要文化財に指定されているそうです。
大阪市で一番古い建物だということを、覚えておきます。
愛染さんを出て、すぐ前にある大江神社に入り、その神社の急な石段をみんなで下りました。実は愛染坂は大江神社の横にあるなだらかな坂なのですが、みんなが降りたのは七坂とは無関係のただの階段でした。ま、メンバーはそんなことには全然お構いなしのようです(笑)。
そのあと、口縄坂、源聖寺坂を巡り、生國魂神社(生玉さん)へ到着。

七五三の時期だったのですね。

結婚式も行われており、若い衆が太鼓を叩いていました。
9時半に天王寺を出発し、いきなりこんにゃくを食べたりしましたが、あちこち寄り道をしながら歩いてもせいぜい2時間。生玉さんではまだ11時半でした。
しばらくの間、そこで休憩をして、「さぁ、行こか!」とリーダーのNさんが立ち上がり、最後の坂である真言坂を下り、一行は、徒歩と地下鉄で阿倍野へ戻り、Nさんが予約をしてくれていたアサヒ・ビアホールへと行きました。
ウダウダ会は「歩こう会」ですが、ひょっとすると「あるこーる会」と違うか? と思われるフシもあります(笑)。
全員テーブルについて、Nさんが「本日はお疲れさまでした。乾杯!」と音頭をとり、みんな一斉に生ビールをゴクゴク…。あぁ、うまい!
やっぱり「あるこーる会」やなぁ、と、ひそかに納得した僕でした。
さて、皆さん。今日で11月も終わり。明日から12月です。本当に1年ってあっという間に経ってしまいますね~。お風邪など召されないよう、ご自愛ください。