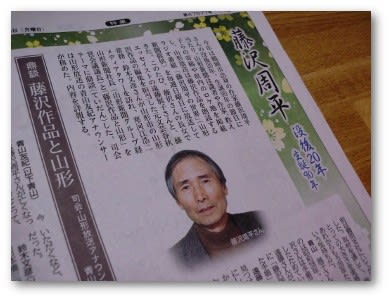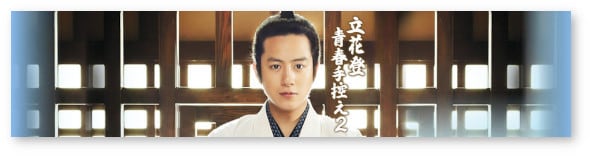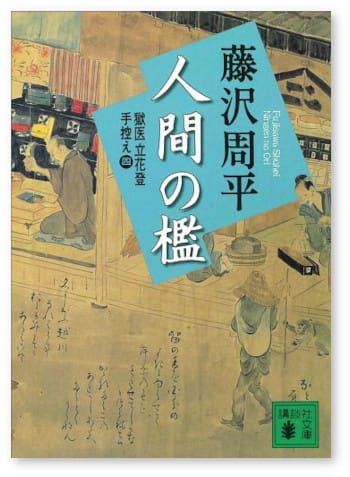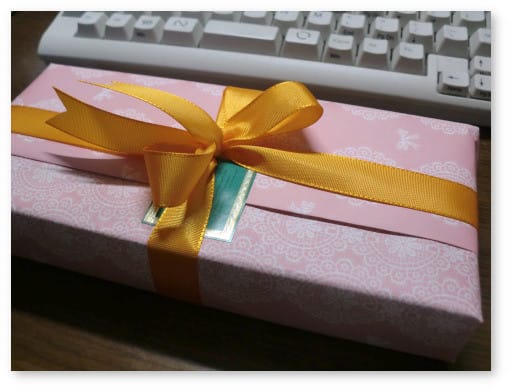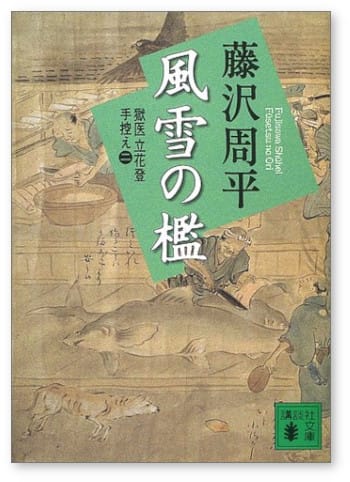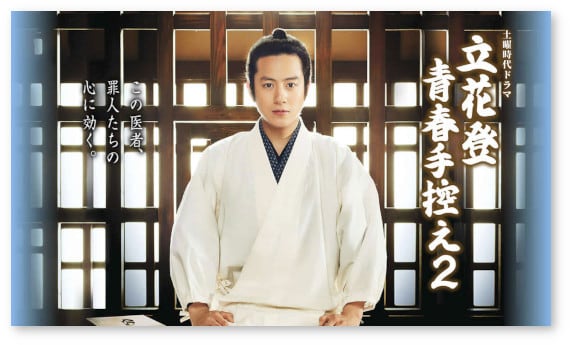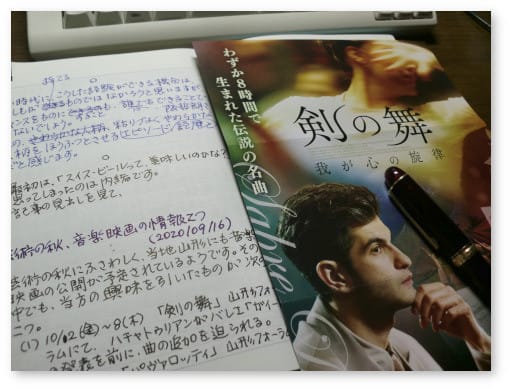NHKの「朝ドラ」最終回を観ました。朝食後、後片付けもそこそこにTVの前へ。夫婦で二人して食い入るように(^o^)/
ドラマの最終回のテーマは「和解」でしょうか。例えば千代と一平がお芝居を通してしみじみと本音を語るセリフとなっているところ。なるほど、前日の「セリフを追加してはどうか」という千代の提案がこんな形で生きてくるとは!
妻も夢中でのめりこんでいたようで、テレビ画面への身の乗り出し方がスゴイです。このところ朝ドラを続けて観られる環境になって、私自身も、なるほど面白いものなのだなと実感しているところです。まあ、作品によるものとは思いますが、「おちょやん」の終盤の盛り上がり方はすごかった。
そうそう、役者人生はきちんと役回りを演じなければならず、それも大変なことです。天海一平役の成田凌さんは、一般の人から役者と役柄とを混同して誤解され、「浮気して子どもまで作るなんて、サイテー、嫌い!」と言われたとか。まあ本人にとっては大変なことですが、身から出たサビというか自己責任というか、それとも役者冥利に尽きることなのか、微妙なところですね〜(^o^)/
写真は、私のお気に入りの、東根市神町の菓子店「チェリー」のケーキです。まるで「おちょやん」のように、甘さとほろ苦さが絶妙。
ドラマの最終回のテーマは「和解」でしょうか。例えば千代と一平がお芝居を通してしみじみと本音を語るセリフとなっているところ。なるほど、前日の「セリフを追加してはどうか」という千代の提案がこんな形で生きてくるとは!
妻も夢中でのめりこんでいたようで、テレビ画面への身の乗り出し方がスゴイです。このところ朝ドラを続けて観られる環境になって、私自身も、なるほど面白いものなのだなと実感しているところです。まあ、作品によるものとは思いますが、「おちょやん」の終盤の盛り上がり方はすごかった。
そうそう、役者人生はきちんと役回りを演じなければならず、それも大変なことです。天海一平役の成田凌さんは、一般の人から役者と役柄とを混同して誤解され、「浮気して子どもまで作るなんて、サイテー、嫌い!」と言われたとか。まあ本人にとっては大変なことですが、身から出たサビというか自己責任というか、それとも役者冥利に尽きることなのか、微妙なところですね〜(^o^)/
写真は、私のお気に入りの、東根市神町の菓子店「チェリー」のケーキです。まるで「おちょやん」のように、甘さとほろ苦さが絶妙。