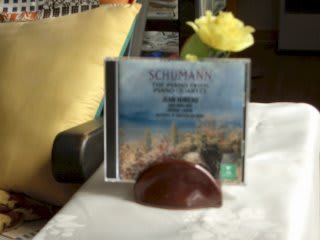今日は、山形県文翔館議場ホールにて、パストラーレ室内合奏団の演奏会に行きました。開場前に到着してしまい、噴水のある広場で待機。ベンチにはすでに数組のカップルが語らい、高校生のお嬢さんが携帯電話をいじっています。夜気は涼しく、18度くらいでしょうか、風はないので上着を着てちょうどよいくらいです。
18時30分に開場、年代は若い人から年配まで幅広く、勤め先から直行したサラリーマンもいれば白髪の老夫婦もいらっしゃるという具合で、やや女性が多いようです。
パストラーレ室内合奏団は、山形交響楽団の奏者を中心とする、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス、クラリネット、ファゴット、そしてホルンの七名からなっています。プログラムは
(1)W.A.モーツァルト、ファゴットとチェロのためのソナタ、変ロ長調、KV.292
(2)M.ハイドン、ヴィオラとチェロとコントラバスのためのディヴェルティメント
(3)ニールセン、甲斐なきセレナーデ
(4)L.V.ベートーヴェン、七重奏曲、変ホ長調、Op.20
今日のお目当ては、もちろんベートーヴェンの七重奏曲ですが、聞いたこともないニールセンの曲も、ちょっと興味があります。
さて、演奏会の開始はプログラムにないバルトークのルーマニア舞曲から。板垣ゆきえさんが進行役をつとめ、ヴァイオリンの中島光之さんが挨拶をします。そして最初の曲目がモーツァルト。ファゴットとチェロの音楽ですが、ファゴットという楽器の音色がこんなに魅力的なものだとは知りませんでした。フルートを吹いていた小学生のときに、ストラヴィンスキーの「春の祭典」のファゴットの出だしを聞いて、ファゴットという楽器を志したという高橋あけみさん、とても素敵な山響の女性ファゴット奏者です。センシティヴで情熱的でよく歌う山響の若いチェリスト・渡邊研多郎さん、通奏低音に終わらず、ファゴットとメロディを交代して、19歳のモーツァルトのメロディを奏でます。
続いてミヒャエル・ハイドンの面白い編成のディヴェルティメントです。山響のヴィオラ奏者・田中知子さんのまじめな演奏ぶりと対照的な真っ赤な衣装がおちゃめでした。それともう一つ、山響コントラバス奏者の柳澤智之さんのニックネームが「ポチ」というのだということを初めて知りました(^_^)/
次にニールセンの「甲斐なきセレナーデ」。面白い曲です。第一次世界大戦の前後、恋しい人の窓辺で、この編成でこの響きでセレナーデを演奏したら、私のような中年が「おっ、いいなぁ」などと顔を出すでしょうが、若い娘さんは顔は出さないかも。確かに「甲斐なきセレナーデ」ですね。
10分の休憩のあと、ベートーヴェンの七重奏曲。大好きな曲の一つで、以前にも記事を書いていますが、実際の演奏を見るのは初めてです。唯一山響団員ではないクラリネットの渡辺純子さんの音色のきれいなこと。山響ホルン奏者・八木健史さんの、思い切りのいいリズム。いやぁ、良かった!第五楽章のチェロの伸びやかで朗々たる歌に、あらためてこの曲の魅力を再確認しました。
弦と管との室内楽というのは、なかなか実演で聞く機会はそう多くありません。地元にオーケストラがあると、こういう機会も生まれるのですね。ありがたいことです。パストラーレ室内合奏団の意欲的な活動に敬意を表するとともに、やはりオーケストラは地域の文化的な財産だと痛感します。
次回はぜひシューベルトの「八重奏曲」を聞いてみたいものです。
18時30分に開場、年代は若い人から年配まで幅広く、勤め先から直行したサラリーマンもいれば白髪の老夫婦もいらっしゃるという具合で、やや女性が多いようです。
パストラーレ室内合奏団は、山形交響楽団の奏者を中心とする、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス、クラリネット、ファゴット、そしてホルンの七名からなっています。プログラムは
(1)W.A.モーツァルト、ファゴットとチェロのためのソナタ、変ロ長調、KV.292
(2)M.ハイドン、ヴィオラとチェロとコントラバスのためのディヴェルティメント
(3)ニールセン、甲斐なきセレナーデ
(4)L.V.ベートーヴェン、七重奏曲、変ホ長調、Op.20
今日のお目当ては、もちろんベートーヴェンの七重奏曲ですが、聞いたこともないニールセンの曲も、ちょっと興味があります。
さて、演奏会の開始はプログラムにないバルトークのルーマニア舞曲から。板垣ゆきえさんが進行役をつとめ、ヴァイオリンの中島光之さんが挨拶をします。そして最初の曲目がモーツァルト。ファゴットとチェロの音楽ですが、ファゴットという楽器の音色がこんなに魅力的なものだとは知りませんでした。フルートを吹いていた小学生のときに、ストラヴィンスキーの「春の祭典」のファゴットの出だしを聞いて、ファゴットという楽器を志したという高橋あけみさん、とても素敵な山響の女性ファゴット奏者です。センシティヴで情熱的でよく歌う山響の若いチェリスト・渡邊研多郎さん、通奏低音に終わらず、ファゴットとメロディを交代して、19歳のモーツァルトのメロディを奏でます。
続いてミヒャエル・ハイドンの面白い編成のディヴェルティメントです。山響のヴィオラ奏者・田中知子さんのまじめな演奏ぶりと対照的な真っ赤な衣装がおちゃめでした。それともう一つ、山響コントラバス奏者の柳澤智之さんのニックネームが「ポチ」というのだということを初めて知りました(^_^)/
次にニールセンの「甲斐なきセレナーデ」。面白い曲です。第一次世界大戦の前後、恋しい人の窓辺で、この編成でこの響きでセレナーデを演奏したら、私のような中年が「おっ、いいなぁ」などと顔を出すでしょうが、若い娘さんは顔は出さないかも。確かに「甲斐なきセレナーデ」ですね。
10分の休憩のあと、ベートーヴェンの七重奏曲。大好きな曲の一つで、以前にも記事を書いていますが、実際の演奏を見るのは初めてです。唯一山響団員ではないクラリネットの渡辺純子さんの音色のきれいなこと。山響ホルン奏者・八木健史さんの、思い切りのいいリズム。いやぁ、良かった!第五楽章のチェロの伸びやかで朗々たる歌に、あらためてこの曲の魅力を再確認しました。
弦と管との室内楽というのは、なかなか実演で聞く機会はそう多くありません。地元にオーケストラがあると、こういう機会も生まれるのですね。ありがたいことです。パストラーレ室内合奏団の意欲的な活動に敬意を表するとともに、やはりオーケストラは地域の文化的な財産だと痛感します。
次回はぜひシューベルトの「八重奏曲」を聞いてみたいものです。