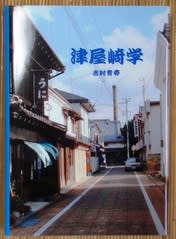写真①:『津屋崎の四季――野鳥と自然のハーモニー』並製本の表紙
=福津市津屋崎の拙宅で、2013年5月10日撮影
津屋崎の自然と野鳥のアルバム
『津屋崎の四季――野鳥と自然のハーモニー』が出来ました
(A6判カラー、194㌻) 吉村青春ブログ「津屋崎センゲン」をもとに書籍化
私の古里・福岡県福津市津屋崎の美しい四季の自然と、あいらしい野鳥の姿を多くの方に知っていただき、愛しんでもらいたい――。そんな想いを託し、吉村青春ブログ「津屋崎センゲン」をもとに書籍化した津屋崎の自然と野鳥のアルバム、『津屋崎の四季――野鳥と自然のハーモニー』(A6判カラー、194㌻)が、平成25年(2013年)5月1日、東京にある発行所(イースト株式会社および欧文印刷株式会社)で出来あがり、宅配便できょう10日、私の手元に届きました=写真①=。
写真180枚に地図、野鳥索引付き
四季に繰り広げられる自然の風物詩と、野鳥が織りなす景観を写真と詩文で描いたアルバム本でもあります。記事は、〈春の章〉・ホオジロから始め、〈夏の章〉・トビや・「恋の浦」に咲くハマゴウの花、〈秋の章〉・マミジロタヒバリ、セグロカモメ、〈冬の章〉・天日干し、古墳群の夕暮れの春夏秋冬の4章に分けて掲載。平成18年から意識的に撮り集めた野鳥をはじめ、郷土の祭りや四季の風景、草花の写真計180枚と地図3枚、野鳥索引付きで分りやすく表現しています。
表紙写真は2006年12月31日午後5時16分、相島(福岡県新宮町)そばの玄界灘に沈む「結びの夕陽」を福津市津屋崎1丁目の津屋崎浜で撮影しました。本書では、「冬の章」161㌻に掲載した「結びの夕陽」で、その年最後の夕陽を見送るイベントとして写真付きで紹介=写真②=。

写真②:表紙(右)写真に使用の夕陽を見送るイベント・「結びの夕陽」を掲載した161㌻(中央)
著書名を『津屋崎の四季』としたのは、玄海国定公園の景勝地で〝九州の鎌倉・江の島〟と謳われる津屋崎の白砂青松の海岸線を中心とした豊かな自然と風物詩を記録したかったからです。サブタイトルに付けた「野鳥と自然のハーモニー」は、四季の野鳥の姿=写真③=が生息環境の自然に彩りと潤いをもたらして、和める津屋崎の四季の魅力を醸し出していると感じたからです。

写真③:「新川」のカワセミ(180㌻)と「津屋崎干潟」で憩うヘラサギ(181㌻)の掲載写真
〈著作津屋崎シリーズ3部作〉の刊行が完結しました
この本には、私が平成18年(2006年)8月から吉村青春ブログ『津屋崎センゲン』に連載中の『津屋崎の四季』、『日記』、『津屋崎の野鳥』、『催事』『詩』などから選んだ写真や記事を収録したほか、平成24年(2012年)2月から始めたfacebook吉村勝利(青春)へのアップ記事・写真などを加えました。私にとっては、平成18年2月に出版した第一詩集『鵲声―津屋崎センゲン』(A6判、175㌻。新風舎文庫刊)=写真④=、同23年2月に刊行した郷土史ガイド本・『津屋崎学――A Quaint Town Tsuyazaki-sengen Guide』(B5判カラー、314㌻。Obunest=オブネスト=刊)=写真⑤=に続く著作〈津屋崎シリーズ〉の第3著書です。
インターネットで書籍化の記事校正を終えて初版を発行しましたが、非売品です。子や孫たちにプレゼントする予定です。

写真④:吉村青春第一詩集『鵲声(じやくせい)-津屋崎センゲン』

写真⑤:『津屋崎学――A Quaint Town Tsuyazaki-sengen Guide』
『津屋崎の四季』に収録した写真は、撮影した月により、「春の章」(3~5月)、「夏の章」(6~8月)、「秋の章」(9~11月)、「冬の章」(12~2月)の順に掲載しています。ただし、最初に掲載した写真に関連する違う時季に撮影した写真は、野鳥のカササギ(8月撮影)に関連して続けて掲載した同じカラス科の仲間・ハシブトガラス、ハシボソガラス、ミヤマガラスを「夏の章」に収めたように、植物(ハマボウの花、並木の黄葉)などでも同じ基準で続けて掲載しました。津屋崎の野鳥索引には、日本で記録された野鳥633種(日本鳥類目録改訂第7版)のうち本誌に写真を掲載した84種を収録しました。
以下、『津屋崎の四季』の目次(概要)を紹介します。
『津屋崎の四季――野鳥と自然のハーモニー』
・はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
目 次
地図・索引
・福岡県福津市と津屋崎の位置図
・津屋崎の探鳥地位置図
・津屋崎の野鳥索引
春の章
・ホオジロ
(以下略)
・ツバメ
夏の章
・トビ
(以下略)
・「恋の浦」に咲くハマゴウの花
秋の章
・マミジロタヒバリ
(以下略)
・セグロカモメ
冬の章
・天日干し
(以下略)
・古墳群の夕暮れ
手引き
・参考文献
・著者略歴
あとがき