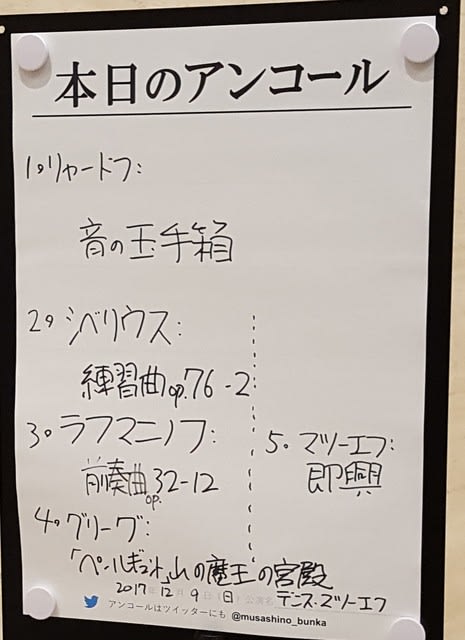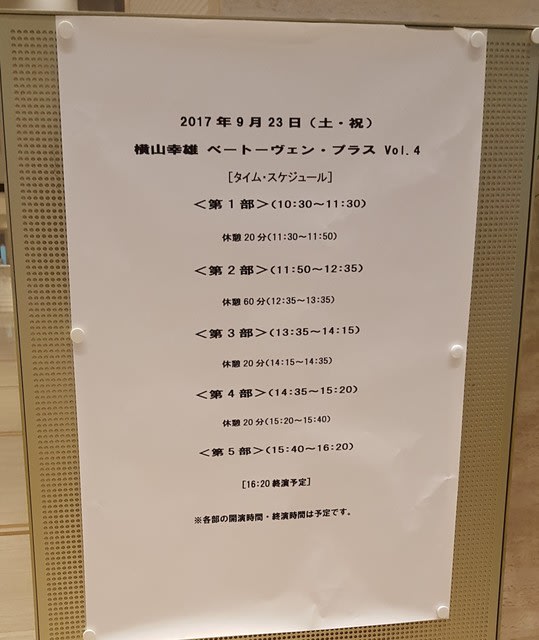2018年1月21日(日) 4:00-5:30pm トッパンホール
瀬川裕美子 ピアノ リサイタル vol.6
〈ドゥルカマラ島~時間の泡は如何に?d→d~〉
J.S.バッハ フーガの技法 BWV1080より I 3′-
ブーレーズ ピアノ・ソナタ第3番より トロープ 5′
メシアン 《4つのリズムの練習曲》より〈火の島 第1〉〈火の島 第2〉 2-4′
ブーレーズ ピアノ・ソナタ第3番より コンステラシオン―ミロワール 9′
鈴木治行 Lap behind(委嘱作品) 8′
Int
モーツァルト 幻想曲 ハ短調 K396(断片) 3′
クセナキス ヘルマ 7′
武満 徹 雨の樹 素描 3′
シューマン 暁の歌 Op.133 12′
武満 徹 雨の樹 素描II―オリヴィエ・メシアンの追憶に― 3′
(encore)
シューマン 暁の歌 Op.133 第1曲にヘルダーリンの「春」の詩を付けた弾き歌い 3′
(ハインツ・ホリガー「暁の歌」より冒頭の合唱曲の瀬川による編曲版)
ピアノ、瀬川裕美子
●
年初から難しいプログラムにあたってしまった。ただいつも通り聴けばいいのだろうが、この25ページにおよぶ詳細なプログラム冊子をみたらそうもいかない。もっともこれをリサイタルの前時間に全部読むのは無理。前もって配ってくれれば、という思いの方が強い。
この日のリサイタルの肝は次のあたりかな。
****
ドゥルカマラ島
時間の泡は如何に?d→d
パウル・クレーのドゥルカマラ島の中央の白い瀕死の顔は、ひっくり返すとd。西洋音楽史の中で長い間、記譜されてきた賛歌ともレクイエムともなったd(ニ長調/ニ短調)。
本日のプログラムの道標となるd。
****
ということで、こうなると、やっぱり、各ピースを皮膚感覚と耳感覚で聴いていくしかない。
作品の断片のようなものが短く奏でられ過ぎていく。断片の集まり。
総じて速め、峻烈で柔らかい音。用意周到な作戦のもと絶妙な仕上げ。それらが見事な果実となった。練り上げられたものですね。
休憩前の最後の曲は委嘱作品で鈴木のLap behind(周回遅れ)、作品の種明かし的解説は冊子に記載されている。むしろ、音の粒が多い曲で泡のモードを最も感じた。
ブレーズ、メシアンの前半、シューマン、タケミツの後半。それぞれ響きの世界に入り込む。暁の歌も企画に合っている雰囲気。やはり、その企画のウエイトにこだわりを感じさせるものだったかな。
リサイタル自体は休憩入れてもかなり短い。一人で全てプレイするのでいたしかたないというところもあるが、作品に身を任せて弾くピースがひとつふたつあってもよかったのではないか。もっともそういう作品もあったのだが、スポットライトの当て方が一方向から、そのような要旨のリサイタルという側面があるのでどうという話しでもない。
このプログラム冊子は、その場のリサイタルとは別に、読んでいて音のイメージが欲しくなるところがあって、この日のプログラム通りCDをつないで聴くのも一興。
アンコールは暁の歌の1曲目に歌詞を付けて、弾き歌いした。
良かったですね。ここに、思いがありそうな気もする。
興味深いリサイタル、ありがとうございました。
おわり