
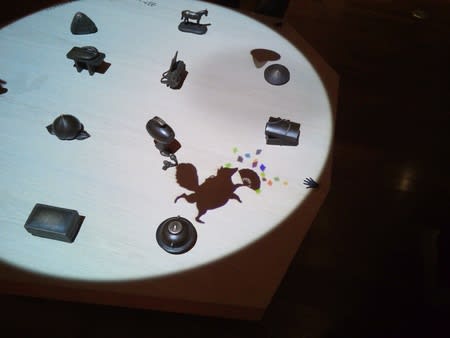
連休に、遠野に行ってきました。
実は先月も夫と二人で訪れたのですが、そのときは観光地なのに閑散としていて。雪はちらつく、雹はふる。
でも、まだ利用共通券も残っているし(3ヶ月有効。五カ所回れます)、子どもたちを連れて行こう、と思ったのです。
まずは伊藤家さんでお昼を食べて、隣のとおの物語の館へ。タッチすると影が浮き上がる仕掛けに喜ぶ子どもたち。(写真はぶんぶく茶釜)
物語を作るスライドコーナーがあるんですが、「桃婆さん」は強烈でした……。
語り部の方のビデオがあり、「寒戸の婆」を聞き比べてみました。やはり話者によって同じ内容でも表現が違うんですよね。聞いてみて驚いたのは、娘が姿を消して再度現れるまでに三十年しか経っていないこと。(片方の語り部さんはその部分をぼかしていましたが)
実際のところ、「寒戸の婆」は四十代なのでしょうか。当時の平均年齢からすると妥当な線なの?
そういえば、以前道の駅で「寒戸のババロア」というお菓子を売っていた印象があるんですが、今回はありませんでした。
続いて遠野ふるさと村へ。野の花が咲き乱れていて、綺麗です。
軒下にさいかちの実が干してあったり、風車の制作体験があったり。ポニーにも乗れました。「軍師勘兵衛」や「愛しの座敷わらし」のロケに使われた南部曲がり家があります。
先月行ってから、佐々木喜善の「遠野奇談」(河出書房新社)を読んでいました。もう五年くらい前に買ったものなんですが。
柳田の「遠野物語」も何回か読んでいるので、佐々木喜善の語りと違う部分が目につきます。
例えば「マヨイガ」の話。迷い込んで何も持ち出さなかった男が、もう一度その場所を探しても見つからないところで終わります。ただただ桐の花の美しさが印象に残る。だから、その後川上から椀が流れてくるのは柳田の創作なんでしょうね。
遠野の山で狩りをする男たちの姿も描かれます。狼のこと。猪や鹿。雉寄せ。
この中で「夜鴨打ちに」行って嘲笑される場面があります。なぜか分からなくて調べてみたら、法令で禁じられていたことなのですね。
喜善は語り口がよく、物語の起伏を意識した表現をしています。柳田たちが彼を評して「日本のグリム」としたのもむべなるかな、という感じです。
当時の背景として、読者にとっても自明のことなんでしょう。でも、それから百年経って、わたしにはわからない部分もありました。
「二面独眼一本足の怪物(二面大黒)」が「三面独眼一本足の怪物(三面大黒)」を倒してほしいと頼みにくる話。面というから、顔の数ですね。その独眼はどこにあるのか? そして、「大黒」にはどんな意味があるのか。それから、汽車に腰を抜かしたお婆さんの話がなぜ「ロマンス」なのか。
喜善にとっては当たり前のこと。実にさらっと語るのです。
彼が地域の伝承に興味を持っていることは、戦争時期に神仏までも加勢しに行った噂を集めていることや、郵便配達人のインタビューから怪異を引き出していることからも伝わってきます。
仙台で無実の罪を負わされた配達人が、家族を惨殺してしまう話は胸が痛くなりました。
喜善の側に息づく、真実とも幻ともいえる物語たち。また違う角度から、「遠野物語」が見つめられそうです。










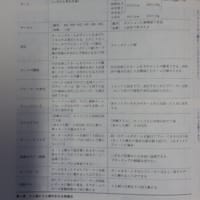

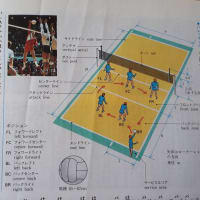

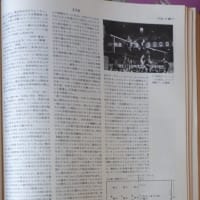

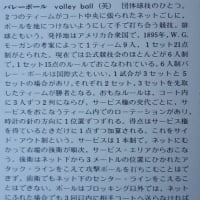

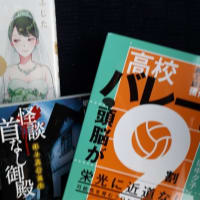
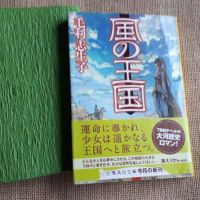
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます