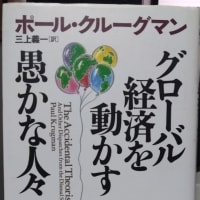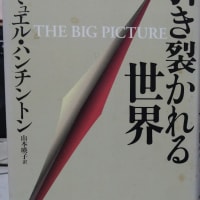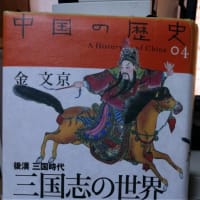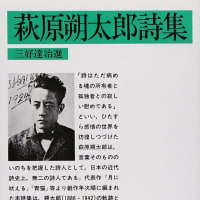経済学の専門家ではない私ではあっても、何が正しいかは見当がつく。宇沢弘文の「社会的共通資本の時代」という文章を読み返して、その主張に共感を覚えた。もう20年も前に日本経済新聞社が出版した『資本主義の未来を問う』のなかに収録されていた。冒頭で資本主義と社会主義の両方を批判し「新しい21世紀の展望を開こうとするとき、もっとも中心的な役割を果たすのが、制度主義の考え方である」と書いている。ジョン・スチュアート・ミルが『経済学原理』のなかで言及した、自由が保障され、人間的尊厳と職業倫理が守られ、安定的調和的な経済発展が可能な経済制度が存在するかどうかの設問に対して、「ソースティ・ヴェブレンのいう制度主義の考え方がもっとも適切にその基本的性格を表している」と断言した。宇沢が強調したかったのは「一つの普遍的な、統一された原理から論理的に演繹されたものではなく、それぞれの国ないしは地域のもつ歴史的、社会的、倫理的、文化的、そして自然的な諸条件が互いに交錯してつくりだされる」との見方だ。とくに宇沢は「さまざまな社会的共通資本と、それぞれの共通資本を管理する社会組織のあり方」にこだわった。社会的共通資本の構成要素は、水や空気などの自然的環境、道路や上下水道などの社会的インフラストラクチュアー、教育、医療、金融などの制度資本である。社会的共通資本は専門家によって運営されるが、官僚的な基準や市場的基準にのみもとづいて行われるのではない。政府の役割は社会的共通資本の管理運営が適切かどうかを監理し、財政上のバランスを保てるようにすることだ。市場原理一辺倒でも、計画経済一辺倒ではない第三の道を私たちは目指すべきなのだろう。新自由主義に抗するためにも。
←新自由主義に屈服すべきではないと思う方はクリックを