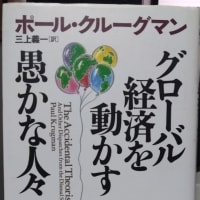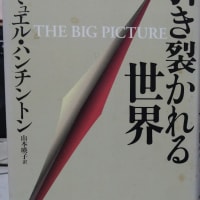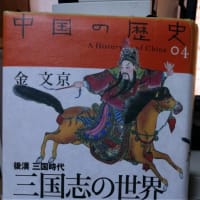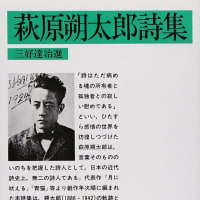どうせ3人に1人は癌で死ぬわけだから、その確率がいくらか高くなっても、そんなことはたいしたことがない。それを公然と口にする科学者もいるので、ここは理論武装しなくてはと思って、色々と本を漁ってみた。そこで参考になったのは、武谷三男編の『死の灰』(岩波新書)であった。昭和29年3月1日にビキニ環礁で行われた米国の水爆実験で、第5福竜丸が死の灰を浴びたので、当時の第一線の科学者が、様々な立場から死の灰について論じたのだった。当初は命には別状ないとか、安静にしていれば2ヶ月で治るといった診断が下された。ところがそれは誤診であったことが、すぐに判明した。東大病院に入院していた乗組員の白血球が減少し、これは大変だということになった。とくに、大阪市立医大助教授であった西脇安博士は、その本のために執筆した「放射能はどのように危険かー放射線生物物理学的立場からー」というなかで、「放射線の遺伝学的な影響に関する限りどの程度まで絶対に安全であるという下の限界がまだはっきりわかっていないこと、言い換えれば可成り微弱な放射線といえども、遺伝的な変化が起こらないとは現在のところ言い切れないこと等のために、放射線障害のなかでももっともやっかいなものです」と書いている。国が年間1ミリシーベルト以内というのにこだわってきたのは、そうした理由があるからだ。そのときから今まで、日本の放射線医学は、少しも進歩していないのであり、それだけに警戒を怠ることはできないのである。
ブログ「草莽隊日記」の執筆者、峰たけしの『先人に学ぶ憂国の言葉』 (長崎書店・神田神保町1-18-1) が全国の書店で発売中。