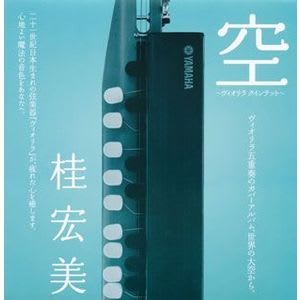きょうは娘の卒業式でした。
末っ子。
これで親の役割は終わった。。と感じた日でした。
卒業生代表謝辞では「患者様の立場で・・」
しかし看護学科長は「患者さんの立場で・・」と訓辞。
妙なところでこだわっている私でした(笑)
これからの医療体制、しっかり担ってほしいと思います。
http://www.youtube.com/watch?v=QJs_hxmiKCw
末っ子。
これで親の役割は終わった。。と感じた日でした。
卒業生代表謝辞では「患者様の立場で・・」
しかし看護学科長は「患者さんの立場で・・」と訓辞。
妙なところでこだわっている私でした(笑)
これからの医療体制、しっかり担ってほしいと思います。
http://www.youtube.com/watch?v=QJs_hxmiKCw