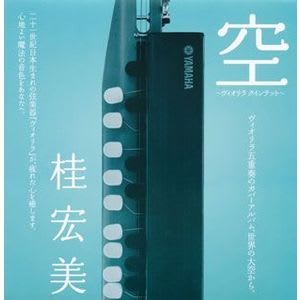「やめたら1万円、批判殺到、見送り」(読売新聞10/14夕刊)
茶髪とそうでない学生との褒賞金の扱いをどうする、金で釣るのは良くない、などの批判意見が大学に殺到したといいます。
「批判覚悟」と言っていた理事長兼学長の小泉健さん、あのガッツはどこ行った!どこも独裁者ほど..。
ピアスは男子は禁止するが、女子はファッションとして定着しているから左右耳たぶ1カ所は認める、と変更に。
結局、世論の前に屈した形です。
残念なのは当の秋田経法大生の声が、さいごまで聞こえて来なかったこと。
茶髪とそうでない学生との褒賞金の扱いをどうする、金で釣るのは良くない、などの批判意見が大学に殺到したといいます。
「批判覚悟」と言っていた理事長兼学長の小泉健さん、あのガッツはどこ行った!どこも独裁者ほど..。
ピアスは男子は禁止するが、女子はファッションとして定着しているから左右耳たぶ1カ所は認める、と変更に。
結局、世論の前に屈した形です。
残念なのは当の秋田経法大生の声が、さいごまで聞こえて来なかったこと。