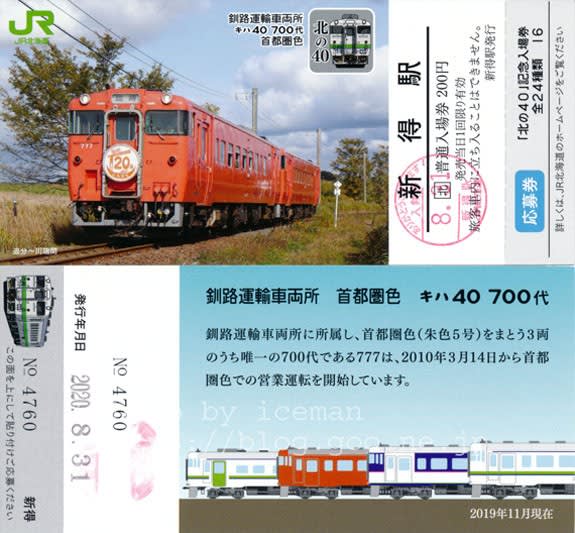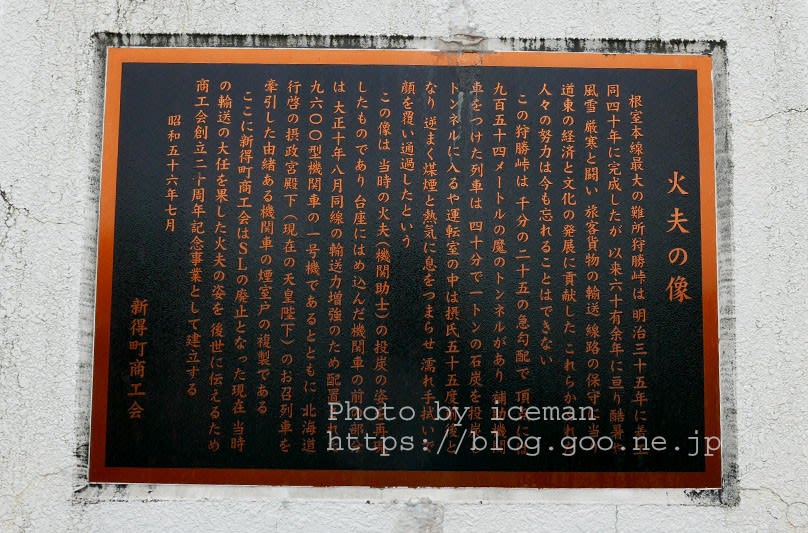ハチ君の初めての車検がやってきました。
もうあれから3年の歳月が過ぎたのかと…
マツダ Cx-8 レビュー 購入編 1月7日 2019年 はこちらから。
購入した当初、家内が「ハチ君のシルバーって青っぽいね」と言っていました。
「そうかなぁ?」などと思っていましたが、こうして見ると確かに「青っぽい」ですね。
「目つき悪い…」とも言われます。

*以下の写真はマツダさんがピット作業を撮影してくださいました。
こちらは…多分ブレーキ・フルードの交換・エア抜き作業だと思います。

う~ん…こちらは何でしょう?
オイルパンの横辺りですが…ドレイン・コックを外しているようには見えないし…
なんだか分かりません。

こちらは…オイル抜きですね。

そして、オイルを補充しているところ…

こちらは…セカンド・シートのリクライニング不良でシートをアッセンブル交換しているところです。
ハチ君はほとんど私一人で使っているので、セカンド・シート サード・シートともにいつも畳んだままです。

年に一度あるか無いかの頻度でセカンド・シートを使うことがありましたが、リクライニングのレバーが動かなくてシートが畳めないことがありました。

レバーに繋がるワイヤーが伸びきっていたとのことでしたが…
ほとんど触ったことの無いレバーのワイヤーが伸びきるはずはなく…おそらく初期不良だったのではと思っています。
そう言えば…作業終了後、自身で動作確認を未だにしていません。
セカンド、サード・シートの存在自体、ほとんど興味が無いみたいです。
そう言えば…八つ当たりみたいですが、ドライバーズ・シートのセフティー・ピローは相変わらず気にくわなくて仕方ありません。
渋滞などで暇を持て余していると他にやることないので特に気に障ります。
3年たっても慣れません。

タイヤの山は 5~6分山程度でしょうか。
出来れば車検の際に、「レグノ」に交換したかったのですが、お金の都合で見合わせました。
本年はハチ君の他に ロードス君 9月車検 カレラ君 11月車検 が控えているのでお金が忙しいのです。
タイヤどころではない…というのが本音です。

千葉のガレージの ロードス君、カレラ君、SL君 はこの「Dr. Charger」(手前の箱みたいなもの)をそれぞれに接続してありますので、バッテリー・コンディションは上々です。
ハチ君は東京自宅の屋外駐車場なので、デバイスを繋ぎっぱなしに出来ないので、たまにこうして半日くらいリフレッシュしてあげます。

今回の整備明細書です。
上の赤矢印 「左・リヤシート Assy 取り替え」となっています。
下の赤矢印部、トータルの費用です。
¥137,166 となっています。
もちろん、支払いは大変なのですが予想していたより低額で済んでホッとしています。

支払い総額の中に「パック de メンテ」というパッケージ・プランが含まれています。
このチャートを見ても何がなんだか?とても分かりにくいので、マツダさんのホームページのチャート図を載せておきます。

こちらが「パック de メンテ」のチャート図です。
お願いしたのは、前車検付き18カ月コース というパッケージです。
今回の車検を含む、次回の車検前までの法定点検、オイル交換4回 オイルフィルター交換2回 ブレーキ・フルード交換1回 がセットになったものです。
パック料金は ¥96,800 となります。
お得かどうかは微妙ですが、ハチ君は普段使いのクルマで、しかも北海道や九州などの奥地に出掛けます。
出先でトラブルになるとかなり困ったことになりますので、点検・整備は欠かせません。
千葉のガレージの趣味のクルマたちとは用途が全く違います。
安心して出掛け無事に戻るために出来る限り万全の整備をするのは当然ですね。
そう考えるとこのパッケージは「安心感」も含めて「お安い」のかも知れません。
もうあれから3年の歳月が過ぎたのかと…
マツダ Cx-8 レビュー 購入編 1月7日 2019年 はこちらから。
購入した当初、家内が「ハチ君のシルバーって青っぽいね」と言っていました。
「そうかなぁ?」などと思っていましたが、こうして見ると確かに「青っぽい」ですね。
「目つき悪い…」とも言われます。

*以下の写真はマツダさんがピット作業を撮影してくださいました。
こちらは…多分ブレーキ・フルードの交換・エア抜き作業だと思います。

う~ん…こちらは何でしょう?
オイルパンの横辺りですが…ドレイン・コックを外しているようには見えないし…
なんだか分かりません。

こちらは…オイル抜きですね。

そして、オイルを補充しているところ…

こちらは…セカンド・シートのリクライニング不良でシートをアッセンブル交換しているところです。
ハチ君はほとんど私一人で使っているので、セカンド・シート サード・シートともにいつも畳んだままです。

年に一度あるか無いかの頻度でセカンド・シートを使うことがありましたが、リクライニングのレバーが動かなくてシートが畳めないことがありました。

レバーに繋がるワイヤーが伸びきっていたとのことでしたが…
ほとんど触ったことの無いレバーのワイヤーが伸びきるはずはなく…おそらく初期不良だったのではと思っています。
そう言えば…作業終了後、自身で動作確認を未だにしていません。
セカンド、サード・シートの存在自体、ほとんど興味が無いみたいです。
そう言えば…八つ当たりみたいですが、ドライバーズ・シートのセフティー・ピローは相変わらず気にくわなくて仕方ありません。
渋滞などで暇を持て余していると他にやることないので特に気に障ります。
3年たっても慣れません。

タイヤの山は 5~6分山程度でしょうか。
出来れば車検の際に、「レグノ」に交換したかったのですが、お金の都合で見合わせました。
本年はハチ君の他に ロードス君 9月車検 カレラ君 11月車検 が控えているのでお金が忙しいのです。
タイヤどころではない…というのが本音です。

千葉のガレージの ロードス君、カレラ君、SL君 はこの「Dr. Charger」(手前の箱みたいなもの)をそれぞれに接続してありますので、バッテリー・コンディションは上々です。
ハチ君は東京自宅の屋外駐車場なので、デバイスを繋ぎっぱなしに出来ないので、たまにこうして半日くらいリフレッシュしてあげます。

今回の整備明細書です。
上の赤矢印 「左・リヤシート Assy 取り替え」となっています。
下の赤矢印部、トータルの費用です。
¥137,166 となっています。
もちろん、支払いは大変なのですが予想していたより低額で済んでホッとしています。

支払い総額の中に「パック de メンテ」というパッケージ・プランが含まれています。
このチャートを見ても何がなんだか?とても分かりにくいので、マツダさんのホームページのチャート図を載せておきます。

こちらが「パック de メンテ」のチャート図です。
お願いしたのは、前車検付き18カ月コース というパッケージです。
今回の車検を含む、次回の車検前までの法定点検、オイル交換4回 オイルフィルター交換2回 ブレーキ・フルード交換1回 がセットになったものです。
パック料金は ¥96,800 となります。
お得かどうかは微妙ですが、ハチ君は普段使いのクルマで、しかも北海道や九州などの奥地に出掛けます。
出先でトラブルになるとかなり困ったことになりますので、点検・整備は欠かせません。
千葉のガレージの趣味のクルマたちとは用途が全く違います。
安心して出掛け無事に戻るために出来る限り万全の整備をするのは当然ですね。
そう考えるとこのパッケージは「安心感」も含めて「お安い」のかも知れません。