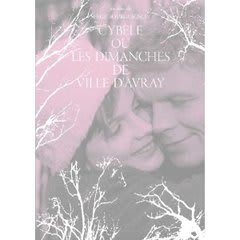
『シベールの日曜日』 セルジュ・ブールギニヨン監督 ☆☆☆☆★
日本版DVDで鑑賞。1962年のモノクロ映画である。
フランスの田舎町を舞台とした静謐な、崇高さすら漂う悲劇。記憶喪失に苦しむ社会的無能力者ピエールと親に捨てられた12歳の少女フランソワーズが知り合い、やがて心を通わせ会い、毎週日曜日の逢瀬を続けるが、それを異常視する周囲の人々の偏見がやがて悲劇を生む。このストーリーとフランソワーズを演じたパトリシア・ゴッジの可愛らしさから、かつてはロリコンものみたいな扱いをされたこともあったらしいが、そんなレベルの作品ではないことは一見して明らかだ。
まず、モノクロ映像の禁欲的な美しさに言葉を失う。冬の湖、木立、郊外の田舎町の風景、控えめに装飾された屋内。どのシーンでも厳格なまでに計算し尽された構図が瞑想的な空気を醸し出す。音楽はアルビニーノのアダージョやバッハが一部使われているが、ほとんどの場面ではきわめて控えめで、聴こえるか聴こえないかぐらいのベースの音だったり、シャーマニズムの儀式のような銅鑼の音だったりする。少なくともストーリーから想像されるような甘い感傷的な音ではなく、むしろ厳しい、ストイックな音だ。それが登場人物たちのささやくような話し声とあいまって、この映画の神秘性をますます深めている。
それから特筆すべきは、映画全体をモザイクのように覆う宗教的なモチーフ。この映画では常にキリスト教的なるものと異教的なるものがせめぎ合っている。ヒンズー教やアフリカの魔術、儀式に使うナイフ、霊能力者といったアイテムがエピソードの中に埋め込まれているだけでなく、たとえば少女は学校で本名が「非キリスト教的だから」という理由でフランソワーズという別の名前を与えられている。彼女の真実の名前は映画の後半にならないと明かされないが、その名前はクリスマスのプレゼントとして少女からピエールへと与えられる。シベールというその名は古代ギリシャのもの(つまりキリスト教以前のもの)で、自然を司る女神を意味する。
それから終盤、ピエールは少女のために教会の風見鶏を盗むが、風見鶏は魔除けであるらしい。彼はミサが行われている教会に忍び込んで「魔除け」を盗み出すのである。またピエールの友人であり、彼と少女の数少ない理解者である彫刻家のカルロスがチベットに言及する場面もある。そしてこれらのせめぎ合いにおいて、映画の作者は明らかに異教的なるもの、非キリスト教的なるものの側に身を置いている。
ピエールと少女シベール=フランソワーズとの交流も、ただ孤独な魂が惹かれあったではすまない重層性を持っている。映画冒頭の戦争の場面で、ピエールはかつて戦闘機に乗り、子供を殺したかあるいは殺そうとしたことが暗示される。その直後ピエールは墜落して記憶喪失になるが、この過去のいきさつは最初は隠されており、観客には徐々に、映画の進行とともにきわめて慎重に開示されていく。さらにもう一つの仕掛けは、ピエールは社会的無能力者であるけれども果たして正気なのか、それともどこかが微妙に狂っているのか、観客にはよく分からないということだ。従って贖罪のためにピエールが再び子供を殺すかも知れないぞ、というマドレーヌの同僚の言葉がまったく見当違いなのかどうか、私たちは一抹の不安を拭いきれない。あるいはそれが見当違いであったとしても、ピエールはなぜ少女を愛するようになったのだろうか。失われた記憶の影響なのか。それは贖罪なのか。日曜日に少女に会いにいけずマドレーヌの前で錯乱したピエールは「あの子は死んだのか? 私が殺したのか?」とうわごとのように繰り返していたという。
少女の前でピエールがナイフを振りかざしているように見える場面もあるし、死体のように手足をぐったりさせた少女をピエールが木立の中を運んでいく場面もある。どちらも二人の遊びなのだけれども、きわめて強く死を連想させるシーンである。また二人が入ったレストランでは、フランソワーズが燃え盛る暖炉の炎の前で、異教の儀式に使うナイフに頬擦りしながら喋る場面もある。この時の少女は、まるで異教の儀式を司る巫女のようである。
こうした重層的なイメージの重ね合わせと慎重に作り出された多義性が、二人の関係をロマンティック、あるいは単純に悲しいというよりも、むしろ神秘的で不可解なものにしている。そして映画全体を通してあの結末にたどり着いた時、オーディエンスはそこにほとんど荘厳な畏怖を、あるいは厳粛な儀式性すら感じるかも知れない。
また一見して明らかなように、この映画には意図的に多くの反社会的な要素が盛り込まれている。非キリスト教的なるもの、社会的無能力者、精神病、親に捨てられ名前まで剥奪された少女、年齢を超越した愛情、社会からの孤立。一方でマドレーヌがピエールに注ぐ際限のない無償の愛には、現実離れした神話性が感じられる。これらの要素が渾然一体となって、この映画独特の空気感を作り出しているのである。
ストーリーテリングで見せる映画ではないが、独特の審美性が凝り固まったようなフィルムだった。こういう雰囲気が好きな人にはたまらない、そうでない人には理解しがたい映画かも知れないな、これは。
日本版DVDで鑑賞。1962年のモノクロ映画である。
フランスの田舎町を舞台とした静謐な、崇高さすら漂う悲劇。記憶喪失に苦しむ社会的無能力者ピエールと親に捨てられた12歳の少女フランソワーズが知り合い、やがて心を通わせ会い、毎週日曜日の逢瀬を続けるが、それを異常視する周囲の人々の偏見がやがて悲劇を生む。このストーリーとフランソワーズを演じたパトリシア・ゴッジの可愛らしさから、かつてはロリコンものみたいな扱いをされたこともあったらしいが、そんなレベルの作品ではないことは一見して明らかだ。
まず、モノクロ映像の禁欲的な美しさに言葉を失う。冬の湖、木立、郊外の田舎町の風景、控えめに装飾された屋内。どのシーンでも厳格なまでに計算し尽された構図が瞑想的な空気を醸し出す。音楽はアルビニーノのアダージョやバッハが一部使われているが、ほとんどの場面ではきわめて控えめで、聴こえるか聴こえないかぐらいのベースの音だったり、シャーマニズムの儀式のような銅鑼の音だったりする。少なくともストーリーから想像されるような甘い感傷的な音ではなく、むしろ厳しい、ストイックな音だ。それが登場人物たちのささやくような話し声とあいまって、この映画の神秘性をますます深めている。
それから特筆すべきは、映画全体をモザイクのように覆う宗教的なモチーフ。この映画では常にキリスト教的なるものと異教的なるものがせめぎ合っている。ヒンズー教やアフリカの魔術、儀式に使うナイフ、霊能力者といったアイテムがエピソードの中に埋め込まれているだけでなく、たとえば少女は学校で本名が「非キリスト教的だから」という理由でフランソワーズという別の名前を与えられている。彼女の真実の名前は映画の後半にならないと明かされないが、その名前はクリスマスのプレゼントとして少女からピエールへと与えられる。シベールというその名は古代ギリシャのもの(つまりキリスト教以前のもの)で、自然を司る女神を意味する。
それから終盤、ピエールは少女のために教会の風見鶏を盗むが、風見鶏は魔除けであるらしい。彼はミサが行われている教会に忍び込んで「魔除け」を盗み出すのである。またピエールの友人であり、彼と少女の数少ない理解者である彫刻家のカルロスがチベットに言及する場面もある。そしてこれらのせめぎ合いにおいて、映画の作者は明らかに異教的なるもの、非キリスト教的なるものの側に身を置いている。
ピエールと少女シベール=フランソワーズとの交流も、ただ孤独な魂が惹かれあったではすまない重層性を持っている。映画冒頭の戦争の場面で、ピエールはかつて戦闘機に乗り、子供を殺したかあるいは殺そうとしたことが暗示される。その直後ピエールは墜落して記憶喪失になるが、この過去のいきさつは最初は隠されており、観客には徐々に、映画の進行とともにきわめて慎重に開示されていく。さらにもう一つの仕掛けは、ピエールは社会的無能力者であるけれども果たして正気なのか、それともどこかが微妙に狂っているのか、観客にはよく分からないということだ。従って贖罪のためにピエールが再び子供を殺すかも知れないぞ、というマドレーヌの同僚の言葉がまったく見当違いなのかどうか、私たちは一抹の不安を拭いきれない。あるいはそれが見当違いであったとしても、ピエールはなぜ少女を愛するようになったのだろうか。失われた記憶の影響なのか。それは贖罪なのか。日曜日に少女に会いにいけずマドレーヌの前で錯乱したピエールは「あの子は死んだのか? 私が殺したのか?」とうわごとのように繰り返していたという。
少女の前でピエールがナイフを振りかざしているように見える場面もあるし、死体のように手足をぐったりさせた少女をピエールが木立の中を運んでいく場面もある。どちらも二人の遊びなのだけれども、きわめて強く死を連想させるシーンである。また二人が入ったレストランでは、フランソワーズが燃え盛る暖炉の炎の前で、異教の儀式に使うナイフに頬擦りしながら喋る場面もある。この時の少女は、まるで異教の儀式を司る巫女のようである。
こうした重層的なイメージの重ね合わせと慎重に作り出された多義性が、二人の関係をロマンティック、あるいは単純に悲しいというよりも、むしろ神秘的で不可解なものにしている。そして映画全体を通してあの結末にたどり着いた時、オーディエンスはそこにほとんど荘厳な畏怖を、あるいは厳粛な儀式性すら感じるかも知れない。
また一見して明らかなように、この映画には意図的に多くの反社会的な要素が盛り込まれている。非キリスト教的なるもの、社会的無能力者、精神病、親に捨てられ名前まで剥奪された少女、年齢を超越した愛情、社会からの孤立。一方でマドレーヌがピエールに注ぐ際限のない無償の愛には、現実離れした神話性が感じられる。これらの要素が渾然一体となって、この映画独特の空気感を作り出しているのである。
ストーリーテリングで見せる映画ではないが、独特の審美性が凝り固まったようなフィルムだった。こういう雰囲気が好きな人にはたまらない、そうでない人には理解しがたい映画かも知れないな、これは。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます