座間市の県立公園。谷戸山公園は高低差の大きい公園です。里山・湿生生態園・雑木林・そしてわきみずの谷。昨日に引き続きわきみずの谷で咲く春の花と鳥とカエルを見物しました。
トップ画像はニリンソウ。そこに毛虫?幼虫を見つけて撮影。確か二十四節気の啓蟄って3月8日前後だったよね。しばらく昆虫観察できてなかったけども。春の訪れを知り土から這い出した虫たちを探し歩くのも楽しそう。

黄色いのはリュウキンカ?かな??

そしてニリンソウの大群落。いや〜。今咲いてるのは木道から遠くてね。花の形もわかりづらい遠さです。ま。リピート訪問しなさいってことね。

え〜とね。コロコロと鳴き声が聞こえてたので、何の生き物かな??と思ってたのですが、正体はカエルでした。繁殖時期らしく、わきみずの谷には小さな池が数個ありまして。一番小さな池が大人気。あっちでもこっちでもカエル達が大騒ぎです。ダルマカエル?いや、ヒキガエルだよね。随分大きいねえ。もう少し近づきたいところですがね。実はニリンソウを楽しみにしてる人が多いようです。そして野鳥観察の人。双眼鏡と大きなレンズ付きのカメラを構えてます。ここで目立つ動きは出来ません。ならば観察じゃ。
カメラレンズの向く方を追いかけると?胴体がオレンジ。少し長めの尾っぽと羽の一部だけに白いポイントがある野鳥が枝と地面を行ったりきたり。私のしょぼい携帯では写せるはずもなく。しばらく野鳥観察を楽しみました。

上の画像を左右に横切る水路。そこにつくしを複数発見。
つくし:スギナ(杉菜)はシダ植物門トクサ綱トクサ目トクサ科トクサ属の植物。日本に生育するトクサ類では最も小柄である。春先に出る胞子茎をツクシ(土筆)とよぶ。

去年のキノコの名残です。立派な群落だねえ。
実はわきみずの谷の端に、野鳥観察小屋がある。普段ここに人がいるのを見たことないのですが。大人気です。ってか数名のカメラを抱えた方が小屋の壁に開けられた窓から向こう側にいる野鳥の姿を追いかけてます。まだ若芽。見通しがいい。野鳥観察に最適なシーズンな模様です。移動。

上の画像奥に映り込んでるのが野鳥観察小屋。それよりも大木が切り倒されてます。ここでは去年カブトムシを見かけたのですよ。カブトムシやクワガタを去年観察した木は、冬の間に次々と姿を消してます。やっぱさ、去年の夏にカブトムシやカナブンに人気だった木はキクイ虫と闘って樹液を出してたんだなあ。で、結局戦いに負けて枯死した木を倒伏回避のため、あちこちの公園で処分してるのだ。む、虚しいぜ。

あ。またカンスゲが花芽を伸ばし咲かせている。

タチツボスミレ。

ここでも枯死した木を切ったようです。む〜ん。枯死した木だけでなく、周囲にあった植物も大きく損傷してるなあ。実は斜面を真横に散策路が作られてまして。斜面の上の木を切り倒し、切り倒した木の枝や主幹などは散策路の低い方に並べられている。大きな木が1本林から消えるだけで環境は破壊される。大変なことだ。
散策路は突き当たり。左へ進めば水鳥のへ。右へ進めば伝説の丘へ。今日は右へ行きましょう。
うっ。上り坂〜〜。マスクと花粉症で詰まった鼻での呼吸が辛い。き、休憩する。
伝説の丘に上がるのを諦めた。どうせ今の季節とりたてて見たいものもない。去年の秋、クコの花と実を観察した道を進む。

ナナホシテントウとハコベの花を見つけた。

里山体験館が見える。田んぼは今どうなってるかな?行ってみよう。

な、謎!白いのは花でなく。ボワボワしてる奴は去年の種が残ってるやつ。弾けて種を飛ばし切ったのは星か手裏剣みたいになってる。花はどんな形だったのかな?ってか品種特定出来るかな?後で調べてみよう。

これは!カラスのエンドウだっけ?ありふれた雑草だけど、3月9日にもう咲いてるとは!!ガッツ溢れる植物だったのね。びっくり〜。
ヤハズエンドウ(矢筈豌豆):ソラマメ属の越年草。ヤハズエンドウが標準的に用いらる和名だが、カラスノエンドウ(烏野豌豆)という名が一般には定着している。花期:3−6月。
原産地はオリエントから地中海にかけての地方。古代の麦作農耕の開始期にはエンドウなどと同様に栽培されて作物として利用されていた。今では栽培植物としての利用はほぼ断絶して雑草とみなされている。

うん!この黄色い花、他の草が消えた1月でも元気に咲いてた奴。アスファルトの隙間から。ブロック塀の隙間から伸びてなんとしてでも花をつける!という強い意志を感じる植物です。何て名前なんだろか?後で調べよう。
調べた!あまりにありふれた雑草で、かえって探すのが大変だった。
ノゲシ(野芥子):キク科ノゲシ属の植物。
和名に「ケシ」がつくが、ケシ(ケシ科)と葉が似ているだけで分類上は全く別系統。
日本各地の道端や畑に自生する。日本には史前帰化植物として入ってきたものと思われる。花期:春から秋で黄色のタンポポのような花が咲く。
坂道は終わり、一旦公園の外へ。改めて長屋門から入る。







































 2021/2/10撮影。花畑のボリュームが違うよね。
2021/2/10撮影。花畑のボリュームが違うよね。



















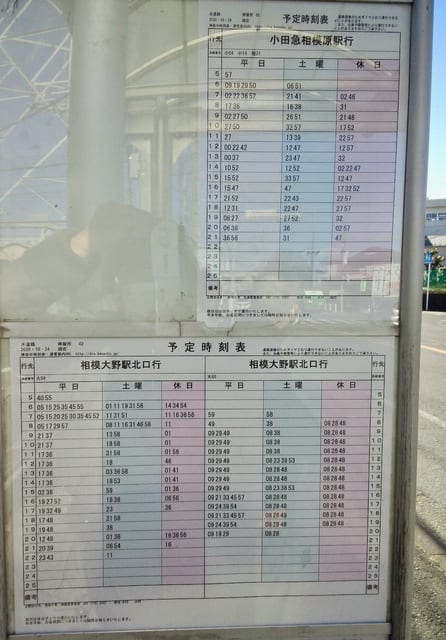





 2017/3/8撮影
2017/3/8撮影









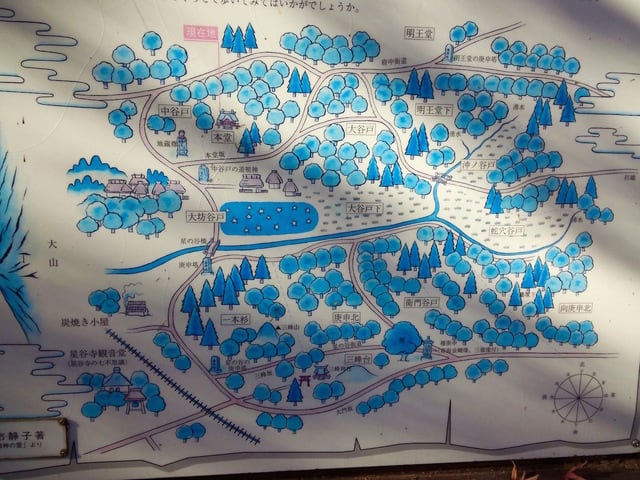

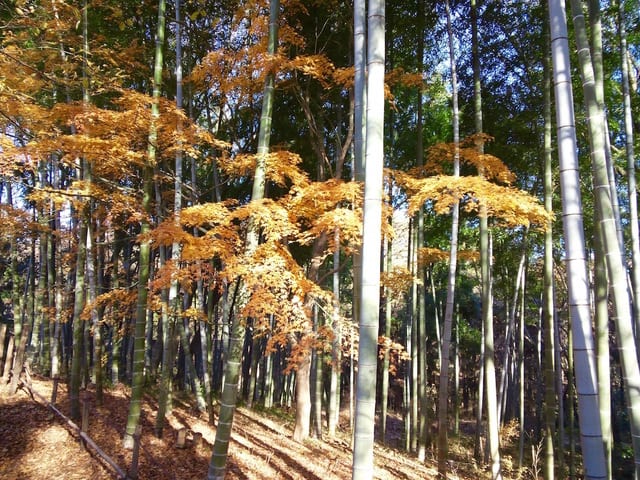

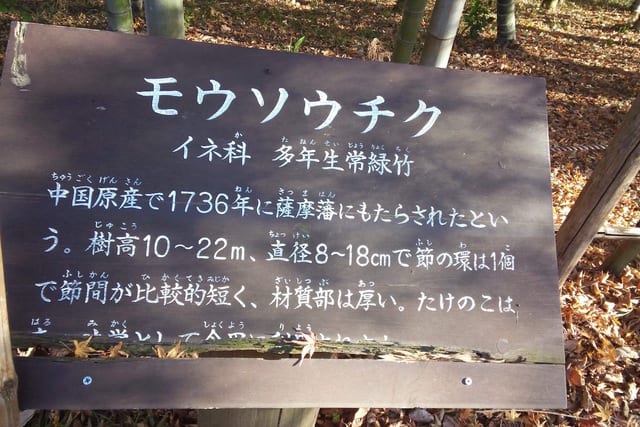

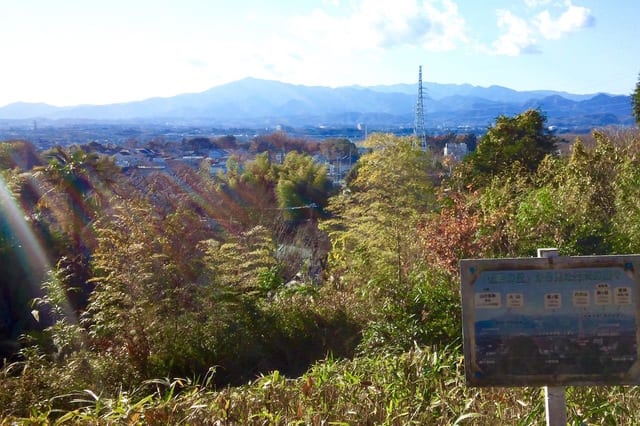









 ど〜みてもつつじっぽい。なんか咲いてました。
ど〜みてもつつじっぽい。なんか咲いてました。























 あ。またあった。9月に入って雨の日が増えたからか。珍しいきのこではないけれど探そうと思えばあちこちで見つけれました。
あ。またあった。9月に入って雨の日が増えたからか。珍しいきのこではないけれど探そうと思えばあちこちで見つけれました。








 見つけた〜。咲いてる場所は、背後の白い部分がテニスコートなので目安にしてください。
見つけた〜。咲いてる場所は、背後の白い部分がテニスコートなので目安にしてください。


















 2019年7月5日撮影画像です。
2019年7月5日撮影画像です。





























