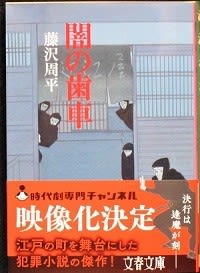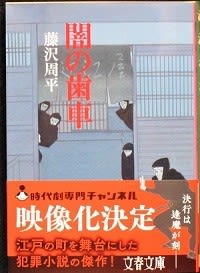
「あらすじ」
「ちぎれた鎖」
六 (きえが囮になり、伊兵衛は掴まる。佐之助はきえと伊兵衛の嘘で助かる)
十日ばかり、佐之助は一歩も外へ出ず家の中に閉じこもっていた。しかし、何事も起こらなかった。佐之助はほっとした。結局、きえは何も言わなかったのだ、と思った。
だが、すぐに別の心配が心をしめていた。伊兵衛が、きえをそのままにしておくはずはないと思えたのである。
佐之助は町に出て、伊兵衛の動きを探った。そして、ある夕方、思った通り伊兵衛が近江屋の様子を窺っているのを突きとめたのである。伊兵衛がきえを狙っていることは明らかだった。伊兵衛がきえに手出しするようであれば、邪魔してやるしかないと佐之助は思った。
だが、きえは佐之助に言われたとおり、用心していると見えて、外に姿を見せなかった。ただ、佐之助に言われてそうしているのではないことが、間もなくわかった。伊兵衛を跟けているうち、ひと眼で奉行所の人間とわかる男たちが、伊兵衛の回りをうろついているのに気づいたのである。佐之助も知っている芝蔵という男もいた。
―――きえは、話したのだ。
と佐之助は思い直した。きえは顔を見たことを話し、奉行所はそれを前から眼を付けている伊兵衛と結びつけた。だから、ああして伊兵衛を跟けまわし、きえには外出を控えさせている。そう思った。
しかし、それにしては裏店の家に、奉行所の人間がやってこないことが不思議だった。伊兵衛がああして勝手に動き回っているのに、捕まえようとしないことも腑に落ちなかった。
―――話したことは、話したのだ。
だが、きえは、たとえば一人は黒江町に住む佐之助だったと、はっきり言っていないのだと思った。
きえを見殺しににすることは出来なかった。それはきえが自分のことを奉行所に喋らないでいてくれるからではなかった。一年ほど同じ家に寝起きした女だからという気持とも少し違っていた。強いて言えば、小心で怯えやすいきえが、伊兵衛のような恐ろしい男につけ狙われているのが哀れだった。
伊兵衛は、海辺大工町のほうに歩いて行く。少し肩を丸め加減に、小幅な足運びでただの商人としか見えない後ろ姿だった。
漠然とした不安が、佐之助を包みはじめていた。その理由がわかっている。いつもなら、このあたりまでくると、どこからか手先ふうの男が現われて、それとなく伊兵衛を跟けはじめるのである。ところがその男たちの姿が見えなかった。佐之助は胸騒ぎがした。奉行所が警戒を解いたとしか思われなかった。伊兵衛は野放しにされていた。
不意に伊兵衛が立ち止まった。佐之助も立ち止まった。そしてすぐに、伊兵衛がなぜ足を止めたが分かった。向こうからきえが歩いてくる。逆光で、きえの姿は黒く見えたが間違いなかった。
一度立ち止まった伊兵衛が、ゆっくりきえに近づいていく。佐之助走り出した。伊兵衛ときえが擦れ違おうとしたとき、佐之助は間に飛び込んで、きえを突き飛ばした。瞬間、匕首のようなもので袖を斬られたのを感じた。振りむくゆとりがなく、佐之助は倒れたきえの上から覆いかぶさった。
後ろから背を刺されるかと思ったが、そういうことはなく、そのかわり背後に突然に怒号と格闘の音が起こった。
身体を起して佐之助が振りむくと、二間ほど先の地面から、捕縄をかけられた伊兵衛が引き起こされるところだった。
そばに奉行所の同心と、芝蔵という岡っ引、それに手先らしい男たちがいる。その男たちが、どこから出てきたのか、佐之助にはわからなかった。
「ちょっと女中さん、この男を見てくれ」
同心が気さくな口調できえを呼んだ。すると佐之助の後から、きえが前に出て行った。きえは囮だったのだ。
「この間、あんたが見たというのはこの男かね」
きえが、「はい」と答える声がした。
「伊兵衛、年貢の納め時のようだな。動かぬ証拠がこれだ」
同心は手に持っていた匕首で、ひろげた片方の掌をぴたぴたと叩いた。
佐之助は、そっと人垣に紛れようとした。するとその背に、同心がおい待て、と言った。
「お前は女中を助けようとしたようだが、知り合いか」
「いえ、ただの通りがかりのものです」
名前は問われ、佐之助は、
「佐之助と申します。黒江町の甚之助店で」と答える。
「女中さん」
同心は、今度はきえに言った。
「お前さんが見た、若い男というのは、その男じゃあるまいな」
きえは、ちらと顔をあげて佐之助を見た。それから、小さいがはっきりとした声で、
「違います」と言った。
同心は縛られている伊兵衛を振りむいた。
「お前はこの男を知らないか」
伊兵衛は無表情に佐之助を見た。石ころを見るような眼だった。佐之助はじっとり汗がにじむのを感じ、身体がこわばったが、伊兵衛はそっけなく首を振った。
「知らねえ奴でさ」
「そうか。いや、町人」
同心は表情を崩し、白い歯を見せた。
「手間かけたな。引きとっていいぜ」
奉行所の人間が伊兵衛を引き立てて行ってしまうと、あとに佐之助ときえが残された。
「おめえのことが心配でな。あいつを見張っていたのだ」
佐之助が言うと、きえはすみません、と言った。俯いている髪から、油のいい匂いがした。その匂いが女と過ごした遠い日を思い出させ、佐之助を少し感傷に誘った。
「しかし驚いたぜ」
佐之助は非難するように言った。
「囮役を引き受けるなんて、無茶だぜ。まかり間違えば刺されている」
じっさい佐之助は、そのことでまだ驚きがさめなかった。
「でもそうしないとお金が戻りませんから」
「金なんぞ、どうでもいいじゃねえか。よその家の話だ。女中で勤めている間のことだろう ? 辞めちまえば関わりねえものを」
「違うんですよ」
きえは、俯いたまま小さな声で言った。
「近江屋の嫁に、と話しが決まっているんです。だからお金が戻って来ないと、あたしも困るんです」
「七」に続く