
高松地方気象台から、今日28日11:00、
「四国地方も梅雨入りしたと思われる」との発表があった。
昨年の2017年は、6/20頃だったので、23日も早く、
平年は、6/05日なので、8日も早いとも、発表されていた。
なんと早いことだ。
5月の梅雨入りは5年振りとのこと。
しかし、毎日、雨が降る梅雨は嫌だな。
早く梅雨が終わってくれるか、
気象台の発表に違いがあってくれることを祈るだけだ。
俳画は「青梅」。 5月末~6月初め頃の田植えが終わったばかりの風景を詠んだ句。

高松地方気象台から、今日28日11:00、
「四国地方も梅雨入りしたと思われる」との発表があった。
昨年の2017年は、6/20頃だったので、23日も早く、
平年は、6/05日なので、8日も早いとも、発表されていた。
なんと早いことだ。
5月の梅雨入りは5年振りとのこと。
しかし、毎日、雨が降る梅雨は嫌だな。
早く梅雨が終わってくれるか、
気象台の発表に違いがあってくれることを祈るだけだ。
俳画は「青梅」。 5月末~6月初め頃の田植えが終わったばかりの風景を詠んだ句。

またまた、藤沢周平の文庫本を購入した。
私は、購入した本を2007/1/17からパソコンに記録している。
理由は色々あるが、ある時、一年前に購入した本をダブって購入した事があったからだ。
その記録のトップに、この作者の「用心棒日月抄」が記載されている。
その記録を見ると、現在まで、この作者の作品を文庫本だけを数えると、
28冊あった。
この文庫本の帯の「犯罪小説の傑作」と裏表紙の「ハードボイルド犯罪時代小説の傑作」が目に這入り、藤沢周平の犯罪小説は珍しい、まだ、この類のものは読んでいないと思い、「解説文」を見ると、その冒頭に、
「『闇の歯車』を読みはじめて、すぐに気づくことがある。文体が違う。いつもの藤沢周平の文章とはだいぶ違っている。抑制と透明感のある文章ではなく、打ちこむような、あるいはたたみかけるような、速度のある強い語り口ではじまり、その調子がずっと続いてゆくのである。………」
とあった。
これを見て、すぐに、本を持ってレジへ向かった。

今年度のOB会総会に出席して、米寿のお祝いを頂戴した。
祝い金に添えて「ウサギのおはじき人形?」も戴いたが、
これを作った方も米寿のお祝いを貰った方です。
いずれにしても、ありがとうございます。感激です。
貰った私も作られた方も、元気で幸せなことだ。
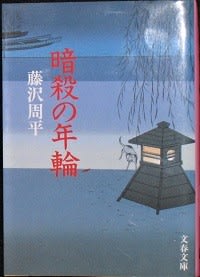
「あらすじ」
第七章
(馨之介は金吾や水尾一派に騙されながらも一人で親の仇の嶺岡中老を刺殺して、金吾らに追われながら侍の皮を脱ぎ捨てる覚悟で徳兵衛の店に向かって走る)
兵庫はまだ城にいて、五ツ(午後8時)に評議を終り、帰途に就くと金吾が探ってきている。嶺岡兵庫は四半刻後には眼の前を通る筈だった。
提灯を持った女が近づいたとき、馨之介は土塀の間の闇に躰を沈めた。三尺ほどの隙間を提灯の明かりが通り過ぎた。
(それにしても、金吾は遅い)
舌打ちして立ち上がったとき、塀の隙間に明かりが射した。見つめている鼻先を提灯がゆっくり通り過ぎた。あッと馨之介は前に動いた。さっき気づかなかった提灯の紋が、貝沼の家の紋である。
「菊乃どの」
低い呼び声が、頭巾姿の菊乃に届いたようだった。立ち止まって提灯の火を吹き消すと、小走りに戻ってきた。
「どうしたのだ ?」
菊乃はいきなり馨之介の胸に倒れ込んだ。
「兄は来ません」
ようやく顔を上げた菊乃は、震える声で囁いた。
その顔をのぞきこんで、馨之介は鋭く言った。
「なぜだ ?」
菊乃は首を振った。
「葛西さまひとりで十分だと言っていました。わたくし、ずーっと立ち聞きしておりましたの」
「だがそう言った ?」
「父ですわ。ご家老さまと野地さまがおられて、父はその前に今夜ここで嶺岡さまを襲うことに決まったと話していました」
「金吾は ?」
「わたくしが出るまでは、兄も家におりました。兄だけではございませんのよ。ご家中の若い方が、ほかに五、六人みえて、父たちとは別の部屋で、兄と何か相談していました」
「………」
「お逃げになることは出来ませんの ?」
不意に菊乃は怯えるように、もう一度馨之介の懐に入ってきた。
「菊乃どの」
馨之介は、菊乃の手をほどきながら言った。
「知らせて頂いて有難かった。しかし、今夜のことは、ひとりでもやらねばならん事情がある。うまくし遂げて命があれば………」
馨之介は言葉を切った。大手門前の闇に、突然提灯の明かりが五つ、六つ浮かび上がったのを見たのである。
「さ、行って下さい。人が来る」
「おやめになることは出来ませんの ?」
「それは出来ない」
「それでは、あなたさまのお家へ行って、そこでお待ちしています」
菊乃の足音が背後の闇に消えるのを耳で追いながら、馨之介はゆっくり襷をとり出してかけ、塀の陰に躰を寄せた。
「嶺岡どののお命をいただきたい」
三人の人影が縺れ合うように後ろに退き、提灯の光が乱れた。その一瞬をとらえて、馨之介の躰は地を這うように走った。
「くせもの ! 」
左側にいた男が刀を抜こうと躰を捩じったが、馨之介の抜き打ちが、一瞬早く胴を斬り裂いていた。
………。
「葛西源太夫の子、馨之介でござる」
兵庫は確かめるように馨之介の眼をのぞいたが、その顔には怪訝な表情が浮かんでいるばかりだった。
馨之介は一瞬にして覚(さと)った。この男はすべて忘れ去っている。父はもちろん、その記憶に怯え、それを知られたとき命を絶った母のことも、この男の記憶には恐らく塵ほども留まっていまい。
地上の火の最後のゆらめきが、怪訝なままの兵庫の表情を闇に閉じ込めた。
その闇に、途方にくれたような兵庫の声がした。
「葛西だと ? 知らんな」
「ごめん」
馨之介の刃が、兵庫の胸のあたりを真直ぐに突き刺し、突き上げてくる憤怒を加えて、剣先はさらに深く肉を抉った。
膝をついて兵庫の死を確かめ、立ち上がろうとしたとき、突然闇の中に火光が走って、馨之介の凄惨な姿を浮かび上げらせた。
反射的に光に向かって刀を構えた馨之介に、右横からいきなり斬りかかってきた者がある。のけぞって躱(かわ)したが、気がつくと右も左も、牙を植えたように光る白刃の群だった。
「何者だ、貴様ら」
馨之介は油断なく構えながら、低く咎めた。敵はすべて覆面に顔を包んでいて、不気味な眼が馨之介の隙を窺っているばかりである。七、八人はいると馨之介はみた。
このままでは殺されると思った。じりじりと回り込んだ背後に川を背負ったとき、不意に菊乃の言葉が甦った。
(父たちは、何か企んでいるのですわ)
これがそれだ、と思った。何のために、と首をかしげたとき、馨之介は思わず呻きを噛み殺した。幕が一枚、二枚と続けさまに切って落とされるように、みるみる水尾一派のいわゆる企みの全貌が見えてきたのである。
嶺岡兵庫を倒すことは必要だが、そこに水尾家老の手が動いた痕跡を残してはならないのだった。痕跡は消さなければならない。しかも馨之介の口を塞いでしまえば、今度は馨之介の死体自身が、父源太夫の横死に絡む私怨から嶺岡を刺したと、雄弁に語り始めるのである。
嶺岡兵庫を暗殺をする人間として、馨之介以上の適任者はいない。あとは汚れた手を洗うように、暗殺者を消すだけである。それで藩政の実験は、滞りなく反嶺岡派の手に移るのだろう。
(あるいは………)
父の源太夫も、水尾家老の画策に踊った一本の手だったのではないか、とちらと思った。新竿打ち直しの時、嶺岡兵庫の対立した一派が誰であったかは馨之介にはわからない。だが、水尾家老がその中にいたことは確かなのだ。
最後の、薄く透けて見える幕の奥に、暗い光景が見える。手傷を負ったが嶺岡は遁れ、呆然と佇む源太夫のまわりに、黒布で顔を覆った人数がひたひたと近付くのである。
「そうはさせんぞ」
馨之介は呟いた。噴き上げる怒気が、四肢に戦闘的な力を甦(よみがえ)らせていた。
「金吾」
怒りとは裏腹に冷ややかな声になった。
「貴様らの腹は解った。さ、来い」
小刀を鞘ぐるみ抜くと、馨之介は躰をひねって龕燈(がんどう)に投げつけた。龕燈が砕ける音がして光が消えた。馨之介は猛然と右側の敵に斬り込んで行った。
………。
背後に追い縋る刃を斬り払うと、馨之介はいきなり走り出した。
(お逃げになることは出来ませんの ? )
菊乃の怯えた声が耳もとにする。
執拗な足音が背後にしているが、二人ぐらいのようだった。闇が逃げる者を有利にしている。
星もない闇に、身を揉み入れるように走り込むと、馨之介はこれまで躰にまとっていた侍の皮のようなものが、次第に剥げ落ちて行くような気がした。
馨之介は走り続け、足はいつの間にか家とは反対に、徳兵衛の店の方に向かっているのだった。
(この後、どうなったかについては記述がなく、読者の思いに任されている)
終
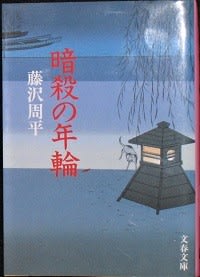
「あらすじ」
第六章
(母への憎悪と弥五郎を刺殺したことを酒で紛らそうと、徳兵衛の店に行き初めてお葉を抱いた。そのあと、家へ帰ると母が死んでいた)
「そのなりは ? なんの真似ですか」
馨之介が茶の間に顔を出すと、波留は目を瞠(みは)り、詰(なじ)るように言った。
「母上。水垣にある嶺岡の別業というのは、景色の好いところだそうですね」
行燈の光に照らされた波留の顔が、みるみる血の気を失って、仮面のように表情を無くしたのを馨之介はみた。
絶望がどす黒く馨之介の胸を塗りつぶした。弥五郎が本当のことを喋ったことは疑いなかった。
「やはり、噂は本当だったのですな」
波留が問いかけるように首をかしげた。鳥のような仕草だった。
「何のためですか ? 」
長い沈黙の後で、馨之介は立ち上がりながら言った。
「葛西の家名のためですか。それとも私のためですか」
「………」
「それとも自分のためですかな」
唇がわななき、波留の低い声が洩れた。
「お前のためにしたことですよ」
「ずいぶんと愚かなことをなされた」
馨之介は冷たい声で即座に言った。狂暴な怒りが心の中に動き始めていた。
「そのために、私は20年来人に蔑まれて来たようだ。我慢ならないのは、近頃それに気づいたことですよ」
馨之介は部屋を出ようとして振り返った。
「今夜、私は人を殺してきましたよ」
外へ出ると、冷えた夜気と秋めいた月明かりが躰を包んだ。背を丸めて馨之介は歩きだした。
足は坂下の徳兵衛の店に向かっている。弥五郎の言葉を信じれば、徳兵衛も馨之介を欺いたのだが、それを責めるつもりはない。ただ酒を呑みたいだけだった。浴びるほど酒を呑んだら、苛立たしく募ってくる母への憎悪も、幾分紛れそうに思うのである。
母が命乞いしたことを責めるのではない、と思った。若い頃城下で評判の美人だったという母が、その美しさを命乞いに使ったことが、やりきれなく惨めな思いに馨之介を誘うのである。
「酒を持って来い、お葉」
「ここではいけません。若旦那」
お葉は囁いてから、板場の方を向いて、「もうお店閉めてね」と言った。
馨之介を案内した二階の部屋に酒を運んでくると、お葉は、
「お爺さんはもう寝ていますけど、ご挨拶させましょうか」と言った。
「何の挨拶だ。酒だけでいい。お前も寝たかったら引き取ってもいいぞ。勝手に飲んで帰る」
お葉は笑った。笑うと、軽い三白眼の眼が細くなって、頬から首筋のあたりに、匂うような色気が走った。
「お相手しますよ、ひと晩でも。ご迷惑でしょうけど」
くく、と喉を鳴らして笑った。
「灯を消して」とお葉は囁いた。
鼻腔から肺の中まで、お葉の躰の香りが溢れるのを馨之介は感じていた。探る指の先に、膨らみ、くぼみ、鋭く戦(おのの)きを返して横たわる女体がある。闇の中に、熱くやわらかに息づくものに、馨之介はやがて眼の眩むようなものに背を押されて埋没して行った。
………。
闇の中で女を抱いている己の姿が、不快な連想を呼び起していた。耐え難いほど醜悪な妄想を振り払うように、馨之介は手を伸ばして女の胸を探った。
………。
「やっぱり今夜は何かあったんですね」
「すまん」
「いいの、謝らなくとも、あたしはそれでも若旦那が好きだもの」
立ち上がった馨之介の背に頬をつけて、お葉は、また来てくださる ?と囁いた。
家に戻ると、家の中は闇だった。
不吉な感じが胸をかすめたのは、やはり虫の知らせのようなものだったのだろう。
闇には人の気配が死んでいた。
玄関を入ったときに血の匂いを嗅いだが、馨之介はいそがなかった。ゆっくり茶の間の襖を開いた。だが、そこには闇が立ち込めているばかりで、人の気配はない。馨之介は行燈に灯を入れると、それを提げて、奥の間との間の襖を開いた。
むせるような血の香りがそこに立ち籠めていて、その中に、膝を抱くようにして前に倒れている波留の姿があった。
波留は穏やかな死相をしていた。冷たい掌から懐剣を離し、足首と膝を縛ったひもを解いて横たえると、馨之介はもう一度手首に脈を採ったが、やがてその手を離して立ち上がった。
貝沼金吾に会って、嶺岡刺殺を引き受けると言うつもりだった。
終りの第七章に続く